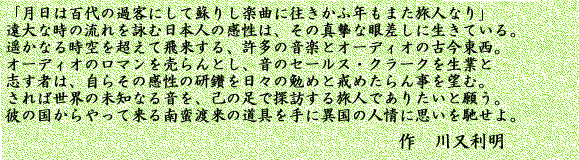第四十七話「純粋主義者」
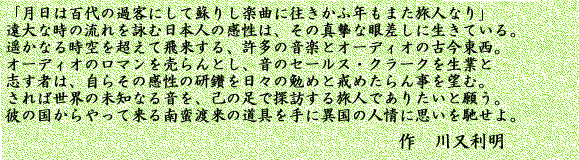
第三部「deep emotion」
第一章「ACドミナス」
今井氏とお会いした週の金曜日、休みあけに私が出社してみると早速PADのサンプルが送られてきていた。長い間並行輸入業者による乱売に辛酸をなめさせられ、苦労の末に日本向け特別仕様としてのレヴィジョンBシグネチャーシリーズへの商品変更が順次進む中で、旧タイプではあるが取りあえずACドミナスを送って下さったのである。私は輸入商社が果たす役割とその価値観について、並行輸入業者への批判も込めて前作の随筆でも述べており、同じ志を持つものとしてそのメッセージが皆様にご理解頂ければと思っている。ところで、このレヴィジョンBシグネチャーシリーズというのはシーエスフィールド側の希望でジム・オッド氏が特別に設計開発したシリーズであり、クライオジェニクスやマグネトストリクションという物性処理に最新のバージョンを施したものである。まずクライオジェニクスは2回行なっている。最初はケーブルを構成するワイヤー、コネクターやラグといったパーツの状態で一度クライオし、ケーブルとして完成した状態で2回目を行いダブル・クライオとして製品化している。その度にNASAに持ちこむわけであり、かつNASAの設備の操作についてはジム・オッド氏ひとりしかライセンスを持っていないので、いきおい生産性を犠牲にすることになる。マグネトストリクションも同様に二回施している。1回目のクライオ直後にワイヤーのみに行い、ダブル・クライオの後に2回目を行なうというのだ。そして、従来のレヴィジョンBよりも1Nランクアップした高純度金属を使って素材である合金を作っているという。ちなみにドミナスでは後述するが7種類の金属各々に対して、6Nから7Nへと1ランク純度を上げている。更に製造段階ではシニアクラスのエンジニアがアッセンブルを行ない、5項目のチェックポイントを設け、3Mの静電防止メッシュを採用し、ジム・オッド氏が自ら検査を行なっているという。封入された液体はEMIとRFIに対して従来の1.5倍のプロテクション効果を持っており、S/Nにおいても40パーセント以上の改善がなされたということで、世界中でもシーエスフィールドのみが販売しているというラインアップである。また、海外で求めたPADの電源ケーブルを日本で使用した場合にも本来の能力は発揮されないという。PADのACケーブルは75Vから135Vの電源電圧用と、180Vから260Vの電源電圧用とでは設計仕様が異なり、もちろん使用はできるもののジム・オッド氏が考えている音質的パフォーマンスは正しい電源電圧が適用されなければ得られないものであるという。
さて、レヴィジョンBからの更なる自己錬磨の結果を具現化しながら、かつ並行輸入業者が扱う品物との差別化のためにもPADはシグネチャーシリーズへ移行したわけだが、ここで面白いエピソードがあるのでご紹介しておく。シーエスフィールドが取り扱う正規のPADケーブルの長さは、各種ケーブルともリードワイヤーの長さを含まないものである。もしも、皆様の知り合いでPADのスピーカーケーブルを使用されている人がいて、ご当人は2メートルの長さを購入し、その代金を支払ったとしよう。事実ケーブルの端子間の長さを測ったらば2メートルあったとして、そのような場合ドミナスを例にあげればシーエスフィールドでは1.5メートルの商品として価格を設定しているのである。特にドミナス・スピーカーケーブルの場合は、この0.5メートルの違いは33万円の価格差となり、並行輸入品の場合はその分お高い買い物をされたということになるだろう。ACドミナスもほぼ同様なリードワイヤーを持っているほか、各種デジタルやインターコネクトもカタログ表記の長さにプラスする形で各々リードワイヤーが引き出されている。このようにPADのケーブルは端子間ではなく、液体封入チューブの長さをもって価格設定しているのが正規輸入元シーエスフィールドの商品である。また、今井氏のもとには何と並行輸入業者から買われた方からもクレームの電話がくるという。商売の常識からして輸入販売を行い利益をあげた会社がアフターサービスの責任を持つべきだと考えられるのだが、届いたケーブルの端子に傷みがあったり何らかのトラブルがあったとしても並行輸入業者はクレームを真剣には受け付けないらしい。もっとも、私が聞いたところでは新品を買い集めてきたものではなく、外国のユーザーが売りに出した中古品も一緒くたにして売っていることもあるらしいので注意が必要であろう。
さて、届けられたACドミナスは三メートルのもの(1本542,000円)が2本、それにACドミナスグレードの内部配線を航空工学グレードの特殊アルミ合金ボックスに納め、レヴィトン社との共同開発によるオーディオグレードレセプタクルを装備したエクステンションボックス・レヴィジョンB(278,000円)の3点であった。これだけで合計価格は1,326,000円となる。このエクステンションボックスは8個のレセプタクル(コンセントの差し込み口)が装備されているが、4個ずつモノラル化されており、独立したACケーブルで壁コンセントから給電するものである。これを当フロアーのパワーアンプ用としている独立40アンペア2回線に一つずつ差し込み、パワーアンプの中央に配置した。
昨年から常設したノーチラスは数多くの局面でエレクトロニクスとケーブルなど周辺機材の違いを面白いほどに引き出すリファレンスとなっており、私の長年のセッティングに関わるノウハウが集大成されたものと自負している。最近はパワーアンプにジェフロウランドのMC6を二台使用することで落ち着いている。6チャンネルのMC6を片側に1台使うのだが、4ウェイマルチのノーチラスにはチャンネル数が余るのではないか、と思われる方も多いと思う。ここでは以下のようにちょっとぜいたくな使い方をしているのである。MC6に計6チャンネルのパワーアンプが搭載されているのだが、その1番と6番に250Wのアンプが内蔵されており、1番にはウーファーを6番にはトゥイーターを接続する。そして、2番と3番をリンクスイッチによって一系統のアンプとして切り替えてミッドローを、同じく4番と5番をリンクさせてミッドハイを接続しているのである。電力的には2番から5番までは各々150Wのパワーであるが、これら二系統を一つにまとめてパラドライブすることでパワーは変わらないが出力電流容量には2倍の余裕を見込めることになるのである。いずれにしても1台300万円のMC6を2台使うのだから、既にノーチラス本体よりもパワーアンプの方が高くなってしまう状態である。また、最近では同社の新製品であるモデル8TiHC(ハイカレントバージョン)にMC6を組み合わせするという事例も出ている。モデル8TiHCのドライブ能力は当然のことながらMC6の1番と6番の2チャンネルとの比較において相当な情報量の増加をもたらしており、このモデル8TiHCをステレオ使用としてトゥイーターを受け持たせ、残り3ウェイ・6チャンネルをMC6が同じくステレオ使用で受け持つのである。MC6をフルにモノラルアンプとして使用するセパレーションの見事さと、ステレオ使用ながらモデル8TiHCのもつ駆動力がノーチラスをどう鳴らし込むか、本当に甲乙つけがたい屈指の選択である。もちろん、究極的にはモデル8TiHCが4セット揃えば文句のつけようはない。そして、プリアンプには同社のコヒレンス2、トランスポートはエソテリックP−0を固定し、D/Aコンバーターはイルンゴのモデル705とマークレビンソンのNo.30.5Lを使い分けるというラインアップである。
当フロアーではフロントエンドにはパワーウェッジのウルトラ116から給電しているのだが、パワーアンプの電源には回路をもつ電源装置は一切使用していない。パワーウェッジの他にもCSEや信濃電気の優秀なレギュレーター電源を試したことがあるのだが、私が各種テストのためにパワーアンプに要求する電力量が大きく、またこれらの製品を使用するとパワーアンプの反応に遅れが出るなど、数々の経験からパワーアンプには極力ストレートでシンプルな電源を使用しているのである。前述のように1系統40アンペアに強化したこのラインには、10数年前からあるテクニカルブレーン社のなんの変哲もない極太のケーブルがついたテーブルタップを使用していたのだが、昨年の秋からカルダスのパワーストリップ電源ボックスに同社のヘックスリンク・パワーケーブルを導入している。この時にも従来の電源ラインとカルダスを何度も差し替えて試聴し、ノーチラスのシステムにおいて確固たる音質の優位性を確認した上でカルダスの新製品を採用したのであった。本当にカルダスの電源ラインは見事に解像度を高め、私の知り得る中で最優秀の音質を聴かせてくれていたのである…、ほんの先程までは…。
イタリアのクレモナ出身の伝説的な弦楽器製作者アントニオ・ストラディヴァリが1712年に製作したチェロの1本を所有するヨーヨー・マ。その貴重な楽器をロンドンの有名な弦楽器メーカーであるジョン・アンド・アーサー・ベアールにバロック・チェロに改造するよう依頼していた。それを引き受けたのは同社の重役でもある弦楽器製作者のチャールズ・ベアールである。チェロの胴の下端にあるエンドピンが取り去られ、スチール弦からガット弦に交換され、指板を変えずに4本の弦の間隔が離れるようにバロック風の駒に取り替えるなど、細やかな配慮のもとで改造されたヨーヨー・マのバロック・チェロによって演奏されたのがソニー・クラシカルから発売されている「シンプリー・バロック」(SRCR-2360)である。3か月前から度々テストで使用するようになったこのCDの1曲目、バッハのカンタータ第167番「人々よ、神の愛をたたえよ」を、ジェフロウランドのMC6とノーチラス付属のチャンネルディバイダーともに付属ACケーブルのままで従来からのカルダスの電源ラインで聴く。本当にバロック・チェロに改造したのだろうか、と思わずテンションのきいたヨーヨー・マの演奏を耳にして、このままでも十分に爽快であり不満の要素は何も感じられない。
濃紺のメッシュに覆われた三メートルのACドミナスは直径が32ミリもあり、それが床を長々とはう姿はまさにニシキヘビのようである。その先端にあるエクステンションボックスの左右各々にMC6とチャンネルディバイダーの電源プラグをそっくりと移し変えた。グッと手応えと安定感を感じさせるレヴィトン社のレセプタクルは、差し込むだけでその信頼性を使う人に思い知らせてくれる。さあ、これで単純ながらパワーアンプとチャンネルディバイダーの電源が入れ替わった。心持ち早足で6メートルほど離れたセンターポジションにもどり、P−0のリモコンで一曲目をスタートさせた。と、その瞬間である。「マジかよ!」もちろん私は、少なくとも仕事中にこんな下品な言葉を使うことはない。あくまでも私の胸のうちでささやかれた驚嘆の一言である。ヨーヨー・マのバックをつとめるアムステルダム・バロック・オーケストラ(ABO)の各パートがスーッと奥に展開され、演奏されている空間の広さを倍以上に拡大させてしまうではないか。今まで一枚の広角写真に写っていたと思われるヨーヨー・マとABOであるが、実はヨーヨー・マだけ一人で写した写真の彼だけを輪郭から切り放し透明なガラスに貼り付け、ABOの全景の写真を背景として二枚の写真を間隔をあけて正面から眺めているようなのである。つまり、ヨーヨー・マが背景からフーッと浮き上がった立体像としてノーチラスの中央に三次元的フォログラフィックを展開しはじめたのである。しかも、先程までまるでスチール弦のチェロではないかと思わせるほどのテンションと、弓を折り返すときの輝きにも似たまぶしいばかりのチェロの音色が激変しているではないか。数週間好天が続きのどがひりつくような乾きを覚える空気を吸っていたヨーヨー・マとABOたち、そこにあたかも突然のスコールが適度な潤いを演奏会場全体に与えたような響きの滑らかさが突如として表れたのである。現代の名工が改造したバロック・チェロの響きとはこういうものなのだろうか。たかが電源ケーブルを、しかも壁コンセントから3メートルの区間だけをACドミナスに変えただけだというのに…。疑り深い私はもう一度電源プラグをカルダス側に差し替えた。「ああ、これは間違いないや、まいったな。」一瞬にしてドライに変貌した演奏会場の空気感は疑いようもない現実として同じ演奏を繰り返すのみであった。
今度は大貫妙子の新譜を持ち出してくる。「アトラクシオン」(東芝EMITOCT-24064)は以前からテストに常用している「ピュア・アコースティック」に代るヴォーカルのチェック用として最近多用しているソフトである。その中の5曲目「四季」をカルダスの電源ラインのままで聴く。小倉博和のアコースティックギターのピッチカートと高水健司のウッドベースが心地よいエコーをともなって展開するイントロ。パーカッションの藤井珠緒が演奏するハンドベルがキラキラと輝きながら流れ星のように左右のノーチラスが立つ空間を流れ去っていく。見事な録音、しかも日本人の感性にひそやかに寄り添うようなヴォーカルとその余韻のきれいなこと。内心「いいじゃないの、このままでも」と、ほんの先ほどまで自分自身が認めていたカルダスの電源ラインの音に自信を取り戻せとばかりに声援を送っている自分に気が付く。曲を聴き終わってから念のためにイントロを数秒間聴き直し、合計四本の電源プラグをACドミナス&エクステンションボックスに差し替えた。先程よりもさらに早足で席にもどる。
「アッ!」これは私の心の声である。イントロのギターが最初の一音を出した瞬間に先程の演奏空間からホールにワープしてしまったのがわかる。スタジオという数メートルほどの空間で一人きりで演奏され、入念な編集とマスタリングの成果できれいなエコーでお化粧されたギター。しかし、あくまでも閉ざされた空間で演奏しているというイメージが拭えなかったものだが、ACドミナスに差し替えた瞬間にギターの弦一本一本が鮮明さをぐっと増して響き、更にギターリストの背中にあったはずのスタジオの壁の存在がパッと掻き消えてしまったのである。しかも、ウッドベースの響きはポンとノーチラスのボティーから飛び出したような定位感に変貌し、それに比べると先程までは右側のノーチラスに張り付いていたようなベースではなかったか。追い討ちをかけるように先程の記憶を瞬間瞬間で塗り替えていくPADのパワーラインは、決定的な衝撃をもってハンドベルのパートを聴かせてくれる。これには本心から呆れてしまった。擬音語で言えば「チリーン、チャリーン」とでも表現するのであろうか、ハンドベルのエコーがひと呼吸つけるくらいに長く尾を引いているではないか。それに比べると先程までは楽器をカーテンでかこって録音されたような違いを感じるのである。
そして、大貫妙子のヴォーカルがきこえてくるとゾクゾクッとするような実在感が更に興奮を高める。空気中に発生した音波に磁性があり、細かい砂鉄を空間に吹き出したように、ヴォーカルのエコーが展開すると頭の中で仮定のイメージを思い描いていただきたい。更にこの音波の磁力を吸引するような磁石をマイクスタンドの先端に取り付け、ノーチラスの中間にポンと置いたようなイメージの変化である。大貫妙子のヴォーカルはその強力なマグネットに吸い付けられるようにセンターに密度感をもって集約され、マグネットから距離が離れるにしたがって磁力線にそって砂鉄の縞模様が出来るように余韻が規則性をもって見やすく整理され、俄然引き立った周辺のエコーはヴォーカルの口元を包むように見事なグラデーションを形作るのである。口元が絞り込まれたフォーカスの高まりを見せ、潮が引くように余分な成分を周辺の空間からかき集めるのである。そして、集約されたヴォーカルのエネルギーが取り残していった空間には先程にもまして純度を高めたエコーが口元と際だったセパレーションをもって空間に溶け込んで消えていくのである。これにはまいった。こんな音楽の浄化作用をもたらしてくれるコンポーネントが他にあっただろうか。
たった2本のACドミナスとエクステンションボックスによる言外の体験に、もう後戻りできないという恐怖を感じていた私に今井氏は更に強力な追い討ちをかけてこられた。4月6日、出社した私の目の前には
PADのカートンが山積みとなっていた。ジェフロウランドのMC6に使用する20アンペア仕様のACドミナス一メートル(390,000円)が2本、通常の15アンペア用IECCプラグのACドミナス1.5メートル(425,000円)が何と4本、これでノーチラス付属チャンネルディバイダーとコヒレンス2とP−0の全てにACドミナスが使用できることになる。D/AコンバーターのマークレビンソンNo.30.5LはL型の特注ケーブルを使用するため、そこまでは無理は言えない。そしてイルンゴのモデル705も設計者が音質を決定した電源ケーブルが本体の基板に直付けとなっているので、これもACドミナスの脅威からは逃れ得ることが出来た。これまでのACドミナスを含めた合計価格では何と3,842,000円の電源ラインがノーチラスシステムに組み込まれたことになる。こんな御馳走を一口でほおばってしまうのはもったいない。私はフルコースのディナーを味わう心境である。
まず、この贅沢を味わう前に環境を整えなくてはと思ったのは私だけではなかった。当フロアーの壁コンセントの器具はごくありふれた松下電工のものである。この壁コンセントも物性処理を施したPADのCRYO−L2(1個13,800円)に交換する。接点にベリリウム銅を使用しエクステンションボックスと同じレヴィトン社のレセプタクルが採用され、漏洩磁束を抑制するハイスティール・カーボン・プレートまでセット化した壁コンセントである。3年ほど前まではCRYO−C2(1個12,000円)という型式であったのだが、これは東芝製のコンセントにクライオジェニクスを施したものであり、同様にエクステンションボックスもレヴィジョンAの時代にはハッベル(HUBBELL)社から供給を受けたレセプタクルで製品化していたのである。ところがジム・オッド氏と親交のあったレヴィトン社の部長レベルの人物とオーディオに対する開発において意気投合し、PADが自社で合金化したベリリウム銅を原料としてレヴィトン社に引き渡し、それをレヴィトン社が成型加工してPADに戻しクライオジェニクス処理を施して製品化するという生産方式に切り替えたのである。これを期にコンセントはL2タイプへ、エクステンションボックスもレヴィジョンBタイプへとバージョンアップされ現在に至っている。このように素材にこだわり自社で素材を内製化してしまうというところがPADの素晴らしいところであり、自身の理論を徹底するために出来合いのパーツに満足しなかったということがオッド氏の信念を裏付ける格好のエピソードとなっているのである。一般の家庭で輸入オーディオを使用する場合、付属品の3P・2P変換アダプターを電源ケーブルの先端に取り付けて壁コンセントにつなぐ。グラグラと安定性に乏しく便宜上で使わなければならないこのアダプターに疑問をもたれている方も多いと思うが、このCRYO−L2を使用されることで音質と信頼性が一挙に改善されるのでぜひお勧めしたいものである。汗をかきながら主要なコンセントをCRYO−L2に交換する。ぐっと差し込むときの抵抗感、ガッチリとくわえこまれたプラグはケーブルの重量などないかのように壁から垂直にACケーブルを保持している。「本来こうでなくちゃいけないよなァ。」と、今までCRYO−L2の存在を知りながら今井氏とお会いするまで採用しなかった私はなんとちゃっかり者であろうかと思わず苦笑がもれてしまった。
さて、私はこれからの試聴に対してあらかじめテストの順序を決めていた。スピーカー側と壁コンセントから順番にACドミナスに入れ替えていくのである。まず、MC6の付属ケーブルとACドミナスを差し替えてみるのである。普通のパワーアンプであれば3本必要となってしまうが、ステレオアンプ3台分が1シャーシに納められたMC6は電源ケーブルのグレードアップもたった1本のACドミナスですむので経済的である。付属品といえども20アンペア用と十分な太さをもつACケーブルで前述の曲を同様な観点で観察し、それではと単純にACドミナスに差し替えて席に戻りP−0のポーズを解除する。「ちょっと待ってよ…」と、厚かましいほどの変化に正気を失いかけた私は直ちに付属品のケーブルに戻し、そしてもう1度ACドミナスに差し替え2度目の試聴で確認してから言葉を探した。
一般的なチェロはエンドピンで床に接地させて演奏するわけで、必然的にホールなどステージの床に響きを伝え楽音の一部として音質を決定しているという。しかし、ヨーヨー・マのバロック・チェロはエンドピンを取り去り、両足で抱えこむようにして演奏している。一般的なチェロほどの音量は出せないものの、体との密着感も含めて演奏者の感性を表現するものとライナーノーツにあるのだが、この時の変化はまさしくヨーヨー・マの足に挟まれた楽器が中空に位置しているという分離と上下の位置関係の変化を聴かせるものであった。同時にABOの管楽器が特に同様な変化を聴かせ、ステージの高さをジャッキアップしたような上方と奥行き方向へのリヴァーブの拡散を聴かせるのである。一言で言い替えれば、このソフトに収録されている楽器群の粒立ちが目に見えて鮮明さを増すのである。こんな違いは今流行りのデジタル・イコライザーなどでは決して実現することのない体験であろう。なぜならば、それは周波数成分に人為的な変化を施したというものではなく、あくまでも楽音の浄化として表現できる変質だからである。とにかくステージ上の空気をサァーッと換気して入れ替えてしまったような透明度の歴然たる変化を感じさせるのである。
このようなケーブルの比較試聴とは実は大変に骨が折れるものである。再び付属ケーブルに切り替えて大貫妙子をリピートする。そして、再び腰を上げてアンプだけACドミナスに差し替えてセンターポジションにもどり、出てくる結果を想像しながらリモコンを押す。ここから感じられたことをたった一言で言い表すのであれば、演奏の全ての箇所に心地よい余裕が生まれる、ということになろうか。イントロのギターは演奏者に数歩近づいていって震える弦が肉眼で確認できそうな音の浮き上がり現象が感じられ、ベースに至ってはドリンク剤を数本飲んでからスタジオに入ったような力強さがみなぎってくるではないか。当然のことながらヴォーカルの変化は目覚ましい。今まで平面に感じられていた大貫妙子のヴォーカルが、実は鮮明な写真でポスターに描かれていたものであったとイメージして頂きたい。その彼女の写真の下には細いパイプがぶらさがっており、あたかも飛行機に備え付けの救命胴衣のように息を吹き込むことによってポスター上の彼女がプーッと膨らんでくるかのような立体感の高まりを見せるのである。ヴォーカルが3D映像のように浮き上がるヴァーチャルリアリティーを、2チャンネル再生においてACドミナスは可能としてしまったようである。決して音声信号が流れることのない、たった1メートルのACドミナスに変更するだけで、MC6は瞬時に成人式を迎えてしまったがごとくの成長を遂げてしまったのである。まいった。
こんな試聴を繰り返していると、せっかくの御馳走をゆっくりと味わうという精神的な余裕が持てなくなり、次の発見と舌と耳が味わう快感を求めてテンポが早くなってしまう。そう、いよいよノーチラス付属のチャンネルディバイダーにACドミナスをつなぐ順番になってきたのである。これまでにもノーチラスのチャンネルディバイダーは音質決定の大きな鍵を握っているものと数々の経験から認識してきたものであり、プアーなノーチラス付属の電源ケーブルの品質から脱却しようとレギュレーター電源の採用やケーブルの変更などと、ノーチラスオーナーの触手を何度も刺激してきたものである。このころになるとヨーヨー・マと大貫妙子は私の耳に明確なデータとしてイメージが転写されており、付属ACケーブルで一通りリピートするとメモリーと心構えは万全という状態になっていた。ACドミナスに差し替えてチャンネルディバイダーの4個のプロテクションが「カチン、カチン。」と解除されていくのももどかしく、ヨーヨー・マのディスクをローディングして待つこと数秒。 PAD、そしてACドミナスは音楽をまさしくpurification「浄化」してくれる魔法のケーブルであると、改めてジム・オッド氏にメッセージを送りたい心境にさせられた。ちょっと、この段階の音は私にとって大きなショックであった。正直にいって待ちきれなくなった私はこらえきれなくなってしまい、この段階でコヒレンス2とP−0にもACドミナスを使用してしまったのである。いったんACドミナスの浄化作用が私の頭に浸透してしまうと、出来るところまでPADで統一したいという欲求が高まってしまい我慢が出来なくなってしまったのである。
今まで聴いてきたヨーヨー・マには大変失礼なことをしてしまった。どうやらチェロを手にしてにっこりとほほ笑むヨーヨー・マのジャケット写真にはうっすらとほこりが付着していたようである。それを今の今まで知らずに「ああ、ヨーヨー・マってこんな男なんだ。」と思って彼の演奏を聴き、彼の演奏を理解していたようだと気が付くと自分が恥ずかしくなってしまった。ノーチラスを駆動するほとんどのエレクトロニクスに対してACドミナスを使用し、その最初の曲としてヨーヨー・マを聴いた瞬間に、ヨーヨー・マにうっすらとかぶっていたほこりをPADブランドのクリーナーは瞬時にして吹き飛ばしてしまったのである。自分の目を疑ってしまうような鮮明な変化を目の当たりにすると、今まで聴いてきたABOの各パートが色あせていたと表現せざるを得ないのである。生の木材を数日間乾燥させると白っぽく表面がかさついてくるイメージがそれである。ところが、十分に水を含ませた刷毛でサッと木材の表面をひと撫ですると、潤いを得た木材は鮮やかな木目を浮かび上がらせ、あたかも生きているかのような生命感を取り戻す。こんな色彩感の再生がACドミナスによってもたらされるのである。ヨーヨー・マの演奏にはピアニッシモとフォルテ、あるいはクレッシェンドと演奏の抑揚が一斉に開花したようで、バロック・チェロを股間にはさみながら体をゆする動きが見えてくるようである。
新たな発見と感動が大貫妙子でも聴けるのだろうか。こんな私のあさはかな心配は聴き初めて数秒間のうちに消し飛んでしまった。「待てよ、アコースティックギターの音色はこんなにもスムーズだったろうか。アレッ、ウッドベースの響きはこんなに色濃く豊かだったろうか。」と変化は大きいのに抵抗感のない自然な方向へのシフトチェンジに戸惑う。そこへ先程のハンドベルが響く。先程の言葉でいえば「チリーン、チャリーン」なのだが、これが「チリィィーン、チャリィィーン」とマスタリングをし直したのではないかと錯覚するほどリヴァーブが尾を引くではないか。「うそだろ!」と内心驚きの声を上げるとヴォーカルのブレーシングで再びショックを受ける。短いフレーズを歌いおえると「ハァッ」「フゥーッ」と緩急取り混ぜた大貫妙子の息づかいがセクシーに聞こえてくるではないか。一分ほど経過したところから篠崎ストリングスの弦楽器が流れてくるのだが、今までこれほど空間に浮き上がってはくれなかった。気が付いてみると大貫妙子のヴォーカルにもひとしおの潤いが添加されているのがわかってきた。艶めかしい声とはこのことである。そして、3分を経過するあたりから藤井珠緒が絶妙のタイミングで演奏する鈴とクラヴィスが本当に美しいリヴァーブで響き渡る。このささやかとも言えるパーカッションの追加が演奏に深みを与えて空間の広さ大きさをイメージさせてくれる。森閑とする静けさの中、皆さん自身が古井戸に石を投げ込む場面を想像していただきたい。手から石が放れ落ちてから数瞬の間をおいて水音が井戸の中に大変長く響き伝わってくる、あの余韻の継続が思い浮かぶのである。このパーカッションは、暗闇に一瞬パッときらめいた音が網膜に残像を残すようにして消えていくありさまに似ている。その鈴とクラヴィスが残す音の残像は、確かにそこに楽器があったという証拠を強力に耳に残しながら消えていくのである。これを臨場感と例えなければ他に何といったらよいのだろうか。今までの電源ケーブルでは、余韻を最後のひとしずくまでこんなに鮮明に聴かせてはくれなかった。一体私はソフトに入っている情報量の何パーセントを聴いてきたのだろうか。そして、これは何を意味しているのだろうか。「ケーブルによって音が変わる」というのが一般論であろうが、それを必要悪として認知した上でケーブルが音を変化させてしまうような作為的な表現が見受けられる。実はケーブルという存在は音を変化させることが目的で作られたものではない。また、どのケーブルメーカーの人たちも自分たちのケーブルが最も透明でありニュートラリティが高いという表現をせざるを得ないので、論争の種が尽きず逆にいえば面白いのである。しかし、ACドミナスを聴いた印象を単純な表現で言い表そうとすれば、そこに一切の誇張感と歪曲した音楽イメージはなく、何物かによって隠されていた情報が本来あるべきそのままの姿で聴けるようになったとしか言いようがないのである。私が不運にも最初にめぐりあったPADの音、それはACドミナスというシステム全体に貢献する最上流に位置するシステムの源であり、ジム・オッド氏の理論と感性を如実に語る道しるべとなる説得力を私のレベルでノーチラスシステムにもたらしてくれたのである。
第二章「CRYOGENICS High end Device」
時系列は前後するが昨年9月、クレルやFMアコースティック、ティールやワディアなどを輸入販売しているアクシス株式会社の木村部長が「実は、こんなものをはじめようと思うんですが。」と突然私のもとに持ち込んできたのがゾウセカス(zoethecus Audio)のラックシステムであった。疑り深い私は自分で聴いて納得しなければ取り扱う気持ちにはなれず、重量級のパワーアンプやエソテリックP−0などを何度も乗せたり降ろしたりして比較試聴して採用したものである。ラックも音質を決定する一つのコンポーネントとしてとらえる時代になったということをゾウセカスを聴いてから認識し、現在は当フロアーのノーチラスシステムでも主な機材に使用しているものだ。同社のZブロック2を2台とZ/3Rシステムで価格的には596,000円となるのだが、その威力は大きい。オーディオにおける各コンポーネントのセッティングに関する共通のセオリーとして次のようなことが言えるだろう。それらを設置しようとするラック、もしくはラックを置かれる床の構造と傾向には次のような音質の特徴が感じられるのである。木製のラックや床が畳や絨緞やカーペットのような柔軟性のある材質で構成されている場合、それらに置かれたコンポーネントの音質も柔軟性のある質感に変化する。これを肯定的に表現すると弦楽器は滑らかになり、ヴォーカルはふっくらと丸みを帯びて聴きやすくなる。否定的に表現すればベースやドラムなどリズム楽器の切れ味が鈍くなり膨らんでしまい、ヴォーカルの口元は大きく見えてしまい解像度の悪化が感じられる。それでは対照的に金属性のラックやコンクリートに直接タイルを貼ったような硬質な床などにコンポーネントを置くとどうなるか。肯定的に表現するとリズム楽器の切れ味が鋭くなりタイトで引き締まった低音表現になるが、弦楽器は乾燥気味にドライな表現になり、ヴォーカルの口元は確かに小さくなるのだが否定的な面もありタ行やサ行の子音の発音はシャープになり刺激成分を含むようになる。一般的には硬質な素材によるセッティングの方がエコー成分が際だつのだが、スタジオ録音では余韻として認識したい響きが余分な付帯音として違和感を感じさせてしまうのである。このような環境による音質変化を経験として認識している私から見て、ゾウセカスのラックは限りなくニュートラルな傾向をコンポーネントに提供してくれるのである。言い替えれば、畳の上にゾウセカスをセットすると低域は引き締まりエコー成分の表現が向上する。逆にガチガチの床にゾウセカスを使えば弦楽器とヴォーカルに潤いが添加され滑らかさを増す。しかし、低域のリズム楽器の切れ味は鈍くなるどころか、逆に重量感を増してくるのである。つまり、あらゆるシステムに対して音楽的な環境ホルモンを整備し、中立的な音楽表現へといざなってくれるのがゾウセカスなのである。これらを逆説的に考えれば一旦ゾウセカスを知ってしまうと、どんなに高価なシステムであろうとセッティング環境の不備によって本来のバランス感覚を喪失しているのではないか、という強迫観念のような考えが頭に浮かび安心して聴けなくなってしまうのである。まさにオーディオの落とし穴である。従って、私はここで演奏するシステムの音質には妥協したくないという考えからゾウセカスの導入を決断したのである。初めてこのフロアーに足を踏み入れたお客様に対して、私はいつも何げなく演奏をはじめ皆様からひとしおの評価を頂いているのだが、こだわりのデバイスを一つずつ外しながら隅々まで解説をしていくと私のノウハウと演奏のクォリティーがやっと理解されるのである。つまり黙って聴かされる分にはノウハウの結晶を理解されない場合が多いのである。試聴対象となる商品に対して、それらのコンディションを左右する設備的なオプション群をどこまで取り入れるのか。それは、ひとえに私のこだわりでしかない。言葉を変えれば設備として不十分な環境によって、本来発揮されるべきコンポーネントの能力が減じて表現されることを私は極力避けたいのである。これは販売においてもハイエンドという思想を貫きたいという私の願望でもあり、数あるハイエンドオーディオの設計者たちに対する礼儀であるとも心得ているのである。
さて、ずいぶんと前置きが長くなってしまったが、こうしたこだわりから黙っていられないようなエピソードがPADによってもたらされたのである。当フロアーにおいてジェフロウランドの製品を取り上げ、その販売実績においても私はプリアンプのコヒレンスでは発売以来の通算販売台数で40台を越える実績をもっている。ほぼ同数に近い同社のパワーアンプも販売してきたわけだが、ここにもオーディオの落とし穴があったことが判明したのである。フル・バランス伝送のコヒレンスには入出力ともバランスタイプのキャノン端子しか装備されておらず、モデル2とモデル6のパワーアンプも同様にバランス入力しか装備されていない。同社はアンバランス入力に対してはRCAピンからキャノンプラグへ変換するアダプターを付属、あるいはパーツとして販売することで対応してきたのだが、この変換プラグが問題であった。というよりも私自身がそのクォリティーに何の疑問も持たずにいたし、パーツとして同型式のアダプターを求めるユーザーにも2個1万円でこれを販売してきたのである。この私の不勉強と認識不足のためにコヒレンスを付属アダプターで聴いておられるユーザーには「お詫び状」までお送りした。
そのきっかけとなったのは、アンバランス1系統しか出力がないイルンゴオーディオのモデル705をコヒレンスにつなぐ際のことである。ACドミナスの威力にPADに対する認識を新たにした私は、偶然にもピン・キャノン変換のアダプターをはじめとして各種変換アダプターをPADが商品化していることを思い出し早速今井氏に発注したのである。翌日に届いたクライオアダプター(CRYO ADAPTOR)をジェフロウランド純正のものの隣の端子に接続し、イルンゴからのアナログ出力をコヒレンスに入力し、このアダプターだけの違いを比較試聴したのである。最初は前述のヨーヨー・マをかけた。ジェフロウランド純正のアダプターで聴く音は以前から馴染みのあるもので、イルンゴの特徴と魅力を私が評価した当時の分析が記憶としてよみがえってきた。ピン・キャノンと変換しなければいけないのでアンバランス・ケーブルにはトランスペアレント、XLO、カルダスなどの最高級ケーブルを使用し、他にこれはという比較対象を思い浮かべていなかった私は、この状態での演奏に何の疑問を持たず今思えば安心してイルンゴの音質を評価してきたのである。期待とも不安ともとれる心境で純正アダプターからPADのクライオアダプターに差し替え、P−0を再スタートさせたその瞬間である。ABOとヨーヨー・マの演奏全てが潤いと滑らかさを忽然と取り戻し、まさにACドミナスによってもたらされた演奏の浄化が起こったではないか。純正品もそうだが、キャノンプラグ1個分の内容積と加工手段を考えると内部に使用されるケーブルは恐らく2センチ程度のものだろう。この本当にわずか2センチのケーブルしか相違点はないはずなのに、なぜこんなにも音質が違うのか。私は今井氏に説明を求めた。このプラグ内部に使用している配線はドミナスグレードのものを採用しており、プラグの接点を含めた全ての金属部分にはクライオジェニクスを施しているという。純正の2個1万円に対してクライオアダプターは2万8千円と割高であるが、この音質差を経験した人には価格差を通り越えた恩恵となることだろう。事実、私と同じ比較試聴をしたお客様はその場でご購入頂いているのである。イルンゴを評価してきた私がこんな落とし穴にはまっていたことを、たった今まで気が付かなかったとは情けない。イルンゴオーディオの楠本氏には全面的に音質評価をやり直して報告をしなければならないだろうし、コヒレンスやジェフロウランドの一部のパワーアンプで変換アダプターを使用されている方々に対しても同様である。全長わずかに62ミリという製品が100万円以上もするコンポーネントの音質評価に対して、まさしく首根っこをおさえるほどの支配力をもっていたとは何たることであろうか。これを知らずに高価なコンポーネントを使用されていた皆様に、あるいはアダプターに構わずにイルンゴをお聴かせてしまった皆様に、私は平身低頭の姿勢でお詫びを申し上げる。そして、必然性から各種変換アダプターを使用せざるを得ないユーザーの皆様に、心からPADの「CRYOGENICS High end Device」をお勧めするものである。また、私の文章だけでは納得できないという方には実物を貸し出しする用意もあることを最後に付け加えておくことにする。
第三章「インターコネクト・アナログドミナス」
ACドミナスとクライオアダプターの参入でノーチラスにもずいぶんと磨きがかかってきた。この上は音楽信号そのものを伝えるインターコネクトケーブルが興味関心の対象になるのは必然のことであり、早速今井氏にバランスのインターコネクト・ドミナスを求めたのである。すると今井氏から逆に質問された。「わかりました。バランス・ドミナスをお送りしましょう。ところでホットは何番ですか。」今まで受けたことのない質問である。私がこれまでに聴いてきた何十万円もするケーブルでさえもホット・コールドの極性指定を問われたことなどなかったのである。驚いたことにPADのインターコネクトケーブルは、ごく一部の製品を除いては全てホット・コールドの極性を指定して製作しているという。ホット側のコンダクターには、金、銀、銅、プラチナ、アルミ、イリジウム、ロジウム、など7種類の素材を溶解したオリジナルの合金で一本のストランドを作り、それら9種類を撚りあわせて使用している。コールド側にも同様な合金によるストランドを13種類組み合わせてひとつのバンドルを構成している。他のケーブルメーカーがまるで気にもしていない着眼点さえもオッド氏にとっては重要なことなのである。それでは、なぜホット・コールドの区別で違う材質のワイヤーを使用するのであろうか。
これがまた量子物理学の世界で理論が展開されるために私の頭ではついていけそうにもないが、PADはこのホット・コールドの極性の違いによる物理的な根拠を実測の上でちゃんと用意していたのである。二つのコンダクタ(ホット・コールドの導体)のシグナルパスにビューポイントを設定し、その観測点を電子顕微鏡を使って観測したのである。2回のシグナル・ランに対して、まったく同一の電圧と電流値を設定し最初はプラス1ボルト、1アンペア/1秒、で観測すると、一秒間に6・28×10の18乗個のプロトン(陽子)が通過していったという。次にマイナス1ボルト、1アンペア/1秒と極性を反転し同条件によって2回目のシグナル・ランを行なったところ6・24×10の18乗個のプロトンが通過したという。つまりマイナス側リターンシグナルにおいて0・04×10の18乗個のプロトンが少なく流れたということで、この差は0・637パーセントの速度差として言い表せる。この差は敏感なリスナーであれば聞き分けることが出来るというのがオッド氏の説明なのである。オーディオシステムにおいて複数のバランスケーブルが使用されていれば、このスピードの違いは累積されより顕著になるという。PADが作るバランスケーブルはリターン・ワイヤーの信号速度とマッチするよう、ホット側の信号速度を遅くしてこの問題を解決しているというのだ。いやはや、何とミクロの視点をもってケーブルの設計にこだわりを持っていることか。知能指数がいくつかは知らないが、ジム・オッド氏はオーディオケーブルにこれほど高度なパラメーターを見い出し、その問題解決のために妥協を惜しまないのだから他社と同レベルで語れるはずもない。まったく、凄いの一言である。
さて、ここで私は大変なことに気が付いてしまった。送られてきたバランス・インターコネクト・レヴィジョンBシグネチャーシリーズのドミナス3番ホット仕様1メートルの価格は1,200,000円である。しかし、当然2番ホットの製品も用意しなければいけないことから、同一商品での在庫負担は2倍となる。今井氏にきいてみるとPAD社の各種ケーブルでは電源ケーブルでは50センチ単位で3メートルまで、スピーカーケーブルは標準仕様の1.5メートルのみ、インターコネクトに関しては1と1.5メートルをアンバランス、ホット極性でバランスを2種類を国内在庫で持つようにして、それ以上の長さになると6週間の納期で特注扱いとされるそうだ。これは経営的に見れば大変大きな負担であろう。今井氏に尋ねてみると、そもそもPADの工場に行ってみても材料はあるが製品としての在庫は一切ないという。PADは世界中からのオーダーには納期6週間の完全受注生産体制をしいており、自社在庫はゼロという羨ましい経営方針の会社なのである。アメリカ国内でPADの商品を取り扱っている販売店は約30店あるそうなのだが、みな6ウィークという納期を設定して販売しているらしく店には在庫をおいていないという。また、日本をはじめとして10数か国に輸出をしているが、それら相手国の輸入元も一律6週間の納期で受注発注のシステムであるという。ということは世界的に見てもシーエスフィールドが最も多くの在庫を抱え即納体制を維持してPADを販売していることになる。日本の商習慣を考えるとすべて受注発注の納期6週間という販売方式も馴染まないだろうし、何よりも即納可能というユーザーサービスでの貢献を果たすことからシーエスフィールドが大量の高価な在庫負担を負うことを今井氏は決断したという。これらの背景をもとにアメリカドルでの現地価格に対して単純な為替の換算で約2倍の定価を日本でつけていることになり、私がこの事情を書いても良いかと今井氏にたずねたところ自信ありげに「事実ですからかまいません。どうぞ」とご返事を下さった。私は定価で販売することはないので実勢価格として表現するのは難しいが、私ども小売店サイドの事情も含めてプライスポリシーを明確に持っておられる経営方針には敬意を表するものである。
PADに関わらず海外にこんな素晴らしいものがある。ということを知らせてくれるのも輸入商社である。そして、その実物を私の求めに応じてサンプル提供してくれるのも輸入元である。どうだろうか、高価な商品を購入するにあたって本当に納得できるものかどうかを試すことができるというサービスに価値はないだろうか。また、その購入前のサービスにコストがかかっているとしても、ユーザーの満足感に直結するものであれば認めることは出来ないだろうか。実は、私のフロアーでドミナスを聴き、自宅で試したいという申し出を何件も頂戴しているのだが、今井氏は私の要請を快く引き受けて下さった。このようなビフォアー・フォローによって製品の価値観が理解され間違いのない商品選択が出来るということに価値はないのだろうか。通信販売や並行輸入業者では無理な相談であろう。また、PADでは自社の製品に「ライフタイムワランティー」という考え方で有償無償のケースバイケースはあれど半永久的サービスを実施している。まずプロテウス、ドミナス、そして後ほど説明する新製品のRLSなどは将来レヴィジョンBからレヴィジョンCへモデルチェンジされた場合、有償ではあるがバージョンアップに対応するという。ちなみに96年にレヴィジョンAからBタイプへ全モデルがアップグレードされており、当時もこれらのサービスを実施している。最先端のデジタル機器や一部の超高級コンポーネントならいざ知らず、オーディオケーブルにおいてバージョンアップサービスを宣言しているという例を私はこれまでに聞いたことがない。そして、液体シールドを大きな特徴とするPADにおいて、大変原始的なトラブルとして液漏れにはどのように対処しているのか。この世に絶対と言えるものはないの例え通り、これまでPADを輸入して7年間という期間の中では正直に言ってほんの数例だが液漏れというトラブルはあったという。PADでは出荷するケーブル一本一本にシリアルナンバーを付けて生産段階のスペックを記録しており、その生産ロットで使用された純正の液体を再注入し封印するというノウハウもシーエスフィールドはトレーニングされているという。ちなみに従来のPADケーブルではレヴィジョンAの時代にはモデルによって赤、青、緑、透明と色々であり粘性も異なる液体が採用されていたが、レヴィジョンBでは粘性もさらっとした弱いものになり青色に統一され、現在のシグネチャーシリーズでは紫色の液体に変更されている。これらすべての液体もシーエスフィールドは純正パーツとして完備している。しかし、これらの液漏れについてはほとんどが製造段階の不良と見なされ、シリアルで管理されシーエスフィールドを経由して輸入されたものは新品と交換するというのが慣例であるという。私はこれらのサービス体制にシーエスフィールドの責任とPADに対する信頼と情熱を感じるものであり、同社が築き上げたPADの知名度とパフォーマンスの実証を横取りする形で並行輸入業者が横行するという事態に深い同情の念を禁じえない。むしろ私の立場からPADの素晴らしさを実体験として確認し納得されたユーザーに、責任あるシーエスフィールドがハンドリングしたPAD製品を提供し末長く高品位な音楽を楽しんで頂きたいと願っている。
さて、92年にPADの輸入をシーエスフィールドが開始したのだが、最初に取り扱いを開始したのはアクエアス、マクシマス、コロッサスのレヴィジョンAからであった。翌93年にはミズノセイ・シリーズとシステム・エンハンサーのレヴィジョンAがスタートしている。94年にプロテウス・シリーズ、エクステンションボックスのレヴィジョンAとCRYO−C2がデビューしており、96年には前述の全シリーズがレヴィジョンBにモデルチェンジを行なっている。そして、この年の12月に登場したのがドミナス・インターコネクト・レヴィジョンBである。翌年にはドミナスはレヴィジョンBタイプとしてデジタルケーブル、スピーカーケーブル、そしてACケーブルへとシリーズを完成させた。同じ97年にはエクステンションボックスやシステムエンハンサーもレヴィジョンBとなり、レヴィトン社とのタイアップで完成したCRYO−L2も発売されている。98年にはRLS(レディエント・ライト・ソース)シリーズのレヴィジョンBがサンプルとして入荷し、本年1月より前述のレヴィジョンBはシグネチャーシリーズへと全モデルが改定されたのである。その最新型のドミナス・インターコネクトが私のもとに送られてきたというわけである。
1937年旧ソ連のエストニア共和国に生まれレニングラード音楽院でエフゲニ・ムラヴィンスキーに師事し、1963年からエストニア放送交響楽団の音楽監督をつとめ指揮棒を振るようになったのがネーメ・ヤルヴィである。1980年にアメリカに移住してからは欧米各地の主要なオーケストラやオペラの舞台に客演として招かれていたが、82年からスウェーデン第二の都市エーテボリに1905年に設立されたエーテボリ交響楽団の音楽監督となりヨーロッパ屈指のオーケストラに育て上げたのである。そのネーメ・ヤルヴィが59歳の時にエーテボリ交響楽団と共に録音した名曲アルバム「ロリポップ」(POCG-10035)の冒頭にハンガリー生まれのフランツ・レハールが作曲した「ワルツ金と銀」が収録されている。これが次なる課題曲である。マークレビンソンのNO.30.5Lはバランスのアナログ出力がパラレルで2系統装備されているので同時に2本のケーブルを接続して比較試聴するのに大変都合がいい。片方には従来からリファレンスとして使用しているカルダスのヘックスリンク・ゴールデン5Cを、そしてもう片方にドミナスを接続しコヒレンス2のライン1にカルダス、ライン2にドミナスを入力する。
これまで述べてきたようにノーチラスのチャンネルディバイダーとD/Aコンバーターを除くコンポーネントにはすべてACドミナスを、そしてゾウセカスを採用して万全の体制で試聴に望むことになった。
長年使い込んだカルダスは上々の展開を最初から聴かせてくれ、解像度やホールエコーの表現に何の不満もない、と思われたのだが…。しかし、それはここまでのことであった。ドミナスに切り替えた瞬間にホールのスケール感が瞬間にして拡大する。まず最初に弦楽器群全員がトゥッティで演奏する冒頭部分で聞き分け出来る楽器の数が急増する。カルダスでは弦楽器の一群を束ねていたようである。ドミナスはそれらを拘束していた解像度の限界に相当するロープをはらりと解き放ち、ユニゾンで瞬間にしてフォルテに移行するフレーズに楽器個々の分散をきちんとえり分けて聴かせるではないか。次にトライアングルほどの小さな楽器がホールの隅々まで届かんとするかのように奏でられ、ハープが左方向で奥行き感を伴って短いフレーズを演奏する。ちょっと待てよ、このトライアングルとハープのエコーが息を引き取るまでの滞空時間はこんなに長かったろうか。ライン1に戻してもう一度、ドミナスに再び戻して執拗にこれを比較する。ドミナスの方が彗星の尾のごとく「フゥーッ」とエコーの存続する時間が明らかに長い。そして、この曲の見せ場ともいうべきオーケストラ全員が、いっせいに強力なフォルテッシモで同じ音階を奏でたかと思うと指揮棒がピタッと止まり、ストップウォッチで測れそうなほど長いホールエコーをこれでもかと響かせる。しかも、ノーチラスはそのホールエコーをこの部屋の天井へ向けて展開していくので爽快きわまりない。このオーケストラ全員が瞬間に発生した楽音の余韻はまったく同じだろうか。これも数回繰り返して比較する。ドミナスの作り出すホールエコーの方が重厚な印象を与える。言い替えれば低音楽器群の余韻も、それ以外の楽器群と同様な情報量としてエコーを形成しているのがわかる。カルダスの方はどちらかというと主旋律楽器群の方が際だって聴こえ、細身の印象が優先されていたのだ。そして、あの懐かしくも有名な旋律が始まった。一言でいってドミナスで聴くこのメロディーには快感を覚える。スムーズで滑らか、微塵のストレスも感じさせることなく展開していく演奏の実に見晴らしがいいこと。
ACドミナスで体験したPADによる音楽の進化論が、あたかもゆっくりとページをめくるように進行していくではないか。豊かな余韻に土台をしっかりと築かれたオーケストラの演奏は、まさに朗々と響くのである。各パートの発する少数楽器の演奏はノーチラスが見せてくれるステージの全景にポッと浮かんでは消えていく。特に管楽器がピシッと姿勢を正してテンションが張った演奏でありながら、演奏者の立っている場所から天井へ向けてエコーを吹き上げる様は筆舌に尽くしがたい快感である。最後の演奏がことさらホールエコーを引いて完全な静寂が戻るまでボリュームを下げることが出来ない、興奮と安堵感の入り混じったオーケストラの存在感をドミナスは目の前に提示してくれた。脱帽である。
設立は1983年アメリカはコネチカット州スタンフォード、そこににトム・ジャングが主宰する高品位ジャズレーベルdmp(デジタル・ミュージック・プロダクツ)がある。ワディア製の20ビット高性能A/Dコンバーター、ヤマハ製20ビットデジタルミキサー、スイスFMアコースティックのマイクアンプなど最新最高のハードウェアを駆使し、同時にプレイヤーとの一体感や緊張感をライブとして収録するという感性を重要視し世界的な評価を勝ち取ってきたミュージックメイカーである。そのdmpが95年に制作したアコースティック・ビッグバンドのソフト「カーヴド・イン・ストーン」を最近テスト用として頻繁に使用している。この1曲目「テイク・ジ・Aトレイン」が驚くべき事実を教えてくれた。マークレビンソンのNO.30.5Lは2番ホットで動作しているので、これまでに述べてきた3番ホットのジェフロウランドで構成されるノーチラスシステムで使うときにはどこかでアブソリュートフェーズ(絶対位相)を反転させる必要がある。プリアンプにもフェーズ切り替えはあるのだが、私の目的にはD/Aコンバーターでそれを行なう必要があり、NO.30.5Lにはちょうど位相反転スイッチがあるので懸案の実験には好都合なのである。
前述のとおりバランス・インターコネクトのドミナスを求めたおりに今井氏には3番ホットのドミナスをお願いしていたが、正直に言ってキャノンケーブル自体がホット・コールドの極性を持っていることが信用できなかったのである。なぜかと言えば単純にこれまで私が聴いてきたどんなに高級なケーブルでも、ホット・コールドの極性についてこだわりを持っているメーカーはなかったからである。アースをフローティングしてプラス・マイナスを別のアンプで伝送する。つまりアース電位をアンプのシャーシ・アースに依存しないバランス伝送で、ホット・コールドの各々に専用の導体を設計するという考え自体がナンセンスに思えていたのである。また、一般のスピーカーではアブソリュートフェーズの反転によって音質差を大きく出すものもあるが、リニアフェイズと球面波再生を実現しているノーチラスにおいては絶対位相の違いはほとんどと言っていいほど認識することは出来ないのである。この特徴を利用してドミナスのこだわりを実際にテストしてみようというのである。
まず前述のセッティングにおいてカルダスを使用し、課題曲とした「テイク・ジ・Aトレイン」をそのままで聴く。そしてNO.30.5Lの位相反転スイッチをオンにして出力を3番とし、各チェックポイントに注意しながらリピートする。ジェフロウランドとフェーズが一致した状態を観察してみると、再生音の情報量変化としては感じ取ることが出来ず、水平方向に若干の定位感と拡がりの変化は認められるものの、よほどの熟練した耳で事前に変化の内容を知らせておかないとわからない程度の違いである。これで現在のノーチラスに一般的なバランスケーブルを使って絶対位相の反転実験を行なっても、その結果として簡単に認知出来ない程度の音質差しか発生しないことが確認出来た。蛇足ではあるが、この実験は複数のお客様にも参加して頂き確認も行なっている。それらのユーザーも違いはほとんどないという印象をもたれていたのである。そして私はNO.30.5Lを再び2番ホットに切り替えてからドミナスのライン2へと切り替えた。「いいじゃない。ホーンセクションのタンギングがシンコペーションをより効果的にしてテンションを高め、かつエコー成分がスムーズに拡散している。これだよ、これ!」と、先程のオーケストラで感じ取った変化にビッグバンドの演奏をなぞらえ、異なる音楽においても自分の分析が正しく変化のベクトルを察知していることに満足感を覚えながら聴き進む。「よし、それでは。」といよいよNO.30.5Lを再び3番ホットに切り替える、すなわちドミナスが指定している極性に一致させて同じ曲をリピートした。その時である。「ちょっと待って、何か違うよ、これは。」と、いきなり表れた変化に言葉が見つからず二度三度と繰り返し聴き直す。「そうか、ここだ。」と、P−0のリモコンを手に取るとA−B区間リピートを設定した。演奏開始直後の0分53秒から1分39秒の区間でルー・ソロフの強烈なトランペット・ソロが展開する。右側のノーチラスのやや内側に定位するルー・ソロフのトランペットは、洗練されたテクニックと高度な録音技術によって見事なフォーカスを結び、演奏の強弱によってリヴァーブの量が変化するような余韻の描写力が光るスリリングな演奏である。これを集中して聴くと思ってもいなかった情報量の変化が確認された。
3番ホット仕様のドミナスに対して意識的にホットを2番と3番に切り替えて入力したわけだが、極性が一致した途端にルー・ソロフのトランペットの背後に空気感とも言えるスタジオ壁面の反射音がオーラのように存在しているのが聴こえはじめたのである。同じ空間で演奏するビッグバンドの中で、トランペット単独にリヴァーブをかけることは不可能だろう。そうするとルー・ソロフのヒートアップしたトランペットが叫んだ瞬間にフッと彼を取り囲むエコーは人為的に追加されたものではないだろう。しかも、3番ホット仕様のドミナスに2番ホットで同じ曲を送りこむと、それはウソのように消滅してしまうのである。もちろん、これまでに使用した高級ケーブルでは2番ホットの逆相で入力した場合の再生音よりも情報量が減ってしまうので比較にもならない。ということは、適切にフェーズを合わせたときにドミナスが本領を発揮したという仮説以外に信ずべき答えはないではないか。これには参った。ひねくれ者の私は、このままで信じきるほど素直な人間ではなかった。すぐさまヨーヨー・マのディスクを持ってきて同じ実験を繰り返す。「おい、そりゃないだろう。」と、内心ぼやく声が思わず上がってしまった。AB0の二人のオーボエ奏者が導入部で奏でるパートでは先程と同じ背景のエコー感が増量され、というよりは本来録音されていたはずの余韻感が見事に蘇生され、演奏されている空間イメージを更に拡大する方向へと更新しているのである。そして、驚いたことにヨーヨー・マが演奏するバロック・チェロ自体に質感の変化をもたらしているではないか。チェロの楽音の輪郭と表現できる音像がノーチラスのセンターで三次元的な集約を見せているのだが、このディティールの描き方がより鮮明になりヨーヨー・マの演奏をポッと中空に定位させるのである。そして、これに一層の美観を添えるのがルー・ソロフの時と同じようなオーラとでも例えたらよいのだろうか、バロック・チェロの微細な響きをすくいあげるようにフォローする本来あるべき余韻の出現が、なんともため息を催すほど演奏の景観にヒーリング効果をもたらすのである。
第四章「デジタル・ドミナス」
4月下旬のある土曜日、このところ週末のたびに天候が崩れ今日も朝から雨の降る一日となった。営業的には低迷を余儀なくされるのだが、来客数の少ないこんな日こそじっくりと試聴出来るので逆に私は忙しい。届いてから一週間ほどかけてバーンインしてデジタル・ドミナスがそろそろ聴きごろとなってきたのである。まず最初にお断りしておかなければならないが、このデジタル・ドミナスは両端にRCAピンが付いているアンバランスタイプである。キャノンプラグはノイトリック社のものが世界的にも汎用とされているが、RCAピンプラグとなると数あるケーブルメーカーの中でも自社でプラグまで制作しているという会社は少ない。オーディオクェストは日本製の特注品をすべてのラインアップに使用しており、トランスペアレントやシルテックなどはドイツのWBT社から供給を受けている。アメリカのメーカーでも自社で、正確に言えばそのメーカーの設計仕様において外注であっても独自のものを制作しているという意味だが、オリジナルのプラグを自社製品に使用しているメーカーは多くはない。XLO、カルダス、そしてPADなどがその代表的な事例であろう。今井氏から聞いたところによれば、PADも液体を含むケーブルの自重を支えるため当初はWBT社製のピンプラグを採用していたという。しかし、今一つオッド氏のおめがねにはかなわず次にはカルダス社製のものへと変更された。だが、これでも物足りなさは解消されず、結局は精密な金属加工を専門としNASAにも納入実績があるというコリンズという専門業者に削り出し加工を依頼して自社オリジナルプラグを使用するようになったのである。シーエスフィールドが以前修理のためのパーツとしてこのコリンズ製ピンプラグを1セット分4個を注文したことがあるという。その時の請求書を見て今井氏は驚き呆れてしまったそうなのだが、何と4個で5万円相当の請求額であったという。これもPAD独自の配合による合金製であり、CRYO−L2とレヴィトン社の関係と同じように、どうやら原材料の合金をPADが作りコリンズ社に納め加工し、それを再びPADに戻してクライオジェニクスと物性処理を施して製品化しているらしい。このピンプラグは他社のように外周のマイナス側を絞り込むというロック機構を一切持っていない。外周部は肉厚のある素材でクライオジェニクスしており、剛性は非常に高くなっているのだが他社のようにペンチなどで締め付けようとすると簡単に折れてしまうという。これもオッド氏のこだわりであろうか、アンバランスタイプのマイナス側の接触部分も信号のリターン側という認識に立ってか重厚な作りのプラグである。このプラグがデジタルケーブルだけでなく、廉価版のミズノセイを含むアナログのインターコネクトにもすべて採用されているのである。プラグのコストを考えるとミズノセイなどはお買い得と思えてしまう。
さて、ここで余談であるが興味深いエピソードがある。PADから送られてきた英文の文献にはハンダに対する記述とこだわりがあった。
シーエスフィールドがケーブルを修理する際には当然PAD指定のハンダを使用しているのだが、このハンダがまた凄いのである。PADではハンダ付けによる接合面には新たな合金が生成されると考えており、単なる錫と鉛の混成物が電気的な接点として優秀であるとは考えていないようである。ちなみに今井氏が実験したところでは一般的なハンダをスピーカーケーブルの代用にすると、ほんの短い長さであっても高域がガタ落ちになり実用にならないという。しかし、PADのハンダを1.5メートルの長さでスピーカーに接続すると、何と市販の廉価なケーブルよりバランスが良かったという。PADのハンダの主原料はもちろん錫と鉛であるが、それに金、銀、銅、はてはイリジウムを含む合計16種類の金属を融合して作られているという。そして、融点は大変に低く設定されており、ジャスト160度Cという規格を表示している。いやはや、この徹底した細かな配慮を今まで知る日本人は少なかっただろう。あえて付属情報として書き加えたものだが正直に言って私も驚きである。
話を戻すが、コンシュマー用デジタルケーブルにはインピーダンスで2種類、プラグ形状において3種類が汎用規格となっている。AES/EBUのバランス伝送では110Ω、RCA同軸は75ΩでピンとBNCの二種類のコネクター方式となる。さて、私が知り得る数々のメーカーでは、これら3種類の伝送方式(TOSリンクとSTリンクの光学伝送を含めれば5種類)の中でどれを基準として製品の音質を決定するのだろうか。私が知り得る範囲でメーカーのリファレンスとなっている伝送方式を列挙するつもりはないが、今試聴しようとしているエソテリックP−0はRCAピンのアンバランス伝送を基準とし、マークレビンソンは自社内のヴォイシングではAES/EBUのバランス伝送を中心にしている。私も経験上同じメーカーで同じグレードのケーブルを使用し、同軸型のピンとバランスのAES/EBUの両方式を聴き比べたことがあるが、各々の特徴を分析した結果で同軸型ピンプラグのデジタル・ドミナスを要望したのであった。この両方式の音質的な相違点や特徴をここで述べることは、色々と誤解が発生する可能性があるので今回は割愛させて頂くことにした。
これまで私がここで使用してきたデジタルケーブルは種々様々である。オーディオクェスト、トランスペアレント、XLO、ワイヤーワールド、カルダス、ゴールドムンド、NBS、などだが、どのメーカーもトップモデルを使用してきた。さて、ここでデジタル・ドミナスを試聴するにあたってはこの中から数種類のケーブルを採用し、多いときにはドミナスに対して4種類のケーブルと比較試聴したが、これら対象となったメーカーはブランド名を明かさずに「その他メーカー」として表現することにした。理由は単純である。それらのケーブルにもグレードと個性があり、試聴の過程で私にはそれらがわかってしまうために比較対象の解説量が膨大になってしまうからである。
まず最初にヨーヨー・マを聴くことにして、他社のケーブルは単純に価格の順に3、4種類を聴いてから最後にドミナスというパターンを繰り返した。価格の順といっても4万円から8万円程度のものであるが、一部のメーカーを除けば高価な部類に属する製品群である。そして、私も従来はこれらをリファレンスとしていたのであって、一通りの再生音に何の疑いや不満も持たなかったのである。これまでに述べてきたACとインターコネクトのドミナスを聴くに当たっても当然これらのケーブルを使用していたのである。本当にひょうきんなもので、この価格の順にクォリティーが高まってくるのが感じられるのだから面白い。さあ、いよいよドミナスの番である。リモコンでポーズをかけて配線を変える。肩の力を抜いて頭を今までの高さに調整し、正面のノーチラスを視野にいれる。いざスタート。と、その瞬間からである。「そりゃあないだろう。今までリファレンスとしてきたものは一体なんだったんだ。」と、同じCDシステムとは思えない視野の拡大に内心では愚痴とも言えるつぶやきがもれてしまう。これほどあっけなく昨日までの基準が根底からひっくり返ってしまったのではどうしようもない。デジタル・ドミナスがP−0を倍の価格に、マークレビンソンのNO.30.5Lに少なくとも32万円以上(新製品のNO.30.6Lを意識しての例えです。他意はありません。)のクォリティーアップを何とも簡単に提供してしまったのである。これには驚いた。数あるデジタルケーブルをもてあますほどに使い続けてきたというのに、現行法式のCDの音をここまで向上させてしまってはスーパーCDの出番がないほどである。根本的に演奏空間の次元が異なる様子を見せられ、戸惑う私は同じクラシック系の課題曲「ロリポップ」の「ワルツ金と銀」で同じテストを繰り返した。
ヨーヨー・マを一本の赤鉛筆とし背後のABOは黒い普通の鉛筆9本としよう。これまで他社のデジタルケーブルでは、これら合計10本の鉛筆を手に握っていたとご理解頂きたい。赤鉛筆の一面は見えるが当然ほとんどは隣り合った黒鉛筆に隠されている。ほかの9本もきっちりと握られていては側面だけ、あるいは頭の一部や削られた芯の先しか見えないというイメージである。つまり10本の鉛筆の束は密着しており、握られた手の中ではひとつの塊に過ぎなかったのである。ところが、ところがである。デジタル・ドミナスは握っていた手の力を吸い取り演奏の力みを取り去ってくれただけではなく、鉛筆を1本ずつ机の上に並べた状態をいとも簡単に作り出してしまったのである。赤鉛筆と例えたヨーヨー・マはあっさりと全身像を見せるようになり、明らかにバックの楽器群とは立体的な分離を聴かせるのである。残りの鉛筆は整列状態となり当然個々の楽音における解像度が豹変していることに気が付く。弦楽の個々のパートが浮き彫りになるにつれて木管楽器の点在するようすが更なるフォーカスの収束を見せ、楽器の数が激増しホールの大きさは一回り拡大する。演奏空間が大きくなった分だけ個々の楽器が浮き彫りになる、言い替えれば塊であったものがひとつずつに分離すると鉛筆の正面だけではなく側面や両端がつぶさに観察できるようである。オーケストラもまったく同じイメージで理解することが出来た。特に弦楽パートは他社のケーブルでは一握りの鉛筆であり、集合体としての一面しか見えていなかったようである。ところがデジタル・ドミナスはそれらの鉛筆を器用に机の上に垂直に立てて並ばせたかのような描写に変えるのである。これは面白い。ひと塊であったはずの弦楽パートの個々の楽器が整列するものだから、そのヴァイオリン一本一本の微妙な差異が音になって聴こえ楽員の数が数えられそうな分離のよさを示すのである。
「待てよ、この変化は何度も聴いてきたものと同じだ。」と気が付く。ACドミナス、インターコネクト・ドミナス、などで経験してきた変化の方向と同じではないか。非常に単純な結論を思いついた私は残る2曲の課題曲を連続して聴くことにした。他社のケーブル数本と2回にわたって聴き比べるので同じ曲を10回以上繰り返すことになる。「ああ、やっぱりそうだ。」この数日間というもの電源とインターコネクトに1本ずつドミナスを加えるごとに起こった変化がことごとく再現される。どうやらドミナスをノーチラスに近い部分から採用していったことが幸いであったようだ。壁コンセントからACドミナスでエクステンションボックスへ、これでパワーアンプとノーチラスのチャンネルディバイダーに変化が起こった。いや、変化というよりは各種の干渉から開放された本来の音に戻ったということだろうか。次に各々の付属ACケーブルをドミナスへ、そしてフロントエンドへとシステムの出口から入り口に向けてドミナスを増やしていった。そして、最後にシステムの最も上流と言えるデジタルケーブルにまでたどり着いたのだが、スピーカー周辺の下流においてこれほどの環境整備がなされていたからこそ起こった変化なのだろうか。いや、デジタルケーブルだけでも同様な変化は起こるだろう。しかし、システムの最上流にいくら高価で高性能な浄水装置を取り付けて水質を良くしたとしても、混濁している下流の水に流し込んだのでは意味がない。むしろ、限りなく透明で澄んだ下流の水質を維持しておけば、そこへ流れ込んだ水の色や香りや味も判断できるだろう。
デジタル・ケーブルの品位は他社との比較では比べようもないほど、ずば抜けているということが感じられた。そして、それはドミナスが作り出したトータルシステムという総合的な浄化作用を通してキャンバスを純白にした、あるいは演奏する空間に配置した音楽的な空気清浄機か、あるいはシステムを流れ下る経路の随所に設置された浄水器とも言える作用をもたらしたのであった。
第五章「ドミナス・スピーカーケーブル」
5月12日「店長シーエスフィールドから大きい荷物が来ましたよ。」と、内線で知らされ行ってみると長さ1.5メートルはあろうかという直方体の長持ちのような白いプラスチック製の容器が届いているではないか。何だこれは、と考えると今井氏からの電話を思い出した。「川又さん、ドミナスのスピーカーケーブルも素晴らしいですからぜひ聴いてみて下さい。」ははぁ、これがそうか、と箱を開けながらうなずく。中には他のドミナスシリーズと同じ太さのケーブルが4本入っている。「バイワイヤー・タイプを送りますよ。」と今井氏は言っておられたが、ドミナスのバイワイヤーは片側2本でプラス・マイナスと独立したケーブルでスピーカー側が2本に分岐しているものである。それにしても、他メーカーでバイワイヤーというとシングルと同じ太さのケーブルから芯線を細くより分けて分岐させているものが大半なのだが、オッド氏のこだわりはたいしたものである。調べてみると、この3メートル・バイワイヤーのドミナス・スピーカーケーブルの価格は379万円である。「フーン、なるほど。」と思いながら自分のフロアーに戻ると、とりあえず空いている所にとぐろを巻いて置くだけとなってしまった。なぜかと言えば、後ほど述べる先週送られてきたジェフロウランドのプリアンプ用DCケーブルの試聴予定が何人も入っているので、メインのオリジナルノーチラスを片付けるわけにいかないのである。ノーチラスは自前のスピーカーケーブルが取り付けられているので、残念ながらどんな高価なスピーカーケーブルがきても試聴対象にはならないのである。
翌週の17日、やっと時間が取れたのでドミナススピーカーケーブルの試聴を開始することにした。当フロアーでは比較試聴を合理的にこなすために、カルダスのヘックスリンク・スピーカーケーブルにキャノンプラグを取り付けた特注品を使っている。確かにキャノンプラグによる中継のために接点は増えるのだが、キャノンプラグ自身は1ピン当たり15アンペアの電流容量を持っているためスピーカーに使用しても問題は発生しない。現にBBC系イギリス製のモニタースピーカーや古くはダイヤトーンの名器2S−305などにもキャノン端子が使われていた。価格的にもメートル当たり10万円というものであり、キャノンプラグが取り付けられるギリギリの太さであることから、このヘックスリンク・スピーカーケーブルを重宝しながら長年にわたり使用してきたのである。そのカルダスのバイワイヤーは1本のケーブルの芯線を4本に分けているので、1本当たり2、3ミリの太さになっている。しかし、ドミナスはプラグへのリードワイヤーの太さが1センチ近くもあり、力を入れて曲げないと配線できないほどヘビーデューティーな仕上がりなのである。最初はジェフロウランドのモデル9TiHCとコヒレンスを使用し、フロントエンドはP−0とNo.30.6L、スピーカーはバイワイヤー端子を装備しているノーチラス801を使用することにした。ここまでの段取りを配線しながら考えていた私は、どちらかと言うと気軽に面白半分という程度の気構えであった。これまで相当高価なスピーカーケーブルも多数聴いてきたが、「ウンウン、なるほど。これでウン万円ね。」と納得すれど感動感激したという経験はあまり記憶がないのである。
スピーカーケーブルの比較はインターコネクトやデジタルケーブルほど簡単にはできない。ターミナルをぎゅっと締め付け、いつものポジションに戻って席につく。「そう、最初はやはりヨーヨー・マにしよう。」お気楽に曲を選ぶと、いよいよP−0のカウンターがスタートした…。「・・・・・・。」言葉がでないのである。そこで鳴っているのは昨日までのノーチラス801ではない。あまりの変貌の大きさに耳を奪われ、ただただヨーヨー・マとABOの演奏に聴き入ってしまうのである。「ちょっと待てよ、ヨーヨー・マのチェロはこんなに鮮明な輪郭だっただろうか。」「低音階の質感はこんなに重量感があったかなぁ。」「ABOの演奏者を取り巻く空気感はこんなに澄んでいただろうか。それにN801はABOをこんなに奥深く定位させていただろうか。」演奏が進展するごとにチェックポイントの各々がすべて更新されていく。これまでに数多くのエレクトロニクスと接続して演奏し、そのことごとくに明確な判定を目の前で示してくれたノーチラス801というリファレンス的な存在に私は絶対の自信を持っていた。その基準となるべきスピーカーが、その直前にあるケーブルの変更だけでここまで変化してしまっていいのだろうか。過去の自分の経験と分析に自信があっただけにその衝撃は大きく、なんとかこれまで下してきた数多くの判定に自信を取り戻さなくてはと、先程まで使っていたカルダスに戻してみることにした。左右8か所のスピーカー側とパワーアンプの出力端子の合計12個のターミナルを接続し直す。さて、私は従来のカルダスに戻した音を今となってはどう解釈するだろうか。ドミナスの音を忘れないようにと急ぎ足で席に戻り、P−0のリモコンを手にする。さあ、スタートだ。「ああ、何ということか。今まで何を聴いてきたのだろうか。」ドミナスで聴いていたヨーヨー・マは素足で毛脚の長い絨緞の上を歩いているような心地よさがあったというのに、カルダスに戻した瞬間に砂をまいた床の上を裸足で歩いているような違和感を感じてしまうのである。それほど澄み渡る音場感とスムーズな楽音の展開、そして力強い低域の充実感がドミナスには感じられるのである。イヤイヤ、カルダスが悪いということではない。ドミナスが良すぎるのである。これにはまいった。
ジェフロウランドのシステムでノーチラス801を使用し、ドミナススピーカーケーブルの実力を垣間見た思いであったが、No.32Lという強力なプリアンプの登場で勢いの上がるマークレビンソンのフルシステムではどうだろうか。非常に単純な期待感が胸中を満たす。そのマークレビンソンのシステムで、私はまたしても日本中の誰も経験したことのない予想外の体験をすることになったのである。
第六章「meet to the Mezzo Utopia and Mini Utopia」
99年5月19日、株式会社ノアの笹本部長から電話を頂き、話があるのでうかがいたいという。どうぞ、と返事をして待つことしばし、久し振りに笹本部長がやって来られた。アメリカでは昨年からリリースされているJMラボのユートピア全シリーズをいよいよ日本でも導入するというのだが、雑誌発表の前に私のフロアーで数か月間先行プロモーションをして欲しいというのだ。現在も同社のフラッグシップであるグランド・ユートピアは展示しているのだが、全モデル4機種を一同に並べて聴けるという日本初のチャンスを頂いたということは、私の初物好きを見抜いてのお誘いのようである。このグランド・ユートピアとJMラボに関する紹介は第37話で詳細に述べているので割愛させて頂くが、正直に言って私はこの申し出をお受けするには迷いがあった。雑誌には登場していないがマークレビンソンがセールスプロモートするハイエンド・スピーカーであるレベル、そして近々発表されるであろうウィルソン・オーディオのシステム6と、評価分析と国内導入の口火を切るプロモーションの予定が多数持ち込まれているからである。スペースもないしどうしようか、と迷った時には実物に相対し、その演奏を聴き製品そのものに説得されて取り組むのが最も自然な動機と言うものである。「実物を聴いて、その気になったらお引受けしますよ。」と生意気な返事をした私に笹本部長は快くうなずかれた。「じゃぁ、早速明日お持ちしますよ。」ここまでやってもらって気に入らなかったらどうしよう。と、自分が客になったような複雑な心境であった。
翌日の正午過ぎ、ノアの営業担当である新井氏が持ち込んで来られたのは私が指名したメゾ・ユートピアである。価格はペア164万円、横幅35センチ奥行き46センチ高さ115センチ、重量は63キロと一人でハンドリングできる適度なスケールの新製品である。これにドミナス・スピーカーケーブルをつなぎ、パワーアンプはマークレビンソンのNo.33HL、プリは当然No.32L、D/AコンバーターはNo.30.6L、トランスポートはP−0、電源および主要なケーブルはもちろんドミナスを使用する。汗をかきながら搬入してくださった新井氏に、人使いがあらい私は遠慮なくセッティングの応援を頼んでしまった。「もう少し内側、今度は間隔を20センチ近づけて。」「もう一度間隔を開いて角度を変えて…。」と、30分程度ポジョションの決定に時間をかける。「おお、だいぶレスポンスがいい、すぐ反応してくるなぁ。」と小振りなスピーカーのくせに素性のいい第一印象を聴かせるメゾ・ユートピアに好感をもった。164万円のスピーカーに対して、概算でも1600万円という法外なエレクトロニクスとケーブルを組み合わせるなんて常識外れだ、と思われる方もあると思うが私は一向に気にすることはない。どんな高価なシステムに組み入れても、基本的に問題のあるスピーカーであれば魅力は感じられない。つまり、スピーカー以外のシステムが、ダメなスピーカーを根底から叩き直して感動的な演奏を聴かせてくれるかというと絶対にそんなことはない。逆に言えばプアーなエレクトロニクスに対して、どんな高額なスピーカーを組み合わせても、エレクトロニクスの貧弱さをカバーしてくれるということもありえない。結果的に原石が粗悪であればいくら磨いても光輝くことはないのである。だから私はコンポーネント相互の可能性を価格を横並びにした製品によるデモで評価しリミテーションをかけたくないし、素性のいいものはおもいっきりその才能を発揮する機会を提供していきたいと思っている。現実的な組み合わせは、お客様の色々な都合をすべてうかがってから一つ一つ決定していけば良いことなのである。そして、私が行なうデモは価格的不均衡がある組み合わせであったとしても、その対象となるモデルにこれほどの潜在能力があるということを理解して頂くことの方がデモとして価値のあることだと考えているのである。専門店としての実演レベルが一般ユーザーをはるかにしのぐ高みになければ、訪れるお客様に夢とロマンを提供することなどできないではないか。皆様がここで試聴され、お求め頂く製品には将来こんな素晴らしい可能性があります、と無言のセールストークをコンポーネントたちが語ってくれるよう、私はいつもデモの音質を真剣勝負でチューニングしているのである。よくお客様から「こんな店は他にはないよ」という言葉を頂戴するのは、きっとこんな自由奔放でありながら再生音の質としてバランスがとれた演奏を実現しているからだと自負している。さあ、納得のいくセッティングができた。メゾ・ユートピアよ、どんな歌声を聴かせてくれるのか。
このメゾ・ユートピアの詳細を伝えるのは、今回のテーマからするとさほど多くの紙面を使うわけにはいかず、概要を解説する程度にとどめざるを得ない。しかし、世界的な高級スピーカーメーカーにユニットを供給するフォーカル社が母体となっており、そのユニットの概要は本随筆の第37話で語っているグランド・ユートピアのそれと同一の設計に基づく「サンドウィッチW」と称しているコンポジット・マテリアルを採用したコーンが最大の特徴と言えるので、ぜひ当時の記述を読み返して頂ければ何よりである。ポイントとしては、そこで解説しているテクノロジーをそのままにトゥイーターとミッドレンジに同質のユニットを採用し、口径の異なるウーファーを新設計しエンクロージャーを開発して商品化したのがユートピア・シリーズ4モデルということになる。
上位2モデルは既に国内で発売されているのだが、それらのトゥイーターとミッドレンジにグランド・ユートピアの27センチウーファーを搭載し3ウェイにまとめたのがメゾ・ユートピアである。ただし、輸入元からの情報ではシリーズ各モデルに搭載されたユニットは外見としては大差ないように見えるのだが、当然トップモデルのグランド・ユートピアやザ・ユートピアに使用しているものと量産ベースの下位2モデルでは各々のユニットの設計仕様では異なるランクの設定があるという。仕上げと外観についてはグランド・ユートピアのそれと同じデザインコンセプトであり、フロントとトップパネルは複層コーティングされたブラック・ポルシェ・ラッカー仕上げが施され、粒子の細かいメタリックが輝く漆黒の塗装が高級感を漂わせている。一般的な3ウェイは一枚のパネルに三つのユニットを取り付けるという手法が大半であるが、メゾ・ユートピアは各々のユニットを専用エンクロージャーに格納し、その三つのボックスを厚さ1インチのアフリカ原産ハードウッドである硬質アニグレード・サイドパネルで左右から挟み込む構造をとっている。トゥイーターを真中に上にミッドレンジ、下にウーファーと各々のボックスには0.5インチのすき間があり後ろを通し見ることが出来る。このように三つのエンクロージャーを完全独立とすることで各帯域間で発生するレゾナンスの干渉をメカニカルな手法で排除し、個々のユニットが極めて純粋な動作を行なえるよう配慮をしている。また、このようなコラム型スピーカーには珍しく、後ろに回ってみると各ボックス間のスリットからトゥイーターの音が盛んに聞こえてくるのがわかる。各ボックスを独立させるという機械的な設計が生み出した副産物と言えるだろうが、トゥイーターの音圧を後方にも放出することとなり、開放感あふれる高域のニュアンスと後方壁面からの反射、それにリアからの回折効果が音場を醸造するといううま味を取り入れる実に巧妙な設計と言えるだろう。
メゾ・ユートピアのWBT製入力ターミナルはトゥイーターボックス後面にありシングルワイヤーだが、バイワイヤータイプのドミナス・スピーカーケーブルを二本ずつまとめて接続出来る。マークレビンソンのリファレンスラインでセッティングを行い、いよいよ本格的に試聴を開始した。最初は何の迷いもなくヨーヨー・マを選ぶ。「ああぁ、これいいじゃない!」何とも単純な表現であるが、私の第一印象は極めて好ましいものになった。まず、ABOのバックの弦楽が何ともスムーズで美しい。コラム型スピーカーは構造上ノーチラスシリーズに比べてバッフルの存在がどうしても付きまとい、スピーカー後方に展開してほしい奥行き感が出にくいのであるが、メゾ・ユートピアはそんな懸念をまったくと言ってよいほど感じさせない。ノーチラスと同等とは言えないまでも、それを補ってあまりある清楚で優雅なストリングスを聴かせてくれる。前述のボックス間のスリットが功を奏しているのかABOとヨーヨー・マとの遠近感もほど好く再現されている。それでは、と同じディスクの10トラック目、ボッケリーニのチェロ協奏曲ト長調G・480にスキップした。導入部の弦楽が聴こえ始めた瞬間にはメゾ・ユートピアの価格を忘れていた。とにかく弦楽器が美しいのである。そしてトン・コープマンが演奏するハープシコードがからんでくると、その余韻の木目細やかさが心地良く耳に後味を残していく。さあ、いよいよヨーヨー・マのチェロが入ってくる。「おや、何か違うぞ。」これはいい方の意味であるが、チェロの再現性に明らかな違いがある。確認しなくては、とヨーヨー・マの以前のアルバムで「ヨーヨー・マ・プレイズ・ピアソラ」(SONY Records SRCR1954)の一曲目、「リベル・タンゴ」をかける。「ああ、やっぱりそうだ。」と確信を持った。チェロの高音階はピンポイントに近い収束した音像を見せるのだが、音階が低くなるにつれてスピーカーキャビネットのキャラクターを引きずるようになり、それまでのチェロの音像は数倍にふくれ上がってしまうスピーカーが多いのではなかろうか。しかし、メゾ・ユートピアで聴くチェロはいかなる音階の変化に対してもフォーカスのゆるみを発生することなく、実にチャーミングでスレンダーなプロポーションを維持するのである。これは実に好ましい。音階が低くなりブォーッと勢いをつけるチェロの再生音に、迫力という形容詞を用いて売り込もうとするのはいかがなものであろうか。再生する周波数によって、言い替えれば演奏している楽器の音階が変化するにしたがって音像が拡大縮小を繰り返すというのは、未完成なスピーカーによる演奏の歪曲とも言えるのではなかろうか。大編成のオーケストラであれば判別しにくいであろうが、ソロの楽器でこのような症状が聴きとれるスピーカーはお勧めできない。つまり、そこにエンクロージャーのデザインのセンスが問われ、ユニットの能力だけが全てではないという難しさがあるのだ。楽音の美しさだけにとどまらず、この点においてもメゾ・ユートピアは合格である。
さて、次に大貫妙子を聴くことにした。私がセッティングしたメゾ・ユートピアでは間隔は左右トゥイーター・ユニット間で2.4メートルであった。ごく一般的な室内空間であれば十分に確保できるスペースであろう。イントロでのウッドベースは先程の分析がピタリと予想を裏付けたものとなり、必要以上に音像を肥大させないタイトな鳴りっぷりである。さあ、ヴォーカルが入ってくるぞ、と心持ち胸騒ぎが始まる。「エェーッ、何なんだこれは。こんなスリムな大貫妙子は始めてだ。」と驚くようなフォーカスの引き絞られたヴォーカルが、そこだ!とメゾ・ユートピアのど真ん中を指差せるほどの眼前に忽然と姿を現したではないか。ノーチラスの場合には三次元的に拡散するエコーであったが、メゾ・ユートピアの場合には左右に拡散するというよりは口元の同じポジションから奥の方へと余韻を引き延ばしていく。新たな発見と感動、これもジャック・マユールが作り出したJMラボ流の美の表現であろう。
美しさはわかった。でも、スタジオ録音の切れ味のいい醍醐味も欲しい、と欲張りな発想が脳裏をよぎり早速次なるテストに取りかかる。
デイヴィッド・サンボーンの「インサイド」(Elektra AMYC-2967)の1曲目「コーナーズ」を次のテスト曲とした。ドン・アライアスのノリのいいパーカッションのリズムにマーカス・ミラーの重量感あるベースがかぶさってくる。しかし、このベースは実によく正確な音程を維持しており、キャビネットとポートの共振による膨張感は感じさせない。先程の分析は的中であり、27センチとは思えないほどの低く重いベースを平然と鳴らしていく。そしてサンヴォーンのブロウするサックスが入ってくる。「やぁ、これは気分爽快だ。これはイケルぞ!」メゾ・ユートピアのセンターに存在する空気がゼリーであったとしたら、スプーンで中心をすくい取ったようにくっきりと輪郭を現すサキソフォンが出現する。しかも、ピンポイントの正確さで空間に穴があいたようなエッジの際立ちを見せ、リードのバイブレーションには濁りなど微塵もないのだ。当然のことながらドミナスにサポートされたマークレビンソンの素晴らしさも大きく貢献しているのであろうが、この演奏を聴いていると何の貢献度が一番大きいのかなどと詮索することが些細なことに思われてしまうのである。商売人的な結論を一言「このスピーカーは安い!」減点の対象が見つからない私は悔しさと期待の入り混じった心境に陥り、何だか罠にはまってしまったような気持ちでノアの笹本部長に電話をかけてしまった。「メゾ・ユートピアいいですね、この際ミニ・ユートピアも持って来てくれませんか。」電話の向うで笑顔に変わる笹本部長の顔が目に浮かぶようだ。「よろこんで、早速明日お持ちしましょう。」
ミニ・ユートピアはどのくらいミニなのか?幅26センチ高さ60センチ奥行き41センチ重量27キロ、専用スタンドの高さは52センチであり、スタンドに乗せた場合の背の高さはメゾ・ユートピアとほぼ同じになる。このスタンドはスピーカー本体と床に接する面の両方に四個ずつ小型のスパイクが取り付けられており、デザイン的にも調和したしっかりしたものだ。上級機で使用されている16センチミッドレンジドライバーを2個、ダポリッド・コンストラクションで中央に向けて傾斜しながらトゥイーターを挟む形で取り付けられており、ユニット配置はウィルソン・オーディオのCUBと同様なのだが、ポーラーパターンを重視する観点からトゥイーターの主軸に向け傾斜させた構造が目を引く。そして、メゾ・ユートピアでは密閉された専用エンクロージャーに納められミッドレンジ用とされていたユニットであるが、ミニ・ユートピアの場合にはミッド・ウーファーとして使用されているため、低域のレンジを確保するためにポートチューニングを施している。このポートチューニングが巧妙であり、単純な丸い穴とパイプではなく一見しただけでは中々わからない。基本的にはメゾ・ユートピアと同様に3個のユニットが独立したエンクロージャーに納められており、トゥイーターのボックスと2個のミッド・ウーファーとのすき間が見られる。リア・パネルは一枚であり、このスリットは素通しではない。ミッド・ウーファーとトゥイーター・ボックスのすき間がバスレフポートとなっているのである。凝りに凝った構造でありながらデザイン的に洗練され、仕上げの美しさとあいまってペア86万円というプライスを手頃なものとして印象付けている。さあ、これにもメゾ・ユートピアとまったく同じシステムとドミナス・スピーカーケーブルをつなぎ早速試聴を始めることにした。
前回メゾ・ユートピアのテストで使用した曲を逆の順番で聴いてみることにする。デイヴィッド・サンボーンの「インサイド」から「コーナーズ」を最初に聴いてみることにした。いきなりマーカス・ミラーのベースを試してみようと思ったのだが、これには私なりの思惑があった。たった16センチのミッド・ウーファー、しかもミニというネーミングにふさわしいコンパクトさ、こんなスピーカーがどれほど頑張っても上級機のような低域が出るわけがない。その限界を最初に確認しておきたかったのである。PADのシステムエンハンサーを辛抱強くかけて待つこと75分、マークレビンソンのエレクトロニクスもウォームアップを完了するまでクレイスーパーコンピューターによって作られた250種類の合成音によるシンフォニーを聴きながら期待に胸を膨らませていた。 さて、ディスクをローディングしながら「この口径なら驚くほどの低域が出るわけもないし、あまりパワーを入れるとミッド・ウーファーがクリップしてしまうとまずい。ほどほどでいくか。」と気軽に身構える。ドン・アライアスの切れのいいパーカッションのリズムにマーカス・ミラーのベースが重なる。さあ、ここで私がどう思ったか。簡単に言えばがっかりしなかったのである。エレキベースの音程を正確にとらえているということ、そしてマーカス・ミラー本人が多重録音でかさねたキックドラムの音がちゃんとベースと分離して再現されるのである。「中々やるじゃないか、これはポートチューニングとドライバーの素晴らしさだね。」正直に言って感心した。上級機ではミッドレンジに使用されている16センチユニットは肉眼で見ても微動だにしない動作であったが、ミニ・ユートピアのそれは激しくピストンモーションを繰り返しているのがわかる。調子に乗ってパワーを上げてもストレスを増加するようすもなく反応する。スリット状のポートからは盛大にエアーを吹き出すのだが、パイプとしての管共振がないためドライバーそのものの音色にダメージを与えることもない。「いやいや、この低域はミニとは言えない。当然上級機ほどの重さは得られないが、出せる範囲での正確さを最優先でこなした低域だ。こんな無理なく欲張らない設計は安心できるね。」
次は大貫妙子だ。「あっ、このヴォーカルいいですねぇ。」ダポリッド・コンストラクションが極めるフォーカスは見事であり、この価格とは思えない鮮明なエコーを残す。まるでバランスと取れた紙飛行機をミニ・ユートピアのセンターに向けて飛ばし、どこまでも真っ直ぐに滑空していくように見事な余韻を疑いなく自然な消失の仕方で継続していく。ヨーヨー・マはどうだろうか。ボッケリーニのチェロ協奏曲をかける。「奥行き方向への展開がみずみずしいね。上級機と同じ贅沢なトゥイーターが思う存分鳴りきっている。」チェロのフォーカスも音程によって拡大縮小することもなく、ステージの一点で演奏しているというオーケストラ全体の縮尺図を丁寧に聴かせる。これで86万円か、かなりいい。専用スタンドによって空間に位置するミニ・ユートピアは、同シリーズの中でも屈指の音場感を再現できるシステムとして評価できるだろう。ちなみにトゥイーター間の距離はメゾ・ユートピアと同じく2.4メートルであるが、ダポリッド構成によるフォーカスの在り方が至近距離でも変化しないため、ニアフィールドでのリスニングには持って来いの選択と言える。ウィルソンのCUBと比較されることが多くなると思い、下のフロアーに展示しているCUBをクレルのモデル600につなぎ、デイヴィッド・サンボーンのディスクを持って聴きにいってきた。スペックによる低域再生範囲は両者共に50 なのだが、タイトな印象のベースはCUBのキャビネットの特徴を表しており、キックドラムとの共存関係をうまくバランスさせているミニ・ユートピアの支持者はかなり多くなるだろう。そして、もっとも違う点はヴォーカルの質感にテンションを求めるならばCUBの得点は高くなるだろうが、そこにヨーヨー・マのような弦楽の質感に欲しいと思われるしなやかさと、微妙な温度感やウェット感を加味したいということであればミニ・ユートピアの得点はさらに高いものとなるはずである。私のフロアーでお聴かせ出来る最低価格のスピーカーとして、オーディオにおける「ウールマーク」のタグを自信を持って付けられる製品であると結論を申し上げたい。
さて、このようなエピソードが繰り広げられる一日前の5月18日、今までは他のショップを利用されていたという横浜市在住のT・O氏がインターネットの情報をもとに来店された。お求め頂いたマークレビンソンのエレクトロニクスを使用してオリジナル・ノーチラスの演奏をじっくりと聴かれていく。この経験がO氏のオーディオ遍歴に大きな衝撃と驚きをもって受け入れられ、同氏は現在のシステムに対して「これでいいのか?」という必然的な見直しを求められたようである。半年前までラジカセのレベルで音楽を聴いていた人が、ここでノーチラスに出会い購入された事例もある。本物のハイエンド・オーディオと巡り会ったことが多くのユーザーに再生芸術への開眼を促し、私は楽しんで頂くことを最優先とした啓蒙活動を行いながらセールスを続けている。普段私は来店された皆様にこう申し上げている。「ここで聴いた音楽に感動されたなら購入を検討して下さい。どのショップでも感動を与えてくれなければ買う必要はありません。」当然O氏にも同様に申し上げたのだが、同氏の感性の相当深い部分で目覚めがあったようである。オリジナルは無理でも801であれば何とか、という考えがO氏の頭に浮かんだ時に突如として現われたのがメゾ・ユートピアであった。多忙を極めるO氏のお仕事柄週末と言えども中々時間が取れないという。ノーチラス801を熱心に聴き入りながら自室のスペースとハンドリングに関して多くの質問を発するO氏に対して、それならばと私が提案したのがメゾ・ユートピアであった。「いいですね。」O氏の素直な一言であった。後日いつも聴かれているというソフトを持参され、オーケストラから歌謡曲までじっくりと聴かれる。そして、私から「買って下さい。」というセリフが出ることはない。最も大切なことは私、つまり販売する人間が説得して商売するのではなく、製品自らが聴く人を口説き価値観を認めてもらうことである。どうやら数時間に渡る試聴の結果、メゾ・ユートピアは自身のアピールに成功したようである。3か月後に国内で雑誌発表される予定の新製品に日本初のオーナーが誕生した。ドミナスの能力がスピーカーの潜在能力を聴く人に知らしめた幸運な巡り合いであった。
|