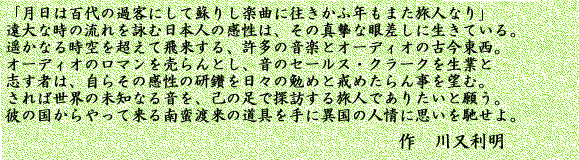第四十七話「純粋主義者」
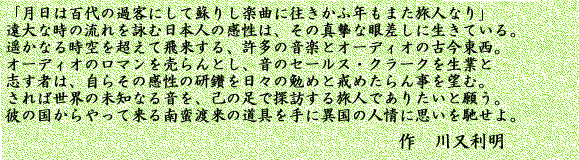
第四部「future project」
第一章「アイソレーション・プラットフォーム」
近年コンポーネントの下に敷き振動対策としてアイソレーション効果を謳い文句にする製品が増えてきた。国産の代表格ではタオックのオーディオボードやラスクなどがそうであるし、アメリカのものではハニカム構造のカーボンファイバーを板状にしたものやJ1プロジェクトのように高分子ポリマーを複層化したもの、振動対策としては各種スパイクやコーンなども範疇に含まれるであろう。実は三年ほど前にPADも板状のアイソレーション・プラットフォームと称するボードを製作し、今井氏のもとに送りマーケティングの相談をしていたという。当時音はいいが値段が高いという意見の店が多く、結局はクリアーサウンドイマイで10数枚を限定販売しただけで計画は頓挫していたというのだ。これまでPADの技術力と感性をドミナスを中心として大いに評価してきたのだが、このアイソレーション・プラットフォームにも関心を示したところ今井氏は快くサンプルを送ってくださったのである。それと言うのも、私はこれまでにJ1プロジェクトのザ・プレーンと称するアイソレーションボードを相当枚数販売しており、その効果を認めているだけにPADのアイソレーション・テクニックに大きな期待と興味があったのである。
これまでにも度々述べてきたようにPADの主眼とするアプローチはEMI(電磁界障害)とRFI(高周波障害)を駆逐することであった。もちろん目では見えないが、携帯電話、ラジオ、テレビ、コンピューター、工場などの設備から発生する電気的ノイズ、そして数えきれないほどの通信衛星が地上に降らせる電波、と数えればキリがないほど現代の都市生活はEMIとRFIを培養する温床となっている。それをスマートで上品な手段によって除去していこうとするのがアイソレーション・プラットフォームの開発意図であるという。送られてきたサンプルは大分使い込んだもので外観に傷みがあるが効果は変わらない。サイズもサンプルということで暫定的なものだが、縦横36センチ×48センチ、厚さ2センチというもので面白いことにアース線が取り付けられている。これも高分子ポリマーが4層となっているが、興味深いのはメタル層が3層挟み込まれ半導体レイヤーを構成しているのである。最も下の一層がアルミ層で、ここからアース・リードが取り付けられている。当時リクエストがあったのだろうか、側面と底面にはウッドパネルが貼付られており、コンポーネントを載せる上面だけが光沢感のあるブラックパネルとなっている。何の変哲もなくこれを敷くだけだというのだから単純なもので、届いて数日間は私も忙しくて聴いている時間がとれず放置してあったものだ。これが後日大きな波乱を引き起こそうとはだれが予測できたことだろうか。
前述しているように私はオリジナル・ノーチラスを一九セット販売している。一般的にはノーチラスほどのスピーカーを買えばすべて一件落着で、その後にはもう何もすることがなくなってしまうだろうと思われる方が多いだろう。しかし、現実は違う。ノーチラスをお部屋に据えられた方は、そこからがスタートになるのである。従って、毎週末ごとに当フロアーを訪れるノーチラス・オーナーは後を絶たない。多いときには三、四人のオーナーが同席され、私が各々のオーナーを紹介するので皆様顔なじみということでオーディオ談義に花が咲くのである。ただし、この皆様の耳のレベルは相当に高いものがあり、私が提示する比較試聴のことごとくに明確な判定を下される。新製品に対しても、ある時は冷酷な死刑執行人、そしてある時は絶賛のお言葉とともに心強い応援団にもなってくださる油断のならないハイエンド・ユーザーの集団である。
4月24日土曜、あいにくの雨にも関わらず米国サザーランド社のトップモデルである#1000シリーズでノーチラスを鳴らしておられる私のVIPのお一人N・I氏が来店された。ちなみに現在N・I氏のお宅にはACドミナスが13本入っており日々音楽を楽しまれている。重たいコンポーネントを載せたり降ろしたりするのは私一人では中々出来ず、ちょうどいい機会とばかり梱包のままだったPADのアイソレーション・プラットフォームをN・I氏の目の前で開封した。ACドミナスの音を知る一人としてPADの製品に興味がないはずはない。しかも、N・I氏は前述のJ1プロジェクトのアイソレーションボードを一挙に5枚購入されるという英断を下された徹底主義者でもあり、ことさら同様な使用法によるPADのアイソレーション・プラットフォームに関心を示されたのである。ここのノーチラスシステムには随所にドミナスを採用しているのだが、たった一ヵ所マークレビンソンのNo.30.5Lだけは特殊なL型プラグのACケーブルを使うため今のところドミナスは使用していない。なんとか、このD/Aコンバーターにドミナスを使っていない分のサポートをしたかったことと、EMIとRFIの影響は当然デジタル処理をするD/Aコンバーターには大きなものがあるだろうということで、まずここにアイソレーション・プラットフォームを使用したのである。
「いいですね。」と、いつも言葉は少ないのだが結論をきちんと出されるN・I氏は、どうやら応援団の側に付かれたようである。これは後日の電話が楽しみである。翌日曜日には今年ジェフロウランドを採用しノーチラスを導入されたS・M氏が同様な試聴を経験され、「川又さん、これきくね、いいよこれ。注文しといてよ。」と、いつもの気さくさでオーダーを頂いた。ちなみにS・M氏もJ1プロジェクトのボードを使用しておられる。更に翌日、やはりジェフロウランドを採用して昨年夏にノーチラスを導入されたK・I氏が遊びにこられ同様な試聴を行なった。そして、この時には当フロアーで使用中のJ1プロジェクトのボードと交換し比較するというシビアな実験を行い、やはり同様な反応を示された。「川又さん、コレいくらくらいで売ってくれるの。」とくる。今井氏から当時のレートで15万から16万円と聞かされていたので、その通りお答えすると、「このJ1の方はいくらなの。」と質問が続く。スパイクコーンとセットにすると174,000円と答えると、「何だ、PADの方が安いじゃない。ボクも頼んでおこうかな。」なんと三人連続のヒットである。
このような成り行きを私が画策したと誤解されると大変に困るのだが、私がしたのは重たいコンポーネントを持ち上げただけである。その間に各々のお得意様がボードを出し入れするという、セルフサービスのデモを行なっただけなのだ。これは完全なフィクションであり私に他意はない。もちろん、同様な実験でJ1プロジェクトを支持するユーザーも表れるはずである。私は単純な実験しかしていないので、J1プロジェクトの輸入元におかれても誤解なきようにお願いしたいと一言申し上げる。
先月今井氏とお会いしてから数々のドラマが展開されてきたわけだが、ドミナスが導入されてからのノーチラスの変貌をご本人は聴いていなかった。以前から私が経験したことを自分の耳で確認したいとおっしゃっていた今井氏が、嫁いだドミナスの仕事ぶりを確認しようと2回目の来訪を果たしたのが4月29日である。事前に予定を聞いていた私は、ノーチラスを所有するか、PADの製品を使用中であるか、あるいは、ここでドミナスの音を体験された方々と、ごく限られた皆様に今井氏の来訪を知らせ招待していたのであった。開店と同時に見えられた今井氏から早速ジム・オッド氏から送られてきた最新情報の説明を聞き、アンプがウォームアップしてきたところで私が経験してきたドミナスのテストを繰り返し実演したのである。今井氏が試聴するときの表情は幸福感にひたっているかのようであり、本当に楽しそうな面持ちで課題曲の各々に判定を下されていく。オーディオビジネスは楽しく、本来こうあるべきという見本のような表情の今井氏に、私も安心して選曲を繰り返していくのであった。
実は、この段階では第48話で紹介しているマークレビンソンのNo.32Lが導入されており、フロントエンド・コンポーネントのレイアウトを大きく変更していたのである。従って、D/AコンバーターのNo.30.5Lと新製品のNo.30.6Lの両者をゾウセカスのラックに収納し、同じコンディションで比較試聴出来るようにしたため、PADのアイソレーション・プラットフォームを抜き差しする実験が出来なくなってしまった。そこで、プリアンプのNo.32Lのサーキット部にこのアイソレーションボードを使用し今井氏に試聴して頂いたのである。私も初めての経験であったが、まったくと言って良いほどD/Aコンバーターにおける変化と同じものが表れ、今井氏も大きくうなずきながら納得の表情を示されていた。ここでテストに使用したのが次に紹介する5番目の課題曲である。
アストル・ピアソラ(1921-1992)は、アルゼンチンの作曲家アルベルト・ヒナステーラと今日では伝説的な存在となったパリのナディア・ブーランジェのもとで作曲を学んだ。このブーランジェこそ、ピアソラに一般のクラシック音楽ではなくタンゴの作曲に専念すべきと勧めた人物である。タンゴを伝統的な形式から開放し、より繊細なニュアンスと複雑な形式を与えようとしたピアソラは古典的なタンゴの六重奏にチェロとエレキ・ギターを加え、1955年にオクテート・ブエノスアイレス(ブエノスアイレスの八重奏団)を結成する。このオクテート・ブエノスアイレスのために1956年にピアソラ本人が作曲したのが「タンゴ・バレエ」である。50年代はパリでジャズに影響を受け、58年にはニューヨークでクールジャズに触発されたピアソラは、バンドネオン、コントラバス、エレキ・ギター、ヴィブラホンからなる五重奏団を結成。更にブエノスアイレスに戻った60年にキンテート・ヌエボ・タンゴ(新五重奏団)を設立し新しいタンゴの創造に邁進するのであった。
時は変わり1997年2月に50歳の誕生日を迎えた現代の音楽家ギドン・クレーメルは、これを機会に自身の半生を振り返り故郷であるリガ(ラトヴィア)に回帰したいという願望を持つようになったという。そんなクレーメルがバルト三国の若手音楽家をメンバーとして設立したのがクレメラータ・パルティカという室内楽団である。98年にはバルト三国の経済的な苦境を憂慮したクレーメルはハンブルクに「クレメラータ・パルティカ基金」を設立し、エストニア、ラトヴィア、リトアニアなどの経済援助に乗り出している。一方クレメラータ・パルティカは国際的な名声を博しつつ、98年にはヨーロッパ、アメリカでもツアーを行い、99年には台湾、香港、日本でも演奏を披露しているのである。 そのクレメラータ・パルティカ初のレコーディングに取り上げられたのが、クレーメル最愛の作曲家であるピアソラであり、かの「タンゴ・バレエ」である。テルデック(WPCS 10032)「ピアソラ・天使のミロンガ」が今回の試聴で大役を勤める課題曲となった。
ここで3年前に今井氏とジム・オッド氏との間で取り交わされた、もう一つのエピソードをご紹介しなければならない。前述のように音は良いが値段が高過ぎると指摘された今井氏は、もっと安い価格で同様な効果が得られないものかとオッド氏に相談をしたという。その結果、前述のような凝った構造ではなく、黒いポリマー製単層構造の一枚板でサイズは縦横55センチと49センチ、厚み3センチと前作よりも大きくなったサンプルを送ってきたという。これで価格は8万から9万円と半額近くになったのであるが、これも同時に比較試聴することになったのである。今後この大小をとって前述の初期段階の試作品スモールをSタイプ、そしてコストダウンしたラージをLタイプとして表現する。
「タンゴ・バレエ」の1トラック目は「イントロダクション」としてクレーメルのヴァイオリン・ソロから始まり、クレメラータ・パルティカの二人のコントラバス奏者による強力なピッチカートがノーチラスの右手方向の奥からバリバリッと衝撃的なリズムの展開を聴かせる。クレーメルのソロが継続していくと、このコントラバスはジャズにおけるウッドベースのような奏法のピッチカートでノリのいいリズムに移行する。このへんでトラック2の「街」に進行し、その繰り返しの後にクレーメルがヴァイオリンを単音階のアルコでキュイーッと鮮烈に弾き奏でるフレーズが何度も登場してくる。何と贅沢なことに、この冒頭の3分程度を何度も繰り返して比較試聴していくのである。計ったようにNo.32Lにサイズはドンピシャリとマッチしている。最初にSタイプのアイソレーションボードを敷いた状態でスリリングに展開していく「タンゴ・バレエ」のプロローグをリピートし、しっかりと頭にメモリーさせた。「恐れ入ります。私が持ち上げている間に抜いて頂けますか」と、今井氏にお願いして重たいNo.32Lをラックから持ち上げた。さあ、Sタイプを外してみました。どうでしょう。と答えを知っている私は余裕の笑みを浮かべながら今井氏に一言、そしてポーズを解除すると…。何と今井氏は「参ったなァ。」という面持ちで表情に笑いがにじんできたではないか。まず冒頭クレーメルのソロに変化がありありと浮かぶ。先程までクールにフォーカスを維持し、ステージにおける立ち位置を明確に主張していたクレーメルの演奏がドンッと膨張し大きくなってしまう。従ってエコー感とヴァイオリンそのものとの境界が薄れてしまい、解像度の劣化は見るも無残な結果が一目瞭然である。そしてコントラバスが弾きはじめたピッチカートにおいては質感がライト級までウェイトコントロールされてしまったようで、減量がもたらしたパワーの低下は集中力を欠くほどと言っていい。弦を弾く瞬間だけがカンカンッとアクセントを持つだけで重厚であったコントラバスにローカットフィルターをかけたようなのである。そして、極め付けはクレーメルがキュイーッと単音を強烈に引っ張るように演奏するパッセージともなると、今までスムーズにストレスの微塵もない余韻をはらんでいたヴァイオリンに刺激成分が混入していることに直ちに気が付いてしまい思わず眉をひそめるようである。もうこの段階になると今井氏も唖然とした様子で「わかりました。」と一言。さて、次はLタイプを試してみましょう、とコストダウンの成果が同レベルの効果の維持につながっていればと期待して、私はもう一度プリアンプを持ち上げた。安くて大きいアイソレーションボード、成功すればそれに超したことはない。いざ、ポーズを解除してもう一度。「アアァッ。」とは私の、もしくは今井氏のため息であったかもしれない。冒頭クレーメルのソロは色彩感を薄めた感じで何とか聴けなくもないが、妙にエコー感が耳についてしまい実態感が乏しい。ないよりはあった方がよいという程度か。そしてコントラバスが入ってきた…。「待てよ、これはどうかな。」もちろん何もないよりはいいのだが、風に揺らいでしまいそうなバスの質感はどうしても軽くなり過ぎと思える。ついでクレーメルの単音を強烈に弾き鳴らすシーンだが、ついついヒステリックなイメージを楽音の中に嗅ぎ付けてしまいストレスがのこる。やはりオッド氏に無理矢理コストダウンを頼み込んでもよい結果は得られないようである。
さて、そうこうしているうちに、今年夏にノーチラスを納入する予定でオーダーを頂いている吉祥寺在住のK・S氏ご夫妻がみえられた。私が今井氏に行なったパターンをそっくり繰り返し、何の説明もせずに「どうですか、今のは?」と尋ねると「コレッ!」と指差したのはSタイプであった。と今度は明後日ノーチラス801を納品する予定で現在ACドミナスを愛用されている世田谷区在住のT・M氏が仕事の合間に駆け付けてこられた。やはり何の前置きなしに3種類の再生音を聴いて頂き同様な問いかけをすると、「これがいいですね。」と明確な一言。T・M氏もSタイプである。そして、最後に来店されたのが五日前にいっしょに初体験をしたN・I氏である。前回のD/Aコンバーターではなく、プリアンプに使用した事例も再度聴き直した結果「川又さん、何度聴いてもやはりこっちですよ。悪いけど安い方だったら私は欲しくないな。」とノーチラスのオーナーだけに自信ありげなコメントが飛び出す。これらの三組のユーザーがそろって同じ結果にたどり着いた有様を目の前で見せられた今井氏は「ウン、ウン」とうなずきながら、微細な音質変化を事もなげに表現してしまう当フロアーのノーチラスシステムと、それに更なる洗練されたニュアンスを追加したドミナスシリーズ、そしてこのフロアーの総合的なルームアコースティックにいたく感激された様子であった。これで相当な自信を得た様子であり、5月にPADを訪ねるという予定からしてもオッド氏に良い土産話もできたことでもあり、アイソレーション・プラットフォームの正式な商品化に向けて十分な手応えをもってディスカッションが展開されることであろう。3時過ぎの飛行機で帰られるという今井氏にはアッと言う間の4時間であった。親しくユーザーと言葉を交わし、自社の製品に対して明確なジャッジが次々と下され、しかも期待と購入意志をいっぺんに言葉として受け取ったのであるから気分が悪いはずはない。羽田に向かう後ろ姿には、後ろ髪引かれる思いがありありと表れていた。収穫は大きい。そして、実は今井氏が時間切れでお帰りになった後、同席された皆様と私には更なる驚きと興奮の体験が待っていたのである。
前述のようにN・I氏はJ1プロジェクトのアイソレーションボードを5枚購入されており、氏の表情を見ていると私としても何らかの答えを出しておきたいという気持ちに駆られてしまう。それでは、と今井氏がお帰りになったあとで他社製品との比較を始めたのである。今までコヒレンスに使用していたJ1プロジェクトのボードを外しておき、再度「タンゴ・バレエ」のイントロダクションを聴く。そして、皆様の力をお借りしてNo.32Lの下に敷き直した。そして、ポーズを解除して間もなく過去の判断を逡巡の思いとともに更新してしまった自分自身を疑っていたのである。昨日まではこのJ1プロジェクトが最優秀のアイソレーション効果を持っているものと確信していたのに、でもこの変化はどう理解したらいいのだろうか。ノンカラーレーションがセールスポイントのJ1プロジェクトのはずなのに、PADに比較すると明らかに違うカラーに染められてしまっているのがわかってしまうのである。その色とはズバリホワイト「白」である。鮮烈であるはずのクレーメルの真っ赤なヴァイオリンにほんのわずかの白を混ぜた。漆黒のブラックであるはずのコントラバスにも微量の白が混じる。鮮やかなオレンジとグリーンの混在をイメージさせるクレメラータ・パルティカの弦楽パートにも、やはり数滴の白が落とされているのがわかってしまうのである。比較対象がなかった今までは、このJ1プロジェクトがもたらす白の添加作用を心地よく感じていたのである。原色のソプラノにほんのわずかに白を、輝くストリングスにも多少の白を、テンションを張り詰めたポップヴォーカルにもひとしずくの白を、まるで濃厚なドミグラスソースやカレールーに生クリームを加えてまろやかな味に仕上げるような効果があったことを新たに発見してしまったのである。そう、J1プロジェクトを使うと微妙なまろやかさを追加することで「聴きやすく」「刺激成分を除去して滑らかに」こんな作用があったのである。私からN・I氏に言い出すことが出来ずにいると氏の方から「川又さん、PADの方がいいね。」と私の心境を察してくださったかのような言葉を口にされたのである。「理解あるお得意様とは本当にありがたいものだ。」と、内心胸をなで下ろした感じの私の胸中は新たにわいた感謝の気持ちでいっぱいになってしまった。それにしてもPADのアイソレーション・テクニックには素晴らしいものがある。ここで改めて思えば、J1プロジェクト他の数社の製品は機械的振動に対するアイソレーションを当然のことだが目的としていたことを再認識することができた。しかし、PADはメカニカルな要素にプラスアルファして、EMIとRFIという目に見えず触れることの出来ない干渉要素を見事に駆逐してしまったことが音に表れているのである。つまり、メカニカルなアイソレーションは必ずそれ自身の素材感を音質に混入させてしまうことを黙認するしかなく、PADは純粋主義者の社名をきちんと自社のポリシーとして細部に表しているのである。PADのアイソレーションはコンポーネントの設置環境に対しても浄化効果を発揮し、まさに今まで気が付かなかった不純物を洗い流してくれるのである。従って、楽音には一切の色彩変化をもたらさない。
さて、このような実験の被験者となってくれたNo.32Lのサーキット部は高さのない薄型のデサジインであり、PADのアイソレーションボードの3センチから5センチほど上にシグナルパスの回路基板が位置していることになる。EMIとRFIの影響を排除するというのであれば、当然シグナルパスである回路部分に出来るだけ接近させてアイソレーションボードをセットするのが望ましいのではないか。そんな考えからすればNo.32Lの基板の位置関係はボードに近いともいえる。
今井氏の解説によるとEMIとRFIはラックの表面にも反射して、その上に置いたコンポーネントに悪影響を与えるという。下からの反射の方がコンポーネントの上方から降り落ちるEMIとRFIよりも大きいため、エレクトロニクス・コンポーネントの下に敷く方がより効果が大きいとオッド氏は述べているという。それならば、ここで使用しているジェフロウランドのコヒレンスはどうだろうか。下側にバッテリー電源を置き、その上にシグナルパスを格納する本体を積み重ねて置いている。よって回路基板とPADのアイソレーションボードの距離はマークレビンソンのそれよりも3倍ほど更に離れ、目測でもボードからは15センチ程度の高さにある。しかもアルミプロックをくりぬいて作られたコヒレンスのボディーはシールド効果絶大と言われている。そして、何よりもバッテリー電源を採用した上にライントランスを搭載し外来ノイズには滅法強いと言われる方式を取っているので、最初からEMIとRFIへの対策は折り込み済みという設計である。さすがにこのコヒレンスにはPADのアイソレーション・テクニックも言うに及ばずであろうと、私も半分は変化なきようにと祈る心境であった。そして、目の前にはコヒレンスを私が販売したK・S氏がいるではないか。果たして回路基板を格納している本体を電源部の上に乗せてしまっているコヒレンスに対して、電源部の下に距離をおいて差し入れたPADのアイソレーションボードが効果を発揮するのであろうか。今まさにギャラリーと化した数名のお得意様を目の前に私は最後の実験に取りかかった。「ウーンッ、ククッ、オモイィィ…。」と情けない声をもらしているのは私である。ラックの上に乗った40キロ以上もあるコヒレンスを配線したままで数センチ持ち上げるのは並大抵の力仕事ではない。私の接客では絶えず実験と試聴を繰り返しているため力仕事は慣れっこであるがきつい。ぐっと持ち上げ皆様が協力してPADのボードを挿入して下さるまで堪える。「フゥーッ」と一息ついて席につきリモコンを手に一言。「よろしいですか。」と、まるでこれから注射をしようとする医者のような発言に思わず自分でも吹き出しそうになる。素材、構造、質量、回路構成と、これ以上はないだろうと思われる高度なシールドレベルで設計されたコヒレンスに対して、果たしてPADのアイソレーションボードは一体何を物申すというのか。さあ、いよいよ「タンゴ・バレエ」が始まった。
クレーメルのヴァイオリン・ソロが始まって数秒後、数人しかいないのだから大勢のギャラリーがあげるため息や騒然たる雰囲気とはいかないが、「エェーッ」「ウッ」「フゥーッ」と押しつぶすように皆一様に声にならない声を発する。何が起こっているのか、同時に集中して聴いていた私は即座に理解することが出来た。それでなくてもヴォーカルではおちょぼ口のピン・フォーカスを見せるコヒレンスは、先程もクレーメルのヴァイオリンを見事にコントロールして暗闇で灯した蝋燭の光のように楽音をノーチラスのセンターにピタッと静止させるほどの定位の素晴らしさを示していた…、はず…であった…。ところが、ところが、である。PADのSタイプボードを敷いた瞬間に、蝋燭を灯したのは六畳間ではなく実は見渡すほどの広さを持つホールであったことを気が付かせるのであった。つまり、クレーメルの発する楽音の余韻は更に遠くへ、そして高くへ、とエコーがグライダーの飛翔のごとくノーチラスの周辺へと飛散していくではないか。そして、クレーメル自身はステージにスラリと立ち姿を表したように、後光のようなバックライトから浮かび上がるシルエットを「更に!」を二乗して表現したいくらいに鮮明になっているではないか。新幹線に乗って霊峰富士の景観をほんの刹那目にしたような思いでクレーメルの変化に目をみはっていると、次の瞬間には強力なコントラバスが待ち構えていた。コントラバスの図太い4本の弦が束になったように聴こえていたバリ、バリ、という激しいピッチカートが、1本の弦だけを望遠レンズで拡大したようなズーム効果をもって解像度の高まりを目の前に展開していく。そして、4本の弦のエコーが4種類に分類できるほど、演奏全体の静粛性が高まっていることに唖然とする。私も「ウッ!」と喉から声が出そうになるのを今しばらくと辛抱して聴き続ける。さあ、いよいよクレーメルのヴァイオリンがキュイーッと引き絞るようなシングルトーンを奏で始めた。「ああ、きれいだ。ストレスは皆無と言っていい。そして、静かだ。」静か?この50畳はあるフロアーで目一杯ボリュームを上げて余韻の行方を追っているというのに、これほどの音量で静けさを感じるのはなぜだろう。自分のインプレッションを適切でわかりやすい言葉に置き換えることを仕事としている私は、大急ぎで自分のボキャブラリーを検索して妥当な言葉を探し出そうとしている。まず「きれいだ」と感じたこと。あくまでも比較論であるが、いままで何の問題も感じてはいなかったがSタイプのボードを敷いてからというもの、ヴァイオリンの音に料理で言う裏漉ししたような滑らかさを感じるのである。楽音自体に大小様々な音の微粒子があって、やや大きめな粒立ちの成分が溶けきらない粉ジュースのように、あるいは荒い網目の茶漉しで淹れたコーヒーが顆粒状の粒々を残したように、使用以前の音はのどごしにざらつきを与えていたように感じてしまうのだ。ところが、PADのボードを敷いただけなのに粉ジュースは搾りたての果汁に変化し、コーヒーは上質のペーパーフィルターを二重に使ったような透明度を高めるのである。もちろんJ1プロジェクトのような白を添加した変質ではなく、純粋に本来の色彩感を維持しているのだから異論をさしはさむ余地もない。そして、次に「静か?」と感じるのはなぜだろう。発せられた楽音がエネルギーを減衰させながら最終的に消滅するまでには、本来録音されているエコーが減衰しながら徐々に息を引き取るわけだが、その直前に正体不明の「雰囲気」と称される霞のような空気感に埋もれてしまうことがある。ノイズフロアーという単語が欧米のオーディオ業界でも用いられているが、ちょうど私の言わんとしているのがノイズフロアーの低下ということである。不思議なことに重厚であり一部のスキもないように思えていたコヒレンスでさえも、このSタイプボードを敷いたことによって更に静粛性を高める。表現を変えれば、余韻の最終段階の最も微弱な成分まで聴こえるようになり、これが静けさという言葉で言い表せるのである。
この試聴を終えてギャラリー一人一人の発言を得ようとボリュームを絞っていくと三組のお客様が申し合わせたように口を揃えて一言。「これ買います。」正直に言って予想外のコメントを頂いた私は、「あっ…、ありがとうございます。」と一息飲み込みながら返事をしてしまった。もうこれほどにユーザーの気持ちを引き付けてしまうのであれば理屈はどうでもよい。オッド氏の物理的な解説を私がいくら代弁しようとも、この実演による説得力の大きさにはかなわない。解説不要の領域である。ここで、一言あえて私が申し上げたいことがあるとすれば、究極的に微細な再現性をノーチラスシステムが実証してくれたという事実に対して、マークレビンソンの新製品No.30.6Lが大きな貢献をしてくれたという事実である。前作と外観は変わらないものの、世界最高と言える解像度をD/A変換部で可能にした威力には素晴らしいものがある。
いやいや、今まで見えなかったもの聴こえなかったものを我々に提供してくれたPAD、そしてジム・オッド氏とは何たる技術力の持ち主であろうか。オーディオのマジシャンとも例えられる彼らの才能にひたすら脱帽の思いである。そして、これからオッド氏は何をしていこうというのか、ただの注目を通り越し神の声としてPADにサムシングエルスを期待してしまう。
第二章「RADIANT LIGHT SOURCE」
ジム・オッド氏によるとケーブルにおける数々のパラメータのうちで最後の難問となっているのが絶縁体であるという。導体を取り囲むものを誘電体といい、その誘電率によって絶縁体として機能するわけだが、前述しているように誘電体の材質によって絶縁体としての能力と特性に大きな変化があるという。導体中で営まれる電子の振る舞いに対して、それを妨げようとする作用が大きいものを絶縁体として考える。そして、実際に導体中に信号電流が流れた場合、その導体の素材が同じであっても絶縁体にテフロンを使うかポリプロピレンを使うか、またポリエチレンを使うかによって結果的に出力信号は変質してしまう。それを導体と絶縁体との間にダイナミックキャパシタンスが発生しているからとオッド氏は説明している。ゆえにドミナスでは複数の絶縁体を使用することによってスペクトル・バランスを均衡化しようとしているのである。
ということは、素材の異なる特性をミックスすることで中和作用、あるいは相互の補完作用を絶縁体に求めたという考え方なのであろうか。オッド氏の理想とする絶縁体とは導体中の電子のダイナミックな活動を妨げないものとして理解されるのだが、果たしてそんな都合のよい彼のめがねにかなった絶縁体は存在するのだろうか。
実は、こんな疑問に対してオッド氏は1987年に既に独自の理論を完成させていたのである。さて、はたまた物理の時間である。「光電効果(Photoelectric effect)」という現象がある。これを簡単に説明すると次のようになる。
「物質に光を当てると光が吸収され、自由電子を生じる現象で、外部光電効果と内部光電効果に大別できる。一般的には単に光電効果という場合には光の照射によって固体表面から電子が放出される外部光電効果を指し、飛び出した電子を光電子と呼ぶ。光電子放出には照射光の波長が対象となる物質によって決定する値より短いことが必要で、光電子の数は光の強さに比例する。内部光電効果は半導体や絶縁体に光が吸収されることによって電導率が増加する光伝導、そして起電力を生じる光起電効果という現象が生じる。」
もうおわかりのように、オッド氏は最も正確なオーディオ信号の伝送を実現させるためケーブルに光ファイバーを利用するというアイデアに行き着いたのである。しかし、当時はこのようなシステムを作るための材料も入手困難であり、実用化のための方法も未知のものであった。ただ、オッド氏の頭の中ではこれこそが理想のケーブルであると、科学的根拠に立った確信と執念だけが彼のアイデアを実現するための開発に立ち向かわせたのである。そして、周知のとおりであるが90年代はコンピューターは日進月歩の進歩を遂げてより速く、光ファイバー技術も飛躍的に進歩した。PADの物性科学と冶金技術という根幹技術と融合して、この10年以上の歳月はオッド氏のアイデアに血と肉を与え、遂にRLS(レディアント・ライト・システム)として実用化のレベルに達したのである。95年には開発の最終段階を迎え、翌96年に最初のRLSインターコネクトのプロトタイプがCESでデモンストレーションされたのである。当時相当な反響はあったのだろうが、直ちに製品化ということも難しく更に数千時間の研究開発を重ねた結果、レヴィジョンBとして実用可能なサンプルが98年には1セットのみ日本にも送られてきたという。RLSは三つの構成要素から成っている。
1.レディアント・ライト・ソース システムに使用する光源。もちろんオッド氏の開発であるので光の波長や強度は計算されたものである。小型のアンプ程度の大きさのボックスであるが、光源の出力数によって価格は以下のように予定されている。RLS BOX/3(3光源出力)65万円、同/5(5光源出力)138万円、同/9(9光源出力)218万円となる。
2.フォトカプラー 光源からの光出力を標準的な光ファイバーによって各々のケーブルに導く。大分長いものまで使用できるが1.5メートルで6万円、3メートルで9万円、0.5メートルごとの追加はプラス1万1千円である。
3.各種ケーブル本体 これにもフォトカプラーが取り付けられており、ドミナスを母体とするケーブル内部に導かれる。ケーブル内部の光ファイバーは大変特殊なもので、ファイバーの周辺に放射光を照射しながらファイバー内部で光を進行させるという光伝送と照射を同時に行なうものである。一般的にはオーディオでいうTOSリンクやSTリンクのように、外部に光が漏れないようにして伝送するというのが光ファイバーの役目と思っていたわけで、こんな都合のよい光ファイバーが10年前には存在していなかったのだろう。この特殊な光ファイバーがコンダクターを囲むテフロンなどの絶縁体の周辺を取り囲む構造となっているのである。これによってRLSは、あたかも絶縁体が存在しないような状態を作り出し、今までの世界中のどのケーブルでも実現できなかった究極の再現性を得ることに成功したという。従って、想像しただけでも値段が張りそうであるが価格は概略で次のような予定である。
RCAインターコネクト一メートルで163万円、同2メートルで208万円、0.5メートルごとの追加はプラス15万円。XLRバランスのインターコネクト一メートルで162.5万円、同2メートルで215万円、0.5メートルごとの追加はプラス17.5万円。RCAデジタル1メートル60万円、同2メートル74.4万円、0.5メートルごとの追加はプラス7.2万円。AES/EBUバランスデジタルは1メートル63.8万円、同2メートル81.2万円、0.5メートルごとの追加はプラス8.7万円。標準的なスピーカーケーブル1.5メートル330万円、3メートル459.9万円、0.5メートルごとの追加はプラス43.3万円。となりバイワイヤー、トライワイヤーも特注が可能である。当然ACケーブルも用意されており、15Aストレートタイプの1メートルで60万円、同2メートル77万円同、0.5メートルごとの追加はプラス8.5万円。20Aタイプ一メートル60.4万円、同2メートル77.4万円、0.5メートルごとの追加はプラス8.5万円となる予定である。
レヴィジョンBタイプとしては一度輸入されたのだが、今井氏はあくまでもサンプルとして認識して欲しいという。オッド氏自身がやり残したことがあるということで、シグネチャーシリーズとしてこの夏に発売するものが最終的な仕上がりを見せるという。これによってオーディオケーブルのノイズフロアーが劇的に下がり、ケーブル自身が持っている電子ノイズに隠されていたマイクロ・ダイナミクス(微弱音が生き生きと表現されること)を聴きとることが可能となったというのだ。現状では聴くことは出来ないのだが、これまでのPADの説得力からすれば大いに期待できるものである。疑り深い私だが、実物を聴いてみて感激すれば相応のプロモーションを展開するはずである。どうぞ、ご期待あれ。
第三章「PAD presents - Special DC Power Cords」
同様に未発売ということなので、この章を借りて紹介しておきたい更なるPADの新製品がある。シーエスフィールドの今井氏はエソテリックのP−0を使用しておられるのだが、実はジム・オッド氏も同じP−0を愛用しておられるという。前章で述べているノーチラスのオーナーの皆様には、P−0に対して付属品の電源ケーブルからACドミナスに差し替えての試聴実験を行い、ことごとくその変化の大きさに驚かれ将来の導入予定を具体化する例が増えつつある。ご存じのとおりACドミナスはP−0の電源部と壁コンセントを結ぶものである。さて、このP−0の電源部と本体を結ぶDCケーブルは純正の付属品を使わざるを得ないのだが、このDCケーブルをドミナスグレードにレベルアップしたら一体どれほどP−0の音質が変化するのだろうか。せっかくACラインにドミナスを投入した方、あるいは当フロアーにおいて各種ドミナスの素晴らしさを体験された方であれば、必然的にその影響力を拡大し使用範囲を広げていきたいと思うことだろう。それをユーザーサイドに立って実現しようとするのがオッド氏の素晴らしいところである。今井氏の言葉を借りれば「NOと言わないアメリカ人」であるという。すでに開発の最終段階に近づきつつあり、近日中にはサンプルが送られてくる予定である。私が販売したP−0のオーナーにはレポートをお送りする予定であるが、他店で購入された方のリストは当然私の手元にはない。こんな最新情報を発信している私から購入して頂ければ数々の特典がつくというものである。
さて、今回の随筆は異例なほど執筆に時間をかけている。それはPADに対して私が納得できないポイントを質問すればするほど、今まで知られていなかった新事実が次から次へと飛び出してくるからである。そんなやり取りを今井氏を通じて繰り返しているうちに、オッド氏はインターコネクト・ドミナス、ACドミナス、インターコネクト・プロテウス、の内部構造のイラストを送ってきたのである。ハンド・ドロウイングらしいイラストには不満な点もあり、コンピューターで書き直したものを本邦初公開として最終ページに追録したのでご覧いただきたい。今まで誰も見たことのないPADケーブルの内部構造なのだが、プロテウスの断面図を見たときに疑問が湧き起こった。インターコネクトのコンダクターであるバンドル(内部芯線の束の一単位)が5本あるのだ。普通であればプラス・マイナスで二芯、ないしは4芯という偶数の本数なのに、5本というのは意味がわからない。と質問したのである。これについては明確な回答が寄せられた。プロテウスシリーズはPADで唯一カスタムチューンを受け入れるケーブルであるというのだ。プリとパワーアンプをつなぐ場合でも、ある場合はホット側二本コールド側3本にしたり、またある場合は各々2本ずつとして1本をオープンにするとか、コンポーネント相互の特性に応じたバンドルの組み合わせをアレンジするという。そこで私は更に質問した。「そこまでのお話しはわかりました。しかし、何を理由に様々なメーカーの製品に対してチューニングの根拠にするのですか。ヒアリングオンリーであれば私はあまりお勧めできるものではないと思いますが。」と詰め寄ったのである。
その答えは第二部の第二章にあった。PAD独自のダイナミック・テスティングにより、実際にコンポーネントにケーブルを接続しDSPを使用したコンピューターとヒアリングの両面でオッド氏のいうスペクトラル・バランスを評価し開発しているという。驚くべきは、その対象となるコンポーネントのデータを実測の上で300種以上保管しているというのである。従って、P−0のDCケーブルに関しても科学的な背景をもとに設計されたものであるということが理解され完成が待たれるが、予定価格を本邦初公開しておく。液体シールドタイプが0.5メートルで109万円、1メートルで130.5万円、0.5メートルごとの追加は21万5千円。液体シールドなしは0.5メートルで59万円、1メートルで70万円、0.5メートルごとの追加は11万円である。
そして、同様なアプローチで取り組み、つい最近発売が決定したのが対ジェフロウランドの製品に関するDCケーブルである。ブリアンプではコヒレンス、シナジー、ペアとなるフォノイコライザー、ケイダンスにおける電源と本体間のDCケーブル。そしてパワーアンプにおいてもモデル9Ti、9TiHC、それからバッテリー電源のBPS9、8、6、2とアンプ本体をつなぐDCケーブルである。予定価格は以下のとおりである。プリアンプおよびフォノイコライザー用DCケーブルは液体シールドタイプが0.5メートルで60.5万円、1メートルで68万円、0.1メートルごとの追加は1万5千円。同じく液体シールドなしは0.5メートルで25万円、1メートルで29万円、0.1メートルごとの追加は8千円である。パワーアンプ用は正式決定していないので参考例となるが、液体シールドタイプが0.5メートルで115万円、1メートルで134万円、0.1メートルごとの追加は3万8千円。同じく液体シールドなしは0.5メートルで51.2万円、1メートルで61.2万円、0.1メートルごとの追加は2万円である。
これまでの私からの質問攻めと、実際にここでドミナスシリーズを導入してのノーチラスシステムの演奏を聴いた印象と、更に私が希望するオリジナル商品の製品化などと、数多くの課題とエピソードをかばんに詰め込んで、5月9日今井氏は機上の人となった。久々にPADを訪ねジム・オッド氏とビジネスミーティングを行い、数々の新製品に対する検討を行なうという。その出発の前日今井氏から電話があった。「川又さん、例のジェフロウランドのDCケーブルが入りました。まずはプリアンプ用の方が先に来ましたので本日送っておきますから、評価してみて下さい。」と、期待に胸膨らませるニュースが飛び込んできた。ちょうどその時に接客中であったコヒレンスのオーナーにお知らせると、「来週何とか時間を作って聴きに来ますよ。」と早速の好感触を得る。
5月10日「シーエスフィールドから納品です。」と待ちかねた知らせが入る。液体入りのDCケーブルはドミナスと同じ箱に入っているが、開けてみて驚いたのはドミナスとほぼ同じ仕上がりであることだ。当日は忙しさもあり、接続はしたものの本格的な試聴は明日にしようと、閉店時にはシステムエンハンサーをリピートさせてバーンインを開始する。翌日、こんな日は出社するのが楽しみであり、デスクについて何本かの電話を済ませ昼食も早々にして試聴を開始しようと定位置についた。と、ちょうどその時である。品川駅近くの高層ビルのオーナーであり、私のVIPのお一人であるM・S氏が、「ちょっと近くまで来たので…」と来店された。氏はコヒレンスを日本で最初に導入された方であり、パワーアンプも三世代にわたりジェフロウランドを愛用し、現在のモデル9TiHCも日本で最初に導入されている。当然前述のPADアイソレーション・プラットフォームにも大きな関心を寄せられ、ご自身のコヒレンスにも採用したいという言葉を頂戴している。この音にうるさいM・S氏といっしょに初物を比較試聴することになったのである。
まず、コヒレンスの望ましい電源コンディションとはどういうことか。ここから実験を始める。まずは付属品のACケーブルを使い、コヒレンスのAC駆動とバッテリー駆動を比較する。当然バッテリー駆動の方がよい結果となることは先刻ご承知のことである。次にM・S氏が現在使用しておられるカルダスのACケーブルに取り替えて同じ実験をする。ACケーブル接続状態ではカルダスを使用した分だけ音質の向上が見られるのだが、やはりバッテリー駆動にした方がよい結果が得られる。
この段階で、それではと私は電源部からACケーブルを引き抜き同じ曲をかけるとM・S氏はすかさず、「こっちのほがいいね」と反応される。コヒレンスのバッテリー駆動状態はプラス・マイナスのACラインをカットはするがグランドはそのままである。確定的な要因を特定することは出来ないが、不思議にACケーブルを外した方が情報量としてエコー感が鮮明になり一皮むけた鮮度が楽しめるのである。とにかくACケーブルがなくても堂々と演奏を続ける様には大きな説得力があり、これこそバッテリー駆動の本領を発揮している状態であろうとコヒレンスにおける最良の電源状態を特定した、はずで…、あったのだが…。
一切の電源供給ラインを断ち壁コンセントからの接続は一切ない状態であり、いかにPADと言えどもバッテリー駆動におけるコードレス再生ほど完璧なものに影響力をもつことはありえないだろうと、ついこの瞬間までは信じていたのである。ところが、その完全無欠であるはずのコードレス状態で課題曲を聴いた後に、ACドミナスを接続すると何が起こったか。これを体験すると、これまでの既成概念、常識が脆くも崩れ去っていく心中の音が胸の中で響き渡るのであった。魔訶不思議なことに、ACケーブルを外した状態よりもACドミナスを接続した方がよりノイズフロアーは低下し一層の美しさを醸し出すのである。つまり、グランドラインが完全にカットされたコヒレンスよりも、グランドラインに対してACドミナスの浄化作用を施した方が目をみはるばかりの向上が聴き取れるのである。いやはや、これには参った。私のかたわらで聴いておられたM・S氏からも思わずため息と笑いがもれる。「しょうがないなぁ。また買い物が増えちゃうなぁ。」とコヒレンスのオーナー皆様が持ち得ていた常識が目の前で覆されたが、より素晴らしいコヒレンスの変貌に喜びを感じておられるのは間違いないという表情である。
コヒレンスの理想的な電源環境とはどういう状態か、これまでのACコードレス化ではなくACドミナスの使用という前提のもとに、いよいよDCケーブルの試聴に取りかかることにした。前述のノーチラスシステムを使用するが、以前と違うのはD/Aコンバーターが新製品のNo.30.6Lになっていることと、PADのアイソレーション・プラットフォームを使用していることである。コヒレンスに標準で付属しているDCケーブルはカルダス社のBC−7Cというタイプのもので長さは80センチである。ケーブルの型式からすると芯線は七本あるのだろうが、5ピンのXLRキャノンプラグが両端に取り付けられている。この標準仕様のDCケーブルを最初に聴き、次にPAD製の液体なしの1メートル(29万円/以後NF(No Fluid)タイプと表記)、最後にドミナス仕様の液体入り1メートル(68万円/以後WF(With Fluid)タイプと表記)という順番でこれまでの課題曲を聴いていこうというのである。
最初にヨーヨー・マをかける。つい先ほどまでドミナス各シリーズを惜しみなく投入してきた音質を再度確認する思いで、これまで述べてきたように電源から始まってインターコネクト、そしてデジタルケーブルと、その段階ごとの道のりを改めて聴き直す充実感さえあった。期待していないと言えば嘘になるだろうが、コヒレンスに付属しているカルダス製のDCケーブルもパーツで注文すると5万2千円というレベルだけに悪いはずはない。さあ、それではとM・S氏にお断りしてNFタイプのDCケーブルに取り替える。主電源を抜いてしまうことから、コヒレンスはその都度リセットが完了するまで数秒間の時間がかかる。ああ、なるほど、質感に変化が表れているのがわかる。しかし、M・S氏からは言葉は出てこない。私も同感である。確かに質的な変化はあるもののドミナスを一度聴いてしまっているM・S氏も私も諸手をあげて投資効果を裏付けるほどの実感に乏しいのである。その表情を読み取り、それではとドミナスと外見がそっくりなWFタイプをつなぎ、同じトラックをスタートさせる。と、その時M・S氏の表情が変わったのを私は見逃さなかった。ABOがステージ上に並んでいるわけだが、各パートがまるで雛壇に乗ったかのように後ろへ奥へと展開し、ヨーヨー・マがスーッと手前に浮き出てきたかのような遠近感の拡大を聴かせるではないか。パッ、と演奏空間が広がったステージ上でバロック・チェロの演奏が周辺に拡散していく楽音の微粒子をかき集めてしまったかに思えるほどに濃厚な色彩感に変化していく。「これはいい、こうでなくちゃ。」と、私は胸中で叫んでいるのだが、M・S氏はまだ口を開かないので感想を述べることは先送りとした。
次に大貫妙子をかける。標準のDCケーブルで聴き始めるが、やはりこれまで慣れ親しんできた印象で特に注文をつけるポイントはない。さて、NFタイプのDCケーブルに取り替えてみた。大貫妙子のヴォーカルをそっくりヨーヨー・マに置き換えて推論することが出来るが、カルダスに対してクォリティーが劇的に向上したという実感はない。むしろ、個性の選択としてNFタイプが違うベクトルを持っていることだけは確認された。ところが、ところがである。次にWFタイプに差し替えたわけだが、この変化は想像以上に大きい。アコースティックギターとウッドベースのイントロが出始めた瞬間に感じ取ることが出来た印象は、大貫妙子のヴォーカルが美しいエコー感を発しながら歌い始めたときに確信に変わった。エコーが拡散する空間が一回り大きく感じられ、しかも楽音各々の余韻がこれまでに聴いた2本のDCケーブルに比べて圧倒的に長く、その消滅までに耳の網膜に焼き付けていく残像のような響きのグラデーションが倍以上に細やかな段階を見せつけるのである。私は思わずうなってしまうのだが、M・S氏はニッコリ笑って一言。「川又さんコレいいねぇ。やはり、私だったら液体入りの方を買うねぇ。液体なしの方はちょっとご利益が薄いみたいだなぁ。でも、これを聴いたら誰でも液体入りの方が欲しくなるんじゃないかな。」同感です。
さて、今度はdmpビッグバンドの「テイク・ジ・Aトレイン」を聴くことにする。今まで当然のごとく付属品のDCケーブルで各種ドミナスを評価してきたわけで、それに疑いをさしはさむ余地などなかったのであるが、同様にWFタイプに変えた時の変化が強烈に印象に残る。
このビッグバンドのメンバーはサークル状に大きな円陣を組むように演奏者が配置されているのだが、WFタイプに変えた瞬間にその一人一人が三歩下がってお互いの椅子の位置を広げたように演奏空間が拡大するのである。そして、例のルー・ソロフのトランペット・ソロが始まってみると、ソロフのポジションがスーッと奥に引き距離感を意識させるようになる。しかも、そのトランペットの音色自身が大きく変貌していることにすぐ気が付く。いままでは何も感じられなかったのに、一度WFタイプで聴いてしまうと、付属品のケーブルにはどうしても研磨剤入りのコンパウンドで磨いたトランペットのように思えてしまうのである。WFタイプできくトランペットはスムーズで滑らかの一言に尽き、若干の刺激成分を一緒に聴くことがトランペットらしさではないかと思っていた既成概念を一挙に吹き飛ばしてしまうのである。PADは心地よい興奮をコヒレンスに提供してくれた。これだったら投資効果ありとお勧めできるものである。
さあ、次はエーテボリ交響楽団による「金と銀のワルツ」をかける。クラシックを中心に楽しまれているM・S氏からどのような反応が得られるだろうか。導入部の弦楽の合奏を付属品とNFタイプで聴き比べる。今まで対象比較するものがなかったのでわからなかったが、カルダスの特徴が数多くの弦楽による演奏部分で聴き取れる。微妙にテンションを張り詰めた印象をカルダスに感じていると、その緊張感を緩和する方向でNFタイプのDCケーブルが中和作用をもたらすようである。同レベルのクォリティーと情報量において両社のケーブルが見せる個性を再認識するよい機会である。さて、WFタイプに差し替えて…と、「エッ!」思わず耳を疑うというのはこのことである。余韻感の拡がりが圧倒的なスケールの違いをイメージさせるものだから、あたかもホールそのものを取り替えてしまったかのような激変ぶりなのである。楽器の芯とエコーのセパレーションが鮮明になるほど個々の楽音の解像度が向上したと言えるだろうし、ヴァイオリンの一つ一つが点に近づくほどのフォーカスの絞り込みによって楽器間の空気にヴァイブレーションが感じられる。音声信号ではなく一定の電圧しか流していないDCケーブルに対しても、WFタイプがもたらしてくれたのはノイズフロアーの低減であった。M・S氏の表情は笑みよりも真剣なまなざしに変わっておられ、このタイミングを逃してはと最後の曲をおお急ぎで用意する。
ギドン・クレーメルの強烈なアルコが印象に残るクレメラータ・パルティカによる「タンゴ・バレエ」の冒頭の一分間を数回繰り返す。付属品においても何本ものドミナスのサポートを受けて、第一章で述べているような鮮烈な印象を記憶に残す。次にNFタイプに変えるのだが、クレーメルの強烈なアルコはそのままであり、勢い余った微量な刺激成分、もしくは輝きとも言えるまぶしさに目を細めるようなヴァイオリンは、本来こういう音なのであろうと納得していたものである。こんな輝きの度合いにカルダスとPADのキャラクターが反映されており、どちらを選んでも過不足なしということであろうか。M・S氏が弦楽の音に集中力を持たれているうちにと、今日だけでもう15回以上繰り返した作業でWFタイプに差し替える。さあ、いかがでしょうか、と横目でM・S氏の表情をうかがう余裕もないほどの衝撃が私の耳を襲った。思わず「本当かよ。」と、もう一度リピートする…。どう聴いてもクレーメルとクレメラータのメンバーが奏でる楽器の位置が違うのである。ノーチラスの後方1メートルほどにセットバックしてフォーメーションを組み直したかのように、あるいは広角レンズに取り替えてステージの全景をファインダーに納めたかのごとく、左右ノーチラスのユニット位置でスクリーンに映し出されていた演奏がポーンッと後方へ拡がりながら展開する。ステージの奥に演奏者が移動すると何が起こるか。そう、直接音と間接音の割合が変化し、遠のいた分だけエコー感が増量されるのである。しかし、決して視野が透明度を失うわけではなく、各楽器の鮮明さは維持されている。そして、先程までスパイスとして微量な刺激成分が本来録音されているものだと思っていたクレーメルの鮮烈なアルコに、快感を催すほどの開放感の高まりと徹底した不純物除去のトリートメント効果が発揮されていることに気が付く。実に滑らかな、そしてテンションに妥協を許さないアルコがステージ上の空気を切り裂くようである。もう一度、先程の分析を繰り返す。絶対に音声信号は流れていないDCケーブルでこんな変化が起こるのである。私がボリュームを絞りながらM・S氏の方に顔をむけると。「いやぁ、いいねぇ。まるで気仙沼が摩周湖になったみたいだよ。」いやはやM・S氏らしいうまい表現である。 予期せぬご来店であったが、エソテリックP−0とコヒレンスの両方でカルダスとドミナスの電源ケーブルによる比較試聴を体験され、おまけに愛用中のコヒレンスに思わぬパートナーが出現したことを確認し、今日は収穫の多いM・S氏との接客であった。しかし、考えようによっては収穫が大きかったのは私の方かもしれない。思わぬ初物の新製品を試聴され喜んでお帰りになるM・S氏の手には、「しょうがないなぁ、ここに来るといつもこうなっちゃうんだから…。」と笑いながら、しっかりとACドミナス2本がぶらさげられていたのであった。どうやら結果的には悪い時にM・S氏は来られたようである…。
実は、今井氏が渡米するというのでオッド氏に提案して欲しい私のアイデアを託すことにした。一つは第一章で述べているアイソレーション・プラットフォームである。既に多くの皆様から購入意志をうかがっており、当フロアーのオリジナル商品として独占販売させて頂くということで現在交渉中である。ただし3年前のコストとまったく同じには出来ないということ、サイズを幅45センチ奥行き50センチとして新規に型を起こすということから本文中で紹介している価格よりも高くなりそうである。予約を頂いた皆様には決定次第ご連絡を差し上げる予定である。 そして、次には大胆な提案をした。ドミナスをはじめとするPADの製品がオリジナル・ノーチラスに対してこの上もない相性を示してきたわけだが、このノーチラス専用ということでオリジナル商品の可能性を打診したのである。本文中でもプロテウスのカスタム・チューンについて述べているが、私からノーチラス付属チャンネルディバイダーをジム・オッド氏に提供し、オッド氏の技術力と感性で分析してもらいイン・アウト双方のインターコネクトを設計してもらうというものである。また、ドミナスやコロッサスのレギュラー商品でも、ノーチラスのチャンネルディバイダーの入出力用5ペアをパッケージ商品として特別価格を設定し、経済的に便宜を取り計らって下さるよう要請もしてある。
さて、オリジナル・ノーチラスのスピーカーケーブルは本体から直接引き出されており交換することは出来ないのであるが、これを何とか改善出来ないものかと私なりに知恵を絞ってみた。ノーチラス本体の内部配線を入れ換えることは、構造的な困難さとアフターサービスの点から私もリスクが大きいと判断している。しかし、実際の納入事例では純正仕様のケーブルが3メートルあるために余ってしまうこともあり、短縮したいという場合もある。そこで純正のケーブルをノーチラス本体から50センチ程度のところで思い切ってカットし、前述のようにEMI(電磁界障害)とRFI(高周波障害)に絶大な効果を確認したアイソレーション・プラットフォームにラグ端子を取り付けたものに接続し直すのである。そして、そのラグ端子の反対側に任意の長さとグレードのPAD製スピーカーケーブルが接続されパワーアンプに導かれるというアイデアを提案した。これに関してはオッド氏の潔癖症と完全主義によるリアクションがあった。つまり、ノーチラスのユニットに配線されている内部配線まで、どうしてすべてをPADに出来ないのかと言うものである。ノーチラスの存在は知っているというオッド氏であるが、さすがに内部構造に至る知識がないのであろうか、気持ちはわかるのだが大変難しい要求であった。このような形式のアイソレーションボードと中継用ターミナルの特注が出来れば本当に素晴らしいことなのだが、オリジナル・ノーチラスは世界的に見ても160ペア程度、日本でも30ペア程度の出荷台数というマーケットスケールなので量産を前提とする交渉が出来ない点が苦しいところである。いずれにしても、シグネチャー・シリーズのRLS(レディアント・ライト・システム)の完成品をプロモートするため、99年10月にジム・オッド氏が来日される予定があるという。その際に私が直接ノーチラスシステムをデモし詳細を説明すれば、ご本人からも発展的な意見が頂けるのではないかと期待している。おそらくオッド氏が来日した際には私が主催するセミナー、あるいはPAD製品のオーナーを招いてのパーティー、そしてRLSシリーズを駆使してノーチラスを鳴らす試聴会なども企画するだろう。こんな私とお付き合いして頂くと、地球上で最も素晴らしい演奏を聴くチャンスと豪華特典がたくさんあるということをご記憶頂ければ何よりである。
そして、あまり公表されていないことだが、近い将来PADは現在の5倍の広さに工場を拡大する予定であるという。前述のようにクライオジェニクスやマグネトストレーションなどを2回行なうという工程の煩雑さを解消し、よりクォリティーを追求していくためにも、それらの設備を自社工場に新設するというのだ。技術力が高いということは開発力があるということで、オッド氏のように向上心と好奇心が旺盛なエンジニアが開発力を合わせ持っていれば、将来レヴィジョンCタイプへ進化したり他社に出来ない新製品を開発したりという可能性は十分にある。経営的安定と世界的評価が高まるPADの未来にご期待頂きたい。
第四章「contribution to Super Audio CD」
99年5月21日はオーディオ業界にとって記念日となることだろう。次世代CDフォーマットとして開発を続けてきたスーパー・オーディオCD(以後SACDと表記)が発売された日であり、将来この随筆を読まれる方にもよいタイムマーカーとして記憶されることだろう。実は開発メーカーであるソニーのオーディオ部門とは色々な意味で懇意にして頂いており、この新フォーマットには昨年から触れる機会を作って頂いたのであった。98年3月10日、まだディスクという形態にはなっておらずコンピューターからハードディスクのデータを読みだす形でDSD(ダイレクト・ストリーム・デジタル)の音を聴かせてくれるというので、品川駅の近くにあるソニー芝浦テクノロジーを訪問したのであった。この日は全国の数社だけを厳選して新フォーマットの内覧会と試聴を行なうということで招待されたのだが、ぜひ午前中に来てもらいたいというのである。うかがってみて初めてわかったのだが、午後からは何社かまとめての試聴をする予定であるというのだが、午前中は私一人だけに聴かせてくれる時間を特別に作って下さったというのである。これには恐縮してしまった。小規模な試聴室に案内され、dmpやヨーヨー・マのサンプル曲を従来型CD、DSDからスーパービットマッピングに変換した現行方式CD、それに96キロサンプリング24ビットへ変換したもの、そしてフルDSDと、ウィルソンのシステム5を使用して聴かせて頂いた。この段階ではハードディスクのデータという形態のため、CDと同形状のディスクになってからの状態でP−0のメカ的な革新技術との比較は出来なかったわけだが、これほど情報量が増大するのかという事実に次世代方式という期待感が強く感じられたことを鮮明に記憶している。
そして、その年の10月、当社のマラソン試聴会で海外のハイエンド・コンポーネントとDSDを共演させようとする企画を私が言いだし、事前に試作品の音を聴きたいという希望に答える形でSACDプレーヤーのプロトモデルを当フロアーに持ち込んでもらったのである。この時にはハイブリッドタイプのディスクをSACDのプロトモデル、それに発売直後のノーチラス801にP−0とマークレビンソンやイルンゴというシステムで比較して試聴することができたのであるが、期待の新フォーマットに対して私の採点は辛いものだった。再生周波数帯域、ダイナミックレンジ、と各項目にわたり大変なハイ・スペックを実現しているのはわかるのだが、この随筆で度々述べているような実態感のあるフォログラフィックな楽音やヴォーカルの再現性ということについては今ひとつであった。フォーカスを意図してあまくしたようなフワァーッとした輪郭表現に対して注文をつけたのである。同席されたソニーの開発担当者も認めていたのだが、何とか動作するようになった段階のプロトモデルだけに、それ以上の要求は酷というものだと、それ以来多くのユーザーの質問に対して静観する立場を取ってきたのである。
実はSACDの発売日は、私は前日の振り替えで代休を頂戴しており、量産モデルのSCD−1を初めて聴くことになったのは翌22日であった。それも開店して間もなく訪れた川崎市在住のオリジナル・ノーチラスのオーナーM・Y氏の要望があってセッティングしてからというのだから、SCD−1の実物を聴く瞬間まで私の静観するという考えに変わりはなかったのである。前述しているノーチラスシステムで使用しているコヒレンス2のとなりにSCD−1をセッティングして、早速M・Y氏といっしょに初物の試聴を開始したのであった。フルにドミナスのサポートを受けて絶好調で鳴っているオリジナル・ノーチラスに対して、まずM・Y氏から「いいですね、やはりドミナスを買い足さなくちゃだめかなぁ。」とおほめの言葉を頂戴する。実はM・Y氏は既にACドミナス1本をパワーアンプのジェフロウランドMC6に採用しているのであった。この最初の第一声ではSCD−1にはアンバランス・インターコネクトのドミナスを使用していた。SCD−1にはバランス出力もあるのだが、バランス出力を使用するときにスイッチをオンにするということになっており、事前にソニーの設計から聞いていたように内部回路はアンバランス設計なのである。従って、便宜上設けられた変換型バランス回路のラインから信号を取り出すよりは、直接アンバランスの出力から信号を取り出そうと考えたのである。
まず、SCD−1を操作して感じたのはローディングメカの精密感あふれる動作と静粛性である。ふだんP−0を使い慣れている私、あるいはM・Y氏を含む一般のP−0オーナーからすれば何と静かなことか。これで再生音さえ問題なければ言うことはない。最初はソニーからプロモーション用に配布されているウィントン・マルサリスの国内ライブ録音のハイブリッドタイプのディスクを演奏する。第一印象はかなりいい。昨年秋に聴いたプロトモデルに比べて格段の進歩が聴きとれ、トランペットのマウスピースに吹き込まれるウィントンのブレスがかすれる質感が何とも生々しい。しかも、ステージに立つ彼のフォーカスが見事にとらえられており、みなと未来ホールの天井に高く高くエコーが飛散していく。自宅で愛用するノーチラスが鳴らすSACDの演奏を何曲もかけるうちに、満足感と安心感がM・Y氏の表情に表れてきたではないか。そこで私が切り出す。「Yさん、ここでちょっと実験してみましょうか」と、私は新品の箱入りACドミナスを持ち出し用意すると、SCD−1付属品のACケーブルのままでウィントンのディスクを再度ローディングして2曲目の「Spring Yaounde」をかけた。小ホールのステージを取り囲む聴衆のざわめきが数秒間続きピアノとのデュオによるウィントンのトランペットが響き渡る。この冒頭の一分程度を繰り返し、付属品のACケーブルからACドミナスへと取り替えたのである。リセットされたSCD−1がTOCデータを読み込む時間がじれったく感じられる数秒間がすぎて、再びホールのざわめきが戻ってきた。その瞬間にM・Y氏は言葉ではなく表情で違いを察知したことを表し、私も同感であるとうなずいていた。付属品のACケーブルで聴く客席のざわめきは、幕が上がる前のステージの中で聴いていたようなのである。ところが、さすがのSACDと言えども、電源ケーブルをドミナスに変えた瞬間にさっと幕が上がり客席の人々の顔が見えるようになった鮮明さに変化するのである。これはソニーの設計者も経験したことはないだろう。当然のことながらウィントンの演奏そのものも緞帳にさえぎられることなく、ホールの隅々までエコーを響き渡らせる空間表現へと変貌する。「全然違いますね。」とM・Y氏も一言。そして「川又さん、これ買います。」と突然振り返って一言。私も「あっ、ありがとうございます。」と答える。あっけないくらいにSACDの第一号のお買い上げとなった。いやはや、定価50万円のSCD−1に対して、電源とRCAピンケーブルのドミナスで156万円のケーブルを使用したことになる。これを非常識なアンバランスと考えられる方も当然いることだろう。しかし、これほどのケーブルを投入して何にも音質に変化がなかったとしたら私も認めるところだが、SCD−1の再生音が劇的に情報量を増大させるという現象を目の当たりにすると果たして無駄と言えるのだろうか。第三部第六章においても164万円のメゾ・ユートピアに対して約1600万円のエレクトロニクスとケーブルを組み合わせるという実例を紹介しているが、対象とするコンポーネントに潜在的な可能性があるのならば、挑戦する価値ありという判断する対象はSACDと言えども同じことである。事実SCD−1の再生音が変化するということは、このプレーヤーの出力端子までは、しかるべき情報量が来ているということではないか。「愚行をおかさずして可能性の発見はない。」これは誰の言葉かというと、この時の心境から思い浮かんだ私のマキシムであった。
さて、初回に発売されたDSDソフトはマイルス・デイビスの名録音が多数ある。ジャズを愛されるノーチラス・オーナーである吉祥寺在住のK・S氏に接客の合間をぬって電話をした。「Sさん、SACDをノーチラスで聴くと素晴らしいんですよ。」と私は誘惑の手を差し伸べる。「川又さん、実はこれからうかがおうかと思っていたところなんですよ。マイルスのDSDソフトは何があるんですか。うちから同じCDを持っていきますから比べてみましょう。」と熱心な提案がもたらされる。
これは面白くなりそうだ。K・S氏が来られるということで楽しみにしていると、中央区にお住まいのノーチラス・オーナーN・I氏がお見えになった。「あれ、Sさんとお待合せですか。」実は、ここにお見えになるノーチラス・オーナーを私が紹介しているうちに、親しくなったお二人は意気投合して先日N・I氏のお宅をK・S氏が訪問してこられたという。N・I氏の素晴らしいインテリアに溶け込んでいるシルバーノーチラスを、K・S氏の趣味とするカメラで見事な写真に納めてきたというのである。私はてっきりお二人が申し合わせてご来店になるのではないかと思ってしまったのである。「いやいや、違うんですよ。でも偶然ですね。」とN・I氏は笑って答えられる。
そろそろかな、とお待ちしていると「こんにちは。」とK・S氏ご夫妻がドアから顔をのぞかせる。「いや、先日はどうも…。」と双方で笑顔の挨拶が交わされ、「でも偶然ですね。」とオーディオを通じて親交の輪が広がるシーンを見ていると私も仕事に張り合いが出るものである。さて、これがSACDです。と、再び私のトークと試聴実験が始まった。午前中にM・Y氏に行なったプレゼンテーションを繰り返す。P−0オーナーのK・S氏から思わず最初の一言。「静かですねぇ。」同じくP−0オーナーであるM・Y氏とまったく同じ感想が口をついて出てきた。ウィントン・マルサリスの大ファンであるK・S氏からサンプル盤の演奏を聴いて拍手が上がる。「いいですね、想像以上だ。ちょうどサブのCDプレーヤーが一台欲しかったんですよ。」と好感触を得る。次にK・S氏が持参されたケイコ・リーのCDソフト「ビューティフル・ラブ」でSACDとの比較を行なうことにした。実は同じ曲を使って昨年の秋にSACDのプロトモデルとP−0を軸とする現行CDとの比較を行なったことを思い出した。あの時のSACDはケイコ・リーのヴォーカルがフォーカスを結ばず、左右ノーチラス801の中間にドーンと大きな音像を広げていたのを思い出した。最初に現行CDをP−0にローディングしK・S氏が愛用されているイルンゴを使用してタイトル曲の「ビューティフル・ラブ」をかける。何とも聴きなれた感触で同席された皆様からは何のコメントも出ない。さて、同じ曲をSCD−1でスタートさせた。「エーッ!」と声にならない声をK・S氏がもらしたのか、あるいは私自身の声だったのか。オリジナル・ノーチラスは空間に浮かぶようにヴォーカルを三次元的な定位感で表現するのであるが、この瞬間に出現したケイコ・リーの口元は彼女を聴くようになって以来初めて、これ以上のフォーカスの絞り込みはないだろうと思われるほど最高のジャストピントで歌い始めたのである。現行CDではある種の高域ノイズ成分がスクリーンとして楽音という色をのせる土台になっており、言葉で言い表すことのできない平面をイメージさせる何物かの上に楽音が描かれていた。しかし、SACDで聴くケイコ・リーにはこのようにイメージされるスクリーン、もしくはパーテーションのようなノイズ成分の幕が一切ないのである。すぐそこの空間にポンと彼女の口元が浮かび上がる快感を感じたのは、どうやら私だけではないようだ。「いいですねぇー!」と、ため息に無理やり言葉を乗せたコメントが皆さんの口から引き出される。と、K・S氏は次なる興味を示された。「川又さん、この普通のCDをSCD−1で聴いたらどんなものでしょうか。」なるほど、現行CDプレーヤー単体としての音質も気になるところである。「実は、SCD−1で聴くCDの音には5種類あるんですよ。」と私はここから説明を始めた。SCD−1のCD再生には24ビット可変デジタルフィルターが使用されており、22キロHz以上のロールオフ特性を5段階にわたり選択できるのである。「ビューティフル・ラブ」の冒頭から8秒間をサンプルとして何度も繰り返し、順番にフィルター特性を変えていくとケイコ・リーのヴォーカルの質感とエコーの残留成分に変化が表れる。「ね、こんな感じにニュアンスが変化するんで、どれをSCD−1のCD再生と考えるかはユーザーにおまかせするしかないんですよ。」これにK・S氏の反応は素早かった。「へえ、なるほど、CDプレーヤーとしてもいい出来ですね。全然不満はないですよ。」
「そろそろマイルスを聴きましょうか。このソフトは同じものを買い直してきて3枚も持ってるんですよ。」とK・S氏のリクエストが出る。持参されたリマスターもののCD「カインド・オブ・ブルー」をP−0とマークレビンソンのNo.30.6Lで聴き、SACDと比較しようというのだ。曲はK・S氏お気に入りの一曲「フラメンコ・スケッチ」である。現行CDシステムは両者合わせて450万円という定価になる。ポール・チェンバースのベースからマイルスが入ってくるまで数瞬の間合に当時のテープヒスが一部の高域情報として流れてくる。これだけ聴いていれば幸せだったものを、とこれからの出来事で皆さんは感じられたことだろう。それでは、とSCD−1で同じ曲をかけた…、その瞬間。テープヒスの音色に劇的な変化がある。あれ、ポール・チェンバースのベースはこんなに輪郭が整っていただろうか、マイルスのトランペットの音像はこんなに収束したフォーカスを見せていただろうか。同じマスターからの表現にこれほどの違いがあるとは驚きである。しかも、たった50万円のSCD−1が単体で再生しているのだ。テープヒスの質感が明らかに楽音と空間的に分離してくれたおかげでプレーヤーの存在感が我々と同じ空気の中に感じられる。今まで一種の膜のようにノーチラスの周辺に充満していたヒスノイズが、完璧になくなることはありえないとしても画面上のバーノイズのように特定の帯域に固定されたようになり視野が格段によくなったのである。これには参った。40年前の録音が蘇った、ではない。もともと40年前のマスターの音質は我々の想像以上に高品質であったということだ。いやはや、DSDというフォーマットはアナログ音源に対する忠実度がこんなに素晴らしいものだとは思わなかった。しかも、今まで未発表であった別テイクの同じ曲がボーナストラックとしてSACDソフトには収録されている。マイルスのファンであれば初めて日の目を見るアナザーテイクに魅了されるに違いない。事実、この「フラメンコ・スケッチ」の別テイクは冒頭のポール・チェンバースが俄然パワフルに演奏しており、マイルスのテンションも一段と高いものが収録されているのである。これは見逃せないだろう。このように2時間以上にわたりSACDを楽しんで頂いたN・I氏とK・S氏が出された結論はこうだった。「川又さん、これ買います。」とお二人の声がそろう。何と今日一日でSACD三台のお買上げとなった。
翌23日の日曜日、好天に恵まれてご来店の数は多い。このフロアーにあるソファーが満席になる9名の皆様がSACDとノーチラスの共演を熱心に聴いていかれる。これほどお客様が多いと、はっきり言って商売にならない。うれしい悲鳴である。「仕方がない、もう一台展示しよう。」とソニーに発注を出す。一店舗に同じ商品をだぶらせて展示することなど前代未聞である。当社で確保した初回入荷分のSCD−1はアッという間に売り切れてしまった。今や遅しと追加の一台を待っている翌月曜日、ノーチラス・オーナー3名が来店される。「いや、川又さんのところにくればあると思ったんですよ。」と、お目当てはSACDであり、しかも私のところではノーチラスで試聴することが出来る。当然オーナーの皆様は考えることは一緒のようである。これまでにも登場している世田谷区在住のオーナーS・M氏に前述と同じパターンの試聴を行なうと、即答で一言「川又さん、これ買ってくよ。」これで4台目となり、もうお一人千葉市在住のN・A氏は「来月お金を持ってきます。」とうれしいご返事を頂戴した。こんな状態が数日続き私自身がゆっくりと試聴する時間が中々持てない有様であったが、何とか翌日には落ち着いてSCD−1を分析することができた。
まず、SCD−1のリアにあるバランスアウトのスイッチをオンにして、アンバランス出力との音質を比較した。幸いに私の手元には両規格のドミナス・インターコネクトがあり、まったく同一条件で比較することができる。このSCD−1を購入するとアメリカのテラークレーベルで制作したハイブリッドタイプのディスクが一枚同梱されてくる。この1曲目エリック・カンゼル指揮シンシナティー・ポップス・オーケストラによる「Let Youeself Go!」をアンバランス出力で聴きなおす。これまでの数日間で何度も聴き慣れた解像度の素晴らしいオーケストラがノーチラスの後方に展開され、ホールの大きさを見事にイメージさせる。さあ、これをバランス伝送に切り替えるとどうなるか。この違いを聴き分けるには私も数回リピートしなければならなかった。ごく若干であるが音像が膨張しているようであり、楽音そのものの質感に白濁したような色彩感の変化が感じられる。この違いを聴きわけるには相当な熟練が必要かもしれない。でも、このフロアーでノーチラスを聴き慣れている方であれば、私が事前にチェックポイントを説明して何とか判別できるだろうという程度である。
さて、SACDの技術的な内容については雑誌でも取り上げられており、ここで解説するとなると私の未熟さが暴露してしまうので差し控えることにする。期待される音楽用の次世代フォーマットとして再生周波数帯域は100キロHz以上、ダイナミックレンジも120デシベル以上というのが二大キャッチフレーズとして記憶されている方も多いことだろう。「ほう、さすがに100キロHzまで延びている音は素晴らしい。」と発言された人がいたとしたら、本当はちょっと違うんだということでこれから述べることを思い出していただきたい。それはSCD−1本体のリアパネル、バランス出力スイッチの隣にあるスライドスイッチが鍵を握っている。このスイッチには金属片でストッパーがかけられており、出荷時にはスタンダードと表示されたポジションに固定されている。取り扱い説明書やカタログにも、同時発売されたソニーのプリ・パワーアンプを使用する場合以外はスタンダードポジションでご使用下さいと書かれている。SACDは原理上1・4メガHz程度の周波数特性を持っているのだが、実際には設計側で数々の要素を考慮して帯域制限をしているのである。スタンダードポジションでは50キロHzでマイナス3デシベルのターンオーバーを設定し、5次のGIC型ローパスフィルターを信号が通過することにより100キロHzでの減衰量はマイナス30デシベルになる。金属片のストッパーを外してスイッチをカスタムポジションに切り替えると、このターンオーバーは70キロHzに変更され100キロHzでの減衰レベルはマイナス18デシベルとなる。このようにSACDのキャッチフレーズに関する正しい解釈、または近い将来に発売されるであろうDVDオーディオに関しても、100キロHzまでフラットで出力されるということはないと考えている。なぜか?現在一般ユーザーが使用しているアンプのごく一部によっては発振を起こし、スピーカー破損などの可能性があるので安全策を取ったということである。もちろん、人間は100キロHzの音を単音として認識することもできないし、従来のシステムが可聴帯域での再生を前提とした設計になっている再生音上では大差ないというのがソニーの主張である。
さて、5月25日SACDの登場で盛り上がる当フロアーにソニーからSCD−1の設計者ご本人が音を聴きにくるという。ソニー株式会社ホームAVカンパニー、オーディオ二部商品設計一課の柏木氏と稲山氏、それに当フロアーの御馴染みである佐藤氏と道下氏が来訪された。まず、ノーチラス・システムでウィントン・マルサリスの「Spring Yaounde」を聴いて頂く。「いやぁ、いいですね。」と稲山氏から称賛の言葉を頂戴すると、私は「昨年の音を聴いてどうなることかと思っていましたが、よくここまで仕上げられましたね。」と素直な評価を言葉でお返しした。「ありがとうございます。」本当にうれしそうな顔で稲山氏は答える。この辺で来店されたお客様に私がお聴かせしている実験をひとつ。ACドミナスで聴いて頂いたわけだが、ここでACケーブルを付属のものに差し替える。「・・・・。」無言のままで注目されている設計者の横顔を見ながら、もう一度ACドミナスに差し替えた瞬間笑顔が戻った。「いやぁ、参っちゃいますね。これでもいい物を選んだつもりだったんですが。」と稲山氏「この電源ケーブルは38万円するんですよ。」と私が言うと一同に笑いが広がってしまった。いやいや、ごもっともです。セットメーカーとしてACケーブルのコストにそれほどかけられるわけがないと私もわかっていますから。ハイテクの限りを尽くしたSACDであっても所詮はコンポーネントの一部、ACドミナスの貢献度は設計者自らが認めるところとなったのである。
そして、この時にもスタンダード/カスタムの切り替えについての説明を受け、設計者の立場からどんなアンプにつながれるかわからない以上はスタンダードポジションを設定したという判断に私も納得した。その場でも切り替え実験をしたのだが、明確な判断が出来ない以上ふたつのポジションに変化なしということでこの場は終わった。しかし、翌日の午前中はありがたいことに…?、来店客がないことをこれ幸いにと疑り深い私がじっくりと比較試聴する時間ができたのである。昨日のように5人も人間がいて、しかもセンターポジションではなかったのだから、今日は納得できるまで聴き込んでみようと思ったのである。ここで私は2枚のサンプルディスクを選んだ。ひとつはエリック・カンゼル指揮シンシナティー・ポップス・オーケストラによる「Let Youeself Go!」である。スタンダードとカスタムの両ポジションを何度も切り替えながら相違点を探す。何と言っても50キロHz以上の帯域で起こる変化を、そうやすやすと発見できるわけがない。オリジナルノーチラスはプラスマイナス0・5デシベルの範囲で20キロHzまで、マイナス6デシベルの範囲では25キロHzまでを再生周波数帯域としている。もちろん25キロHz以上の帯域も緩やかな下降線をたどりながら出力しているのだろうが、その倍の超高域で起こる変化を見せてくれ、と言うほうが無理なのであろうか。それでは、と国内におけるフルDSD収録、マスタリングというプロセスで制作されたウィントン・マルサリスのサンプルディスクはどうか。ここでは一曲目の「Portrait of Louis Armstrong」を聴き始めた。1回目、2回目、スタンダード/カスタムのポジションを3回ほど切り替えていくうちに、「ムム、これは。」というところが見つかってきた。2曲目の「Spring Yaounde」とは違って大ホールのステージは奥が深い。そのステージの右奥から聞こえてくるシンバルのリズムに全神経を集中する。もう一度確認のためにスタンダードポジションに「ああ、こんな感じ。」と、しっかりとその音色を記憶して素早くカスタムポジションに切り替えてリピートする。「ウン、間違いない。変化してるぞ。」と大変微妙な違いをやっとの思いで発見した。カスタムポジションの方がシンバルの位置を手前に移動した感じ、もしくはシンバルの色彩感が鮮明になった感じと言えるだろうか。メーカー側の心配も無理からぬところであるが、ここで鳴らすノーチラスシステムでは問題はなかった。それどころか使用するアンプの選択やルームアコースティックのチューニング、そしてドミナスに支えられた伝送系と、スペックでは計り知れないシステムの完成度が超高域でのレスポンスを捕らえたことに一種の勝利を感じてしまった。たとえ100キロHzまで再生可能というスーパー・トゥイーターを使用しなくても、ここのノーチラスとドミナス、そしてジェフロウランドによるシステムは、そのまま次世代CDフォーマットに対応できると自信を持って断言できるのである。
エピローグ
異例とも言える過去最大の長編作がケーブルメーカーを主題にしたものということで、営業的に見ても意外に思われる方も多いと思われる。しかし、前述しているように私が納得できない点、あるいは知っておきたいと思われる点が多かったこと、それらの質問に対する答えが実に興味深く説得力があり手が抜けなかったこと、そして試聴されたユーザーの感動レベルが非常に高かったことなどが長文となってしまった理由だ。 しかし、いかにもPADのケーブル(私が評価したドミナスが前提だが)は高価である。だが、これまでに述べてきたPADとケーブルに対する認識を改めることで、価格対比の価値観は変化するだろうと考えている。この3か月間で私はPADは世界中で最もハイエンド思想に徹したメーカーであると断言できる自信が持てるようになり、ジム・オッド氏の人柄に本来のオーディオファイルが持つべきロマンとミュージックラヴァーとしての情熱を感じ取ることが出来たのである。
2年前に書いた第41話で「ハイエンド」という言葉の定義について、傅信幸氏のコメントを引用して表現している一節があるので紹介したい。
「ハイエンドオーディオ機器は確かに高価である。しかし、金ムクのパネルだから、ダイヤがボリュームに埋め込まれているから高価なのではない。そんなのはまやかしだ。ハイエンドオーディオの設計者は自分に忠実でうそがつけなくて、妥協するということをあまり知らず、了見の狭いせいもあって没頭し、ただし一種の鋭い感は働いているが、その結果生まれてきたために高価になってしまうのである。」「しかし、そうやって誕生した製品は、わかるユーザーを大変納得させる。ハイエンドオーディオの存在価値はそこにある。ユーザーは音楽とオーディオに情熱を注ぐ人である。そういうあなたと同じ思いをしている人たちの作った作品は、あなたの五感から更に第六感まで刺激するに違いない。それをハイエンドオーディオと呼ぶ。」
実は、先日業界誌の取材で記者が訪れ、私に「ハイエンドオーディオとは、いくら以上のことを言うのですか。」と尋ねられ、「金額ではありません、思想的な意味ですよ。」と、この傅信幸氏の言葉に含まれる意味を説明したことがある。さて、皆様の価値観をもう一度自問自答していただきたい。あるスピーカーメーカーは振動板の材質にこだわった、あるいはネットワークの素子に最高級のパーツを採用した。その結果いくらになったという。また、あるアンプメーカーは最高品質の基板を作るために高価な新素材を採用し、また電源に要求される能力を妥協なく設計するために法外な価格であることを承知で特注トランスを搭載した。その結果で価格はこうなった。これらはみな設計者がコストに対するパフォーマンスに自信と根拠を持っているからであり、言い替えればスピーカーやエレクトロニクス製品の評価基準にプロとして実に多項目にわたるパラメーターをもっているからに他ならない。
皆様が手を触れて操作するもの、あるいは音楽を聴きながら眺めることが出来るものに対しては、皆様は知らず知らずのうちにメーカーのこうしたセールスポイントをおおいに認めているのではないだろうか。ところが、配線してしまえば見ることも触れることもないケーブルに関してはどうだろか。そして、仮りに皆様が認めたコンポーネントを設計通りのパフォーマンスで使いこなせないとしたら、一体その責任はどこにあると考えられるだろうか。見方を変えれば、ここは金のかけどころだ、妥協したらいいものは出来ないと、設計者本人がわかっているということが肝心なのである。そして、それがわかっていなければ評価の対象となることなく業界から自然消滅していくだけである。私が申し上げたいのは、PADをなぜ世界最高のケーブルとして位置付けるのか、という問いかけに対して今回の随筆がその答えになっているという自信なのである。私がこれまでに聴いてきた高価なケーブルは多数あるが、価格の根拠となる技術的な説明を求めても「非公開ということで教えてくれないんですよ。」と輸入商社が情報公開を諦めてしまっているか、あるいはそれを執拗に要求していないのだろう。
ケーブルの善し悪しは聴けばわかる、ヒアリングがすべてだ。と、こんな理屈を分からなくはないが、感性が支配するヒアリングでの判定はあまりにも主観的にならざるを得ない。ところが先程述べたスピーカーやアンプの設計者たちは科学的な測定結果を満足させるためにコストをかけ、そしてそれを測定の上で証明しているではないか。ヒアリングがすべてだと言いはるのは日本のオーディオ業界をばかにしているのか、あるいは設計者の技術レベルが低いのだろうとしか考えられない。オーディオケーブルというアイテムの商品は価格の裏付けが難しい。逆に言えばメーカーのノウハウを明かさず、マーケティングで一度成功すれば大変に利益の上がるアイテムでもある。消費者側からこれを裏返しに考えれば何をか言わんや、ということになるだろう。
本文中にも述べているように、スピーカーの価格の10倍以上もするエレクトロニクスとケーブルを使ったり、50万円のSACDプレーヤーに対して3倍もするドミナスの電源とピンケーブルを組み合わせたりとか、平然と価格的アンバランスのシステムを皆様に聴いて頂いている。しかし、多くの場合それを聴かれる方の感性を大いに満足させ、こんな音は今まで聴いたことがなかったと、皆様自身が自分の聴覚で反応し確認した新しい発見に大きな価値観を感じているのである。ここで日々繰り返されている皆様の感性の自己発見、つまり舌ではおいしいものをおいしいと感じ、目では美しいものを美しいと評価する、これらと同じように耳でも自分の好ましいと感じるものをはっきりと指摘し判断するという感性での認識がオーディオにとっても大変重要なのである。
ここで話しは変わるが、フジテレビ系列で放映している「料理の鉄人」は既に多くの人々が知る番組であると思う。私も可能な時にはよく見ているのだが、卵、野菜、肉、魚、等々日常の生活で口にするもの、言い替えれば、どこのスーパーマーケットでも買える食材をテーマにして調理するわけだが、毎度のようにテーマ食材に対してキャビアやフォアグラにトリュフ、中華食材でもフカヒレやツバメの巣などと、テーマ食材の価格の一千倍もする高級食材を平然と当たり前のように使っている。これを皆さんはどのようにお考えになっているだろうか。同様に非常識とも思われる私のデモ・システムを皆様はどのようにお考えだろうか。 テレビの世界はしょせんは作り物、非現実的な見せ物を真剣に考えたことなどないという方も多いと思われる。エンターテイメントとして彩られた演出によって作り出される数々の料理は、多分一生かかっても我々の口に入ることはないかもしれない。しかし、おそらく当の鉄人たちも、それをわかって作っていると私は思う。つまり、自分の店で採算に乗せられる商業ベースのメニューとしては考えていないだろう。試聴の対象とするコンポーネントに対して得られる限りの贅を尽くし、その能力と魅力を絞り切れる限界まで抽出して聴いて頂く。テーマ食材が例え数百円で買える庶民的な食品であっても、その素材の可能性を追求して世界中のあらゆる食材を値段にこだわらず駆使して調理し味わって頂く。聴くという行為にしても味わうという行為にしても、対象とする事物に視点を絞り込んだときに、それをどの様にして第三者に伝えるかという方法は、それをふるまう当事者の感性によって天と地ほどの差があるだろう。そこに「オーディオの鉄人」になりたいという私の希望がある。
あの場所で作られる料理は鉄人たちの自己表現であり、料理の世界に彼らが寄せるロマンに他ならない。この点において、私が日常的に組み合わせする価格的アンバランスなシステムが演奏する音楽も、同様に私の自己主張でありオーディオに対するロマンの現われであるとご理解頂ければこれ以上の喜びはない。
今回の執筆中にPADを知れば知るほど、あきれるというか感心するというか、とにかくジム・オッド氏の各分野に対するパラメーターの発見と研究が実に広範囲であることが印象に残った。他のケーブルメーカーが着眼し開発したパラメーターの数十倍もの項目をオッド氏は見ることができるのである。それは彼の優秀な頭脳がもたらしたものだろうし、その項目の一つ一つに妥協せず、自分に忠実であるがゆえにうそをつけず、儲けようとして製造コストを抑えるという知恵は彼の辞書の中にはないのである。それがピューリスト社が付けたプライスであり、シーエスフィールドが生き残るために今井氏が判断した日本価格なのである。蛇足であるがドミナスがPADのすべてではない。ミズノセイのRCAピンケーブルは一メートル5万円であり、PADには7ランクのバリエーションがあることを補足しておく。
同様に私が知り得るハイエンドオーディオの多種多様な組み合わせによって発生する音質変化の可能性と、その素材となる個々の音質的特徴に由来する膨大なパラメーターの集積は私の経験と分析から蓄積されてきたものである。従って私が演奏するシステムにおいても自分自身がいいとわかっているものしか使わないし、例え価格がどれほど高価であっても納得いかないもので皆様に演奏をお聴かせしようとは思わない。
さあ、それではピューリスト・オーディオ・デザインの製品に対する価値観はどうしたら理解できるか。もちろん、当フロアーにお越し頂けるのが最短最高の手段でもあり、今回の随筆を読んで私を信用していただくのも手段の一つであるが、(特に今後製品化するアイソレーション・プラットフォームは雑誌に紹介されていなくても当フロアーでの実演により既に予約が入っており、これを機会に私の信用を賭けても皆様に予約をお勧めしたい)今井氏の同意を得て全国の皆様に可能な限り実物の貸し出しによって評価をして頂きたいと考えている。さえないパフォーマンスであれば3万円でも高いと思う。そして、これを知らなかったら一生後悔するくらいに感動できる、皆様が知らなかった未知の音楽体験を提供してくれるのであれば、例え数十万円であっても皆様自身の感性が認めたものとして納得出来るのではないだろうか。
オーディオという再生芸術のレベルを考えたとき、自分が「井の中の蛙」であることを知らないことは本人にとって一番幸福であると思う。しかし、オーディオケーブルに関して自分は「井の中の蛙」であったと多少なりとも自覚され、久しく自宅以外のステレオ装置は聴いたことがないという方であれば、PADを使用して私がセッティングしたシステムで一度は音楽を堪能されてみてはいかがだろうか。純粋にオーディオのことだけを考えているジム・オッド氏、素晴らしいものは日本のユーザーに紹介していくという純粋な使命感を持たれる今井氏、最高の演奏をお聴かせしたいという純粋な気持ちで日々努力している不肖この私。そして、純粋に音楽とオーディオを愛してやまない人であれば、皆様を含むピューリストの連鎖を実際の演奏によって感じとって頂けるだろう。その鎖の輪の最初のひとつとして本編が役に立てば本望である。【完】
筆者より
最後までご精読頂きありがとうございました。いやお疲れ様でした。
多かれ少なかれ本文をお読み頂き皆様が感心を持たれたこともあろうかと思います。ここで当フロアーのプロモーション予定をご紹介させて頂きますので、実際の音質を検証する手段としてご利用頂ければ幸いです。
・恐らくは総額一千万円に及ぶドミナスを中心としたPADケーブルを導入して本編で述べている試聴が可能です。ぜひご来店ください。また、全国を対象にPADケーブルの貸し出し試聴を行ないます。特にジェフロウランド、エソテリックP−0のオーナーは関心が高ま る新製品も用意されています。アイソレーションボードの予約も同様、気軽に私、川又まで電話、FAX、Eメールなどでお申し込み下さい。
・ジム・オッド氏がRLSシステムを携えて今秋来日予定。当フロアーのノーチラスシステムでヒアリングの予定。セミナー等のイベントの企画もあり、現時点から同様に予約を受け付けます。
・今年九月に雑誌発表となるフランスJMラボのユートピア全シリーズを全国に先駆けて展示しております。実際の音質をご確認ください。
・次世代音楽専用フォーマットSACDを本文にある最高クラスのコンポーネントを駆使して試聴して頂けます。期待を裏切りませんよ。
・ウィルソンオーディオの新製品システム6が六月下旬にサンプル入荷。ジェフロウランドの新世代パワーアンプ、モデル12Ti同時期入荷。これらは私に評価分析してほしいということで期間限定で導入します。気になる方は電話でアポイント下さい。日程が決まり次第連絡します。
・PADとは相反するようですが、ケーブルの存在を否定する新伝送方式CASTシステムを搭載するクレルの新型パワーアンプ650MCが六月末に到着予定。ここには三日間ほど滞在して試聴分析する予定。
・LINNの超薄型モノ・パワーアンプ、クライマックス(KLIMAX)を聴いた。予価ペア240万円で何と500Wのパワーもうすぐ入荷。
本文にもあるように偶然の出会いが思わぬ発見につながることがよくあります。私に気軽なコンタクトを取って頂きたいというのも本随筆を制作している目的の一つであり、今後は小さなことでも気兼ねなくコミニュケーションが図れるよう私も努力していきたいと思います。どうぞ
今後ともよろしくお願い致します。サウンドパーク・ダイナ 川又利明
|