第四十七話「純粋主義者」
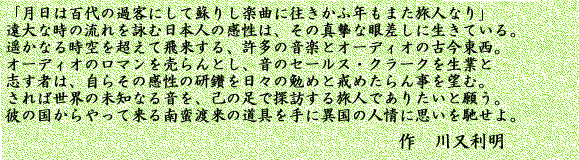 第二部「physics」
私の私見であるが、オーディオ用ケーブルに対して、ここ数年は日本と海外ではセールスポイントが大きく異なると思われる。なぜならば、皆様も記憶しておられると思うのだが、日本の場合にはOFC、LC−OFC、PCOCC、などと銅の結晶体の大きさを取りざたする時期があるかと思えば今度は6N、7Nなどと素材の純度を表す小数点以下の桁の数で競いあったり、銅の原子構造をもってストレスフリー・カッパーという独自表現も登場した。ところが私が日頃親しんでいるレベルのケーブルは、素材の優秀さもさることながら自社の製品のアピールポイントはほとんどと言って良いほど構造的な特徴を主張するメーカーが大多数なのである。カタログにおいても構造の解説が多くの項目を占め、次に絶縁方法、端子へのこだわりと取り付け方法、そして最後に導体の素材にふれるという優先順位である。広告の紙面を飾るこうしたキャッチフレーズを読んで、どうせだったら素材と構造の両面で理想的なものはないのだろうか、と思われた方も少なくないのではないだろうか。私はPADに関する調査と分析を進めていくうちに、これこそこの両分野を十分に満足させるだけのノウハウを持ちえる最高級のケーブルであるという結論に至った。まず、世界中でPADしか行なっていない大変個性的な素材へのこだわりを理解しようと試みたのだが、何とPADがシーエスフィールドに送ってきた英文資料は量子力学の講釈からはじまっているのである。すなわち、「通常の物体は全て原子の集合体である。原子は中心の原子核とその周りを回る電子で構成され、原子は約1億分の1センチ、原子核は更にその10万分の1。中性原子は陽子と同じ数の電子を持ち、電気的に中性である。原子核の陽子数は原子数と呼ばれ元素を決定する。」というような内容で、日本では高校の物理の科目で登場してくる基本的な項目からジム・オッド氏の解説が始まるのである。非鉄金属、特に銅を取り上げての原子数と元素の解説、銅を素材とするワイヤーの特性、金属結合と結晶格子、結晶格子をまとめている原子間のエネルギー、不純物欠損と転位欠損、そして銅の製造からワイヤーロッドへの加工と続く。次に電気の定義と電流の原理、伝導体と絶縁体、電圧と抵抗、オームの法則、電力と磁場、電流と磁力線、ここまできてから電子が金属固体に及ぼすエネルギーの話に戻り、半導体と誘電率、そして周波数が登場して果てはハンダの原理と特性にまで堂々40ページに及ぶ文献なのである。しかも分かりやすく専門家がかみくだいた解説をしたものではなく、ジム・オッド氏からの英文をシーエスフィールドの今井氏が辞書引きで訳したものなので正直にいって面白いと言える文章ではない。また、私も読んでいるうちに頭が痛くなってしまうので、ことさらこの文章の解説にこだわっても仕方ないだろうという結論に至った。当然この随筆を読まれる方にしても原子物理学の講釈などは期待しておられないだろうし、ジム・オッド氏の本意でもないであろうと思い切って割愛させて頂くことにした。しかし、「あなたの作ったケーブルは何が素晴らしいのか」と問いかけてくる日本人に対して、初等物理の講義からはじめたというオッド氏の実直さと純粋さが印象付けられるエピソードである。なぜならば、ごく一般的なケーブルメーカーは「どこどこで作られた高級素材を使用して…」とか「ラボラトリーグレードの純粋な銅を厳選して…」のように出来合いの材料を大手の金属メーカーから入手するところから自社の製品作りをアピールし始めるのだが、PADはこのスタートラインからして違うのである。
さて、前述のように多くのケーブルのセールスポイントは素材である銅や銀の純度にこだわるところが多く、純度の高さによって音の善し悪しに導いていこうとする論法が主流を占めているように見受けられる。しかし、この素材論争の時点からPADの独自性が大きく感じられるのである。まず、PADのケーブルはすべてがマルチストランドの多芯線構造であるということが前提となり、同時にマルチゲージストランド構成となっている。ストランドとは「糸、ひも」という意味であるが、もう一つ「ひも状の中に通したもの」という意味も含んでいる。つまり、数種類の異なるゲージ(太さ)のワイヤーが撚り合わさって一本のバンドルを構成しているということになる。これは異なった数種類のゲージを採用することでスペクトル・バランスが良くなることを目的としており、スペクトル・バランスとは、位相、周波数特性、情報量を左右するダイナミックレンジ(英文ではアンプリチュードとなっているが、適切な訳が思いつかず私の解釈である)の均一な伝送を示している。ここでPADから注釈があったのだが、研究と試聴を繰り返していく手法で開発を行なっているが、仮りに科学的に証明されていないことでも結果が良ければ採用するという柔軟性ある姿勢をもっているという。もちろん、そのような事態における解析は継続され、電子的な分析だけにとどまらず物性化学や量子物理学の分野でも研究していくという。そして、同時にスペクトル・バランスを決定する要素としても絶縁体の特性に重きをおいており、テフロン、ポリプロピレン、ポリエチレン、など単一の絶縁体で同一素材の導体を覆ったときにも入出力信号の特性は異なってくる。そこでPADでは複数の絶縁体を採用してスペクトル・バランスを整えているのである。さて、素材の話に戻るが、PADのケーブルは一部の製品を除いては一貫してコンダクター(導体)に合金を用いている。ドミナスを例にあげれば、プラス側の極性に使用するコンダクターには、金、銀、銅、プラチナ、アルミ、イリジウム、ロジウム、という7種類もの素材をメルティングした合金を使用し、各々配合が違う9種類のストランドをバンドルに束ねている。ここで前述のマルチゲージという見方からドミナスを分析すると、何と一本のバンドルには合計8種類のゲージが組み合わされている。AWG(アメリカン・ワイヤー・ゲージ)規格による14GAと、26から32GAのレンジで7種類からなるゲージを採用している。カルダスのように黄金分割比で各々の割合を構成しているわけではないということだが、どうやらこれから先の詳細に関しては企業秘密になっているようである。マイナス側のリターンワイヤーには、同様な合金素材を使いながら13種類のストランドからなるワイヤーでバンドルを構成している。しかし、オーディオ用のケーブルとして、金、銀、銅、ここまでであれば他社の製品で御馴染なのだが、プラチナ、イリジウム、ロジウム、などの大変高価なレアメタル(稀少金属)を使用しているとは大きな驚きであった。大手金属メーカーからドラムリールで大量にワイヤーを買い付けて原料としているメーカーとは大きな違いである。ここでオッド氏に尋ねてみると、PADは工場を三つ持っているというのだ。一つはRAW WIRE(未加工線材)を作る工場で、原材料を同社のノウハウによってミックスし溶解された合金から未処理の合金ワイヤーを製造する。これを後ほど述べるようにNASAに持ちこんでクライオジェニクス(超低温処理)してから第二工場へ送る。次の工場はアッセンブリーを行なう工場で、ストレスに対応する処理として強力な磁場を用いる磁力処理を施して撚りあげ端子加工や液体の注入を行ってケーブルとしての商品化を行なう。第三の工場はスペシャルプロジェクトが目的であり、エクステンションボックスやアイソレーションプラットフォームといったケーブル以外を製造している。
前章でPADのケーブルはNASAにおいて特別な処理を施されているとあるが、ジム・オッド氏はNASAの依託研究員であり特別に施設を使用する許可をもらっているのだという。他にも民間の石油掘削会社二社が同じ施設を借りているということで、ビット(ドリルの刃先)をクライオジェニクスすると寿命が四倍になるというのである。さて、PADの大きな特徴としてデビュー当時から言われているのがクライオジェニクス(超低温処理)であるが、具体的にどのような行程を経ているのか今井氏も見たことはないという。五月に訪米する折には今井氏もNASAの内部に案内してもらい、この秘密の処理現場を初めて見せてもらう約束になっているというので報告を待ちたいところである。従って、現状ではジム・オッド氏から口頭で聞いたことを私が知り得る範囲で言い替えることで説明することしかできないのだが、先に述べているように金属中の原子は結晶格子の振動に媒介されて互いに引き合いクーパー対と呼ばれる電子対をもって運動している。この電子の運動は絶対零度(マイナス273.15度C)に近い超低温状態では、それら電子間の相互作用が新しい秩序状態に変化していくという。この超低温状態まで温度の変化をどのような時間経過でもたらしていくのか、またどのような器具を使って低温状態を作りだすのか、その辺の情報は一切明かされていないのだが、NASAという強力なバックアップを活用できるオッド氏の人望とこだわりの強さは、まさにハイエンドという志向を十分に満足させてくれるだけの説得力を持つものである。
絶縁体が回路中の伝導体を取り巻いているものを誘電体と呼んでいる。理屈としては内部の導体が通している電流に対して絶縁体の原子が反発しているということで説明されるが、この絶縁体がある一定の電圧範囲で絶縁機能を維持できる領域を誘電率として表している。それ以上の電圧がかけられた場合には絶縁体中を電流が流れはじめる絶縁破壊が起こる。この誘電率は絶縁耐力とも言い替えられ、絶縁物の厚み、温度や湿度、物理的圧力や経年変化、そして誘電体にかけられた電圧と経過時間の長さによっても変化する。この誘電率が低下すると導体から電気的エネルギーを吸収してしまい熱や漏れ電流として放出されてしまう。 |