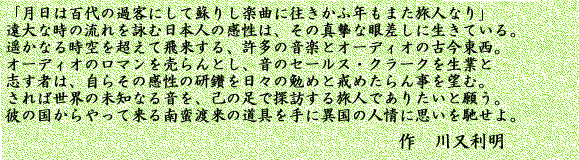第四十四話「スタンディング・オベーション」
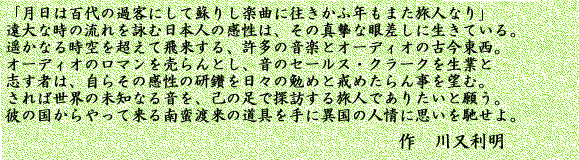
第二章『奴隷の開放』
第一部「プロトモデル」
1997年8月、ティアックより新製品の資料が送られてきた。
タンノイのキングダム15と一緒に記載されていたのがP−0(ゼロ)
である。技術的なポイントは文書で説明はされているのだが、その段階
ではとくにピンとくる手ごたえは感じられなかった。
数年前から本格的なトランスポートを作りますよ、と同社の技術者から
話は聞いていたが、正直に言ってあまり大きな期待はしていなかった。
なぜならば、前述のP−2sも評判は良かったものの、以前ワディアが
同社のP−2メカを搭載して商品化したWT−2000、それを新型メ
カにバージョンアップしたWT−2000s、そしてワディアのフラッ
グシップであるWADIA7と、すべて実物を並べての比較試聴を行っ
た結果、明確に音質は価格通りの序列であると判断を下していたからで
ある。技術力はあっても、音の取りまとめはやはり外国製にはかなわな
いであろうと高をくくっていたのである。
そして、9月に行われた「インターナショナル・オーディオショー」の
会場でP−0の実物を見た。一般公開の時間を終えてから行われたパー
ティーの席上でも、何人かの顔見知りの評論家からP−0はいいよ、と
声をかけられた。「ウ|ン、本当かな・・・・。」確かに重厚な作りである
が、私の性分として自分のホームグランドに持ち込んで聴かなければ納
得は出来ない。
私が総合プロデューサーを務めることになった当社のイベントである
「マラソン試聴会」にも、P−0をとりあえずエントリーはしたが、疑
り深い私は、ティアックの営業担当者に率直な希望として数時間でいい
からP−0を持ち込んで下さるように要請をしたのである。
10月18日、まだ音が出るものは一台しかないというP−0が、
エソテリックの設計者を伴って私のフロアーに持ち込まれた。
「これはまだプロトモデルの段階なので、最終的な音質決定にはもう少
し時間をかけたいと思っています。」と言う設計者の言葉などは上の空
で早速セッティングに取りかかる。いよいよ実物の音が聴けるのである。
当時も複数のスピーカーがあったのだが、このトランスポートの違いを
聴きわけるには聴きなじんだものが良いと判断し、システムもひとつに
固定して試聴を開始することにした。
スピーカーはウィルソンのシステム5、パワーアンプはジェフローラン
ドのモデル9T、プリアンプも同じくジェフローランドのコヒレンスと
した。私はP−0を聴く上で、今の段階ではあまり多くの他社製トラン
スポートと比較するつもりはなかった。
狙いはだだひとつ、エソテリックのP−2sメカを搭載したワディア7
と一対一の比較を集中して行いたかったのである。
当時はマークレビンソンのNO.31.5Lやゴールドムンドのミメー
シス36PLUSといったフィリップスのメカを搭載したトランスポー
トもあったのだが、V・R・D・Sメカとの相違点をこれまでに何度とな
く比較してきており、ワディア7が現有トランスポートの中でもっとも
リジッドな質感とテンションを持っていると判断しているからである。
従って、D/Aコンバーターもワディア9と一台に固定、トランスポー
トからの接続もまったく同じSTリンクの光ファイバーを使用し、ワデ
ィア9の入力を切り替えるだけという単純な比較を行うつもりであった。
さて、システムの配線が完了して、実際にP−0にディスクをローデ
ィングする段階となった。ここで気になることが一つ表われた。
ローディングする際に発生するメカノイズがけっこう大きいのである。
メカの設計者に直接質問すると。
「これはP−0のスレッド送りメカの発する音です。0.1ミクロンの
精度でピックアップを送るには1回転で500ステップという超高精度
なステッピングモーターを使用し、これを32ビットのマイクロプロセ
ッサーによって更に20分の1に細分化しています。この回転運動をリ
サーキュリング・ボールスクリューベアリングによって直線運動に変換
しています。従って、ピックアップはステッピングモーターの1回転で
はわずかに1ミリの移動しか行われず、ローディングの際に再生に必要
なディスクの情報を読み取るには、2秒前後で6センチ前後の移動を行
なわなければなりません。一般的なユーザーが許容してくれるだろうと
思われる時間内にピックアップをそれだけ動かすには、毎秒30回転と
いう大変な高速でモーターを回さなければなりません。そして、このス
レッド送りのリサーキュリング・ボールスクリューベアリングを貫通し
ている、ネジが切られたシャフトとステッピングモーターを連結してい
るカップラーがステンレス製であるというのが機械音を発生してしまう
原因となっています。このノイズを消すのは簡単です。モーターを含む
メカをゴムなどでフローティングするか、ボールスクリューベアリング
の内部に潤滑剤のような半液体を注入すると言った方法が考えられます
が、変位する素材や構造を採用すればもうこの段階で0.1ミクロンの
精度は出なくなってしまいます。当然の事ながら、ローディングと距離
をおいた頭出しの際にしか発生しないもので、演奏中には出ないノイズ
ですからご理解頂きたいものです。」なるほど、再生中には発生しない
のであれば、私としては何の問題もない。
それを言葉にしようと思った矢先に、「中をお見せしましょうか。」と
言われて私は「ぜひ!」を二回繰り返して返事をしてしまった。
まず驚かされるのは重量8 にも及ぶというアルミ削り出しのメカシャ
ーシーである。フライス盤が削り取った跡が幾何学的な模様を残し、サ
ブミクロンオーダーの精密メカを搭載するのにふさわしい重厚さである。
(私はこの時に前述のステレオサウンド誌に掲載されたすべての内部写
真と同じものを見たことになる。)
トップパネルを外した状態でディスクをローディングすると、前述のス
レッド送りメカがステッピングモーターの回転によって運動しているの
が眼前で観察出来るようになった。
「キュン、キュン。」という微弱な動作音を伴って、本当に頻繁にスレ
ッド送りのメカが偏芯に追随しているのがわかる。
この音も聴きようによっては気になるのではないか。
そこで、ふと気がついたことがある。
演奏が始まった内周では1秒間に8回転以上も高速回転しているのだか
ら、スレッド送りのメカもそれに合わせて高速稼働しているわけだ。
外周にピックアップを移動する、つまりディスクの回転数を落したらど
うなるのかを実験してみた。トラック送りのボタンで「ヒュン、ヒュン」
とディスクの最終部に曲を飛ばしていくと、「アレーッ!」と意外とも
思えるような静けさに変わってしまうではないか。
「なるほど、ディスクの冒頭で聞こえていたものはスレッド送りメカが
あまりにも高速で動くために発生した振動がエネルギーを蓄積していた
のか。その証拠にスレッド送りが運動する回数が減ると、ほとんど無音
になってしまう。これこそがメカの工作精度を表しているものなんだ。」
と、私は頭の中でうなってしまった。感心してばかりもいられない。
とにかく音を聴かなくては、とディスクをローディングした。
通常のCDでは、TOC(テーブル・オブ・コンテンツ=目次の意)デ
ータを読み取って、ディスプレーに何トラック(曲)入っていて総演奏
時間が何分何秒と表示が表われて演奏スタンバイ状態となる。
しかし、P−0はこのTOCデータを読み取ってディスプレーに表示を
出した後も、「ヒュン、ヒュン。」と何かを読み取っているのである。
これを質問してみると意外なことがわかってきた。
「P−0は先ず最初にTOCがあるかどうかを見ます。ない場合にもP
−0自身がTOCを作成するプログラムを内蔵しているので、独自にT
OCを作りリードインを可能とします。まあ、これは一般的なことでは
ありませんが。次に、そのディスクの線速度を読み込みます。」
そこで私はエッ、と質問を割り込ませた。
「線速度を読み込むと言っても、そもそもCDの線速度は1.2から1.
4メートルと決められているんじゃないですか。」
「そのとおりです。しかし、CDは一枚一枚ごとに線速度は、その1.
2から1.4メートルの間でまちまちなんです。皆さんがお使いになっ
ているCDプレーヤーも同じようにディスク一枚ごとの線速度を読み取
ってから再生するようになっているんですよ。」
「あぁ、そういうことだったんですか。では、欲張りなディスクは線速
度を遅く(短く)して収録時間を増やそうとすることも出来るわけです
ね。」そうそう、とエソテリックの設計者はうなずいて続ける。
「でも、実際の市販ディスクにはごくまれに規格よりも線速度を遅くし
ているものもあって、プレーヤー側はそれにも対応しているんですよ。」
更に、P−0の驚くべき賢さを披露してくれたる。
「実は、一般のCDプレーヤーの初期データの読み込みはここまでなん
ですが、P−0はリードインエリアから一定のあるポジションまでピッ
クアップを進めて、そのディスクに記録されているピット列のトラック
ピッチをも読み込んでおり、そのディスクに記録されている曲のスター
トIDまで含めてP−0内部にディスク一枚ごとの地図を書き込んでし
まうんです。」
ああ、なるほど。P−0はトラックピッチを最初に読み込み、更に再生
中も絶えず偏芯量を測定し、サーボ用の32ビットマイクロプロセッサ
ーに信号を送り続けているのだ。その変位量に合わせてマイクロプロセ
ッサーが演算処理したサーボ用のデータによって、再生中もずっとスレ
ッド送りのモーターに駆動電流が送りこまれるというわけだ。
そして、普通のCDプレーヤーはディスク内部のスタートIDを1、2、
3、と数えながら曲の頭を出していくのだが、P−0は読み込んだデー
タによってディスク上の曲の頭がある場所が地図としてわかっているの
で、いきなりそこへピックアップをストレートに運んでいってしまうと
いうことか。私が、こんなふうに繰り返すと、「そうそう、簡単に言う
とそういうことです。」と肯定の言葉が戻ってきた。
そうか、CDは一枚ごとに線速度が違っているということも初耳であっ
たが、P−0はトラックピッチまで読み込んでしまうとは凄い。
ということは、ディスク一枚ごとにトラックピッチも違うんだろうか。
これを質問すると、ちょっと困った顔をされて、「ウ|ン、実は・・・。」
と言葉の歯切れが悪い。ああっ、そうなんだ、0.5ミクロンのピット
のスケールから見ればディスクを製造する上でけっこうな許容範囲があ
るんだ。それをプレーヤーのサーボがすべての誤差を吸収しながら音を
出していたということか。
大体これまでのCDプレーヤーはサーボ用に8ビット程度のマイクロ
プロセッサーを使用している例が多かったが、P−0が32ビットもの
高速演算処理を必要としているのもこの辺からうかがい知れる。しかも、
このP−0のマイクロプロセッサーのデバイスはプラグイン方式で交換
が出来るようになっているので、将来より高精度なチップが開発されれ
ばアップ・トゥ・デート出来るのである。雑誌記事にもあったように、
ピックアップの光学系の交換によって将来の新フォーマットにもバージ
ョンアップ可能ということもあり、ピックアップと制御系チップの両分
野において将来性を確保しているのは大きな魅力でもあり、未来永劫に
変わりようのない高水準なメカニズムの完成度の高さがそこにある。
単純に言えば、いくら新フォーマットのスーパーCDが登場しても回す
のは円盤であり、ディスクの宿命である面ブレと偏芯はいつまでも続く
大きな課題であるからだ。
ここに、商品として、道具として、P−0の魅力が色あせない不変性と
他の追随を許さない機能的長寿命が確立されたことになるのである。
さて、前章で述べたフィリップスのレッドブックは、そもそもCDシ
ステムの中でディスク側の規格を明示しているものである。
後日、その点が気になった私は、さる筋からCDに関するJIS(日本
工業規格)の資料を取り寄せて見たのである。
それは、このような前書きから始まっている。
「この規格は、1987年版として発行されたIEC908( Compac
t disc digital audio system )を翻訳し、技術的内容及び規格票の様
式を変更することなく作成した日本工業規格である。」
その第二章にディスクパラメータとして次のような記載があるのだ。
7・3・1・1 垂直方向変位 12cm±0・5ミリ
7・4・1・1 トラックの半径方向の振れ140p−p(±70ミク
ロン)なるほど、ヨーロッパの規格でもJIS規格でも、前述している
ようにディスクの偏芯量は最大で140ミクロンと決められている。
そんなことを考えつつ、ディスクを交換しながらP−0のスレッド送
りを駆動するステッピングモーターの回転をしばらく見詰めてみる。
「先程の説明では、P−0は0.1ミクロン精度でピックアップをコン
トロールするということでした。そして、スレッド送りのモーターは、
ピックアップを1回転で1ミリ移動するんでしたね。」
私が何を言いたいのか、エソテリックの設計者はもう半分わかったよう
で「そうですね。」と口元をほころばせながらうなずいた。
「規格によるディスクの偏芯量はピークで140ミクロン以内とされて
いますが、1回転で1ミリ移動するということは140ミクロン以内の
偏芯量であれば、ステッピングモーターの回転は大体・・・え−と・・・、」
恥ずかしいのですが、私の頭は計算に弱いので考える時間がかかる。
「ちょっと待って下さいよ。P−0のスレッド送りメカで140ミクロ
ンの送りを行うのであれば、大体7分の1回転で済むことになりますね。
でも、でも、この動きは七分の一回転どころの騒ぎじゃない。もっと強
烈にモーターが、言い換えればスレッド送り自体がもっと大きく振幅し
てますよ。これって、どういうことなんです。」
エソテリックの設計者は、笑顔から困惑顔へとあっという間にヘンシン
(変身)してしまった。ウ−ン、この切り替えのサーボも大したもんだ。
「実は、あまり我々の口からは言いたくないんですが、ディスクの偏芯
に関しても基準となるテストCDがあって、そのディスクには意図的に
作られた偏芯量が0から始まって、70、140、210、280、と
段階的に記録されているんです。ラジカセやミニコンポ、あるいはカー
ステレオなどのCDプレーヤーでは、トレーシングアビリティーを最重
要視しなければなりませんので、280ミクロンという偏芯にも対応出
来るサーボを考慮する必要もあるでしょう。デリケートな音質よりは、
まず音が途切れずに出るということのほうが商品としての優先順位が高
いんです。ソフト屋さんにはソフト屋さんの都合もありますから、こん
な答えでご勘弁頂けないでしょうか。」
「それではP−0はどの程度の偏芯に対して調整されているんですか。」
「あくまでも先程の±70ミクロンに対応することを前提に考えていま
す。とにかく、P−0はいかなる状態でもジャストポイントでレーザー
スポットが偏差ゼロでピットを捕らえています。」
いやぁ、これには驚いた。P−0のスレッド送りのモーターが相当大
きく回転しているように見えるのだが、半回転していれば500ミクロ
ン、4分の1回転では250ミクロンの偏芯があるということである。
そう言えば、スレッド送りの直線運動もじっくりと凝視を続ければ肉眼
でも振幅運動しているのがわかる。ということは、今まで、そして他社
のCDプレーヤーは数百ミクロン単位の偏芯に対しては、すべてレンズ
が動いて対応していたのだ。いや、正確に言えばレンズの可動範囲を超
えてしまう偏芯にはピックアップ自体をスレッド送り機構を通じて動か
していたという事になる。そして、言い換えれば、それほど強力なサー
ボによって音楽を途切れることなく再生しているということなのだ。
思い出してみると、たった0.5ミクロンのピットをレーザースポット
がトレースしなければならないのに、数百ミクロン単位でピット列の軌
道がずれるということは、ひとつのピットの数千倍もの振幅でサーボが
追いかけているということになる。
LPレコードの音溝が、本来の数百数千倍も蛇行してしまったら笑い
話にもならないが、いやはや、CDのミクロの世界は恐るべし、そして
何気無く使っている道具の底深さを改めてかいま見てしまったようだ。
そこで、もう一つ疑問が頭に浮かんだ。
「JIS規格などはディスクそのものに対しての各種パラメーターを設
定しているが、肝心のレーザースポットの大きさに関しては何も触れて
いませんね。」
「ええ、その通りです。対物レンズとディスクの間隔、それにビームス
ポットの直径もメーカーの設計次第で各々決められており、特にこれと
いった決まりはないんですょ。」
そうなんだ、改めて驚くのと、ソフト側には良く言えば柔軟性のある配
慮、ハード側では統一された基準がないというCDのフォーマットを、
業界の内部にいる私にしてさえも16年目にして初めて知ったのである。
私は最後に思い切った質問をしてみた。
「私はこれまでにも数多くの最高級と言われるCDシステムを聴いてき
ました。メーカー各社では、トランスポートとD/Aコンバーターのク
ロックを統一するGENロックやワードシンク、タイムシンクと呼ばれ
るような電子的な対策を、またワディア9のようにTBCをインターフ
ェースに採用することで独自のクロックでデジタル信号を受け入れるな
ど、電子的な手段でジッターの害悪に対応する手段に重きをおいてきま
した。V・R・D・Sを開発した貴社では、これら電子的手段によるジッ
ター対策と、P−0に代表されるようなメカニカルな解決手段と、どち
らがより多くの効果があるとお考えですか。」と、エソテリックのメカ
ニズムを設計した当事者に質問をぶつけてみた。
この答えは早かった。「間違いなくメカの方です。我々がP−0の開発
に関して自信を持って言えることは、すべての機構と素材の決定に関し
てそのすべてをヒアリングの上で決定してきたということです。今回お
持ちしたプロトモデルも、ターンテーブルのブリッジ部分はアルミです
が、これから最終の詰めでスチールに素材を変更するかもしれません。
このように些細なこともヒアリングしていくと、メカの変化による音質
の変化が想像以上に大きいことを実感しているわけです。それは、間違
いなくメカです。」
と何とも説得力のある力強い返事が返ってきた。
ここで、アナログプレーヤーで独自の理論に基づき、何度も試作を繰
り返しながらΣ5000を設計された寺垣武氏の開発における苦労話し
が思い起こされた。
「要は原因があるから対策が必要になるんですよ。だから、原因そのも
のがない設計をすればいいんです。」
当意即妙と言おうか、エンジニアとして的を得た発想と発言であった。
そもそもCDトランスポートで発生するジッターがなくなれば、電子的
な対抗手段などは必要ないのである。
「非接触」である以上、サーボは絶対に必要なのだが、その使い方を考
えれば「過ぎたるは及ばざるが如し」ということになる。
いや、ほんとに素晴らしいものを作って下さいました。
「P|0の開発ご苦労様でした。」と、思わず心の中でねぎらいの言葉
が出てしまったのである。
さて、そろそろ音を聴かなければと試聴を開始する。
私は大体においてスピーカーならスピーカー用、アンプならアンプ用、
トランスポートならトランスポート用とテストする際のソフトは聴くポ
インをこれまでの経験上で決めてあり、連続して次々と課題曲をかけて
いった。低域、高域とチェックポイントを何回も比較し、各項目におい
て分析した結果を頭の中の採点表に記入していく。
あっという間に10数枚のソフトをかけ、ワディア7が唯一勝っている
という点を何とか見つけだした。
その他はすべての項目で私はP−0の方に軍配を上げていたのである。
「何というか、低域のボリューム感と言おうか、弾力性と言うか、厚み
や重量感といったものはワディアの方が楽しく聴かせるね。」と感想を
述べると、エソテリックの設計者もうなずいている。
「実は我々が最後の課題としているのもその点なんですよ。最終のツメ
をこれからやりますから、ぜひ期待していて下さい。」
私としては本心からの評価を大分控えめに言葉にしたのに、この上更に
進展があるというのか。土曜日という週末の書入れ時だというのに、そ
れから6時間もの時間でプロトモデルのP−0を聴きこんでしまった。
一体何が、この音のキーポイントになっているのか、技術的好奇心がア
ドレナリンの分泌に比例してふつふつと湧きあがってきたのである。
第二部「1001」
97年も押し迫った12月27日、待ちに待ったP−0の一号機が運
ばれてきた。待った甲斐があったのか、偶然にもシリアルナンバーは正
真正銘の「1001」である。エソテリックの10周年を記念する製品
でもあり、この「1001」は私も感謝の気持ちを込めた記念碑として
ずっとここに置いておきたい一品にしたいものだと考えたのである。
そして、当面の間は日本広しと言えどもP−0実物を見て聴けるのは本
当に唯一これ一台だけでなのある。
早速梱包を解いてセッティングにかかる。
すると昨年のプロトモデルにはなかったパーツがあるのに気がついた。
説明書ではフットと記載されているが、直径8センチ厚み1センチで中
央にスパイクの先端を受けるくぼみがある円盤である。
「なかなか細かいところまで気をつかっているな。」と感心したのだが、
この後、このフットが仇になろうとは思いもよらなかったのである。
鉄製のスパイク脚によってセットするラックにキズがつかないように
と、P−0の底部にはプラスチックの脚が付いており、これがわずかに
メインとなるスパイク脚よりも長いのである。つまり、P−0をそのま
まラックの上に置くと、まずプラスチックの脚が接地してスパイク脚が
浮いているのである。そこで先程の付属のフットを四コーナーにあるス
パイク脚の下にはさむと、今度はプラスチックの脚が浮いてスパイクが
接地するという具合だ。
次に、ごっつい電源部から本体に太い2本のケーブルを接続して電源を
とる。この電源用ケーブルもプロトモデルでは60センチの長さであっ
たが、当時私が短かすぎると言ったものだから商品化に際しては120
センチとしてくれたようである。この長さがあればラック上段に本体を
置いて、ラック外に電源部を離しておいても接続出来るであろう。
もし、これ以上の長さを必要とするときには私にご相談頂ければ特注も
可能である。ただし、エソテリックでは電源ケーブルの長さにもこだわ
りがあるようで、あまり長いものは音質に影響ありとコメントされた。
さて、ディスクをローディングしての第一印象。
プロトモデルではトレイの開閉にともないメカノイズがあったが、本番
の仕上がりではトレイの動作音は大変静かになった。むしろ、リジット
な構造のイメージが高度な精度感となって聞こえる動作音は信頼性を物
語るようで心地良い機械音となっている。合格である。
ローディングの完了を待ちきれずに早速プレイボタンを押す。
「あれ、ターンテーブルの回転音もスレッド送りの動作音も、昨年のプ
ロトモデルより大きく聞こえるぞ。もうティアックも年内の業務を終え
てしまったので連絡も取れないし、こりゃ、まいったなぁ。」
P−0入荷を待ちわびて早速来店された何人ものお客様からも同様な疑
問の声が上がる。
V・R・D・Sのターンテーブルは250グラムの重量であったが、Pホ
0ではマグネットが大型化しており270グラムと重たくなっている。
そして、従来のP−2sはそれを2相6極のブラシレスモーターで駆動
していたのだが、P−0では同型式で3相8極という強力なモーターに
変更され、モータートルクは従来の4倍になったという。
静止状態からスタートさせると、グググッ、とターンテーブルにトルク
がかけられる音がして回転が安定すると無音状態となる。
しかし、今回はこのターンテーブルの回転音にスレッド送りの音も加わ
って耳ざわりと言えるレベルの大きさになって聞こえてくるのである。
そして、P−2sのメカはゴム系素材によってフローティングされてい
るが、P−0は一切のフローティング構造を持たないリジッドな作りに
なっており、内部の動作音はそれとわかる聞こえ方をするのである。
そこでハッと思い付いて、アシスタントの社員を呼んで二人で回転中の
P−0を静かにほんのわずか持ち上げた。すると、耳ざわりなメカノイ
ズがフッと嘘のように消えてしまったではないか。
「なんだ、そういうことだったのか。」
私のフロアーでは厚み5センチの木材で作られた重量70キロのラック
にメインのシステムを収納しているのだが、気を利かせたつもりの付属
フットの円盤が動作中のP−0のスパイクとラックの間で共振していた
のである。かといって、この円盤で高さを作ってあげなければスパイク
が浮いてしまうので本来の音は期待出来ないであろう。
そこで、私はP−0をよいしょっとひっくりかえし、プラスチック脚の
ビスをゆるめて外してしまったのである。
これでスパイクが直接接地するようになりメカノイズも大分軽減された。
しかし、これでも不十分と考え、アメリカで開発された特殊なダンパー
をスパイクの下にはさんでみた。「まぁ、こんなもんかな。」と、とり
あえず最初の難関をクリアーして試聴に値するセッティングが出来た。
この状況もティアックに説明してあるので、正式な出荷が行われた際に
はP−0の取扱説明書にこの辺の説明書きが追加されるはずである。
ちょうどP−0と同じように、一切のサスペンションを持たない設計の
アナログプレーヤーΣ5000も同様な配慮が必要であり、P−0に関
してもラックとの相関関係を吟味の上でセッティングされることをお勧
めする。もちろん私にご注文頂けるものに関しては、その辺のノウハウ
をいっしょにお買上げ頂くつもりなので何も心配はない。
私のフロアーのシステムも、この時点では昨年プロトタイプを聴いた
時とは大変さま変わりしていた。スピーカーはブラックのノーチラスで
あり、ゴールドムンドのフルシステムが偉容を誇っている。トランスポ
ートのミメーシス36PLUS、D/Aコンバーターはミメーシス20、
プリアンプも同じくミメーシス22、パワーアンプはミメーシス29が
三台とミメーシス29.4が二セットという豪華なラインアップである。
この中でトランスポートだけをP−0として本格的な試聴を開始したの
である。
さて、P−0はフロントパネルの一番左下に「プロテクト(PROTECT)」
と表示されたスイッチがある。これは停止中かポーズ時にだけ反応する
ようになっており、点灯していない時はP−0の最大の特徴である偏芯
追従動作を行い、スレッド送り機構が偏芯に追従してピックアップのレ
ンズを静止状態で再生するモードとなる。そして、点灯しているときは
従来の再生方式と同様にスレッド送りを等速送りする制御となり、トラ
ッキングサーボによるレンズの動きはこれまで解説したような状態とな
る。次に、その上にサーボモードの切り替えスイッチがあり、リファレ
ンス、マニュアル、ノーマル、の3モードが選択出来るようになってい
る。このマニュアルモードから説明すると、そのスイッチの右側にある
フォーカス、トラッキング、スピンドル、の各サーボゲインを自在に調
整出来るモードである。
この変化についても後述するので、ぜひご記憶頂きたい。
リファレンスモードは、良い状態のディスクで最高の音を出すようにエ
ソテリックでチューニングしたポジションである。このモードは音質優
先の設定値になっているので、ディスク面の傷や汚れなどにデリケート
に反応し「プツッ、プツッ」というノイズを発生することもある。
もし、このような症状が表われたときにはノーマルモードにすると良い。
これはP−0のサーボICによるオートゲインコントロールをオンにす
ることでもあり、傷、ほこり、反射光量不足などディスクごとのバラツ
キを緩和して安定動作させるためのモードである。
ここで興味深いのは、ローディングした各々のディスクによって、この
オートゲインコントロールが設定するゲイン値が一つずつ違ってくると
いうことだ。簡単に言えば、P−0の頭脳が状態の良いディスクと悪い
ディスクを判別して最適値を設定するので、ディスクによってサーボの
かかりかたの強弱が表われ、ディスクの善し悪しをP−0が判断した結
果がディスプレーに表示されるパラメーターの数値で確認出来る。
これも他社製品にないP−0の特徴として是非お知らせしておきたい。
ところで、私はトランスポートの比較試聴には定番としているディス
クが何枚かあるが、まず最初にチェックしておきたいのが瞬間的にパル
ス状の鋭い立上りの音が発せられて、徐々にエコーを残しながら消えて
いくという演奏を繰り返し聴いて見るということである。これらの表現
によって個々のトランスポートが持つテンションの張り方を推測するこ
とが出来、その延長線上で様々な楽器も同様な傾向に聴こえるのである。
ハイエンドレベルのトランスポートは、低音が豊かになるとか高域が伸
びるとか、ひと昔前の常套句とされたような量的な変化を各々が出し得
るということはない。むしろ、楽音のテンション、感触、空間的背景情
報、などの微妙な質的変化を聴かせてくれる分野なのである。
それらを推測するには、最初から多数の楽器が演奏しているものよりも
なるべく少数の楽器がシンプルな演奏をしている録音を集中して聴き込
むことをお勧めしたい。
よく「川又さんは、どんな音楽が好きなんですか。」ときかれること
があるのだが、少なくとも仕事上ではありとあらゆるジャンルの音楽を
広い範囲で使いわけている。邦楽、クラシック、ジャズ、ポップス、あ
るいはジャンルをつけがたいような様々なソフトを蓄えており、エ−ッ
こんな曲も聴くんですか、という意外な選曲も度々登場する。
ここに登場するソフトも、およそハイエンドショップというイメージか
らはいささか脱却しているかも知れない。鈴木雅之のベストアルバムで
「MARTINI」(Epic/Sony ESCB1145)の1トラック目にイントロダ
クションとして鈴木雅之のヒット曲「別れの街」をオルゴールで演奏し
たものが入っている。このわずか35秒間の効果音的なオルゴールは、
最初の3秒間でネジを巻く「カリッカリッ!」という音がエコーをかけ
られて収録されている。この「カリッカリッ!」という立上りの鋭い音
がトランスポートによって様々に変化するのである。
私の記憶によれば、この「カリッカリッ!」がこれまでに最もリジッド
な印象でハイテンションな音質で再生していたのがワディア7であった。
マークレビンソン、ゴールドムンド、バークレー、などフィリップス系
のメカを採用したものは一様に柔軟性のある感触となり、「カリッ!」
の「カッ」「リッ」の発音時間が長くなったような聞こえ方をする。
その代りエコー感が引き立ちみずみずしいイメージを補足していた。
そして、P−0にこのディスクをローディングし、プロテクトモードを
オンとしてインジケーターを点灯させて聴くことにした。
一聴してピンの感じた。「ウ−ンッ、早い!」というのが第1印象。
先程の「カッ」「リッ」の発音時間がこれまでにないほど短縮されてい
るではないか。ネジを巻くたびに逆回転しないようにストッパーとなる
鋼の板片に焼き入れが何回も加えられたようなテンションの高まりを見
せるのである。更に、「シャーッ」と聴こえる付け加えられたエコーが
消えていこうとする直前の肉厚が、以前と比較にならないほどの薄さに
スライスされているではないか。プロテクトモードをオンにした状態で
もこれほどの解像度を持っているのは、いかに設計精度が高いかを物語
っているのだろう。
それでは、プロテクトモードをオフにしてレンズの動きを止めてしまっ
たらどうなるのか。一旦ポーズをかけてインジケーターを消した。
今度は「カリッカリッ!」と連続音として「カッ」と「リッ」が同じ音
量感で感じられたものが、明らかに「カッ」の力強いインパクトの瞬間
と、「リッ」がそれに続きながら若干音量感を弱めているのがわかった。
時間軸でごく至近距離に発生している瞬間的な再生音に対して、今まで
聴いたことのないレベルでの分析をP−0は簡単に実現してしまった。
「ようし、同傾向の曲でもう一度確認だ。」と、次のディスクをかける。
今度は神山純一「水の音楽」(ビクターエンターテイメント VICG5297)の6トラック目
「スウィート・ラプソディー」という曲である。
このソフトは水の音だけで作られている。
蓼科高原や八ヶ岳高原のせせらぎの音、HOYA株式会社製の様々な形
のクリスタル製品に水滴を落した音を音声サンプラーに記録させ、オリ
ジナル曲としてCD化されたものである。水滴の音は音階の高低によっ
て30種類以上ものガラス器に落され、本当に透明感のある美しい音色
に仕上がっている。私がテストに用いる曲では特に高音域の音階を繰り
返して演奏する個所で、「ピィーンッ!」と小さな肉薄のグラスに水滴
が落された音をイメージして頂ければわかりやすいと思われる。
この演奏も他のトランスポートで聴くと「ピィーンッ!」の音が始まっ
て終わるまで、時間軸に対してのエネルギーの推移が均等化されてしま
うものがあるのだが、P−0では頭の「ピッ!」の部分が鋭角に切り立
った印象で聴こえてくる。そしてプロテクトモードをオフにすると、音
の出始めが直角三角形の縦線部分で斜め線にそってエコーが消えていく
ようなグラフをイメージしていたものが、「ピィ!」の頭の部分は垂直
に立上り頂点から同様にほぼ垂直に底辺近くまで落ちこみ、そこからエ
コーが横軸にそって消えていくようなグラフにさま変わりしてしまうの
である。とにかく強烈なインパクトが浮き上がってきて頭の「ピッ!」
と「ィーンッ!」というエコー感のセパレーションが際立ってくるので
ある。しかも、そこにテンションと緊張感が追加されるものだから、リ
アルさが倍加するのは認めざるを得ない。
私も多くの人たちと話しをするが、バイオリンはバイオリンらしく、
ピアノはピアノらしく、と一人一人が個々の楽器に対する思い入れと期
待感で判断力にバイアスがかかっている場合に遭遇することがしばしば
ある。つまり、一口にバイオリンやピアノと言っても、ふくよかなエコ
ー感が印象に残るオフマイクで捉えたテンションが緩く聴こえるものが
本当のバイオリンやピアノだと主張する人もあれば、オンマイクで音像
をしっかりと捉えて目の前で炸裂するような鮮明さで録音されているも
のこそリアルなバイオリンやピアノだと主張する人もいるのである。
結局は自分が好きだという単純な理由に、記憶、体験、理論、著名人や
演奏家の言動、などを収集することで理論武装を可能としてしまったと
ころに個人の好みと思い入れを複雑な表現にしてしまう原因があるよう
に思われてならない。要は、その人にとって「うまいかまずいか。」が
オーディオにおける本質であろうと私は考えている。
これから未来に向けて様々な技術革新が行われていくことであろうが、
レコーデッドミュージックは「冷凍食品」であって半永久的に生演奏と
は異質であると言わざるを得ない。生演奏とは、演奏者と時空間を共有
する体験であって、それを楽しんでいる時間こそがいわゆる「生」なの
である。そこから時間と場所が移り変わってしまえば、いかに高度な技
術を労して〈冷凍〉と〈解凍〉をしようとも、やはり「冷凍食品」なの
である。
こんな考え方から、楽音に対する個々人の思い入れを排除して、ひど
く客観的にコンポーネントを分析しようとする場合に、これらのソフト
が好適であろうと思うのである。つまり、「生に近いバイオリンの音」
「より自然なピアノの音」等々を客観的に判断するのは困難であると思
われるからである。故に私は、前述のような無機的な音の再生によって
個々のコンポーネントの個性を分析して記憶のファイルに蓄積していく
ことにしているのだ。これら一般的な楽器とは異なる無機的な音が、こ
のシステムだとこういう特徴を提示する。そのシステムで先程のバイオ
リンやピアノを再生させると、無機的な音が示した特徴にのっとって表
現するので、その延長線上にお客様の好みが一致するかどうかを試聴に
よって確認していくという販売方針なのである。
さて、ここで、最近のテストでは必ず最初にかけるほど気に入ってい
るディスクが登場する。ダイアナ・クラールの「ラヴ・シーン」(ビクターエ
ンターテイメントMIVC‐24004)である。トミー・リピューマのプロデュースであ
り、録音とミックスをアル・シュミットが行うという前作と同じメンバ
ーによる制作である。これも前作と同様にドラムなしのトリオによる演
奏であり、特に11曲目の「マイ・ラヴ・イズ」のイントロで「パシッ、
パキッ。」と指を鳴らしてリズムを刻み、そこへクリスチャン・マクブ
ライトのベースが重なり、次にダイアナのヴォーカルが登場する部分は
まさにトランスポートの比較には好適な演奏個所である。
ここでも無機的と言えるインパルス的な指を鳴らす音がエコーを伴って
広い空間に拡散していき、ダイアナのヴォーカルも同様なエコー感が施
されてピンポイントのおちょぼ口というよりは響きの豊かな空間で歌っ
ているような雰囲気を作り出している。ところが、クリスチャン・マク
ブライトのベースだけはオンマイクで鮮明さを優先する録音であり、ラ
イブ録音のような雰囲気をたたえるエコーを否定しているのである。
結果的に大いにスイングして楽しめる演奏なのだが、指を鳴らす音とヴ
ォーカル、そしてウッドベースが、生演奏ではありえないまったく異な
る音響的コンディションで録音されているのである。
そして、このディスクだけは慎重に聴きたいこともあり、ノーチラスに
オール・ゴールドムンドという非常にハイスピードを意識させるシステ
ムで聴きはじめることにした。すなわち、トランスポートもゴールドム
ンドのミメーシス36PLUSから同じ曲を聴いていくわけだ。
「ああっ、いいじゃないですか。」
さすがにオール・ゴールドムンドでは不自然さを感じさせる懸念は微塵
もない。特にエコー感が美しく、ヴォーカルのみずみずしさが余韻の美
しさとして空間を埋め尽くし、ノーチラスが最高レベルで駆動されると
いう好ましい事実を私のフロアーの歴史として残してくれたようである。
次に、P−0に行き着く前に同じシステムの中でトランスポートのみを
交換してみることにした。これまでに最高のテンションを発揮していた
ワディア7をもう一度確認の意味も含めて聴いてみようと思ったのだ。
但し、トランスポートからD/Aコンバーターへのケーブルはワディア
が標準としているSTリンクではなく、オーディオクェストのデジタル・
プロのRCAタイプの同軸ケーブルを使用している。
これはP−0の試聴に関しても同条件で変わりはない。
さて、結果としてはほぼ100%これまでに何度も経験したような私の
推測通りの変化が起こった。まず、「パシッ!パキッ!」という指を鳴
らす音に明らかな肉厚が加わる。そして、最も顕著な変化がウッドベー
スである。ゴールドムンドで特に低域が軽いということはないのだが、
トランスポートだけの交換であるのに、アメリカ製のパワーアンプに交
換した場合と同じ傾向でベースの重量感が変わってしまったのだ。
とにかく、重心がグッと下がり重々しく変化したベースの音だけを聴い
ていると、この変化を好ましいと思われる方も多いかも知れない。
しかし、私としてはオール・ゴールドムンドで聴いた場合の針の先ほど
も埋め尽くす緻密さは捨てがたいものがあると再評価する一面もある。
昨年持ち込まれたプロトタイプの音質に関して、この辺の低域表現につ
いて注文を付けていたことが再度思い出された。
さあ、この低域の魅力をP−0はどのように聴かせてくれるのだろうか。
第三部「アジャスタブル・サーボ」
先程の手順通りP−0のプロテクトモードをオンとしてディスクをロ
ーディングした。レンズの動きは従来通りということだ。
「パシッ!パキッ!」という指を鳴らす音が始まった。
アレッ、一体どうしたことだろう。
いままでワディア7で聴いた場合も十分に鋭角な立上りを見せ、予測通
り他のトランスポートを上回るテンションを発揮していた・・・、ように
見えていたということなのだろうか。
比較するものがなければワディア7で聴いた「パシッ!パキッ!」とい
う音は目前で鳴っているように聴こえた、と表現しえるであろう。
しかし、P−0がいったん再生を開始すると、今まで聴いていて最も近
い場所をイメージさせてくれたワディア7がいっきに1、2メートル向
こうへ跳んでいってしまうのである。つまり、P−0では弾かれる指が
眼前に接近してアタックの瞬間がよりインパクトを強めたというイメー
ジである。「パシッ!パキッ!」の「パッ!」と「シッ!」あるいは
「パッ!」と「キッ!」の間にあるはずの0.0何秒かの時間が蒸発し
てしまったようだ。
「これじゃ、ダイアナの指が折れてしまうんじゃないか。」と思わせる
ほど限りないハイスピード感を聴くものにアピールしてくるのである。
こんな愚にもつかない心配をしていたのはあっという間のたった4秒間、
息つく暇も奪われてしまいカウンターが秒を刻んでいくのを目で追いか
けているうちにクリスチャン・マクブライトのベースが入っている。
「あれ、まいったなぁ、去年のプロトモデルと違うじゃないか。」
ワディア7が聴かせてくれたベースよりも、更にグッと音階を引きずり
おろすような重量感の追加が感じられる。
しかも、ベースの音の輪郭を犠牲にして量感を得たという印象の低域で
はない。明らかにテンションの高まりが感じられるのである。
この張り詰めた緊張感の高揚は、あたかもジェット旅客機が離陸の際に
滑走を開始し、普段車で感じられる慣れ親しんだ加速感で「もう、この
辺で終わりかな。」と思った瞬間に今まで体験したことのない領域の重
力でシートに背中を押しつけられたような驚きを感じさせるのである。
「これだけで勝負がついちゃうなぁ、サーボによるレンズの動きなんか
忘れちゃいそうだ。まいったなぁ、もう、これだけでも十分凄いよ。」
この冒頭の再生音をしっかりと記憶に残すために同じパートを何度も
繰り返して聴く。何度も見せられるテレビコマーシャルは最初の0.5
秒を見ただけで残り全部が頭の中に浮かんでしまうように、執拗に同じ
パートを繰り返して私の耳に音楽のコピーを取らせた。
そして、「ここだ!」という瞬間を狙ってプロテクトモードを解除し、
私はP−0のスレッド送り機構にプログラムされた動作を開始させ、
同時にレンズには静止するようにスイッチングした。
この瞬間に私の頭の中にはオーディオ用のトレーシングペーパーが繰り
出され、先程コピーを取った音の残像に重ね合わせて直ちに比較検討を
開始したのである。
まず、先程の「パシッ!パキッ!」という指を鳴らす音は、更に時間軸
が短縮されていることが横軸の比較ですぐに判明した。
数秒前に聴いていた、つまりレンズがサーボによって運動していた状態
でもダイアナの指が目の前に迫ってきたというのに、今度は耳元で「パ
シッ!」と指を弾かれたような鮮烈なエネルギーの集中は経験がない。
しかも、とげとげしく鋭角さをましただけという単純なものではない。
この「パシッ!」の後には「シィーン・・・!」と、音のほとばしりがノ
ーチラスの周辺にある空間に波紋を広げていく有様が高解像度な連続写
真のごとく見事な展開を見せつけるではないか。
この余韻感の鮮度を他のトランスポートに見出すのは困難であろう。
このように、空間上にスウィートスポットで捉える極小の定位点から、
ぐっと視野が広がっていく室内の背景という三次元空間に余韻が放出さ
れていくのは何とも言えぬ快感ではないか。
点から空間へ、音響表現のビックバンとも例えたくなるような極限とも
言える音像の圧縮から爆発、そして拡散という瞬間的なプロセスを構築
出来るP−0は、クラシック音楽全般をはじめとしてオーケストラの再
生にも威力を発揮することが後の試聴でも明らかにされたのである。
この状態で試聴を開始してから四秒後に、予測もしていなかった次の
衝撃が襲ってきた。クリスチャン・マクブライトのベースは、P−0で
聴き始めた先程の状態でも神がかりな変身を遂げているというのに、今
度の変化を聴いてしまうと図らずも改宗を迫られる心境に陥ってしまう。
プロテクトモードをオンにして聴きとった音のコピーに、オフにした後
に記憶した音のトレーシングペーパーを重ねて見ると一目瞭然なのであ
る。先程のベースの音が面積として感じられていた周辺部の20パーセ
ントくらいが、プロテクトモードをオフにした状態の下からはみ出して
いるではないか。つまり、ベースの音像が縮小されているのである。
しかも、同じエネルギーを凝縮したために楽音表面の密度感が高まり、
目がつまった繊維のように光を反射するほどの光沢を持ち始めたのであ
る。これをホールで演奏したチェロやコントラバスの音色で例えれば、
間違いなく緻密な滑らかさとして移し変えが出来る変貌と言える。
そして、注意深く聴いて見るとピッチカートの弾かれる瞬間のインパク
トにおいてもテンションを高めているようであり、もう一度ワディア7
にもどしてみると、ベーシストの姿勢そのものが「気をつけっ!」から
「休めっ!」になってしまうのである。
さて、「今まで聴いてきたCDは一体何だったのか。」と空いた口が
ふさがらない思いを振り払うように次の課題に目を向けることにした。
サーボモードはリファレンスの状態でこれらの経験をしたのだが、これ
をマニュアルモードに切り替えたのである。
ディスプレーには「3d 5E 47」と二桁ずつ数字とアルフェベットのペ
アが三組表われ、左からフォーカス、トラッキング、スピンドル、各サ
ーボゲインを表すリファレンスモードでのパラメーターが表示された。
AからF、0から9までを組み合わせた16進法の累進となり、「A0」
から「9F」までと256通りの設定が可能となっている。これを自在に
変化させることが出来るのである。
だだ、これはディスクによって上下動の幅が限られており、あまり大き
く動かすとエラーになってしまう。好奇心は決断に要する時間を短縮し、
ある時は行動力とリスクをも高める。躊躇なくボタンに手が伸びる。
まず、左からフォーカスサーボのパラメーターを「30 18 10 4」と
低い方へと変化させる。「ハハァ、なるほど。」と、その音質変化を見
届けながら思い切って「A0」へ・・・。「アッ、エラーしちゃった。」
こうなるとP−0は「ヒュンッ。」といって動作をやめてしまう。
今度は逆に「59 69 85 9F」と数値を大きくしていった。
当然のことながら、「9F」ではエラーとなりP−0はため息とも聞こえ
るメカ音を最後に動作を停止する。
次にフォーカスサーボも同様に256通りのパターンを持っており、ス
ピンドルサーボは「40」から「47」までの8段階となっている。
このパラメーターの大小はサーボゲインの大小を表しているのだが、
P−0内部で電子的にどのような設定になるのかはエソテリックのノウ
ハウであり企業秘密であるので教えては頂けなかった。
実は、この技術的な設定を行うのに作成された8ページにも及ぶチャー
トを見せられたのだが、専門的なコンピューターのプログラム原稿らし
く私にはチンプンカンプンだったのである。
たとえ私がそれを理解できたとしても皆様には面白くもおかしくもない
と思え、32ビットのマイクロプロセッサーにエソテリックが何をどん
なふうに書き込んだかという話しは割愛させていただくことにした。
また、16進法の変数を逐一説明していると大変なので、P−0のボタ
ン操作でパラメーターがアップダウンするに従って起こる変化を、私の
耳で感じ取った印象をもとに、その応用として推測しながら解説するこ
とにした。
結論として三つのパラメーターで最も変化が大きいのがフォーカスサ
ーボであった。V・R・D・Sで面ブレをキャンセルしているのにもかか
わらずサーボゲインの変化が大きいのは奇妙にも思えるが、逆に面ブレ
を起こさず機械的に安定しているからこそ電子的な操作に敏感なのかも
しれない。
まず、先程の「パシッ!パキッ!」というインパルス性の反応であるが、
フォーカス・サーボゲインを上げるにしたがって演奏している部屋の温
度が低くなっていくように感じられるのだ。不思議なことに、この逆に
フォーカス・サーボゲインを下げていくと室温は上がっていくのである。
このようにサーボゲインを上げ下げする事で起こる変化を、私は「室温
が下がったような変化」または「室温が上がったような変化」と表現し
たが、皆さんの日常体験から推測して頂けないだろうか。
物理的に言えば、音波の拡散状態と周波数帯域ごとの進行速度は温度
湿度にも影響を受ける。冬の冷え込んだ朝には、夏場には聞こえてこな
い遠くの騒音が聞こえて来るのも、音が屈折して大気中を進んでいく現
象によるものである。我々は意識せずに環境の変化による音波の変質を
生理的に認識してはいるものの、日常体験の些細な出来事として記憶に
留めるほどの重要性を与えていないだけの事である。
湿度が急上昇する季節にエアコンも止め、周囲の騒音から逃れるために
窓を閉めきり、アンプの放熱が緩やかな対流を室内に引き起こす、こん
な環境を汗をかかない程度に意図的に作り出しながら自室で聴くオーデ
ィオシステムの印象をまず頭に思い描いて頂きたい。
フォーカス・サーボゲインを下げていくという変化の方向付けとしては、
この状態の雰囲気に近づいていくということである。これを基準にして
イメージして頂ければ、次にフォーカス・サーボゲインを上げていった
ときの変化は大変説明しやすくなるのである。
朝日がまだ窓枠の中に見えるほど低い空にあり差し込む日差しは目を焼
くものの部屋を暖めるまでには至らず、厚手のセーターを着こんで何と
か辛抱出来る範囲でオーディオシステムのスイッチをオンにする。
さすがに吐く息が白く見えることはないが、室内の空気にはひんやりと
研ぎ澄まされた冷たさが肌にも感じられる。スピーカーの周辺にはオー
ラのような緊張感が漂う中で、もぎたての野菜のような鮮度の高さを印
象づける「シャキッ!」とした感触とイメージして頂きたい。
この変化を大変デフォルメして単純表現すれば、フォーカス・サーボゲ
インの数値が大きくなるにつれて、「鈍角から鋭角へ」「テンションの
張り方は弱から強へ」「エッジの際立ちはラウンドからスクェアへ」
ということになろう。しかし、くれぐれもお断りしておきたいのは非常
に微妙な変化であるということだ。
さて、同様にトラッキング・サーボゲインはどうであろうか。
これもパラメーターのアップダウンに従って次のような表現が出来るの
である。誰もが演奏を聴いていると頭の中には何らかのビジュアルイメ
ージがわき上がって来ることと思う。あるときは風景であり、あるとき
は演奏する人物であり、そしてあるときは幾何学的な模様や色彩が脳裏
に浮かび上がるかもしれない。このビジュアルイメージがどんなもので
あるにせよ、それを形作る輪郭線があるはずだ。トラッキング・サーボ
ゲインを下げていくと、この輪郭線がわずかながら太さを増すのである。
逆に、トラッキング・サーボゲインを上げていくと、この輪郭を描く線
が筆を持ち替えたように細くなっていくのである。言い替えれば、サー
ボゲインの大小の変化は解像度に高低差をつけていくのと似ているかも
しれない。個人の好みであろうが、細い筆の方が微細な表現を描きあげ
るには好都合である。しかし、ダイナミックなタッチで線よりは面での
表現を引き立たせたい場合には太い筆に替えた方が良いのではなかろう
か。そして、これにも大変微妙な変化であると注釈が必要である。
最後にスピンドル・サーボゲインであるが、前述の二者に比べると表
現がもっと難しくなって来る。このパラメーターは「40」から「47」ま
での8段階となっており、各サーボモードも最初はみな「47」で設定さ
れている。とても1ステップずつでは分析が大変なので、最大最小で比
較試聴をしてみた。この私でさえも、この変化を聴きとるには何回も同
じパートを繰り返して聴かなければならなかった。
最大の「47」で聴いた状態を前述のビジュアルイメージの色彩感に例え
ると、すべての色を原色で描いたものを基準として先ず思い描いて頂き
たい。赤、黒、青、緑、黄、とすべてが一本のチューブから絞りだした
絵の具そのものの色である。今、まっ白なパレットにそれぞれの色を三
センチほど均等に絞り出したとしよう。そして、お互いの色を一切混ぜ
合わせないで何らかのイメージにあったラフスケッチを描いたとする。
さて、これで下書きが出来た。
そして、サーボゲインを最小の「40」に切り替えた時に起こる変化はこ
うである。それぞれの原色の絵の具に耳かき一杯の、ほんの微量な白を
混ぜて同じスケッチをもう一度描くのである。あまりにもわずかに白を
混ぜたので、それを初めて見れば、黒は黒、赤は赤、青は青、と誰でも
原色のままだと思ってしまう程度の変化なのである。
しかし、これら2枚を並べて子細に観察すると微妙に色彩感が違ってい
ることにようやく気がつくのである。
トラッキング・サーボゲインを最小の「40」にまで変化させたときの感
触は、楽音の色彩感にほんの微量な白を混ぜることによって口(耳)当
たりを優しく滑らかにしたという例えでイメージをつかんで頂ければあ
りがたい。これも大変に微妙な変化である。
くどいようだが、ご理解いただきたいのはどのサーボゲインの変化もグ
ラフィック・イコライザーやパラメトリック・イコライザーのように、
周波数特性が変化したような特定帯域の極端な量的増減という変化では
ないのである。
言い替えれば、P−0の基本性能によって描かれる音楽の原形は、サー
ボゲインをどのようにいじろうとも崩れることはないということである。
さて、それでは、誰にでも簡単にわかるという変化であればともかく、
よほどの機材と環境、そして熟練の耳をもってしなければ判断出来ない
ような微妙な変化をするキーをトランスポートに設けて意味があるのか、
と疑問の声を上げられる方もあろうかと思われる。
その答えは、この随筆の第一章をもう一度お読み頂くことで半分は理解
されるであろう。高度な技術によって開発されたCDシステムは、我々
の常識をはるかに超えるデジタル/サーボ技術によって「非接触」で音
が出るという夢を実現してくれた。
しかし、LPレコードの再生ではカートリッジを交換したり、カートリ
ッジだけでも取付け方や針圧を変えるだけで音が変わったりと、使い手
の技量と好奇心に応えるだけの調整ポイントがたくさんあったものだ。
しかし、ボタンを一つ押せば音が出るというCDでは、ユーザーが自分
の意志を音に反映させるにはコンポーネントの選択という根本的な選択
肢しかなかったのである。
いわば、CDは音の出る「ブラックボックス」的な存在であったのだ。
この「非接触」であるがゆえに、内部に調整機構を持たせることは製品
としての安定動作を保証する上でリスクがあったのだろう。
P−0は高精度な再生を約束した上で、ユーザーが音質調整に介入出来
る余地を提供してくれたのである。
だが、ここで断言出来ることがある。エソテリックの設計陣はCDの音
質を変化させることが目的でP−0を作ったのではない。
今まで世界中の誰もが取り組もうとしなかったCDの宿命とも言える
「非接触方式」の弊害に、サーボシステムの使いこなしとメカニズムに
よる諸問題の解消という正攻法で挑戦した結果の副産物として、前述の
サーボ調整機能というユーザーに開放するキーを作り出したのである。
第四部「スタンディング・オベーション(standing ovation)」
年も明けて1998年1月16日、今度は日本ビクターが新製品を持
ち込んできた。XP−DA999(定価55万円)である。
EXTENDED K2プロセッシングを搭載し、トランスポート(C
D/MD/BS/DATなどすべてのデジタル機器との接続も含む)か
らのデジタル信号から波形変化点を抽出し、それから波形変化の形態を
推測、と同時に波形変化の間隔も推測し生成してアナログ元信号の想定
を行う。それをもとにK2ハイ・サンプリング演算を行ってデジタル信
号を再出力するのが大きな特徴となっている。
そして、XP−DA999には96KHz/24ビット対応の左右独立
のD/Aコンバーターを搭載しており、前述の回路を経て2倍サンプリ
ングを行い88.2KHzに変換してCDを聴くことが出来るのである。
更に、業務用の同期フォーマットである「ワードシンク」出力も装備し
ており、P−0の「ワードシンク」入力に接続することも出来る。
ほんの短時間であったが、このXP−DA999にP−0を接続し前
述のオール・ゴールドムンドとノーチラスで試聴する機会に恵まれたの
である。XP−DA999はリモコンでサンプリング周波数を44.1
KHzと88・2KHzとに瞬時に切り替えることが出来るので、P−
0のサーボモードはリファレンスと固定しておき、もっぱらサンプリン
グ周波数の変化による試聴をこれまでと同じ選曲で進めていったのであ
る。先ず最初は44・1KHZで聴き始めた。
「ウ−ンッ、これってなかなかいいなあぁ。」というのが私の第一印象
である。P−0が正確無比な信号を供給しているという印象をそのまま
に大変鮮明な輪郭を描きだしている。このままでも十分なクォリティー
であるが、リモコンで88・2KHzに切り替えるとエコー感と余韻の
表現に変化が発生する。これで終わりか、と思っていたエコーが更に今
一歩空間に浸透していくのである。
最近は「優秀なCDプレーヤーを探しているんだが、P−0を採用す
るとD/Aコンバーターまで手が回らない。手頃な価格でとりあえずP
−0の魅力を引き出せるものはないだろうか。」という質問が多い。
とりあえず、というレベルで55万円が安いか高いかはユーザーに判断
して頂くとして、インポートの最高級D/Aコンバーターと比べれば大
変に安価であろうと思われる。両者共に他社が出来ないことを真剣に作
り込んだ製品だけに、現時点において私がクォリティーを保証しえる高
レベルの組合せの一例として推奨しておきたい。
従来からエソテリックではペアとなるトランスポートとD/Aコンバ
ーターを同シリーズで発売してきた。ご推察の通り、エソテリックはP
−0のペアとなるD−0をこれから開発していくという。
早ければ98年秋の発表、遅ければ2000年までにという長期的な開
発プランである。期待がふくらむのはもちろんだが、私が注目している
のはP−0、D−0の両者を収納する専用ラックも同時に開発するとい
うのだ。前章でも述べているとおり、リジッド・コンストラクションの
P−0は置き台によっても音質変化を認めることが出来るので、P−0
のためだけにも専用スタンドが欲しいところなのである。
アナログプレーヤーの世界では、VPI、ロックポート、ウィルソンベ
ネッシュ、ザークシーズ、とプレーヤーを設置する専用スタンドを発売
しているメーカーも多い。エソテリックに対しても、同様な発想による
専用スタンドの開発を強く望むものである。
さて、エソテリックは、P−1、D−1、から始まりP−2以降へと
製品のバリエーションを拡大していったわけだが、ここにきてP−0と
いう原点を指し示すナンバリングをつけるということは、いかに10周
年記念と言えども相当な覚悟で望んだであろう事が推測されるのである。
CDも登場してから16年も経つと、メーカーの設計者は出来あいの各
アッセンブリーを組み合わせて商品を設計する時代となり、本当の意味
で基本と原点に帰った技術革新を志す設計者が減ってきたと言われる。
そして、昨今の平成大不況、金融不安といった社会情勢の中で、エソテ
リック(ティアック)がP−0のような採算を無視した物作りを完遂さ
せたことは、近年のオーディオ界において記憶に値するものと言える。
これまでに私が取り扱ってきた多くのハイエンド・ブランドも、ただ
会社の利益と拡大だけを目的としてコンポーネントを作ってきたという
メーカーはほとんどないであろう。
経営トップ自身が音楽が好きでたまらず、満足出来るコンポーネントが
ないという状況下で自分が作り始めたという経緯がほとんどである。
エソテリックの設計陣におかれても、私が知りえる海外メーカーと同様
な発想と熱意のもとにP−0を生み出されたということを高く評価する
ものである。
この随筆でも取り上げてきたように、これまでに親交のあった国産メー
カー数社の設計者の皆さんとも懇意にして頂いているが、これからはエ
ソテリックも目が離せない存在となってきたようだ。
去る97年11月8・9日、東京赤坂のTBSホールで行われた第2
1回「マラソン試聴会」には予想を上回る数多くの皆様にご来場頂いた。
総合プロデューサーを務めながら、私自身のセールス活動の集大成とし
て皆様の前で数多くのハイエンドオーディオを演奏出来たことは大変に
幸せなことであり大きな喜びでもあった。後日計算して見ると出展され
た機材の総額は約3億6千万円を超え、総来場者数は1,146名と過
去最高の記録となった。この事前に、私は以前にはなかった趣向をイベ
ントの演出として取り入れようと考えていたのである。
これまでのオーディオの試聴会やイベントというのは大変形式化してい
たと言わざるを得ない。解説者の話し、試聴、静粛、話し、試聴、静粛、
の繰り返しではなかったか。そこで私は本イベントの実行委員会が顔を
揃えたミーティングの際に、司会進行を担当するメンバーにこう訴えた。
「名だたる演奏家やアーティストも聴衆を感動させるために演奏に磨き
をかける。それを収録してCD(ソフト)を制作する人たちも、聴き手
を感動させようと努力している。これらを再生するハードウェアを作り
出す人々も、ユーザーに感動と満足そして幸福を提供するために情熱を
かたむけている。すべてが音楽を聴こうとする人々を感動させようとす
る目的で一致しているのだから、今度のマラソン試聴会では試聴した音
楽でお客様が感動して下さったら拍手をしてもらおうじゃないか!」と。
何だかんだと理屈を並べても、オーディオの究極の目的はエンターテイ
メントである。生身の人間がエンターテイナーとしてステージに上がれ
ば、この才能に拍手で応えるのが観客のマナーとなっているではないか。
それでは、ハイエンドオーディオを作り出した多くの設計者(経営者)
たちの才能に対しても聴衆の拍手でそれをたたえるという演出をとりい
れてもおかしくはないだろう、と私は考えたのである。しかし、「でも、
そんなのってやったことないからねェ・・・。お客さんがのってくれるか
なぁ・・・。」というのが実行委員の率直な意見であった。
「とにかく、やってみるよ。」と私は本番に望んだのであった。
これまでにも「オーディオフェア」「インターナショナルオーディオシ
ョー」また、地方各所でのイベントや販売店におけるデモなど、プロモ
ーションを目的としてオーディオを聴く機会は何度もあったと思う。
しかし、オーディオシステムによって演奏された音楽に対して、言い替
えればソフトに記録された演奏家たちとコンポーネントを作った人々に
対して観客の拍手が贈られたということがあっただろうか。
「マラソン試聴会」の本番では、夕方近くになって会場が満席となり、
雰囲気も盛り上がってきたところで私はこの思いを語り始めた。
すると、どうだろうか。
演奏が終わって私がボリュームを下げてから、ほんのわずかの間をおい
て、オーディオシステムで聴かれた音楽に対して大きな拍手が寄せられ
たのである。その時の気持ちをどう表現したものか。
生身のエンターテイナーが感じる感動とよろこびの、ほんのかけらほど
の体験として私にもわかるような気がしたのである。
そして、この拍手のほとんどはコンポーネントを生み出した人々に贈ら
れたものであるということを、この場に居合わせなかった多くの人々に
もご理解頂きたいのである。ハイエンド・オーディオに贈られる拍手、
そんなイベントを実現出来たことが私にとっての喜びでもあるのです。
そして、今まで私の認識が大きく欠落していたのであろうが、これま
で述べてきたようなこだわりの定義に照らし合わせ、今後は日本におけ
るハイエンド・オーディオブランドとして「エソテリック」が高いポジ
ションに位置付けられることを私は断言するものである。
これからも、私のフロアーでP−0を聴かれるであろう多くの人々と
いっしょに、私は立ち上がって大きな拍手を贈り続けるであろう。
最後に、P−0をご提供頂いたティアック株式会社の皆様に心から
お礼を申し上げたい。「本当にありがとうございました。」 【完】
あとがき
「今回の随筆は半年ぶりというブランクもあり、題材としているP
−0がステレオサウンド誌に大々的に特集されてしまったことも重なり、
今さら一体どんなことを書けば良いものかと迷いながらの執筆となって
しまいました。
しかし、何とか書き終わってみると、これを書くということで私自身が
数多くの調査と学習をすることも事実であり、これらの知識を皆様と共
有することでセールスのレベルアップが図れれば何よりであると考えて
います。
さて、本文中でも紹介している「マラソン試聴会」に来場された多く
の方々から本随筆の総集編を送付して欲しいという要望が寄せられ、
お陰様で手元にあった在庫がすべてなくなってしまいました。
今回の第四十四話を追加として組入れ、総集編の第三刷として相当数を
制作する予定でございます。
ご精読頂きました皆様には厚くお礼申し上げると共に、まだお届けして
いない皆様には今しばらくご猶予を頂けますようお詫びを申し上げます。
そして、当分の間はこの文章が総集編の巻末を締めくくることになり
ますので、改めて皆様のご健康を心よりお祈り申し上げ、オーディオを
通じて有意義なお付き合いが生涯続きますことを願いまして略儀ながら
ご挨拶を申し上げます。
|