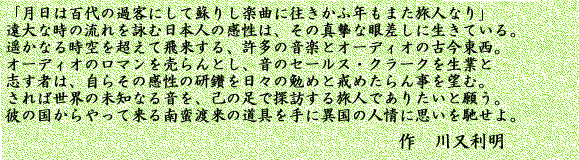第二十八話「アナログ世代の疑心暗鬼症候群」
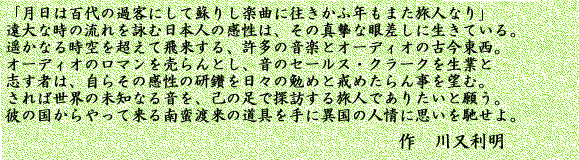
第一章『発端』
時は1989年2月、東京は飯田橋に近いホテルエドモンドの一室において、近代の
オーディオ史上稀に見る大変エポックメーキングな技術発表が行われた。それは、アナ
ログレコードを完全非接触で再生するという、過去60年間に渡るアナログディスクの
歴史と発展の中で大変画期的な出来事であった。仕掛け人は1990年に株式会社エル
プとして社名を変更することになる、当時は株式会社CTIジャパンの社長である千葉
三樹氏である。この株式会社CTIジャパンの前身は、国内初の外資100%のオーデ
ィオメーカーである株式会社BSRジャパンである。1972年に設立された株式会社
BSRジャパンは、英国BSR(ブリティッシュ・サウンド・リプロダクションズ)社
の出資により、高級レコードプレーヤーを中心に生産販売を行っていた。その後、75
年には米国のADC社のカートリッジ、80年代にはdbx社の製品を取扱い、製品企
画から生産販売を行う拡大を見せる。この当時には、ドイツに約70名の陣容からなる
海外支社を開設するなど拡大基調にあった。そして、1988年に米国資本のCTI(
キャリロン・テクノロジー・コーポレーテッド)グループに売却され株式会社CTIジ
ャパンとなるのだが、この時期に現社長の千葉三樹氏との接点が発生して来るのだ。千
葉氏は、青年時代から揺るぎない信念の持ち主であられたようだ。弱冠25歳で米国G
E(ゼネラルエレクトリック)日本支社の門を叩き、「当時は芝浦の倉庫番の仕事から
始めたんですよ。」と笑いながら思い出を語られる。その千葉氏は大手米国企業におい
て、その経営手腕を認められて80年代にはニューヨークに活躍の場所を移した。そし
て、1984年日本人で初めてGE社のコンシュマー・エレクトロニクス部門の副社長
という要職を勝ち取るのである。しかし、当時のスクラップ化を前提としたマス・プロ
ダクションとマス・セールスに大きな疑問を感じ、87年にGE社のキャリアを棒に振
って日本に戻ってしまったのである。千葉氏は千代田区神田に経営コンサルティング会
社として株式会社エルプを自ら設立し、大組織から逃れた一匹狼となってビジネス展開
を始めたのだった。そんな時期にGE社時代の同僚で、同時期に退職をしたミスター・
ロビンソンというアメリカ人から電話が入る。当時、やはりGE社を出たロビンソン氏
が経営に参画しているCTI社がBSR社を買収したので、その子会社であるBSRジ
ャパンを経営してくれないかという打診があったのである。せっかく大組織から開放さ
れホッとしている千葉氏は、6、7人の小さい会社だから気軽に引き受けて欲しいとい
う要請を受け入れて株式会社CTIジャパンの社長に就任するのである。しかし、既に
ドイツに70人も人材を抱える支社を持ち、また当時としても、在日米軍に対しての大
規模なPX事業も展開中で、国際的に大きな根を張ってしまった同社の実態をあとから
知る事になり再びご苦労の時代が始まったのである。さて、この時米国CTIグループ
の傘下に、名も知れない研究開発会社フィニアル(FINIAL)社があったのだ。そのフィニ
アル社から送られてきた分厚い英文の技術資料が、千葉氏の半生と株式会社エルプの事
業内容に一大変革をもたらすのである。
第二章『二人のロバート』
フィニアル(Finial Technology)社は1983年12月に、たっ
た一つの目的のためにカルフォルニア州サニベールに設立された。設立したのは当時ま
だ27歳という若さのロバート・ストッダート氏で、設立の目的とは唯一レーザーター
ンテーブルの開発である。同氏は1956年の生まれで、七八年にミシガン大学を卒業
後、スタンフォード大学で電子工学の修士課程を修了している。このスタンフォード大
学院に在学中の一九八二年に、アナログレコードを光学式で再生できる事を理論的に解
析したのである。しかし、当時の彼の指導教授や学友全員から不可能と反論され、「エ
ンジニアに不可能はない」という信念を持つストッダート氏は卒業と同時にスポンサー
を見つけフィニアル社を設立した。翌年84年、ストッダート氏の理論に共鳴した力強
い共同研究者が表れる。ストッダート氏より3歳年上で、1975年にカルフォルニア
大学、77年にはハワイ大学を、いずれも電子工学を専攻して卒業したロバート・スタ
ーク氏である。スターク氏は既に77年からシステム・エンジニアとしてサーボ回路の
設計や、アナログ・デジタル両分野の電子回路と信号処理の研究に従事していた。しか
し、理論を現実の物とするには想像以上の苦労の連続であった。まず、当時は彼らが要
求する重要部品すらない。例えば、光を電気信号に置き換える超高性能スキャナーであ
る。当時、米軍内で開発されたものはあったが、当然軍事目的に作られた物で入手はで
きない。このスキャナーを自社で開発するのにも一年半という時間がかかる有様で、当
然資金も底を突いて来る。ストッダート氏は、その度に新しいスポンサーを見つけ研究
を繰り返し、7年という歳月と24億円という開発費を費やして、遂に基礎開発に成功
するのである。基礎開発には成功したものの、悲しいかな彼らには製造能力も販売手段
もない。革命的な技術を世の人々に提供するためには、事業化という難関が残っていた
のである。これが、いきなり大衆商品として大量生産出来るような物でなく、ましてや
米国企業の生産技術と品質管理では事業化して成功する見込みが無いと判断され、二人
のロバートの文字通り汗と涙の結晶である研究論文は海を渡ることになったのである。
第三章『なぜ、エルプなのか。』
その分厚い技術資料を読みおえた千葉氏はさすがに半信半疑であった。しかし、実際
にレコードを再生する実物を目の前にすると、その革新的な技術力と可能性から、自社
だけの事業としてスケールを限定してしまって良いのだろうかという疑問を感じたので
ある。古くはオランダのフリィップスがコンパクト・カセットテープの技術を無償公開
して、全世界に多大なる事業化の波を広げたように、一社独占というのはいかがなもの
だろうか。レコードという文化遺産を未来永劫に保存し、同時に再生して文明としての
記録を後世に伝えるためにも、もっと多くの企業が商品化すべきではなかろうか。当時
、ハイテクを駆使してカラーテレビやVTRで世界市場を席巻していた日本においてこ
そ事業化の可能性がある。千葉氏は、もっと広い視野で事業化の提案を行おうと決断し
たのである。そして、1989年初頭、松下電器やソニーはもちろんのこと全てのエレ
クトロニクス産業とマスコミに、このレーザーターンテーブルの技術発表会の案内状を
送り届けたのである。いかんせん、誰も見たことも聞いたことも無いものであるだけに
、一体どれほどの人々が来てくれるか皆目検討がつかなかったという。ところがフタを
開けて見ると用意したひと部屋では収まりきれず、急遽間仕切りを取り払って三部屋ブ
チぬきでホールを拡大し、それでも立ち見の人垣が溢れんばかりの想像以上の来場者が
訪れた。シャープを除く全ての電気メーカーとマスコミが押し寄せる有様で、数百人と
いう規模の発表会となってしまった。そこで、千葉氏が力説したのは、合弁事業でもO
EM生産でもよいからレーザーターンテーブルを世に送り出そうという使命感あふれる
呼びかけであった。もちろん、二人のロバートも来日して、自らが技術説明にあたり千
葉氏の訴えに花を添えたのは言うまでもない。昭和天皇崩御にあたり、平成と年号が変
わった2月の出来事である。世界中のエレクトロニクス市場で成功を収めている名だた
る日本企業の回答を待つこと一か月、千葉氏の心中は期待と不安が入り混じる複雑な心
境であった。ところが、近代民主主義でもこれほど見事な全員一致の結論はないと思わ
せるような足並みを揃えた回答が出た。レーザーターンテーブルの事業化については、
いかなる手段においても全社「NO」の回答だったのである。理由は簡単で「市場性が
無い」つまり、儲かる見込みのないものには手を出さないという、経営上手な日本企業
としては懸命な?判断なのであろうか。この回答を二人のロバートに話す時の千葉氏の
心境はいかなるものであったか。大学卒業と同時に青春の全てをかけて研究に打ち込ん
できた純真なエンジニアである二人のロバート、彼らが流した涙を今でも忘れる事は出
来ないと千葉氏は語る。そこで、千葉氏は自らの生涯を賭した決断をする。当時、株式
会社CTIジャパンが持っていたPX事業と米国ADC社の営業権を売却し、自らの資
産も投げ売ってレーザーターンテーブルの事業化に挑戦しようと決断したのである。そ
して、この年にフィニアル社からレーザーターンテーブルに関する全権利を買取り、翌
90年に社名を株式会社エルプとしてレーザーターンテーブルの製造販売に着手するの
である。話は変わるが、千葉氏に「エルプ」という社名の由来を尋ねた事がある。氏は
「エルプという命名には、特に由来や根拠は何もないんですよ。」と笑いながらお答え
になった。私には、ここまでのエピソードを伺いながらパッとひらめいたものがある。
それは、「エルプ」とは謙虚にも頭文字を取り払った「ヘルプ」ではないかと。
第四章『生い立ち』
株式会社エルプは元々がメーカーであり、当然エレクトロニクスの技術に精通するエ
ンジニアも数多く擁している。1990年の某日、そのエンジニア達に千葉社長から招
集がかけられた。二人のロバートが作り上げたレーザーターンテーブルの実物が目の前
にある。その設計図も専用の特殊な工作機械も、全てアメリカのフィニアル社から買い
取って用意した。これらの条件をもとに、千葉氏は自社のエンジニア達に問いかけた。
「わが社で、これを生産出来るかね。」居並ぶエンジニア達も、設計図と実物を目前に
置かれ多少の思案はあったのだろうが、ここまで条件を揃えられたのではエンジニアと
してのプライドが許すはずが無い。「図面と、実際に音が出る実物が存在する以上は作
って見せます。」と答えが返ってきた。しかし、基礎開発は終わったとは言え、商品化
への道程は決して甘いものではなかった。まず、原理は確立されていたものの、対象と
なるLPレコードの規格の曖昧さが最初の強敵となった。レーベルによって、プレスさ
れた年代によって、また保存状態によってと、とにかく音溝に針を落し込んでさえすれ
ばトレースするという原理のアナログディスクにはミクロン単位の工業規格など無かっ
たのだ。このレコードは音がでるが、こちらはダメ。そんなアナログレコードのバラツ
キを、いかに克服するかに多くの時間が使われていったのである。二人のロバートが作
り上げた実物を羨望の眼差しで見詰めながら、量産化に向けての悪戦苦闘を繰り返すこ
と1年、1991年にLT-1として発売にこぎつけたのである。当時の価格が198
万円という高価なものであったが、その後78回転のSP盤も再生出来るように改良を
受けたLT-1Xが300万円、LP/EP用としてLT-1Lが210万円という二
機種が現在まで生産販売された。さて、これだけ高価なものを世の中はどの程度受け入
れてきたのか。前述の通り、レーザーターンテーブルとしては過去に3モデル存在して
いたわけだが、それらを合計して何と約140台の販売実績があった。その内の約六割
が個人ユーザーで、四割が個人の業務用または文化的公的機関に納入されている。例を
挙げれば、国内では、国立劇場、国立文学劇場、国立文化財研究所、武蔵野音楽大学、
東京外語大学、金沢工業大学、NHK、海外では、カナダ国立図書館、ホンコン放送局
、イタリア国立大学、そして、かのスティービー・ワンダーと、これはほんの一例だが
、列挙すればキリが無いくらいだ。この納入実例を見れば、いかにレーザーターンテー
ブルがアナログレコードという文化遺産に対して貢献した存在であるかがご理解頂ける
であろう。また、昨年の秋にイギリスのロイター通信が全世界の主要なメディアに画期
的な技術としてニュースを配信し、その後イギリスのBBCテレビがクリスマス番組で
レーザーターンテーブルを特別放映した。これらの影響もあってか、国連のユネスコも
レーザーターンテーブルへの援助を検討するなど、世界各地の文化財保護団体から強い
関心が寄せられるようになったのだ。そして今年、レーザーターンテーブルの心臓部で
ある光学系システムの部品を含めて完全内製化に成功し、特許料の償却も終わるなど、
性能とコストの大幅な向上に成功したのである。その結果1995年10月1日より、
今まで高嶺の花であったレーザーターンテーブルも、LT-1XAとして205万円、
LP/EP用 モデルLT-1LAとして135万円とされて、一般の人々も何とかち
ょっと無理をすれば手が届く程度の射程距離に入ってきたと言える。
第五章『原理と特徴』
レーザーターンテーブルの特徴としては、その性格上次のように分類して表現出来る
。まず、最大の特徴である完全非接触という事から、次のような利点が考えられる。
(1)レコード盤の摩耗が一切ない。
(2)ハウリングも完全にない。
(3)5mmから6mmまでレコードが反っていても安定再生する。
(4)針跳びするような傷も再生可能。
(5)ニードル・トークが皆無
次に操作性だが、
(1)曲間の頭だしが1プッシュで可能。
(2)再生面の時間経過、残量時間、トータル演奏時間が表示可能。
(3)プログラム演奏、リピート演奏、早送りやポーズが可能。
(4)回転数(ピッチコントロール)の調整が高精度で連続可変出来る。
(5)針圧調整、オーバーハング、ラテラルバランス、インサイドフォース・キャンセラ ー、アーム・ハイト、オイル・ダンピング量など、従来の煩わしい調整から一切開 放された。
そして、再生状態の蘇生能力がある。簡単に表現すれば、何百何千回と針でこすられ
た音溝でも、針でトレースされていた音溝の底部ではなく、音溝の上部にあたるバージ
ン・ゾーンをレーザーがトレースするので、どんな古いレコードも蘇ってしまうのだ。
また、ピックアップはリニアトラッキングなので内周歪みは発生せず、サーボコントロ
ールによってLPの偏心にも影響を受けない。最後に光学系からL・R独立のピックア
ップと伝送を行うため、針式のカートリッジの宿命であったクロストークとチャンネル
セパレーションが飛躍的に向上している。これだけ列挙すると良いことずくめだが弱点
もある。1.5g程度の針圧を印加したスタイラスチップの先端は、1c㎡あたりの単
位面積になおすと数トンもの圧力でトレースするので、ホコリなどを掻きだしながら進
行してしまう。しかし、レーザー光線はホコリなどを排除する力はないので、ノイズと
して再生してしまうのである。このホコリが大きいとレーザー光を遮断してしまいクリ
ック音を発生するが、電子的に音楽信号とクリック音を識別してキャンセルする「ノイ
ズ・ブランカー回路」を搭載している。レコード愛好家であれば常識的な事なので、レ
ーザーターンテーブルの弱点という表現はふさわしくないと思うが、レコードのメンテ
ナンスには充分なケアが必要ということだ。さて、レーザーターンテーブルの原理を文
章だけで解説するのに、どうしたら良いものかと考え、参考事例として私の自宅のアナ
ログピックアップのお話をする事にした。私が使用しているカートリッジは、自重がわ
ずか2.5gしかないのだ。有名なデンオンのDL-103が8.5g、オルトフォン
のMC-30Sが10.5g、同じくSPUシリーズが約30gと、大変軽量であるこ
とが不思議であろうと思われる。そのカートリッジとは、アメリカのウィンラボラトリ
ーという小規模メーカーのSDT-10というもので、SDTとはセミ・コンダクター
・ディスクトランスデューサーの略なのである。なぜ、これほど軽量かというと、ブロ
ンズ色の半透明なプラスチックのボディーには2枚の金属片が入っているだけで、一切
の発電機構を持っていない。この金属片の厚みは数十ミクロンと不明だが、幅が約1.
5mm程度で長さが10mm程度の小片で、ストレインゲージと呼ばれる半導体である
。軍需用のミリタリースペックを満たす高精度な物が採用されており、通常の半導体が
電荷と電流によって大きく抵抗値を可変するのに対して、ストレインゲージは機械的な
変位によって抵抗値を変化させるのである。従って、SDT-10には電源部が付属さ
れ、直流15Vのバイアスが供給されている。この電源部に出力端子が設けられており
、最大で3Vの出力を取り出せるのだ。従って、私は世の中にCDプレーヤーが登場す
るはるか以前から、カートリッジの出力をパワーアンプに直結してレコードを聴いてい
たのである。こんな概要でご説明すれば、2枚のストレインゲージは90度のアングル
で音溝の壁面に平行に配置され、ステーを介してカンチレバーと連結されているという
構造で納得して頂けると思う。つまり、カンチレバーを介して1本の音溝に対して1枚
のストレインゲージをあてがい、音溝の変位に対してストレインゲージの小片が極微小
な折れ曲がりという機械的変位を起こし、この変位が半導体として抵抗値を大きく変化
させ、バイアス電流に変調を与えて音声信号として出力されるのである。従って、一般
的なカートリッジのように、磁束を切る速度によって出力電圧の大きさを変化させない
ので、フォノイコライザーによるRIAA補正も必要としない完全な振幅比例型であり
、針先からパワーアンプまで完全なモノラル・コンストラクションが得られるのである
。自慢話しが長くなってしまうので、結論を言うと素晴らしい音である。さて、レーザ
ーターンテーブルの原理であるが、やはり発電機構は持っていない。原理としては光を
LP盤上に照射してから、どの様にして電気信号に変換するかという点に絞って解説し
てみる。まず、光学系のあらましだが、位置検出用と信号検出用の二つの半導体レーザ
ー発振器から、波長が785ナノ・メーターというレーザービームを照射する。それを
コリメータ・レンズに導き、ビームの平行化を行うが、この時のレーザービームの径は
2mm×6mmの楕円形をしている。そして、キューブ・スプリッターを経過し左右チ
ャンネルに分光される。その後、4枚のミラーとスプリッターを経由して円筒系フォー
カス・レンズへと導かれ、最終的にLPの音溝には6ミクロン×20ミクロンに収束さ
れて照射される。1チャンネルあたりのビームはこの通りだが、左右チャンネルの幅は
VSO(バリアブル・スキャナー・オフセット)システムにより、レコードの種類や年
代によって柔軟に対応出来るようになっている。この信号検出用のレーザービームに一
定の間隔(信号用ビームの上方向)で対となり、サーボ用のビームが音溝の肩の部分を
トレースしている。よって、サーボ用ビームが傷で損傷したりへこんだりしている部分
にさしかかると、それ自身の変動と同期して信号用ビームを音溝の深いところに瞬時に
誘導し、傷の影響が無いようにコントロールするのである。そして、レコードの反りに
対しては、先行してもう1本のビームが照射されており、その反射ビームを位置検出し
てサーボに働きかけピックアップの可動部分を上下動させて反りを難なくかわしてしま
うのである。詳細はカタログの図を見ながらご説明しないと文章表現では限界があるの
で、それでは音溝の変位をどうやって電気信号に変換するかを解説したい。まず、皆様
の頭の中で縦方向に引き延ばされたアルファベットの「S」の字を思い浮かべて欲しい
。この「S」の字の中心点から真横に位置するところに、レーザービームの発射点があ
る。この発射点から間横にまっすぐビームが放たれた時には、「S」の字の中心点から
まっすぐ反射が返って来るものと仮定して欲しい。次に、「S」の字が連続して縦方向
に移動する、つまり上から見た音溝の一波長のうねりがレコードの回転と共に移動して
いくわけだ。すると、「S」の字のカーブの部分にビームが当たるので、反射角度が変
化していく状態がご理解頂けると思う。この反射ビームを受け取るのが、PSD(ポジ
ション・センシティブ・ディテクター)と呼ばれる位置検出センサーなのである。浜松
ホトニクス株式会社が製造するPSDの中で、一次元位置検出用PSDと称される走査
幅12 の小さな受光素子である。また、発生する電荷は入射する光量によって変動す
るため、レーザーターンテーブルでは1枚ずつLPを変える度にキャリブレーションが
働き、レコードの反射率の誤差も補正しているのである。このPSDには両端と中心点
の三か所に電極があり、真中の電極に5Vの直流バイアスが供給されているのである。
PSDは平板状シリコンの表面にダイオードの表面効果を応用した層が形成されており
、光スポットが入射すると光電変換され、両端の電極に向けて光電流として出力される
。前述の「S」の字の中心点から反射したビームが、このPSDのセンターを捉えた場
合にはPSD両端に流れる出力電流は同レベルとなるが、「S」の字が動いて反射した
結果、センターを外れて入射した場合にはPSD両端の電流誤差が発生する。この電荷
の変化がバイアスによって強化搬送されて、音声信号として取り出せるというものだ。
これを後段の回路で電圧変換して音声出力としているのである。音溝の変位に対して反
射ビームが記録信号の周波数分だけ高速でスキャンするということは、一般のカートリ
ッジの磁気回路がもつ構造上の宿命とも言うべき、速度比例型発電と同様の出力変動が
発生することになる。簡単に言うと、周波数が高くなるほど単位時間内に反射ビームが
走査す る速度も回数も増加するため、周波数が高くなるにつれて出力電圧も 高くなる
ということだ。従って、レーザーターンテーブルにはRIAA特性を有するフォノイコ
ライザーが必要となるのである。さて、この様な概要を解説したところで、私が使って
いるウィンラボラトリーのSDT-10のお話を、参考事例として取り上げた意味がお
わかり頂けるかと思う。SDT-10もレーザーターンテーブルも発電機構を持ってい
ないという所が共通点であり、信号系は完全なモノラル伝送が可能である。また、両者
共にバイアスを必要としており、一定の電気エネルギーの流れに変調を与えて音声信号
として取り出しているのだ。従って、発電機としての従来のカートリッジのように、発
電効率のバラツキから微弱な信号の取りこぼしが無く大変豊富な情報量を引き出すこと
が可能となる。そして、大変なハイスピードである。また、バイアスの電力に支えられ
て信号が伝送されるため、カートリッジによる発電直後の微弱な信号を、増幅段まで導
くアーム内部のケーブルやピックアップケーブルを含めた伝送系からの影響も受けにく
い。ただ、両者の音質比較を想像する上で、SDT-10はパワーアンプに直結出来る
が、レーザーターンテーブルはフォノイコライザーが必要になるという点で安易な比較
は出来ない。つまり、レーザーターンテーブルはフォノイコライザーのグレードによっ
て再生音質の変化があること、逆に言えばフォノイコライザーの選択によって個人の好
みとグレードの上下が発生するということだ。レーザーターンテーブルの原理をご理解
いただく上で、音質の決定要因に従来のカートリッジと同様な一面がある事を強調して
おきたい。
第六章『ある日本人の覚醒』
時系列は相前後するが、レーザーターンテーブルを開発したロバート・ストッダート
氏がスタンフォード大学に在学中で、まだ23歳のころ。日本では一人の技術者が、ア
ナログレコードの再生における規制概念に一石を投じ、過去に象牙の塔として語られて
きたレコードプレーヤーの存在に大きな問題提起を行ったのである。どこかの企業の専
属という、行動と発想に制約をかせられる立場を好まない孤高のエンジニアである寺垣
武氏がその人である。寺垣氏の半生は森谷正規氏の著作になる「アナログを蘇らせた男
」(講談社発刊)に詳細に語られているので、ここでは実際のハードウェアとしての技
術に的を絞ってご紹介する事にした。今から一六年前の事だが、寺垣氏はオーディオ雑
誌の次のような一文に触発された。「LPのカッティングには、片チャンネル数百ワッ
トのエネルギーを 投入して切っている|。」全身全霊を込めた演奏家の演奏と、録音
機材の能力の全てをけてレコードを制作しようとしている姿には心打たれるものがあっ
た。しかし、寺垣氏が見た再生メカニズムの方は、「世界の名器と言われるものでも不
完全で変調のかかる要素が多過ぎる。これでは、技術が芸術の上にあぐらをかいている
ようなものだ。」こんな思いが、寺垣氏をレコードプレーヤーの開発へと導いていった
動機でもあり、以後の研究に対する原動力となったのである。一九七九年いよいよ寺垣
氏の試作第1号機が完成した。レコードの反りという曖昧さを当初から否定し、真空バ
キューム式の吸着機構でレコードの平面化を既に実現している。アームはリニアトラッ
キングで、二本のパイプに水を満たしフロートを浮かべ、そのフロートからY字型のス
テーを吊り下げてカートリッジを装着するという奇想天外のアイデアであった。そして
、2号機ではターンテーブルをベークライトに素材変更し、レコードの縦方向の曖昧さ
である反りをなくす吸着機構に加えて、レコードの水平方向の曖昧さである偏心を手動
で修正するという機構を開発した。この当時から、ターンテーブルの駆動方式はダイレ
クトドライブでもベルトドライブでもない、剛性をもつ特殊なストリングスをモーター
プーリーに5条がけにしてからターンテーブルへ渡すという、トルクを失わないような
駆動方式を採用していた。しかも、この2号機ではパンタグラフ式のリニアトラッキン
グ・アームを搭載したのである。次の3号機では、ターンテーブルはアルミ製となり前
作と同様な機構を持たせたが、大きく変化したのはトーンアームであった。パンタグラ
フ式で伸縮伸長するアームのヘッド部は、確かにリニアトラッキングで動作するが、機
構的に剛性と質量に欠けるという点が問題であった。そこで、ターンテーブルをブリッ
ジの如く橋渡しをする機械的なレールを構成し、ヘッド部に何と1.5kgという質量
を持たせたのである。次なる4号機当たりから、ハイテクを駆使してのアームのコント
ロールに主眼が移される。レコードの音溝をレーザー光線で読み取らせモーターを精密
に駆動して、アームのヘッド部を移動させたのである。さらに、5号機では4号機でア
ーム用に複数のモーターを使用していたものを、高分解能のステッピングモーター1個
に変更をした。しかし、試聴の結果は最悪で、この5号機はわずか3時間の寿命で研究
室の片隅に押しやられてしまった。実は、この4号機の開発からオーディオテクニカの
支援を受け、ハイテクの駆使が始まったのである。5号機から7号機にかけては、過去
のノウハウから得た技術をオートマチック化させ、プレーヤーとしての操作性も向上し
ていくのである。そして、協力を惜しまなかったオーディオテクニカの松下秀雄社長に
支えられて、7号機ではオーディオ史上例の無い究極のプレーヤーとしてその勇姿を一
般に発表したのである。総重量120kg、ターンテーブル重量30kg、もちろんレ
コードの反りと偏心に対しては電子的に自動で修正が加えられる。リニアトラッキング
方式のアームは、本体に強固に固定されており上下動はしない。そのかわり、ターンテ
ーブルがせり上がってきて、必要な針圧分だけカンチレバーを押し上げるという驚異的
な発想と機構の産物となったのである。もし生産販売すれば2,000万円という価格
にはばまれ、製品化はされなかったが、正に究極と表現しても差し支えないプレーヤー
が完成したのである。この時、1983年にアメリカではフィニアル・テクノロジーが
設立されていたわけである。しかし、これで寺垣氏の探究が終わりを告げたわけではな
い。ある日、寺垣氏が床に入ると奇妙な「ジャランコ、ジャランコ」という音が聞こえ
てきたという。ふと頭をあげて見回すと、そんな音を発するものなどありはしない。も
う一度枕に頭を乗せると、また聞こえてくる。不思議に思って枕元の目覚まし時計を取
り上げると、何とそのゼンマイが音の正体であることがわかった。良く見かけるベルを
頭に乗せて細い足の付いた、丸い旧式のゼンマイ仕掛けの時計を手に取ればカチカチと
いう時計の音しか聞こえない。ゼンマイの波動が細い足から畳に入り、布団と枕を通し
て耳に入ってきたのである。実は、私にも同様な経験があった。二歳の娘を寝かし付け
るのに添い寝をして、娘の背中をゆっくりと平手で叩いてやっているときだった。私が
枕を通して聞いたのは、娘の背中をそっと叩くに従って、「ジャラーン、ジャラーン」
とベッドのスプリングが振動する音だったのである。私も思わず我が耳を疑ってしまっ
た。小さく柔らかな子供の背中をやさしく叩いても、枕から耳を離せば何も聞こえない
。私の手の平のわずかな衝撃が子供の体内を通り、ベッドのスプリングを揺さぶり、柔
らかい枕を通して伝わってくるのである。そして、寺垣氏はこの時にハッとして、これ
までの研究に大きな見落としがあったことに気がつく。いかに大きな質量と、剛性の極
みを尽くしてプレーヤーを設計したところで、波動エネルギーは難無くその中を通過し
ていってしまう。ということは、ピックアップの針先で発生するエネルギーも波動とし
て伝わっていく。可動部分がある以上は必ず変位を伴っていくはずだ。つまり、可動部
分には機械的なアソビがなければならず、ミクロ的には必ずガタツキが伴わないと動か
ないという事実である。そこで、波動理論が第二の開発スタートのきっかけとなった。
回転するターンテーブルから、いかにしてガタツキを取り去るか。レコード面上をトレ
ースするアームから、いかにしてガタツキを取り去るか。この二点に新たなる研究のテ
ーマを見出して試作13号機までが開発され、Σ3000の完成となり現在のΣ500
0が誕生するのだ。
第七章『支点の明確化』
いくら電子的に制御しようとも、プレーヤーは機械であり物理的な理論が支配するト
ランスデューサー(変換器)であるはずだ。前章で述べたとおり、ガタツキを完全に取
り去ってこそ本物と言える。つまり、単純でありながら困難である「支点の明確化」を
実現したのがΣ5000である。そして今、1995年9月、私の手元には待望久しか
ったΣ2000がいち早く到着した。Σ5000の320万円という価格からすると、
同じ命題を背負って設計されたΣ2000が140万円というのは大変なコストダウン
の成果として評価出来る。さて、この両者の機構を比較しながら解説すると概略次のよ
うになる。まず、ターンテーブルの軸受構造であるが、皆様の頭の中で重量あげ(ウェ
イトリフティング)に使うバーベルをイメージして頂きたい。棒の両端に円盤の錘が付
いた例のアレである。このバーベルをうんと小型にして、円盤の周辺を丸みを帯びて磨
きあげたものを2本用意する。それを縦方向に寄せ、平行を保ったままで上下端を固定
して1.5度傾ける。上下に2枚ずつ合計4枚の円盤が位置している真中に、太さが1
2mm、長さが158mmのSKS鋼にクロームメッキを施した主軸を寄りかからせる
のである。主軸の下部は超硬ボールで点支点として摩擦は最小限とする。円盤と主軸の
接触幅は1mm以下で、円盤の硬度を僅かに落してあるので、使うほどに主軸の仕上げ
面が転写し、円盤の外周が磨かれていくことによりS/N比は向上していく。この主軸
の上に重量12kgで黄銅系押出し材のターンテーブルを、4本のネジでフランジ結合
させて乗せたのがΣ5000である。前述のバーベルの円盤で下側の2枚を取り去り、
重量8kgのターンテーブルを乗せたのがΣ2000である。当然、原理と効果は同様
だ。さて、ここまでの解説で、主軸を1.5度傾けたという事を疑問に思う方もあるの
ではなかろうか。カートリッジが滑らかにトレースするはずの水平なターンテーブルに
対して、主軸を傾けてしまったら「皿回し」のごとくフラフラしてしまうのではないか
と。そこで、正面から見て右側のカートリッジがトレースする面を、主軸同様に水平面
から上に1.5度傾けてある。これでトレース面での主軸の傾きがキャンセルされ、正
面から見て左側はバンクを描きスリ鉢状態となるのである。これは、両者共に同一の設
計だが、このスリ鉢状のターンテーブルにレコードを乗せてから、2kgはあろうかと
いう重量級のスタビライザーを乗せる。すると、まるでレコードがため息でもついたか
のようにフ|ッと、ターンテーブルに吸いつけられてしまうのである。この効果は大き
い。しかし、レコード盤と密接するターンテーブルの表面仕上げには大きな相違がある
。電柱ほどの太い黄銅系の丸太んぼうを輪切りにしたターンテーブルには、メッキやク
リアーニスなどの表面コーティングは一切行われていない。天体望遠鏡の非球面レンズ
を磨きあげる超高精度のダイヤモンド旋盤は、世界的に見ても30台程度しか存在して
いない。その内の2台が日本にあって、Σ5000のターンテーブルは長岡市にある2
5m以上の厚さがある大理石岩盤上に設置されたそのマシンによって高精度な鏡面仕上
げが施されるのだ。この工程にかかるコストだけで「軽自動車一台分くらいかかる」と
いうのは1ロット10台の生産台数であるΣ5000ならではのエビソードである。従
って、Σ5000のターンテーブルに写る私の顔は、回転していることがわからないほ
ど鮮明な反射像として輝いて見える。さすがにΣ2000のコストでは同様な加工は無
理だが、表面仕上げだけで音が愕然と変わるわけではない。寺垣氏のこだわりから設計
されたΣ5000の加工精度からすれば、コストダウンの格好の標的となったことも十
分うなずける。さて、第五章では代表的なカートリッジの重量を述べたが、シェル一体
型のオルトフォンSPUシリーズなどは重量級の好例である。しかし、Σ5000はカ
ートリッジなしのアームヘッド部だけで400g以上、Σ2000は同様に300g以
上と大変な質量をアーム先端に持たせている。しかも、アーム支点からそのヘッド部に
至る内部には、高張力鋼の棒が組み込まれており、強力な圧縮応力でアームを前後から
締め付けている。これほどの重量を従来のようなスタティック・バランス方式で、水平
バランスを取ろうとするとメインウェイトには2.8kg以上の巨大な重量が必要とな
ってしまう。これではスムースな動作が出来ないので考えられたのが、2つのテコを利
用し、レバー比の差によって軽量ウェイトでバランスをとった工夫である。そして、ア
ームの各支点は鋭いピボットとスリ鉢状の金具の組合せになっており、ピボットから金
具の方向に向けての一方向に接触圧力がかかる構造になっている。従って、一切のガタ
ツキなくスムースに動作するが、機械的な遊びが全くない構造となっている。軽量であ
ることがスムースなトレース能力につながる、という規制概念が見事に打ち破られたこ
のアームは、先端の指かけを持ってその質量を受けてみれば一目瞭然でその異様さを感
じることが出来る。アンプのボリュームを絞って、レコード盤上をゆったりとトレース
するカートリッジに耳を近付けてみると、以前のアームでは少なからず溝に刻まれた音
楽がニードルトーク(針音)として聞こえてくる。しかし、Σ5000とΣ2000で
は一切ニードルトークが発生しない。これはアームが共振していない証明であり、音溝
の機械的なエネルギーを余すところなくカンチレバーにピックアップさせている事実に
他ならないのである。さて、主軸構造とアームの特徴を理解した上で、ターンテーブル
の駆動原理に触れてみる。Σ5000はDCコアレスモーターを、Σ2000はコアレ
スブラシレスモーターを搭載したアイドラードライブ方式を採用している。問題は、こ
のアイドラーの使い方である。Σ5000は、ネオジウムマグネットが入って面着磁さ
れ、周辺に1mm程度の厚みでゴムを巻いた直径12mm、長さが17mmの円筒のア
イドラーが、モーター軸とターンテーブルの間に吸着して、それ自身が最も安定した場
所で回転してトルクを伝えている。Σ2000のアイドラーは、ちょっと見ただけでは
わからないが金属性のアームによって保持されており、そのアイドラーの中心には直径
が約3mmの穴があいている。そのアームから垂直に上方に伸びているアイドラーシャ
フトは、直径がわずか1mm程度の極細いものなのだ。これではガタガタしてアイドラ
ーが正しく回転しないのではないかと誰もが思うだろうが、実際には見事に静粛性を保
ってきちんと回転してトルクを伝えている。不思議に思ってよくよくながめて見ると、
静止している状態ではアイドラーはアームのうえで落ちないように保持されているのだ
が、回転するモーターに接触すると、瞬時にターンテーブルとモータープーリーとの間
で挟み込まれてスルスルとほんのわずかにせり上がる。1mm程度のアイドラーシャフ
トが、直径3mmのアイドラーの穴の中心に位置するようになり非接触状態となるのだ
。つまりターンテーブルとモーターの間の空間に浮き上がった状態で、アイドラーシャ
フトから開放された状態で回転しているのだ。絶妙なからくりに感心して、セイコーエ
プソンの担当者に思わず聞いてしまった。「ヘェ|ッ。なるほどネ|。それで、これは
誰が考えたの。」Σ2000の設計段階で、量産化におけるコストダウンのポイントで
主導権を握ったのはセイコーエプソンの方であったと聞いているが、さすがにこのアイ
デアまでは思い付かなかったらしい。担当者は声のトーンを一段落して、「これは、や
っぱり寺垣先生です。」と答えられた。いずれにしても、レコードクリーナーをかなり
の強さで押しつけてもビクともしない、高トルクで回転するターンテーブルも過去のプ
レーヤーとは大きな相違を感じさせるものである。このように基本思想は全く同じにし
て設計されたΣ2000であるが、Σ5000の上面デッキ部分に施された漆仕上げは
さすがにコストが高く、Σ2000では10mm厚の硬質アクリルに変更されている。
寺垣氏自らが「表面粗さ計」という測定器的な観点から設計されたプレーヤーだけに、
ロマンチックなデザインであるとは言い難いかもしれない。しかし、レコード芸術にお
いて本当にロマンチックであって欲しいのは、レコードの中身すなわち音楽そのもので
はないだろうか。
第八章『ミクロの接点』
さて、LPレコードは1分間に33.3回転で回っている。これは、LPの内周と外
周で線速度が大きく変化する、いわゆる角速度一定のコンスタント・アンギュラー・ベ
ロシティーという変調方式の一つである。そこで、一秒間に針先がトレースする長さを
周波数で割って見るとある高さの音の波形の長さ、波長を計算することが出来る。直径
30cmのLPの外周では、20キロHzの波長は約26ミクロン、25キロHzの波
長は約21ミクロンとなる。同様に、直径15cmの最内周では20キロHzの波長は
約13ミクロン、25キロHzの波長は約10.5ミクロンとなる。この長さの音溝に
対してカートリッジの針先はどの程度の大きさで接触しているのかというと、丸針では
直径7ミクロン程度の円形であるが、楕円針やラインコンタクト針の場合だと、音溝を
上から見て1から3ミクロン程度で、横から見ると高さが10ミクロン程度の接触面積
を保ちながらトレースしているらしい。以前、寺垣氏からスタイラスチップの先端が音
溝に接触している顕微鏡写真を見せて頂いたことがある。6,000倍程度の倍率だと
思われるが、針先が進行方向に対してうねりのような起伏で音溝の表面を盛り上げなが
ら擦っている画面であった。塩化ビニールのレコード盤には弾性限界があり、人の皮膚
をつねるとシワができて離せば元に戻るように針圧をかけてトレースする針先はレコー
ドの表面シワをよせて、通り過ぎれば元に戻るということを繰り返しているのである。
この数ミクロンの接点に1gから3g程度の圧力を加えるということは、1平方センチ
当たりの単位面積に換算すると5トン程度から10数トンという強大な圧力にもなると
言われている。音溝の深さは左右の録音レベルと位相によって深くも浅くもなるが、針
先の接点の何と小さいことか。この小さな接点に総重量が2kgを超えるアームで、音
楽情報を余すところなく引き出そうとする寺垣氏のプレーヤーの独自性がある。はたま
た、この針先の接点の40倍もの面積で安定した音溝の変位を捕らえようとするレーザ
ーターンテーブルの独自性も納得出来るものだ。前述したとおり、レーザービームのス
ポットは幅が6ミクロンということで、最内周で25キロHzの波長である約10・5
ミクロンも十分に安定トレース出来る分解能を持っているのである。これらミクロの世
界は、我々にとって想像でしか届かない領域であった。しかも、エネルギーの蓄積が時
間軸に対して物理的な形状の変位として記録されるアナログの世界では、時間軸に対す
る分解能が更に強化され奥に秘められた情報の再現性を深めていく可能性があるのであ
る。さて、私はレーザーターンテーブルとΣ5000の登場によって、アナログ再生に
かかわる使い手の、理解力の分岐点が発生したと考えている。ある雑誌の評論文を数行
引用させて頂けば、「鳴っているのは音楽ではなく、楽を差し引いた音だけ。」「音の
潤いや風情や情緒的甘美さはなく、醒めた音だけが鳴っていた。」音楽は楽しむものだ
から、楽しく聴かせるプレーヤーが良いものだ、という考え方。もちろん、正論であり
間違いではありません。しかし、個人的な趣向と快感を求める度合いに限界がないこと
も事実である。しかも、変換器という大変な重責を負った装置に対しては、より一層の
主観が介入してしまう可能性がある。これは、設計者側にも使用者側にも共通する人間
の摂理かもしれない。とすれば、特定の人間が思い入れた好みによって作られた物を、
そうであると判断するための基準が私たちに取って必要なものではないだろうか。スプ
リングやゴムを素材とした場合、オイルやシリコンを使用したダンピング機能を持たせ
た場合、これらの使用量や調整によって再生音が変化することを設計者たちは知ってい
る。では、それらの調整の過程で、彼らがコレで良いとした根拠はどこにあったのか。
素材に変位するもの(形や柔らかさ、蓄積されるエネルギーが変化するもの)を使って
、その使い方がうまいと言われる事が世界の名器の条件なのだろうか。確かに、オーデ
ィオコンポーネントの数々は、その調整によって音が変わる楽しみを与えてくれるもの
である。そして、その変化の幅を広げることも技術であるならば、一つの技術指向に向
かってどれだけ深く追究し妥協なく完成度を高めるかということも、曖昧さを駆逐する
という意味においてはより高度な技術力を要求されることであろう。心地良い音を出す
プレーヤーは過去にたくさんあったが、言わばプレーヤーが優秀な演出効果を演奏にも
たらしたものと考えられるのではないだろうか。なぜかと言えば答えは簡単である。演
出家が変われば演奏に大きな変化をもたらしてしまい、プレーヤーによって同じレコー
ドの再生音があまりにも大きく変わってしまう事実があるからだ。つまり、化粧を施し
た役者の顔はおなじみだが、素顔を知っておく必要はあるが今までは素顔を見ることが
出来なかったのだ。そして、演出を拒絶したプレーヤーの登場によって、初めてそれが
可能となったと言える。この両者の登場によって、録音の善し悪しや演奏者の裸の技量
を忠実に表現する物差しとして、変換器という目的に徹したプレーヤーの存在意義を再
認識させてくれるものと私には思えてならない。今、オーディオマニアが感染しやすい
「疑心暗鬼症候群」の特効薬を手に入れて、重厚なアームがブラックディスクの音溝を
捕らえている実物を前にΣ2000とΣ5000を聴き比べ、LT-1XAの再生音に
馴染深さを覚えるようになり、私はこれまでのアナログ遍歴を思い出しながら、ホ-と
深いため息を吐いてしみじみと思った。「あ-、やっと。やすらかにアナログを味わう
事ができる。」と。
【完】
|