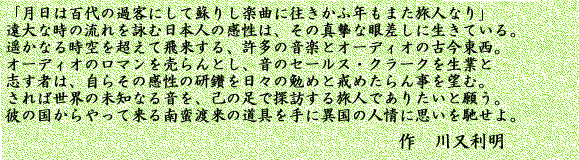第二十四話「額縁職人の腕前」
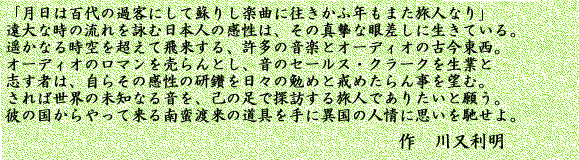
第一章『素顔美人』
1994年10月某日、ダイナミックオーディオ・サウンドハウスの五階。テクニク
スブランドによる久々の高級スピーカーをオーディオフェアーに先駆けて聴かせてくれ
るというので、営業が終わってから訪ねてみた。ダイナミックオーディオが毎年開催し
ているマラソン試聴会の実行委員長をこの年は私が担当しており、このスピーカーもエ
ントリーしていたのである。実は、この随筆の第二十一話でもご紹介したとおり、ジム
・ティール氏が近々来訪されセミナーを開催する予定があった。このテクニクスの新製
品がパッシプラジエーターを搭載しているという事前情報があり、ティールの新作スピ
ーカーであるCS7もパッシブラジエーターを採用したという共通点から大変興味があ
ったのである。今思えば、当時の試聴室やアンプとの関連性が好ましくなかったと分析
が出来るのだが、聴かせて頂いた私の個人な印象は今一つであった。正直にいえば今一
つどころか、あと三つくらい注文を付けたいくらいである。近代の海外高級オーディオ
を多数聴いてきた立場から、またそれらを評価するお客様の意見を含めて、思わず同席
されていた設計者に噛み付くが如き議論を持ちかけてしまったのである。この設計者こ
そ松下電器産業株式会社オーディオ事業部において、長年スピーカーの設計一筋に生き
てこられた古田真仁氏である。昭和28年生まれの42歳という、男性として大変油の
乗った働き盛りのエンジニアである。とにかく、氏のお人柄は謙虚の一言に尽きる。私
も仕事がら内外のメーカーの社長、設計者、あるいはその両者を兼務する人など多くの
人に出会ってきた。世の中には頑固一徹な技術者で素人の戯言など聞く耳持たぬという
御仁もおられるが、古田氏は生意気な私の意見を真正面で受け止め真剣に聞いて下さる
のである。「この人だったら本音で話しが出来そうだ。」と、営業マンの嗅覚が本能的
に教えてくれる親しみやすさがあったのである。無遠慮にも私が指摘した不満点の概要
は、次のようなものであったと記憶している。
(1)先ず低域が出過ぎ、低音のリズム楽器の立上りが遅く膨らんでしまうイメージが
付きまとう、ブーミーな低音でオルガンの脈動感に代表される低域の輪郭が不鮮
明。
(2)ヴォーカルの口元が見えない、ミッド・ローの帯域がマスキングされているよう
に、量と質ともに物足りない。
(3)高域のレンジ感は認めるが、奥行きの表現と音場感の表現には乏しい。
こんな具合に、今考えれば随分と無礼な意見を多々申し上げた事になる。さて、次に
このスピーカーを耳にしたのが94年11月5・6日に池袋のサンシャインシティープ
リンスホテルで行われたマラソン試聴会の会場の一室である。この時は私自身が会場の
一室を担当しており、じっくりと聴くことは叶わなかったが弦楽器のアンサンブルで大
変鮮明な高域が印象に残った。化粧をしていない素顔がきわだつ若い女性を瞬間的に見
かけて、ふさわしい衣装とセンスのいいメークを施したら、さぞかし絶世の美女に変身
するであろうと予感するような閃きである。「ウ|ン、何か、これは結構、可能性があ
るみたいだなァ。」と、自分の担当するデモに忙しい中で煌めくものが記憶に残ったの
である。
第二章『テクニクスSB−M10000』
昨年、この素顔美人に出会った時には、まだ最終段階の仕上がりではなくサンプル機
として製作された段階のモデルであったらしい。九四年の一二月に発売されたステレオ
サウンド誌第113号の582ページに紹介されているが、私なりに違う切り口でこの
SB−M10000を紹介してみたい。私は職業柄マスコミ・メディアに籍を置く人間
ではないので、何かを表現するときに他社製品との比較をもって解説出来るところは大
変便利なものである。また、その方が具体例として皆様にも理解して頂きやすいと思う
。まず本機のエンクロージャーを造形する上で低域再生の手段が、その特徴としてデザ
インに表われている。横幅590mm、高さ1370mm、奥行き500mm、重量1
49kg、価格は2台で420万円(95年5月現在ブラック・グレイ仕上げ)これは
、皆様ご存じJBLのK2S9500のアウトラインである。これに対してテクニクス
のSB−M10000は、価格はセットで460万円、重量160kg、横幅486m
m、高さ1575mm、奥行き575mmである。K2S9500は、650Hzをク
ロスオーバーとする2ウェイ3スピーカーであることは今更説明の必要もないと思うが
、仮想同軸と表現されるように中高音を受け持つコンプレッション・ドライバーを二本
の大型ウーファーが上下に挟む形の構造になっている。SB−M10000も、これと
同じように最低音部を受け持つパッシブラジエーターが中高音部のユニットを上下に挟
んでいるのだが、完全に上下対象の仮想同軸構造ではない。低い方から分析していきた
いと思うが、SB−M10000はシステムの上下、前後に四つのパッシブラジエータ
ーを搭載している。このパッシブラジエーターの動作原理については、この第二十一話
でもご紹介しているので是非読み返して頂きたい。実は、この点でティールのCS7に
ついての後日談がある。CS7の30センチ口径のパッシブラジエーターを駆動する同
口径のアルミ合金のウーファーは、上の帯域を受け持つ16センチのミッドロー・ユニ
ットと100Hzのクロスオーバーでつながっていた。現に私のフロアーに入荷した初
期ロットの生産分もそうであった。ここで、日米同時に両国の販売店から(日本では私
が文句を言ったのだが)ティールに対して、ある不満点が申し入れられたのである。店
頭で必要なデモの音量まで上げていくと、この一六センチのミッドロー・ユニットがク
リップするのである。この16センチのミッドロー・ユニットが100Hzから一キロ
Hzを一手に引き受けるということは、低音楽器が最も集中する100Hzから250
Hzあたりの信号を30センチ級のウーファーと同じ能率で働かせなければいけないと
いうことだ。言い替えれば、30センチ・ウーファーと同じ音量を維持するためには、
大変大きな振幅が要求されるということだ。そこで、ティールは第2ロットの生産分か
ら、この部分のクロスオーバーを220Hzに改良してきたのである。この改良によっ
て全体でのピーク・マージンを15デシベル向上させたとのティールからの連絡があり
、私も安心して販売出来るようになった。さて、SB−M10000はパッシブラジエ
ーターの受持ち帯域を、何とカタログ上ではクロスオーバー60Hzと表示している。
一体どのような観点から設計されているのであろうか。これはカタログにも明示されて
いるように、「ケルトン方式」という特殊な構造をとっていることが大きな要因となっ
ているようである。ケルトン方式とは、簡単に云うとパッシブラジエーターのドライバ
ーを従来のように露出させるのではなく、パッシブラジエーターの後方にドライバーを
配置して両者を専用のキャビティーで包み込み密閉したものとご理解頂きたい。従って
、ドライバーは特定の容積を擁する密室の空気に対して音波を放出し、その気圧変化に
よってパッシブラジエーターを駆動することになる。英語では「ケルトン型」という表
現ではなくバンド・パス型と表現されるのだが、前述のようにドライバーとなるウーフ
ァーが露出している場合は、それとパッシブラジエーターの混合した低音を聴くことに
なる。この場合は、ドライバーとなるウーファーは電気的に設定されたクロスオーバー
周波数の数オクターブ上の帯域まで音波を放射している。しかし、駆動源であるウーフ
ァーをパッシブラジエーターの後方に隔離してしまい、それ自体が発生する不必要な高
域を閉じ込めてしまったものと考えられる。しかも、パッシブラジエーターの質量によ
って共振点を設計しえるという動作原理を応用すれば、特定の帯域だけを引き出すこと
の出来るバンド・パス型という低域再生方式が可能となる。従って、カタログ上では最
低音部のクロスオーバーを何と60Hzと表記してあるが、ドライバーに供給される電
気信号は大体その四オクターブ程度上の周波数から下側を入力していると思われる。こ
のチューニングについて思い起こされる事例として、随筆の中でも紹介したティールの
CS7ではパッシブラジエーターの質量は190gで共振周波数を19Hzに設定して
いるという事である。昨年、古田氏にこの話しをしたところパッシブラジエーターはテ
ィールよりは軽めの設定だと言っておられた。国内メーカーの場合は企業秘密というノ
ウハウがおありになるのではっきりとは発言されないことがあるが、いくつかの技術的
な質問をした中でポロッと「ドライバーの振動板の質量は、大体70gくらいかなぁ」
というコメントを思い出した。実物を聴いた上で私の個人的な推測では、パッシブラジ
エーターはこの倍の140g程度、共振周波数は28Hz程度に仕上がっているのでは
ないかと考えている。(注・あくまで個人的な推測です)さて、この様に独自な方法で
鮮明な重低音を生み出しているわけだが、ドライバーとパッシブラジエーターは、なぜ
仮想同軸のように上下前後に四組も必要と判断されたのであろうか。低域に再生限界が
伸びれば伸びるほど、エンクロージャーに対する制振構造が求められるのは推測に難し
くない。しかし、家庭用としては大きさや重さに限界があるのは当然の事であろうと思
う。ティールの場合にはレジンコンクリートと称されるグラスファイバーの繊維を混入
した、いわゆるコンクリートという新発想の素材を採用してバッフル板を製造すること
で解決策とした。テクニクスが採用した手段はデュアルダイナミックドライブというキ
ャビネット構造で、同社はこの難関をあっけなく解決してしまった。前述のドライバー
とパッシブラジエーターを二組尻合わせに対向させたのである。これは丁度、数年前に
フランスのJMラボが日本でデビューさせたユートピアのウーファーがこれに酷似した
方式を採用していた事が思い出される。ユートピアもウーファーの後に、振動板のない
同一な磁気回路をもつユニットを背中合わせにして搭載し、機械的な振動をキャンセル
させて大変鮮明な低域再生を実現していた。これも私の随筆で取り上げたエピソードで
ゴールドムンドの2トンのコンクリート塊の実験の話があったが、単なる質量の拡大に
よって振動を吸収しようとしても、質量だけでは振動の抑止には限界があるものだ。テ
クニクスの採用したこの方式は大変コンパクトでありながら、大音量再生の場合にそれ
とわかる優れた効果を発揮している。そして、その副産物として描かれる低音楽器群の
位置関係に対して、臨場感と奥行き感を満足させる効用が上部に搭載されたウーファー
の存在として感じとれるのである。
さて、次に60Hzから600Hzを受け持つミッド・ロー・ユニットに目を向けて
みた。カタログ上ではこの帯域を二つのユニットが並列駆動されているように受け取れ
るのであるが、実際に大きな振幅の信号を入力してみると、この二つのユニットの振幅
が違っているのである。これは何か秘訣があるな、と推測の領域を広げてみることにし
た。この場合は上側のクロスオーバーである600Hzまで、というところにヒントが
ありそうだ。つまり、600Hzというとヴォーカルの低音階部やコントラバスの高音
階部が存在する帯域である。これらが60Hzから少し上の、100Hzから250H
Zに存在する低音リズム楽器が集中する大きな振幅と一緒の振動板上から放射されると
いうことに何か問題はないのだろうか。これも、簡単に云うと600Hzと60Hzの
音が同時に発せられた場合、一秒間に60回ピストン運動する上に一秒間に600回振
動する音が、大きなエンベローブとして前後運動している振動板の上で小きざみに震え
ながら動くことになる。600Hzの再生音に対して、10分の1の周期を持つ60H
zの信号がドップラー効果を与えてしまうということになる。つまり、60Hzの信号
で振動板が前に迫り出してくる過程では600Hzよりも若干周波数が高く聴こえ、逆
に奥へ引き戻される過程では600Hzよりも若干周波数が低く聴こえてしまうのであ
る。これが毎秒何百回と繰り返されるのだから、たまったものではない。この状態をオ
ーディオ用語では「変調歪」というのだが、簡単に説明するとこういうことになる。こ
の「変調歪」に侵されてしまうと、音像が不鮮明になり空間表現が損なわれ再生音の品
位を著しく低下させることになってしまう。これを解消するためにはどうしたらよいか
、どうやらこの答えが二つのミッド・ロー・ユニットの振幅が違っているところにあり
そうだ。つまり、外見は同じでも上部についているミッド・ロー・ユニットを、100
Hzから250Hzといった低音部のボリューム・ゾーンから逃れられる所でミッド・
ハイ・ユニットとつなげていくという事である。私は先程のティールのクロスオーバー
周波数変更の事例を思い出して、60Hzから600Hzの中間で少し余裕を見て30
0Hzくらで、更に緩やかな帯域分割をしているのではないかと推測している。この様
に、多くの楽器群の基音部分を支えているミッド・ローの600Hzから3.5キロH
zを受け持つミッド・ハイは六cmのドーム型ユニットである。ここで大変大事なこと
なので強調しておきたいのは、テクニクスはミッド・ローとミッド・ハイの振動板に同
素材を採用したという事である。両者共にマイカを主材料としており、18cm口径の
ミッド・ローには漆のコーティングを施し高域側に対しての質感の連続性を図っている
。さて、前述の中で「完全に上下対象の仮想同軸構造ではない。」という一節を述べて
いるが、SB−M10000の中・高域のユニット配列は確かに仮想同軸とは言い難い
。上からトゥイーター、ミッド・ハイ、ミッド・ロー二つ、と並んでいる。先程のJM
ラボのユートピアはスコーカー二つにトゥイーターが挟まれる上下対象の仮想同軸型で
あったが、新型のアルコアではスコーカー二つの上にトゥイーターが並ぶ配列に変わっ
てしまった。今はなき、米国ヘイルス社のシステム1リファレンスも試作の段階ではス
コーカー二つにトゥイーターが挟まれる上下対象の仮想同軸型であったが、完成品では
上のスコーカーが外され上にトゥイーター一つだけになってしまった。JBLのK2や
パイオニアの仮想同軸型のように、2ウェイで中央に何らかのホーンを採用したものは
よいのだろうが、コーン型やドーム型のユニットで波長の近似する二つのスコーカーの
間にトゥイーターを位置させることは、指向性を抑制してしまう傾向があるようだ。ス
ピーカー主軸上の正面で聴く場合にはさしたる問題はないのだろうが、上下左右の方向
へ主軸から外れた角度で聴いてみると高域の音色に変化が表われる場合がある。SB−
M10000に搭載されたスーパーグラファイト・ダイヤフラムのトゥイーターは、何
と100キロHzまでマイナス10デシでカバーする大変な広帯域再生を実現した強力
なユニットが採用されている。この超高域をスムースに拡散放射させるためには、中・
高域を仮想同軸構造にしたくなかったということが推測出来るのである。
第三章『ニッポンのオーディオ』
ひと昔前は国内メーカーの新製品発表会や店頭においても、知った顔をしたマニアが
A社が発売した新製品のアンプを聴いて「やっぱりA社の音だ」と云い、B社の新しい
スピーカーを聴いて「B社トーンとも云うべき音だ」と語る場面をしばしば目にしたこ
とがある。その場に居合わせた私は「そんなものかなァ」と半信半疑であった。よい意
味で伝統を重んじる物作りには賛成である。しかし、ブラインドで聴かされたならば、
ここまで明確に特定メーカーの音だと言い切れるものだろうか。疑い深い私の性格から
すると、メーカーロゴのエンブレムが目の前の製品に貼付られているという先入観から
生まれてきた社交辞令のように思えてならないのだ。少なくとも、現在私が毎日聴いて
いる海外メーカーのコンポーネント群は、そういう意味では首尾一貫した個性を持ち合
わせていることは断言出来る。最近では、ジム・ティール、ジェフ・ローランド、デビ
ッド・ウィルソン、フランコ・セルブリン、ゴールドムンドのミッシェル・レバション
など、この随筆でも海外の色々なマニュファクチャラーを紹介してきた。彼らのほとん
どはリーダーシップを握る特定の人材が、その理想とする物を作り出そうとする姿勢そ
のものを企業のメインテーマとして製品に反映している。この個性的な音作りの姿勢こ
そがインポート・オーディオの面白さであり醍醐味である。そして、ここにはリーダー
シップを握る人物の感性の進化と遍歴が色濃く表われており、そのブランドが送り出す
製品に対しての伝統と格式として受け取れるのである。一人のパーソナリティーに支配
されているがゆえに、そのトーンキャラクターを大変明確に認識する事が出来るのが海
外メーカーの特徴である。それでは、国内のオーディオメーカーに対するイメージはど
うか。数十万円から数百万円の超高級コンポーネントのイメージで認識されている海外
メーカーに比べれば明らかに不利である。ソニー、ビクター、松下電器、パイオニア、
など日本の場合は数千人から数万人という大企業である。従って、経営上の宿命から市
場拡大を目的とした一般大衆向け商品を開発し、次々と新しいマーケットを創造してい
かなければならない。「ハンディカムとウォークマンのソニー」「ビデオのビクター」
「レーザーディスクのパイオニア」「画王の松下電器」などのキャッチコピーに象徴さ
れるように、既に各社の企業イメージはオーディオから程遠いものになってしまった。
舶来品崇高が根強いマニア層の心理から察すると、ニッポンのオーディオに対して正当
な評価がなされにくい土壌を醸成した原因がこの辺にあると思われる。ここまで極端な
ことはないとしても「マスコミの宣伝活動だけで売れてしまう大衆商品ばかりを、大量
生産している国産メーカーが作った高級オーディオなんて。」という先入観を抱いてい
る人は少なくないと思う。海外メーカーの最大手といっても、マークレビンソンのマド
リガル社でさえ社員数は130名前後である。前述の著名ブランドの社員数にしたとこ
ろで、数人から20数名という零細企業がほとんどである。さて、それではSB−M1
0000は、どの様な企業力によって作られたのだろうか。大変大ざっぱな数字だが、
松下電器産業株式会社の全社員数としては凡そ10万人程度であると云われている。そ
の内のオーディオ事業部としては約2,500人、その中で単品のコンポーネントを設
計している設計六課は25人という陣容である。更に、この中でコンポーネント・スピ
ーカーを専門に設計しているグループが10人である。しかし、古田氏をはじめとする
このスピーカー部門の数人がすべてを開発したわけではない。松下技研は博士号をもっ
ている人が何人もいるような30名程度の同社のシンクタンクである。この中に新素材
研究所というセクションがあり、3人のエキスパートがスーパーグラファイト振動板を
開発したのである。この振動板をユニットとして完成させているのが松下電子部品株式
会社で、4人のユニット製作の職人とも言える専任者が担当している。約300人程度
の研究員を擁する映像音響研究所は、製品化以前の基礎開発研究を行っている。同等の
陣容で具体的製品化のデザインを行っているのが、同社のAV研究所である。これらの
五部門の開発力が結集され、五年以上の時間をかけてSB−M10000の完成をみた
わけであるが、当然の事ながら単純に五部門の全ての人が着手していたわけではない。
専従で開発に当られた人員は、数十名程度の少数精鋭で行われたものと伝え聞いている
。そして、このプロジェクトの技術的な総括で、頭脳部分としての役目を古田氏が果た
したのである。従って、世界に冠たる松下電器を母体とする各セクションの開発技術力
をおおいに活用して作られた作品ではあるが、企業の規模とは切り離して、古田氏をは
じめとする開発メンバーの感性が色濃くSB−M10000によって表現されているこ
とをご理解頂きたい。海外のメーカーでも設計と音質決定を行って、実際の製造は外注
という形態で運営されているところも多いのである。つまり、私が言いたいのは、物作
りの核心に携わった頭脳集団の規模は海外の著名ブランドとそれ程かけ離れていないと
いう事である。ここで、皆様の経験上で前述の国産メーカーのトーンキャラクターとい
うものがあるとしたら、少なくても過去のテクニクスのイメージを一端は白紙に戻して
頂きたい。テクニクスの伝統を重んじるという同社の皆さんの反発を買うかも知れない
が、既にSB−M10000は過去のマーケティングの領域で評価されるレベルではな
い。正直申し上げて、斯く言う私のフロアーには日本の製品は殆ど無いのだが、理由は
大変簡単である。お客様の評価を聞くうちに、自然と無くなってしまったのである。3
年程前、オーディオ雑誌で大層評価の良い、120万円もする国産のアンプがあった。
そのアンプを聴きたいというお客様が来店され試聴して頂くと、必ず次のような成り行
きになってしまうのだ。「すみませんが、そのマークレビンソンに替えて下さい。」「
そこにあるチェロのアンコールも聴かせてくれませんか。」と、複数の製品を試聴して
頂くと、「私はこちらの方が良いなァ」「こっちの方が好みだねェ」と、ほとんど海外
の製品に評価が移ってしまうのである。国産製品を売りたいと思っている私は、無理言
ってそのアンプの設計者に来て頂き店頭での出来事を話した。まず、私はお客様と同じ
方法で試聴をして頂き、意見を求めましたのである。「確かに違いますねェ」そして、
次に質問をした。「御社では、アンプの音を聴くのに、どこのスピーカーを使っている
のですか。」この答えは、私の想像通りのものだった。「自社製品です。あとドイツ製
の業務用モニターもあります。」私でもこのドイツスピーカーのメーカー名は知らなか
った名前であり、今も思い出すことはできない。すなわち、高級オーディオ販売の最前
線であるこのフロアーで聴ける音、ここで多くのお客様が語られるようなスピーカーと
は程遠いものだった。日本のユーザーが求めている感性を、私なりに事例をもってお話
したつもりだが、その設計者の方は最後にこう述べられた。「当社のアンプは正常に機
能しております。」私はその瞬間、無力感に捕らわれてしまった。「製品の感性をもっ
てユーザーの感性に訴え説得する」このような販売方針を大切にしている私としては、
もうこの設計者に対して次ぐ言葉はなかったのである。本随筆の冒頭に私の所信を述べ
ておりますが、どうかニッポンのオーディオを作られる立場にある(敢えて一部のと申
し上げる)皆様は、広い視野と最新の情報、家庭用の再生装置として現代の日本人が求
める感性、これらの時代的変化を察知し理解して頂きたいと願うものである。この私の
願いがかなったものなのか、テクニクスSB−M10000は見事に海外ハイエンド・
オーディオとの共存共栄を実現した最新事例であることが断言出来るのである。
第四章『超ワイドレンジ化の副産物』
1995年5月15日、いよいよSB−M10000が私のフロアーに到着した。「
本日間違いなく送り出しましたので、よろしくお願いします。」と、四日前に古田氏か
ら電話を頂いている。それだけに、私としては、氏が目に入れても痛くないほど愛して
やまない一人娘をお預かりする心境である。まず、外観から受けた第一印象は多層コー
ティングによる仕上げが大変美しい、さすがメイド・イン・ジャパンである。そのコー
ティング部分に指紋一つなかったところをみると、きっと嫁がせる前に古田氏が入念に
磨き込んでくれたのであろうか。当フロアーのスピーカー・ステージは煉瓦タイルによ
って仕上げられているので、そのまま置いてしまうと傷も付くし位置決めも大変である
。毛足のあるパンチカーペットを敷いて慎重に組み上げる。SB−M10000の底部
はまったく平らであるので、この上を滑らせながら位置を決めていくのである。とりあ
えずパワーアンプはマークレビンソンのNO・33Lと、プリアンプはジェフローラン
ドのコヒレンスを、CDシステムは聴き馴れたマークレビンソンのNO・31LとNO
・35Lをセットアップする。果たして昨年出会った素顔美人はどの様な成長を遂げて
いるものか、ハラハラドキドキしながらの作業は実に楽しいものだ。昨年聴いたのと同
じ聴き馴れたソフトをかける。「アレッ。これは、もしかして、大変身しちゃってるん
じゃない!」と、心の中で思わず叫んでしまう。このフロアーでお客様が感動的な音を
聴かされた場合には、怖いほど真剣に聴く人、呆れたようにポカ−ンとしてしまう人、
などなど実に色々なリアクションをその表情に見ることが出来る。私の場合は単純であ
る。うれしくなって笑い出してしまうのである。ソフトをかけ変える度に、顔がゆるみ
笑いが止まらなくなってしまう。第一章で述べた(1)(2)(3)が、すべて夢でも
見ていたかのように、まったく見事に消え去っているのである。音についての第一印象
は実に素晴らしいの一言である。暫定的に置いただけなので早速位置を割り出していく
作業に取りかかる。現在は逞しい若手の部下がいるので座ったまま、「あと10センチ
左、もう一度反対に20センチ、角度を気持ちこちらへ」と、曲を変えながら30分以
上かけて納得出来る位置が決まる。次はスパイクを使うべきかどうかだ。まず四点に米
国アヴァロン社のアペックス・カプラーというスパイクを底部に取り付ける。160k
gという自重から、グサッと煉瓦に食い込みガタツキは微塵もない。ところで、このス
パイクを取り付けた光沢のある黒で塗られた底部の素材は、どうやらMDFのようであ
る。海外のメーカーでも、このMDFをエンクロージャーの素材としているところは多
いので、SB−M10000も本体にMDFを採用したものとばかり思っていた。上側
が65kg、下側が95kg、合わせて160kgという重量の本体にはパーチクルボ
ードが採用されている。確かにMDFは透過損失が大きく共振が少ないのだが、大きい
面積になると曲げ剛性に問題があるらしい。一般的な規格サイズである90cm×18
0cmの大きさでも、端と端を持ち上げると歪んでしまうのだ。そこで、SB−M10
000には二五〇番タイプの三層構造パーチクルボードを採用した。熱によって結合す
る接着剤をまぶした、大きさの違う木材繊維を三層に敷き詰めていく。その厚みが15
cm程度あったとしても、加熱圧縮処理をして仕上げていくと、何と10分の1程度の
厚みになるそうだ。この強靱なボディーには、アフリカ原産の「ボビンガ」という木目
のツキ板がきれいに貼られ、多層コーティングによって透き通るような木目の家具調フ
ィニッシュとなる。さて、スパイクの効果はどうだろうかと試聴を繰り返す。一瞬、オ
ャという変化に気がつく。ごく一般的なスピーカーの場合には同様なセッティングを行
うと、まず低域が鮮明になるという変化を起こすはずなのに今回は違うのである。高域
の鮮やかさが際立つ向上を見せ、低域は残響が整理される程度で激変するという程では
ない。なるほどと関心した。これがデュアルダイナミックドライブと称する、低域ドラ
イバーを背中合わせにしてエンクロージャーの振動を抑止するというアイデアの効果だ
と実感された。これは、一般家庭にとっては大変ありがたいことだと思う。絨毯、畳、
フローリング、コンクリート、色々な床の条件があるが、低域の質感をスピーカー自身
でコントロールしているわけだ。何曲か聴くうちに霧吹きでシュッとひと吹きするよう
に、弦楽器の高音部に湿度感をつけてあげたくなった。「よいしょ!」とスパイクを外
してフエルトを貼り付け、スピーカー底部との間に挟むことにする。「ウ−ン、第一段
階としてはこんなところかなァ」と汗をかきながらの三時間に及ぶセッティングに一応
の結論を出して更に試聴を繰り返していく。見事な低域再生能力である。ここで、昨年
のジム・ティールの言葉を思い出す。「スピーカーの特性が低域側に延びた場合、その
音はむしろゆるやかで「タイト」ではない。より「タイ」な低音を演出するのであれば
、超低域を減らして倍音を強調することで「タイト」な音を聴くことが出来る。大きな
エネルギーを持つパイプオルガンやベースドラムで、その音が「タイト」なものは存在
しない。」正にその通りである。SB−M10000の低域は、深く重厚な響きを再現
するが、ドンッドンッといったユニットのある所から直線的に向かってくるような低域
ではない。それがオーケストラの再生では大太鼓やティンパニーの位置関係に、深みと
奥行きが伴って大変好ましい表現となる。後部の上下にも低域のユニットを搭載して完
全な同相の低域を再生していることが妙味となっているのか、プレーナー型の振動板が
前後に放出する逆相の低域とは明らかに違う、爽快で自然な無理のない後方への拡散が
実現されている。特に圧巻なのは、パイプオルガンやエンヤのシンセベースである。実
に見事にそれらの脈動を捉えている低域は、振動面積の大きなコンデンサー型スピーカ
ーの低域を更に濃厚にしたものを感じさせる。ジム・ティールの云うところは、図らず
も日本人が作りだした傑作によって確かに実証された。スタジオで録音された目の前で
炸裂するような、ジャズやフュージュンでのキックドラムの鋭敏な反応はどうか、空間
表現よりも目の前の実態感という意地悪な曲に変えてみた。これはまいった、逆にSB
−M10000という新指向のスピーカーに屈服させられ逆効果であった。今までドシ
ッズシッと歯切れの良さだけに気を取られていたのだが、実際にはインパクトの瞬間の
音はもっと重く低い音域まで録音されていたのである。ドッドッと圧縮された極めて瞬
間的なエネルギーが空気を揺さぶる。低域再生においてウーファーに倍音がのり、エン
クロージャーの共振も含んでいるのがドッドッに〈シ〉が追加されてドシッズシッと聴
こえていたのであろうか。今まで、この〈シ〉が付きまとっていたスピーカーが正しい
と思っていた記憶を私も訂正しなければならない。その証拠にキックドラムよりも音程
の高い、タムやスネアーのインパクトが大変鮮明になっているのに驚かされた。低域の
変調歪から開放されているせいなのか、ミッド・ロー・ユニットから放射される中・低
域は下側の周波数に煩わされずに目が覚めるような超高速・ハイスピード感がある。次
は、私の定番となっているヴォーカルで大貫妙子をかける。まいった、実に新鮮である
。セロリやレタスなどの野菜は、鮮度が高ければ高いほど引きちぎる時に「シャリッ、
シャクッ」と勢いの良い音がする。音と一緒に水分が飛び散るような映像をイメージし
て頂ければ、私が文章でお伝えしたいところがご理解頂けるだろうか。私も、以前にテ
クニクスのEAS−10TH1000というリーフトゥイーターを愛用していた事を思
い出してしまった。SB−M10000は何と100キロHz(マイナス10デシベル
)までの高域再生を実現した。そして、高域へのエクステンションは様々な副産物を伴
うものである。それは、萎れてしまった観葉植物に、霧を吹き水分を与えて起こる変化
にも似ている。うなだれる茎は精力を取戻しピンと伸び上がり、くすんで色褪せていた
小葉が透き通るような緑を取り戻すのである。「そんな事言っても、100キロHzま
で再生することが出来たって、CDには22キロHzまでしか入っていないじゃないか
。」大変ごもっともなご意見である。前回の随筆でジェフローランド氏はアンプ設計の
主眼を正確な波形伝送にあると言っておられた。アンプにおける広帯域化とハイスピー
ド化は、グループディレーを発生しないために必要なことだとも言っておられた。これ
は私の推論でもあるのですが、スピーカーにおいても同様に考えれば、ワイドレンジ化
は単一周波数の再生という一元的なものではなく、正確な波形伝送の手段として録音さ
れているものを正確に伝えていくという本質に結び付くと思うのである。つまり、録音
されている音楽にはもともと十分な水分が含まれているはずなのに、再生系のどこかで
乾燥してしまうということだ。従って、潤いのある楽音には音場感が付随してくる。今
まで私は、音場感の表現にはユニットの特性よりも、ティールやアヴァロン、ウィルソ
ンのWATTのような、最小面積のバッフル・デザインの方が重要ではないかと思って
いた。ところがである、低域再生から必要とされるエンクロージャーのデザインで、こ
れらのスピーカーよりも大きくなってしまったSB−M10000は、前述のスピーカ
ーに勝るとも劣らない音場感を展開している。高域へのエクステンションを可能とした
SB−M10000の高域が、これほどまでに音場感を含有しているものとは思っても
いなかった。私の仕事は音を聴くことから始まり、音を販売することで終わりとなる。
だからといって、朝から晩まで音楽を聴いているわけにはいかない。でも、このスピー
カーが来てからは売る事を忘れてしまって、あれこれと聴いてばかりいて困ってしまう
。昨年出会った素顔美人は、秀麗なメークを見事に自分の物として一層の美しさを煌め
かせ、その魅惑的なボディーには知的で洗練されたファッションを装って現われたので
ある。仕事中であるにも関わらず、その魅力に負けてしまい聴き惚れてしまう私は、何
と意志の弱い男であろうか。一時「遠距離恋愛」という流行語があったが、新幹線に乗
ってまでも逢いに行きたくなる程のお相手をご紹介したつもりである。たまには電車賃
を奮発して、一生の伴侶を見つけるためのお見合いの席に「我こそは!」と参じて頂け
れば、これほど嬉しい事はない。ちなみに、オーディオ的「バツイチ」の方も大歓迎で
ある。
第五章『リアリズムの洗礼』
1995年5月26日、いよいよ設計者の古田氏を招いての試聴会当日となった。早
め来訪された古田氏に、まずセッティングの過程を説明し音を聴いて頂く。「スピーカ
ーの存在感がなく、音場が良く表現されていますね。」合格である。さて、本番の選曲
をしながら開演を待つ。この日、一番早い方は一時間前からみえられ、開演時間には満
席となる。毎回、当日の連絡なき欠席が何人かいらっしゃるのが常だが、今回はご予約
の皆様は全員来場されパーフェクトである。第二章から第三章で述べてきたことを演奏
の合間に質問し、古田氏ご自身からご説明頂いた。この日は、飛び入りでサザーランド
のC1001とA1000を持込みめったに聴けない組合せでSB−M10000を鳴
らしてみた。同じCDシステムを使って、アンプだけを切り替える。逆に同じアンプを
使ってCDシステムだけを切り替える。要所要所で同じ曲を使って、システムの変化が
分かりやすい実験も行う。本当に二時間というのは、あっという間に過ぎてしまうもの
だ。会も終盤に近づいたところで、「ところで古田さん、ご出身はどちらなんですか。
」と、質問の鉾先を設計者ご本人のパーソナリティーに向けてみた。「実は、ここから
ふた駅めの両国なんですよ。ですから子供の頃から秋葉原は庭みたいなものでした。」
松下電器に入社してからどのくらいなんですか。「ちょうど今年で20年になります。
ですから、このスピーカーは20周年記念モデルみたいなものですか。」当時を思い返
して、オーディオ好きだった青年が松下電器の門を叩き面接をしたのが、サインをもら
いたいくらいに憧れていた石井伸一郎氏であったということだ。石井氏は三菱電機株式
会社の佐伯多門氏と並ぶ、日本オーディオ界の技術分野の重鎮とも言うべき存在の高名
な方である。実は、私は5年前に当時流行の兆しを見せていたホームシアターを売り物
にしようと、当社の役員を口説き松下電器のバックアップを得て、小売店レベルで日本
初のTHXのフルシステムを当店の6階に導入したのである。その時に私も、音響的な
設計で石井氏には大変お世話になったのである。そもそも、THXというものがアメリ
カで評価されているが、一体どんなものかを調べるために渡米されたのが石井氏であっ
た。そして、ルーカスフィルム社のスタジオを訪れた石井氏は、その特異な音響設計を
見た瞬間にアッと思った。早速、尋ねてみると、「数年前のAES(オーディオ・エン
ジニアリング・ソサエティーの意。音響工学を国際的に論じている研究機関)の論文で
発見した音響デザインを採用して設計したものです。」と、答えが返ってくると、石井
氏は「その論文を書いたのは私です。」一瞬の間をおいて、仰天したルーカスフィルム
社のエンジニアは感激し、力強い握手を求められて待遇が一転したというエピソードが
あった。ハリウッドの先端技術を駆使した映画の高音質化、そのおおもとの入れ物とな
るスタジオの音響設計を考えだしたのが、目の前の日本人であったのだから驚くのも無
理はない。当然、ビジネスの面でもトントン拍子に進み、松下電器が日本で最初にTH
Xのライセンスを取得したのも、こうしたいきさつがあったからなのだ。AESのよう
な国際的な場で評価される論文を提出するほどの頭脳であり、スピーカーを含む音響工
学において古田氏が師と仰ぐ石井氏の存在はそれ程大きなものであったのだ。この様な
権威に支えられた開発では、古田氏は相当やりたい放題の研究を多々行ってきたという
ことだ。「如何にして低域を再生するか、直径が一メートルもあるウーファーを試作し
たこともあります。しかし、それ自身の質量と、それを支持する機構の反応から良い結
果は得られませんでした。今回のケルトン型パッシブラジエーターの採用は、こうした
開発の集大成と言えるものです。」ここで来場者の一人から、「日本のメーカーは、や
れダイヤモンドだとかベリリウムだとか、素材に目新しいものを使いたがるが、しょう
もない音しか出していない。海外のメーカーはユニットを自社では作れず、日本製と比
べれば粗末に見えるような振動板を使っているものが多いが、ハイエンドとして大層評
価されている。この辺をどう思いますか。」と海外製品に精通する方から鋭い質問が出
る。「日本メーカーでは素材開発を専門にしている部門があり、彼らが新しいものを作
ったからと言ってドンドン持ってくる。だから、たまには採用してみようか、というも
のが黙っていても手元に並んでしまう。しかし、すべてを採用するわけではありません
。彼らがいくら物性が良いと主張しても、試作してみてダメなものは沢山あります。当
然採用しないわけですが、選択肢が多いのは事実ですね。でも、新素材を使いこなすた
めに時間がかかっていると、また新素材が開発されてくるようなこともあるんです。そ
こに行くと海外の設計者は使いこなしがうまい。得られたユニットを十分に知り尽くし
、見事に仕上げてくる。その点は大変評価しています。」実に正直な回答である。次に
、「これは、後にもパッシブラジエーターがありますが、後の壁からはどのくらい離し
ておけば良いんですか。」と、現実的な問題点が発せられる。「スピーカーの動作上は
5センチもあれば十分です。何故かと言えば、パッシブラジエーターが再生する60H
zから28Hzの波長は5メーターから一二メーターと大変大きなものです。従って、
回折効果が大きく一元的な反射の問題はあまり深刻ではないので、スピーカーの動作と
しては影響を受けることはありません。ただし、部屋全体のルームアコースティックの
影響から考えれば、当然その環境に合った適正位置を割り出していく必要はあります。
」また、初歩的であると思われるような、こんな質問に音場感を発生させる大きなヒン
トがあった。「最近の国産スピーカーは、ユニット固定用ネジの頭が見えないようにカ
バーされているものが多いですね。一時流行った「ネジの増し締め」が出来なくなって
しまったわけですが。」古田氏は、こう答えた。「以前は内部に埋め込んだナットにむ
かって、六角レンチで締め付けるボルトを使っていました。従って、ボルトとナットの
締め上げた間隔は、エンクロージャーに使っている木材の収縮によって隙間が発生し「
増し締め」が必要な状態になってしまったのです。しかし、最近は専用の木ネジを使っ
て、木材に食い込む形で固定しているので「増し締め」は必要無くなってしまいました
。」そして、「もっと重要なことは木ネジの頭から音が聞こえてしまうという事実を、
私は何度も確認しているからカバーを付けて隠してしまったのです。音源である振動板
以外に、振動して音を発するものがあっては音場感は再現出来ません。この振動板以外
の全てのものを振動せず動かなくすることで、間違いなく音場感は生まれてきます。テ
ィールがコンクリートのバッフルを採用したこと、ウィルソンオーディオがエンクロー
ジャーにメタクリレートを採用したこと。これらすべては、この単純でありながら大変
実現が難しい制振構造を得るための手段なんです。」なるほど、私はエンクロージャー
・デザインが音場感を発生させる最大要因だと思っていたら、もっと根本的な要素があ
ったわけだ。つまり、振動板以外に音源があってはいけないという事か。さすがに筋金
入りのエンジニアの発言には大変な説得力があり、うなずく事しきりである。この様な
盛り上がりを見せる中で、日本人の設計者であり、当然日本語で質問出来ることから、
一時間も予定を上回る質疑応答が繰り返された。ご参集頂いたユーザーのレベルの高さ
に、古田氏もはりきっての答弁が続いた。最後に、私がどうしても聞いてみたい事があ
った。「このスピーカーの製作に携わって、古田さんは楽しかったですか。」私は、こ
れまでにも、試作品を持ち込んでくる国内メーカーの設計者と話すことが幾度となくあ
った。同じ質問をして、「いゃぁ、仕事ですから。」と頭を掻きながら答える人も中に
入るのだ。期限、コスト、各部所との確執、そして、上司のご機嫌等々と色々なストレ
スと制約の中でのご苦労は分かるのだが、これでは良いものが生まれてくるはずがない
。古田氏はこう答えてくれた。「私は額縁職人でありたいと思っています。世界の名だ
たる美術館では、歴史的な絵画は立派な額縁に入れられて、私たちは見ることが出来ま
すね。私には絵を描く素養はありませんので、せめて立派な額縁を作りたいと思ってい
ます。オーディオの世界で言えば、額縁の中に納められる芸術的絵画とは演奏家であり
、その人の演奏です。つまり、音楽そのものが絵画と例えれば、観衆に鑑賞の枠組みを
提供し、その音楽と絵画にふさわしい土台を作り上げる事が私の天職であると考えてい
ます。」なるほど、音楽が主役であり自分は脇役、いや黒子的存在に徹するというのは
、いかにも古田氏らしいコメントである。なにより、演奏が主役でスピーカーは脇役、
黒子と言うよりは透明人間的で音源の存在感がない響きが、このフロアーのSB−M1
0000を聴いていると実感出来るのである。私は今まで「スピーカー作りの大半は、
作者の感性の産物であろう。」と、考えていました。しかし、SB−M10000と巡
り合ったことで、その認識を大きく改めなくてはいけないという思いに駆られている。
古田氏が述べた「額縁職人」の例えをお借りするならば、その中に納まるべき絵が画家
の感性を表現する抽象画であった場合、スピーカーの音作りは主観的な演出と色付けと
言えなくもない。オーディオという近代の科学技術に支えられ、録音・再生系の装置を
駆使して音楽という芸術を享受しようとした時に、録音される楽音そのものに対する忠
実度をどの様に定義すべきなのか。本随筆の第一七話の第二章で述べた「音のリアリズ
ム」に次のような一節がある。近代リアリズムの画風が当時の観衆にとっては、まだ不
評であった時代を表して、「抽象表現派の感情を基礎とした保守的な評価につながる一
面もある。時代によってはリアリズム(ハイファイ)の受け入れられる感性が観衆(聴
衆)の中に芽生えているかどうかが問題になる。」私は、今回の試聴会を行ってみて「
リアリズムに徹したハイファイの受け入れられる感性が、聴衆の中に芽生えている。」
という実感を大変強く感じることが出来た。それは、SB−M10000が物事をあり
のままに描くという、リアリズムを象徴する音を聴かせてくれたからに他ならない。一
人でも多くの方が、この音を聴き真のリアリズムの洗礼を受けて頂きたい。と、願うの
である。
【完】
|