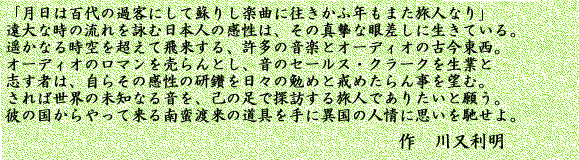第二十二話「オーディオの原点を知る事の喜び」
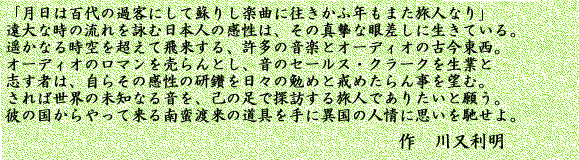
第一章『社長からの贈り物』
株式会社ダイナミックオーディオは、昭和40年3月千代田区外神田いわゆる秋葉原
に産声をあげた、当時では異色のオーディオ専門の販売会社である。弱冠26歳の若さ
で有志を募り、時のオーディオブームという追い風に乗って瞬く間に支店数を拡大、高
級オーディオのビジネス分野で日本一の業績をあげるまでに育てていった人物が現社長
の萩原統志郎である。実を言うと私の勤務するビルの八階に社長室があり、私のデスク
の真上に社長の執務デスクがある名実ともに〈頭上の人〉なのである。従って、社長の
お膝元で仕事をしている関係上、直接指導を受けることもしばしばで、現在の私もこの
様な境遇によって育てて頂いた感があるのは言うに難しくないことなのである。
さて、昨年の秋だったと思うが、頭上の社長から私のもとへ一冊の本が届けられた。
ハードカバーで豊富なカラー写真が掲載されたパルコ出版局発行のグラビア本で「蓄音
機の歴史」という題名である。発行日をみると1976年9月10日とあり、裏表紙に
は社長の筆跡で同年の9月18日と記されているところから発刊を待ち兼ねて入手した
のであろうか。定価4,500円とあり、20年も前だとさぞかし高価な書籍であった
にちがいない。著者の梅田晴夫が今もご健在であるかは預かり知らぬところだが、大正
9年のお生まれであることから大変ご高齢であるはずだ。この本の発行は舞台となるア
メリカ合衆国の建国200年を祝祭の年でもあり、前回の随筆でも述べたようにアメリ
カ国内において近代的なオーディオブランドが誕生する活気ある時代でもある。タイト
ルバックのページにはトーマス・アルヴァ・エジソンの直筆と思われるサインが印刷さ
れており、彼の言葉として次のような一節が記されている。「人の驚くような発明をす
るということは、まことにやさしいことだが、それを完成し、それに商業的な価値を与
えることは極めてむずかしい。」凡人の私としては、商業的な行為によって生業を営ん
でいながらも、一世紀に渡る音と関わる人間たちのドラマをどれほど知っているのだろ
うかと自戒の念を込めて思いをめぐらせる事にした。前人たちの偉業を知識として持ち
合わせることによって、既成事実として存在するオーディオ機器に対して感謝と敬意を
表していく機会をこの本が与えてくれたのである。
第二章『アメリカの父の生い立ち』
トーマス・アルヴァ・エジソン(1847−1931)は、ただ単に蓄音機、電灯、
映画その他多くの発明者であるというだけではなく、それらの発明がアメリカ合衆国の
全ての家庭と人間たちの日常生活を根底から改革し、その文化的、精神的側面をすっか
り現代化したという点で近代アメリカの父の一人として建国200年際の折に見直され
たのである。しかし、その生い立ちを知るものは決して多くないのではないだろうか。
エジソンはオランダのゾイデル海岸に代々住みついて製粉業を営む家系の末裔である。
J・G・クラウザーの「エジソン小伝」によると、その一家は1730年にアメリカに
移住し、エジソン家は独立戦争の際に敵味方に分裂してしまったとある。すなわち、当
主のトーマス・エジソンは議会事務局の書記となり合衆国の信用状に署名する権限を与
えられていたが、親戚のジョン・エジソンはイギリス側に立って後にアメリカ軍に捕ら
えられ反逆罪に問われてしまったのである。独立戦争が終わってからも三万五千人の人
々が相変わらずイギリスへの忠誠を誓ったので、イギリス政府は彼らを原始林に囲まれ
たノヴァ・スコシアに移住させた。ジョン・エジソンもそうした人々の一員として一家
をあげてその地に移り住んだが1814年にこの世を去り、息子のサミュエル・エジソ
ンが後を継ぐことになる。その息子のサミュエル・ジュニアというのが、発明王エジソ
ンの父親にあたる人物となる。彼は1828年にクエーカー教徒の家に生まれたナンシ
ー・エリオットと結婚し、その19年後にトーマス・アルヴァ・エジソンが生まれたの
であった。エジソンの父サミュエル・ジュニアは、1854年家族を引き連れてポート
・ヒューロンに移り住むことになるが、そこで穀物と家畜飼料の取引を始めるかたわら
、ヒューロン湖を見晴らせるところに100フィートもある塔を建て望遠鏡を設置して
有料で観光客に眺望を見せるようなこともしていた。少年トーマス・アルヴァ・エジソ
ンが、その望遠鏡に取りついて湖の眺めを楽しんでいたことは想像に難くない。トーマ
ス少年は幼い頃世間の人々から頭の悪い子だと評されていたらしい。それは何かにつけ
て根ほり葉ほり物を問いただす癖があったからだと言われている。あまりに強すぎる好
奇心が凡庸な大人たちには奇異に思えたのだろう。加えて、トーマス少年が幼い頃から
耳が悪かったということも一因しているようだ。1859年トーマスは12歳のころポ
ート・ヒューロンからデトロイトに向かう急行列車の中で新聞販売の仕事をしていたが
、その列車の喫煙室で科学実験を楽しんでいた。ある日彼が実験中に、列車の振動で黄
燐の入ったガラス瓶が棚から落ちて火を噴いてしまい列車に燃え移ってしまった。かけ
つけた車掌のスチーヴンソンが火を消したが、ひどく怒った彼はトーマス少年を殴り付
け、その時に鼓膜が破れてしまったというのが通説である。しかし、エジソン自身の思
い出話しによると、ある朝彼が列車に乗り遅れてしまい、危うく郵便車のステップにし
がみついている彼をスチーヴンソンが両耳をひっぱって引き上げてくれた時から耳が悪
くなったのだと言っている。トーマスはこの様に少年時代から新聞や野菜の駅売りをや
ったり、列車の中で南北戦争のニュースを伝える新聞を売って好評を得たり、商才にた
けアイディアの豊かな少年であった。後に彼は、自分で記事を書いて活字を拾い印刷し
た車内新聞「ウィークリー・ヘラルド」を編集発行し、戦争の成り行きに深い関心を持
つ乗客たちに便宜を与えていた。やがてトーマスは当時最も新しい発明であった電信技
術を学び、16歳の時には既にこの分野で自動的に信号を送る時計を発明している。そ
れからの5年間は、デトロイトからニューオリンズにまたがる各州の駅を渡り歩き電信
技術を研鑽し、インディアナポリスで電信を記録再生する装置を発明した。これは紙の
円板の上に螺旋状の刻み目を付けて通信文を記録するというもので、この発明が後の蓄
音機の発明へと結び付いていくのである。1868年からエジソンの発明家としての本
格的な生活が始まるのだが、最初のパテントを申請したのは議会で使うための〈議員が
席を離れなくても投票出来る〉機械装置であった。しかし、議員の多くは投票にかける
時間は遅いほど良い議事妨害になると考え、そんな機械は議会にとって百害あって一利
なしと不採用になってしまった。まるで、どこかの国の現与党が牛歩戦術で時間の浪費
をしていたことを考えると、120年間の科学技術のめざましい進歩に対して、政治家
の進歩は牛のあくびの回数だけであったという事実を嘆かわしく思うのは私だけだろう
か。さて、それ以来エジソンは電信と電話の技術改良に精力を注ぎ、やがて1876年
にベルが電話の特許を取ると翌年には炭素送話器を発明してそれに答えるのである。そ
して、エジソンの発明した自動記録電信機とはパラフィンをかけた紙の円盤の上に刻み
目を付けて電文を記録するものであった。後でモールス記号をゆっくりと回転させて再
生して聞き取るという形の物であった。紙の円盤を回転させると刻み目がテコを上げ下
げして電文を高速度で送信出来るのが特徴であった。これを早めに回転させると不思議
な楽音が出ることに気がついたエジソンは、これを使えば人間の声も記録再生出来るは
ずだと考えたのである。彼はまず水平に置いた円筒の表面を錫箔でおおい、振動膜の中
心に針を付けたものをその錫箔の表面に接触するように取付け、ハンドルで円筒が回転
するようにしたのである。振動膜に向かって話しかけてみると、それに取り付けられた
針は見事に錫箔の上に深浅両様の刻み目を付けたのである。ゆっくりとハンドルを回し
錫箔の円筒を回転させながら振動膜に話しかければ、針はその振動そのままの刻み目を
彫り付けていくという機械装置は単純極まるものであった。その証拠に、工場で作らせ
てみたら製作費は一八ドルであった。トーマス・アルヴァ・エジソンは1877年7月
に完成した、未熟極まりない機械に向かって初めて呼び掛けた言葉は「HULLO」で
あった。その叫びは見事に録音され、そして再生された。ここに後の世界文化を一変さ
せる偉大な発明の一つ〈蓄音機〉は誕生し、その第一歩を踏み出したのである。
第三章『商品化に苦しむ蓄音機』
アメリカのアンティーク業界のカタログをみると、そこにはエジソンという項目があ
って蓄音機の総てがそこに統括されている。つまりアメリカ人にとっては昔も今もエジ
ソンとは蓄音機のことであり、蓄音機とはすなわちエジソンに他ならないのである。日
本では大正末期の手動式で機械式の旧吹き込み時代までは〈蓄音器〉と書き表していた
が、昭和初期の1927年頃から電動式で電気吹き込み時代に変わってからは〈蓄音機
〉と〈器と機〉を使いわけているようだ。現代の外国ではアメリカではフォノグラフ〈
Phonograph〉、イギリスではグラモフォン〈Gramophone〉と呼ばれている。大変面白い
ことに、これらの語源をたどっていくことが蓄音機の成長の過程を知ることにつながっ
ていくのである。さて、1877年12月6日「サイエンティフィック・アメリカン」
の編集部に、改良された錫箔フォノグラフを持ち込んでデモンストレーションを行った
。その時にエジソンが吹き込んだのが有名な一節である。「MARY HAD A L
ITTLE LAMB」(メアリーの子羊)確かにこの言葉は録音され再生され人々を
熱狂させるに至ったが、蓄音機の用途と普及についてはまったく手つかずの数年間が過
ぎていった。奇遇にもエジソンと同じ年の生まれであり、電話を発明したグラハム・ベ
ル(1847−1922)の存在が大きく影響力を発揮し始めることになる。実はベル
の妻の父親はエジソン・スピーキング・フォノグラフ社の大株主であったのである。不
完全な上に目の飛び出るほど高価な錫箔フォノグラフは、とても一般の人々に普及する
ことは難しく投資を取り戻す目処が立たない状態にあった。義父の投資の危機に刺激さ
れたグラハム・ベルはフォノグラフの可能性を見直す研究を開始した。そして、188
0年にフランス政府からナポレオン三世が制定したヴォルタ賞を受賞すると、その副賞
金をそっくり投げ出してヴォルタ研究所を設立するのである。科学者であり楽器の製作
者でもあるチャールズ・サムナー・テインターと、彼の従弟で化学者であったチチェス
ター・ベルを協力者として電気音響学の研究を始めたのである。当時で一万ドルという
大金と5年間という歳月をかけてフォノグラフを研究し、一八八五年にようやくグラフ
ォフォンという改良モデルを発表する。このグラフォフォンの原理はエジソンのフォノ
グラフと全く同じであったが、相違点としてはフォノグラフが円筒に錫箔を塗ったもの
を使っていたが、グラフォフォンではボール紙の円筒の表面に蜜蝋を塗ったものを使う
ようになったということである。単純な改良であるが、これだけで録音再生される音質
はかなり明瞭になったと言われている。しかし、まだ致命的な欠点があった。グラフォ
フォンとフォノグラフという言葉を並べて見ると気がつくのだが、前者の言葉反対にひ
っくり返した言葉となっている。これは「記されたものから音を生じる」という意味で
あると解釈されている。既に録音済みのものを再生するというレコーデット・ソフトの
原点ともいうべきであろうか。つまり、グラフォフォンも円筒を原版としているので、
再生用の円筒を複製することが出来なかったのである。そこでヴォルタ研究所では円筒
を円盤に変えることも試みたが、針が内周に進むに従って音質が損なわれてしまった。
最後までこの問題の解決を果たせないままグラフォフォンは円筒のままで終わってしま
うのである。さて、1887年ヴォルタ研究所ではエジソンを招いて共同研究を申し入
れるのだが、エジソンはきっぱりとこれを断わってしまう。そこで、ヴォルタ研究所は
自分たちが持っているパテントを使用させてグラフォフォンを製作する会社を設立し、
独自の立場で製品の販売に 踏み切ったのである。これがアメリカン・グラフォフォン
社で、世界最初の蓄音機会社として同年に設立されたものである。この頃エジソン自身
も自分の発明したフォノグラフに改良を加えており、1888年9月6日、ブリティッ
シュ・アソシエーションにおいて、ベルの作り出したグラフォフォンといっしょにパー
フェクテッド・フォノグラフとして発表される。この時点では、エジソンのパーフェク
テッド・フォノグラフも円筒には蝋が塗られており原理は全く同じであった。従って、
ビジネス向きの用途は認められたものの、音楽の録音再生という可能性はまだ危ぶまれ
ていたのである。エピソードとしてエジソンの発明の翌年、日本では明治10年に東京
で公開されたフォノグラフに対して付けられた日本語の名称はつぎのようなものであっ
た。〈写声器〉〈蓄語器〉〈蘇語器〉つまり、もっぱら人の声を録音再生することが目
的の機械であると考えられていたのである。
第四章『グラモフォンの登場』
実はエジソンよりも先に蓄音機の原理を思い付いた人間がいたのである。フランス人
のシャルル・クロである。シャルル・クロは言語学の研究をしながら化学を教え、医業
を行うかたわらカラー写真のプロセスを発明し、輻射エネルギーの働きを示すラジオメ
ーターという装置を発明し、しかも後にヴェルレーヌが絶賛したという詩を書くという
多彩な人生をわずか46年で終わらせて若くしてこの世を去った特異な人物である。彼
は1877年10月10日、「聖徳者週報」という雑誌にフォノグラフの可能性につい
ての一文を発表しているが、それは既に4月10日付けで封印され科学アカデミーに寄
託登録されていたのである。彼のアイデアの全貌は、エジソンの錫箔フォノグラフが完
成発表された後の12月3日に本人の要請によって開封され公表された。クロの考案と
いうのは、振動膜に針を付け、その針が表面に煤をかけた透明な材質で出来た円盤の上
にくるようなしかけである。振動膜が振動すると針が円盤上に螺旋状の線を描き、写真
のプロセスによって薄い金属板にそっくり転写され、その金属板に針を当てて回転する
と音が出るというものだ。ただ残念なことに、このアイデアを実際の機械として作りえ
なかったことがエジソンに取って変わる存在となりえなかったということであろう。し
かし、このクロのアイデアは10年後になってから、ある男の努力によって甦ることと
なる。遠く故郷のハノーヴァからアメリカに移住し、下積みの仕事をしながら独学で音
響学と電気学を研究し、ついにはマイクロフォンの発明者となったのがエミール・ベル
リナー(1851−1929)である。彼はマイクロフォンの特許をベル電話会社に売
り渡し、ベル社の巨大な資本力の傘の下で十分な庇護を受けながら研究に没頭すること
が出来たのである。その対象となったのはフランス人のレオン・スコットが1857年
に発明し、1859年にコーニックという音響メーカーが販売していた〈フォノトグラ
フと呼ばれる機械だった。当時ワシントンのスミソニアン博物館に展示されていたフォ
ノトグラフは、振動膜を張った大きなホーンの中心に針を付け、その針が油煙をかけた
紙の円筒に接触して刻み目を付けていくようになっていた。ベルリナーはこのフォノト
グラフを、シャルル・クロのアイデアと組み合わせることによって新しい可能性を発見
したのである。しかし、ベルリナーの試みで注目されることは、これまでの円筒から平
円盤に変えることを目指したことである。円筒という構造上、原盤から複製を作るとい
うことが出来ないこと。平円盤は写真製版技術を応用して硬いゴム板のレコードをプレ
スすることに成功しており、1894四年(明治27年)には本格的なプレス作業が始
まり、1897年(明治30年)にはシュラックを主体とする混合物のレコードを作る
ことに成功している。また、錫箔や蝋管は音溝を縦波(上下動)として捉えていたが、
円盤では歪の少ない横波(左右動)としていることなど多くの利点がある。ベルリナー
のグラモフォンは、固定した針の下で円盤が回転し、ガラスの円盤に塗った亜麻仁油の
皮膜が針の振動で削ぎ落されていくというものだ。それによって波形の刻み目が円盤上
に残るというものだった。そして更に改良を重ね、磨き上げた亜鉛板にベンジンで溶か
した蜜蝋を塗り、針がそのワックスの上に螺旋状線を描くとクローム酸をかけて亜鉛板
を溶解させるという方法を取った。このようにベルリナーは写真製版技術にかわる新方
式を開発して、より鮮明に音を録音再生することに成功したのである。1888年5月
16日にフィラデルフィアのフランクリン協会で公開されたベルリナーのグラモフォン
は大変な関心を引き付け、それまでの蓄音機とは全く違った可能性を示した。1893
年にはワシントンのアメリカン・グラモフォン社で小規模ながら製作販売が行われるよ
うになり、更に1895年にはベルリナー・グラモフォン社が機械と円盤の両方の生産
を行うようになっていた。しかし、1896年にシーマンがその独占販売権を握り、ナ
ショナル・グラモフォン社を設立して大がかりな販売に乗り出すことになる。同時期に
フォノグラフやグラフォフォンは次第に姿を消していく運命となるのである。そして、
グラモフォンという言葉は、すなわち蓄音機 そのものを意味するようになり、ベルリ
ナーの考案はついに世界的に広まっていくのである。1900年代に入ると機械式録音
ながらオーケストラによる吹き込みが盛んになり、レコードも大量生産の時代に入って
くる。蜜蝋の厚板に音を刻み付けた上で銅メッキを施し、ファザー盤、マザー盤、スタ
ンパーを作り、プレスマシンによって大量生産されるようになるのだ。当然生産コスト
も引き下げられ、急速な普及が始まるのである。1925年には、かねてから研究され
ていた電気を応用した録音再生の技術が取り入れられ、ヴィクター、コロムビア、グラ
モフォンの各社がより鮮明な音質を求めて相次いで電気吹き込みを開始する。その後、
第二時世界大戦中に開発された磁気テープによる録音再生にとって変わられる1939
年まで、本質的な原理に変わりはなかったのである。今日のハイファイシステムが開発
されることによって、その使命を完全に果たしきった蓄音機はアメリカの歴史そのもの
でもあるのだ。蓄音機をエジソンと総称する感覚は決して間違ってはいないのです。そ
して、1912年にはエジソン自身も平円盤式のダイヤモンド・ディスクと呼ばれる蓄
音機を発表して、1915年エジソンが最後に商品化した〈エジソニック〉という蓄音
機で幕を閉じる事になる。さて、「蓄音機の歴史」には大変興味深い写真が掲載されて
いる。歯形の付いた蓄音機である。晩年、ほとんど聴力を失ってしまったエジソンは、
ダイヤモンド・ディスクの研究をするために木枠の骨組みだけの蓄音機の試作機を作っ
たのである。耳が聞こえなくなったエジソンは、その木枠にかじりついて歯で振動を感
じながら音楽をイメージして研究を重ねていたのだ。その歯形の付いた蓄音機の写真を
見ながら、私はエジソンは大変なロマンチストではなかったかと思えてならないのであ
る。飽くことのない好奇心と研究心が生き甲斐を与え、生涯何かを追い求めていたこと
だろう。例え耳が聞こえなくても、蓄音機にかじりついている彼の姿が目に浮かぶよう
だ。そして、そのらんらんと輝く眼差しは、若き日のトーマス・アルヴァ・エジソン少
年のそれと何ら変わることのない輝きであったと思えてならないのである。
第五章『蓄音機の産業化』
さて、話しの時系列は多少前後するが、グラハム・ベルが私費を投じて設立したヴォ
ルタ研究所は後にベル研究所として世界に大きく貢献する足跡を残すことになる。彼が
協力者のテインターと共に開発したグラフォフォンは、本来エジソンの発明したフォノ
グラフを改良したものであったことから、両者の間では特許権をめぐるデリケートな争
いが絶えなかった。次々と開発される新技術と、それをめぐるパテント争いは後々蓄音
機産業が巨大化するにつれて激しさを増していくのである。ベルとテインターは188
5年にグラフォフォンの特許を出願し、それが認められると1887年にはアメリカン
・グラフォフォン社を設立したわけだが、エジソンとベルの間ではきびしい争いが起こ
りリッピンコットンという人物が調停役として登場することになる。彼は、まずベルか
らグラフォフォンの独占販売権を買い取るかたわら、エジソンの特許を使用してフォノ
グラフ蝋管機を製造するための北アメリカ・フォノグラフ社を設立し、自分はその中間
に立って両者の激突を避けようと試みたのである。この会社は経営方針としてフランチ
ャイズ制をとり、全米各州に代理店を設け、ビジネス・マシンとして蝋管機を事務口述
用に一台40ドルの賃貸料で貸し出すことも始めた。この商法は全くの失敗に終わり、
同社は1890年遂に破産してしまった。しかし、同社からメリーランド、デラウェア
、コロンビア各州の営業権を取得していた1888年設立のコロンビア・フォノグラフ
社だけは緒官庁に大量に売り込むことに成功し生き残るのである。それは蝋管機を娯楽
用としてセールスした事が成功の秘訣でもあり、同社の財政的にも稼ぎ頭の商品となっ
ていった。さて、これらの動きと時を同じくして、蓄音機産業はイギリスにも渡り広く
ヨーロッパ全土に広がっていく。この発展の過程において大変重要なカギを握る人物が
、イギリスにおけるJ・E・ハウ(1848−1925)の活動であった。エジソンの
オリジナル特許と、ベルとテインターのグラフォフォンに関するイギリスにおける特許
の両方を買い取ったエジソン・ベル・フォノグラフ・コーポレーション社が設立された
のは一八九二年のことだが、この会社ができる前から既にエジソンやベルの興業権とい
うものは各国のショービジネス業者に売却されていた。というのも、蝋管機の目的と使
命は事務用口述機械であると信じられており、娯楽的、興業的な側面などはどうでもい
いと考えられていたからである。北アメリカ・フォノグラフ社の滅亡もまさしくその考
えが誤りであったことを示すもので、蝋管機は発明者の思惑とは全く違った分野に大き
く花を咲かせることになるのである。さて、それらの興業師の一人であったJ・E・ハ
ウは、エジソン・ベル社が700台あまりをオフィスに売りこむという快調な出足を横
目に見ながら、最初からロンドン・フォノグラフ社の名で蝋管レコードの製作に踏み切
ったのである。エジソン・ベル社は、このハウのやり方にクレームをつけ特許権侵害で
訴え商品の供給を停止してしまった。だが、ハウの会社にはアメリカのメーカーから、
はっきりと同社を宛先としない埠頭渡しの形でどんどん商品が送られてくるのであった
。結局1897年両者の間に妥協が成立して、今後ハウはフォノグラフを家庭用娯楽機
器として、エジソン・ベル社は業務用として市場を分けあう形を取るのである。ハウは
早速エジソニア・リミテッドという会社を作り、アメリカからのフォノグラフやレコー
ドを輸入する。そして、レコードの複製の製造機械を入れて「ボピュラー」「エボニイ
」「インデストラクティブル・アンド・グランド・コンサート」などのレコードの自家
生産も行うようになり、たちまちのうちに大成功を納めるのである。一方アメリカでは
、前章で述べたとおり1895年にベルリナーがベルリナー・グラフォフォン社をフィ
ラデルフィアに設立するのだが、ロンドンにもザ・グラフォフォン社を設立するために
W・B・オウエンをイギリスに派遣するのである。翌年には同社からエルドリッジ・ジ
ョンソンが蓄音機の製造を請け負い、いわゆるヴィクターの蓄音機が登場することにな
る。このジョンソンとベルリナーが協力して、1901年に設立されたのがヴィクター
・トーキング・マシン社である。ベルリナーが派遣したオウエンの努力が実り、189
8年にはザ・グラフォフォン社が誕生する。同社はベルリナーによるグラフォフォン蝋
管機およびレコードのヨーロッパにおける独占権を持って、エジソン・ベル社が支配し
ていたイギリス市場に殴り込みをかけることになる。同社はロンドンのストランドにあ
る、メイドン・レーヌに本店を置き、そこにエルドリッジ・ジョンソンから送られてく
る機器を備えた録音スタジオをも併設していたのである。1898年にヨーロッパ本部
をパリに設けたアメリカのコロンビア・フォノグラフ社が1900年にはその本部をロ
ンドンに移し、1897年エジソンが設立したナショナル・フォノグラフ社がアントワ
ープにヨーロッパ本部をひらき、フランスでは1894年に設立されたパテ・フレール
社がフランスにおける独占権を確立する。ヨーロッパは、まさに蝋管蓄音機とレコード
の戦国時代に突入したのであった。また、ベルリナーの故郷であるドイツでは、早くか
らハノーヴァにプレス工場が作られ、グラモフォン社のレコードは総てここでプレスさ
れるようになる。これが後にドイツ・グラモフォンとしてレコード産業の先駆的役割を
果たすことになる。そこまでベルリナーグループで活躍していたシーマンは一転してプ
レスコットと手を組み、インターナショナル・ゾノフォン社を設立しレコード制作を始
め、最初は廉価なポピュラー盤を出し、後に一流音楽家の録音をレコード化するように
なりグラモフォン社の強敵となった。しかし、同社はまもなくグラモフォンとヴィクタ
ー両社に買収されゾノフォンの名前は廉価盤のレーベルとして残ることになる。このよ
うに20世紀に入ってしばらくの間、蓄音機業界すなわち蝋管機業界はエジソン・ベル
、コロンビア、パテ、の各社が市場を分割していたが、1905年からレックス、スタ
ーリング、ホワイト、ロンドン・ポピュラー、クラリオンなどの会社が新しいタイプの
レコードを発売して戦線を賑わせるようになる。1902年アメリカ・コロンビア、1
906年パテ・フレール、1913年にエジソン・ベルという順番で蝋管から平円盤と
呼ばれる黒いシェラックのレコード製作に移行していくのである。この1900年から
第一次世界大戦が始まる1914年までの間に発売されたレコードの比率は、蝋管式が
30%で平円盤式が70%であった。グラモフォン社は1901年に10インチ盤、1
903年に12インチ盤を出すが片面録音であった。初めて両面に録音されたレコード
は1904年のオデオンが最初である。これに続いてベッカ、フェイヴォライト、ホモ
フォン、リラフォンとレーベルが増え続けていく。さて、話は変わるがエジソンがフォ
ノグラフを発明した直後、フランシス・バラローという画家がフォノグラフの横にちょ
こんと座った犬が蓄音機から流れ出てくる音に耳を傾けている絵を描き上げた。その犬
はフォックステリアであったが、それに着目したW・B・オウエンはエジソンのフォノ
グラフを塗り消して、代わりにベルリナーのグラモフォンを描かせて自社のトレードマ
ークにしてしまったという話しだ。ライバル商品を塗りつぶして自社の製品に描きかえ
た絵を、アメリカのエルドリッジ・ジョンソンが一八九九年に発売したレコードのレー
ベルに使ったというのは興味深いエピソードである。そして、その絵のモデルになった
蓄音機は、ほかならぬジョンソン本人が一八九七年にベルリナー・グラモフォン社との
契約で作り上げた改良型だったのである。さて、このW・B・オウエンの果たしたもう
一つの大きな功績がある。蝋管時代に吹き込んだ口笛の芸術家といわれたジョン・Y・
アトリーという口笛の演奏家がいた。この吹き込みに際して、ピアノ伴奏者にF・W・
ガイスバーグという若干20歳の若者を起用したのである。ガイスバーグは後にイギリ
スに渡り、イギリスのグラモフォン社でオウエンに協力し、その才能をピアノ演奏以外
の面で発揮するのである。ガイスバーグがグラモフォン社でやった最大の功績は、世界
的な一流芸術家たちにレコード吹き込みを承諾させたことである。劇場の廊下をカクテ
ルを乗せた銀盆をもって行き交う給仕たちは、舞台から聞こえてくる歌声にカクテル・
グラスと銀盆がカチカチと共鳴するほどの声量に驚いたというシャリアピンを始めとし
て、当時世界的な美声の持ち主といわれたエンリコ・カルーソー、メルバ、タマーニョ
、パッティなど次々に口説いてグラモフォンのスタジオに引き入れることに成功したの
である。こうした世界的に有名な一流芸術家たちが吹き込んだレコードを作り上げたこ
とが、グラモフォン社の社名と品格をおおいに高め大きく業績に貢献したことはいうま
でもない。同社の総帥であるオウエンがガイスバーグの才能を見込んでの思い切ったレ
コーディング・ポリシーの成果である。そして、それまで蓄音機やレコードに対して冷
ややかな見方をしていた、いわゆる音楽愛好家たちの視線ががぜん熱を帯びてきたので
ある。これまでは家庭用の手軽な娯楽機器であった蓄音機は、これ以来優れた芸術を鑑
賞するための高級な文化機器として位置付けられるようになるのである。そして、蓄音
機は高価であっても人間の文化的生活に必要なものであるという観念が生まれ、以降の
蓄音機産業の発展を大きく加速することになった。オウエンとガイスバーグをこうした
歴史のなかで重要な人物として評価しなければいけないのは、まさにこのためなのであ
る。こうした発展を遂げてきた蓄音機産業であったが、1925年に決定的ともいえる
技術上の一大改革をむかえ、歴史の一部としてその時代を終えることになった。それは
、電気録音技術とレコードの完成と、それを再生する電気蓄音機の完成である。189
5年にオリヴァ・ロッジが研究に着手したといわれるダイナミック型スピーカーの開発
は営々と続けられており、遂に一九一九年イギリスで電気吹き込みレコードの世界初の
実験が行われたのである。ライオネル・ケスト及びH・O・メリマンという二人の青年
技師がその実験を行って成果を上げ、同時にベル研究所においても同じような実験が行
われた。ベル研究所では1924年にマックスフィールドとH・C・ハリスンの努力が
実り、レコードの電気吹き込み技術が完成の域に達した。その翌年アメリカのヴィクタ
ー社、コロンビア社、イギリスのグラモフォン社が次々に電気吹き込みレコードの発売
に踏み切り、同時に再生用の電気蓄音機を製作するに至り、新しい時代の幕開けとなっ
たのである。それは「僅か3か月の間に旧来の方式を完全に追放した巨大な質的改良で
あった」とエヴリマンズ・エンサイクロペディアの「レコードプレーヤー」の中で述べ
られてほど、まったくあっという間の変革であった。これまでの機械式録音に比べて大
変美しい音が一般の人々の耳に伝えられるようになり、ハイ・ファイという表現も表れ
てきたのである。この時代から1939年の第二次世界大戦の勃発までの期間に加えら
れた改良といえば、ピックアップデザインの変化、アンプ・サーキットやラウドスピー
カーの改良といった既存の技術の改良がほとんどであった。そして、第二次世界大戦の
終結と共に三たび蓄音機産業は抜本的大変革をむかえるのである。1948年アメリカ
のコロンビア社が9年の開発期間をかけて作り上げたロング・プレイング・レコード(
LP・長時間演奏・両面46分)を発表したのである。これまで、四分から五分という
演奏時間しかなかったスタンダード・プレイング・レコード(SP)に比べて、何と画
期的な演奏時間であることか。さらにSPのシェラック盤にかわってLPのビニール盤
は、あのスクラッチ(針音)を見事に取り去ってしまったのも大変な出来事だった。L
Pは33.3回転であるが、1949年にはRCAヴィクター社から七インチ四五回転
盤も発売された。そして次ぎにはステレオの時代がやってくるのだが、蓄音機と称され
る時代はこの辺で終焉をむかえたのである。
第六章『必要は発明の母であること』
広大な空間の中に、それもあっという間に機械文明による豪奢な国家を作り上げてし
まったアメリカという国は、人間の日常的な娯楽までが総て機械によって拡散されてい
る。広過ぎる国土のなかに散らばっている多くの人間に、出来る限り同時に情報を伝達
し、生活上の便宜と娯楽さえも送り付けたいという素朴な理想主義がアメリカの発明家
たちを生み出した原動力となっているのかもしれない。まずエジソンを例に上げてもフ
ォノグラフや電信の目的は、より便利なコミュニケーション手段の開発に向かわせたと
いうのが実情であったわけだ。蒸気機関者や電信機械がそうした新しい人々の要請に答
えて早々とこの国で開発されたのは当然のことのように思えるが、驚くべきスピードで
蓄音機が発明され改良され普及していった事実をどう捉えたらいいのか。地域性と密着
した町ごとに寄り添って生きるヨーロッパの都市生活とは、全く違った条件がアメリカ
という国には開拓当時から存在していたのだ。劇場や音楽堂や競技場や博物館といった
、そこへいけばいつでも楽しめるという機関はヨーロッパでは既に完備していたわけだ
。しかし、アメリカでは広い国土を長時間かけて移動しなければ、これらの設備機関の
楽しみを享受することが出来ない。ちなみに、アメリカ合衆国において最初のオペラハ
ウスがニューヨークに建設されたのが1833年の事であり、ニューヨーク・フィルハ
ー モニック・オーケストラが創立されたのが1842年、ワシントンにスミソニアン
博物館が創立したのが1846六年、最近話題となっているヨットレースであるアメリ
カズ・カップの第一回大会が開催されたのが1851年。日本では、ペリー提督が浦賀
に入港して極東進出のための大統領の親書を持参したのが1853年ということだ。そ
の後アメリカではリンカーンの大統領就任と暗殺や南北戦争があり、1860年代にな
って世界中から大量の移民がアメリカに向けて開始されるのである。そして、私が現在
試聴に多用するボストン・シンフォニック・オーケストラが1881年創立されるので
ある。トーマス・アルヴァ・エジソンの生まれた時代背景というのが、この様な世の中
であったわけだ。必然的に文化的な情報と娯楽を〈出前〉する必要性にも迫られてくる
のである。シアーズ・ローバックが通信販売で全盛を極めていた頃は、間断なくベルト
コンベアが品物を運びだしていく物量の物凄さに目を奪われたということだ。また、最
近では日本でもマスコミが盛んにニュースとして取り上げている〈マルチメディア〉の
開発がアメリカは10年先行しているという話も同様な現象ではなかろうか。音楽・映
画といった娯楽、通信販売の高普及、クレジットカードの普及、そして日常生活の必需
品である自動車の普及と、どれを取ってみても〈出前〉への要請によって開発されたも
のではなかろうか。従って何分か歩けば、新製品のテレビやステレオが見て触ることが
出来るような狭い国に住む人間達にとっては、いたれりつくせりのサービスは必要とは
思われなかったのである。蓄音機がアメリカで発明される以前にも、町の辻々の店に設
置されたオルゴールが人気を呼んでいた。これもいわば広い国土に満遍なく音楽を出前
するということである。このアメリカで蓄音機が発明されるのはむしろ当然の成り行き
だったといえる。だが、蓄音機を発明した理由は日常のビジネスにとって有用でありた
いと願ってのことであったのは、いかにもアメリカ的だが、当のエジソンが二の次ぎに
考えていた〈エンターテイメント〉に役立つというアイデアこそが、実はアメリカ的で
あったといえる。アメリカ中に音楽を中心とするエンターテイメントを〈出前〉するこ
との出来る機械として改良を受けてきたのである。やがてはラジオやテレビがアメリカ
で普及して、その〈出前〉機能をフルに働かせるに至る前兆が蓄音機の出現であったの
だ。国の存亡をかけて戦う戦争は、良くも悪くも科学技術の進歩には大変な加速を与え
るものである。レコード産業に第二次世界大戦が終わってから一大改革が起こったよう
に、オーディオ業界においても1950年代ゴードン・J・ガウによるマッキントッシ
ュ、ソウル・B・マランツによるマランツ、エドガー・マリオン・ヴィルチャーによる
アコースティック・リサーチ、ジェームス・B・ランシングによるJBLと、現代にも
名を残す老舗のブランドが数多く設立された。世界初の原子力潜水艦ノーチラス号が進
水した1954年にはカルロス・クライヴァーが弱冠24歳にして指揮者デビューし、
マイルス・デイビスがビル・エバンスと共にキャピトルレコードで最初の録音をしてい
る。これらの出来事もレコード産業のハイファイ化を受けての再生装置への要求であり
、エジソンから営々とつちかわれてきた文化とエンターテイメントの〈出前〉機能の延
長線上に考えられる出来事なのである。そして、1962年にアメリカがベトナム戦争
という泥沼にはまり込み、一九七五年にベトナムから撤退するまではオーディオ業界に
新興の機運はほとんど見受けられなかった。また、ベトナム戦争のあった10年間はア
メリカ国民の感情からしてエンターテイメントの世界に対する欲求が、当時の反戦的世
情からしてあまり高じていなかったともいえる。なぜなら、同じ戦争中であっても第二
次世界大戦のさなかミッドウェー海戦でアメリカが大勝を納めた1942年には、グレ
ンミラーの「チャタヌガ・チューチュー」のレコードが100万枚を突破する売上げを
記録し、史上初のゴールドディスクを獲得したのである。この対比からもベトナム戦争
の特異性として、オーディオを含む音楽産業界への文化的貢献はほとんどなかったので
はなかろうか。そして、1976年か10年間で現在の雑誌の紙面を賑わしているよう
なアメリカのハイエンド・メーカーが続々と誕生してくるのである。この様に考えてみ
ると古くは蓄音機、近代のオーディオ産業という形で、アメリカでは〈エンターテイメ
ントの出前〉という事が望まれ、発明の母と表現される〈必要〉という社会的欲求があ
ったということが云えるのではなかろうか。仕事がらアメリカオーディオ界が送りこん
でくる傑作に巡り合うたびに、蓄音機からの一世紀に渡る歴史を知っているという事に
価値多かれと 思うこの頃である。
【完】
|