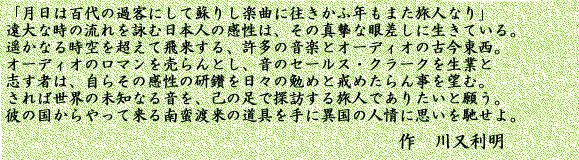第三十五話「ハイオンド・オーディオの仲人」
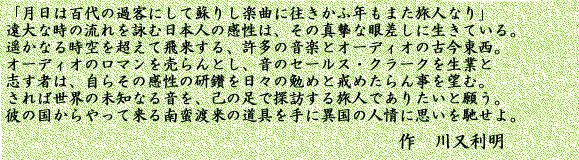
第一章『クレルのイメージ』
「美しい夕焼け、家族団欒の語らい、温かいスープに冷えたビール、そして素晴らし
い音楽。人生において大きな成果を上げようと焦ることはないではないか。ささやかで
も心を満たしてくれることはたくさんある。しかも、誰にでもたっぷりと分け前のある
楽しみが。」オーディオに関連した言葉としては「音楽」しかないという、少しキザか
なと思われるような文章だが、クレルの旧輸入元であるラックス株式会社が制作したク
レルのカタログの裏表紙に使われており、ダゴスティーノ氏の自宅リスニングルームの
写真に添えられる形で掲載されていたものだ。問題は、ダゴスティーノ氏の当時のメイ
ンシステムの写真のほうなのだ。現在ではディスコンになってしまったが、最終的な現
地価格が7万5千ドルというアポジー社のグランドアポジーがクレルのKASを4セッ
ト従えて堂々と鎮座しているのである。私も海外メーカーのトップとお会い出来たとき
には、必ずと言って良いほどリファレンスシステムは何かと質問している。この回答に
、私は彼らのビジネスの上手さを感じ取っているのである。「現在はアレを使っている
が、去年はアレを使っていたし、来年は違うものを使うかもしれない。」少なくとも、
国内だけではなく輸出も盛んに行っており、世界的なスケールでビジネスを展開してい
るハイエンドメーカーの社長たちは、試聴機材として特定のブランド名を上げることを
憚っているように見受けられる。これには考え方がふた通りある。「当社の製品は世界
中のあらゆるコンポーネントと組み合わせても、その能力を十分発揮する。だから、試
聴用の製品には特定の物だけを使うのではなく、色々なものとのマッチングも考慮に入
れているのだ。」という自信の表れとも思われる見方。もう一つは、「特定の製品を使
って音質を決定したということが公になると、それ以外の製品との組合せによるセール
スの可能性にブレーキとなりかねない。」という考え方だ。自社の製品カタログに自宅
のリスニングルームの写真を使用し、グランドアポジーの存在が露出してしまうことも
含めて、クレルとアポジーの間には蜜月の関係があったのではないかと詮索されても仕
方の無いことではなかろうか。しかし、後ほど述べる事にするが、両社の間において宿
命的な出会いがあったというのは事実であろう。さて、クレルの現在と未来を語る上で
、この写真を撮影した後が肝心なことなのだ。私が聞いたところによるとダゴスティー
ノ氏のリスニングルームには、現在はウィルソンのX1グランドスラムがメインとして
置かれているらしい。サブシステムとして同じくウィルソンのWATT&PUPPY、
そしてB&Wのノーチラスも所有しているようなのだ。この変化に私は強い関心を抱い
ており、クレルという高級アンプメーカーを再度見直して見る事にしたのだ。さて、ク
レルというブランドに対して一般ユーザーが持っている印象と、我々業界仲間が持って
いる印象とは微妙に違うところがあるのかも知れない。まずは、そのビジネススタイル
のあり方である。1980年のデビュー当時から10年以上も、日本におけるクレルの
輸入販売と知名度の向上に尽力してきたRFエンタープライゼスを一方的にキャンセル
したという事がある。「冷たい奴だ」「情けが無いね」とか、「長年連れ添ったパート
ナーを、よくもスッパリと切ったものだ」終身雇用と浪花節が好きな日本人の感覚から
すると、クレルはクールでドラスティックな経営方針の会社なのだと思ってしまう。そ
して今度はラックスが三年目にして同様な結末を迎えたのである。ダゴスティーノ氏か
ら直接話を聞いた訳ではないのだが、過去の経緯では氏の胸中にも何らかのフラストレ
ーションがあったのではなかろうか。
第二章『クレルの軌跡』
第一部『創業からデビューまで』
クレルの創立者であり設計者でもあるダニエル・ダゴスティーノ氏は1946年のお
生まれであり、33歳の時に同社を設立している。ダゴスティーノ氏は大学時代に電子
工学を専攻し、その後海軍では高周波関連の部署で兵役に従事した。除隊してからはフ
リーのエンジニアとしてオーディオのアンプからスピーカーまでの設計、測定、クリニ
ックまでの仕事をこなし、70年からはカナダのデイトンライト社でエレクトロ・スタ
ティク・スピーカーの開発で主導的な仕事に関わっている。その間、かのマークレビン
ソンの社長であるマーク・グレイジャーと知りあうなどして、スレッショルド社ではエ
レクトロニクスの分野にも関わりを持っている。七五年からはイギリスのゲイル社、7
7年からはグレート・ホワイト・ホエール社でアンプの開発を担当した後独立するので
あった。そして十数か月間、ピュアAクラスアンプの開発に没頭するのである。79年
秋に最初の試作機が完成し、コネチカットの工場でクレル社の第一歩がスタートするの
である。この年ダニエル・ダゴスティーノ氏は弱冠33歳の青年技術者であった。ダゴ
スティーノ夫人のロンディーとたった二人だけで完成品を組み上げて、翌1980年の
1月はるばるラスベガスのウィンターCES会場に持ち込んだクレルの処女作、ピュア
Aクラス・ステレオパワーアンプKSAー100は一大センセーションを巻き起こした
のである。ハンドメイドならではの味わいを持ったシルキーホワイトのアルマイト仕上
げパネルに、金メッキ仕上げの精緻な止めビスを配した秀麗なデザイン。そして、緻密
な再現力とエネルギー感を合わせ持ち、自然で暖かい肌合いの再生音は瞬く間に世界中
のオーディオファイルの心を捕らえたのだった。KSAー100は純A級で100W+
100Wのパワーを持っているが、最大の特徴はあらゆる出力状態で完全なA級動作を
行っている事である。負荷インピーダンス対出力特性のリニアリティーは抜群で、2Ω
負荷でも380Wを保証するという能力は当時でも驚異的であった。また、電源トラン
スから独立した完全デュアルモノ・コンストラクション、スペースを十分に取ったパー
ツレイアウト、パワートランジスターを常時70度Cに保つためのローノイズ・ファン
・クーリングシステムの採用、厳選したパーツを贅沢に採用したシンプルなピュアー・
コンプリメンタリー回路、等々粋を凝らした設計もオーディオファイルを魅了する大き
なポイントにもなっていたのである。
第二部『デビューに続く第一世代とは』
KSAー100に次いで発表されたのは、独立した電源でボリュームまで別々の完全
デュアルモノ構成のプリアンプPAMー2である。極力単純化したシグナルパス、ハイ
グレードパーツで固めた最高水準のS/Nを誇り、ハイエンドのオーディオファイルの
みを対象として設計された超高級アイテムとしてクレルのラインアップが始動したので
ある。1986年までの数年間は、パワーアンプではKSAー100をベースにしたバ
リエーションモデルを展開していく。同一構成で50W+50WのKSAー50、更に
はモノラルのKMAー100、とKMAー200、及びそれぞれのマーク2バージョン
を発表していく。このKMAタイプはKSAの内容をパラレル化することによって、2
Ω負荷でも完璧なパワーリニアリティーを安定化させたことに大変大きな功績が認めら
れる。KSAに比べても全帯域において音の立上りがよりシャープになった上に、低域
の制動感も強力になり引き締まった低音を聴かせてくれた。そして、何よりもローレベ
ルでの敏感な反応は当代最高のパワーアンプとして讃えられ、クレルブランドを不動の
ものとして位置付けたのだ。さて、プリアンプではPAMー2に次いで八一年に発表し
たKRSー1(クレル・リファレンス・スタンダード)で一つの頂点を目指していた。
完全モノラル構成、アルミ削り出しシャーシー採用など贅を尽くした別電源4ボディー
のプリアンプは、まさに当時の考えられる限りの最高峰を現実化したのである。数年後
に発表されるPAMー3は、こうしたモノラルタイプの性能を一つのボリュームコント
ロールで操作できるステレオタイプとして追求された意欲作なのである。
第三部『クレルの第二世代』
1987年に入ってからのパワーアンプにおける一大テーマは、何と言っても冷却用
ファンの追放であった。いくら静かなファンを使用したとは言え、その動作音をも耳は
聴いてしまったのである。リスニング環境のより高いS/Nを求めて、クーリングファ
ンを排除して自然空冷のシステムを全面的に採用する設計に着手した。妥協を排して堅
実にすべてを一から見直した設計が行われた結果、2Ω負荷で800Wまでをリニアに
出力するためのヒートシンクや電源部の大きさはとてつもなく巨大化してしまった。そ
れは、モノラルパワーアンプKRSー200として結実し、世界的に超弩級の名を欲し
いままに評価されたのである。そして、この時代にアポジーアコースティクなどの低負
荷プレーナー型スピーカーが市場でイニシアチブを取るようになり、低負荷駆動能力と
大電流供給能力を求めてヘビーデューティーなパワーアンプへと変貌を遂げていった。
しかし、その一方ではこうした現象の反動とも言える製品開発も進んでいたのである。
100W以下はA級動作で、それ以上になるとAB級動作へシフトするという実用サイ
ズのKSA|200や、更に小型のKSA-80、ALTAIR(AB級)などのライ
ンアップも加えられ製品の幅を拡大していったのである。
第四部『大変革の第三世代』
企業としても順調に成長を続け商品構成も広がりを見せる中で、ダゴスティーノ氏の
オーディオにかける情熱は更に高度な技術革新に向かって同様な進化を表すこととなる
。1990年、オートキャリブレーティングによってA級動作におけるバイアスレベル
切り替えの技術を確立する。実用的なサイズで発熱をセーブし、消費電力と自然空冷の
関係を適正化するA級動作のパワーアンプとして、現在にいたるまでクレルの基幹アン
プとして君臨する存在となったKSA-250が登場するのである。翌年にはKSA-
250のパラレル化で、入力から出力まで初の全段完全バランス構成を採用し、出力ト
ランジスターを48個も搭載するモノラルパワーアンプとしてMDA-500を発表す
るのである。ちなみに、MDAとはモノ・ディファレンシャル・アンプリファイヤーの
頭文字である。また、同年発表した高S/N比を誇る完全バランス・アクティブクロス
オーバーユニットKBXは、若干デザインを変えながらも現在まで継続されているロン
グセラーモデルとなっている。様々なメーカーの様々なスピーカーに対して、スピーカ
ー設計者側のソフトウェアに合わせて製作される個別対応のプラグインカードを使用し
、最適なクロスオーバー周波数、スロープ特性、イコライゼーション、などを正確に得
られるようにした優れたシステムを既にこの当時に開発していたのである。また、一方
ではKC-100、200などのMCカートリッジやKPAフォノイコライザーをもリ
リースし、KSP-7やKBLなど一連のプリアンプの発表と共にアナログ入力部の増
強もはかられていたのだ。さて、ここまでの数年間でクレルは比較的短いサイクルで意
欲的に新製品を送り出し続けてきた。ダニエル・ダゴスティーノ氏にとっては技術的進
展に伴った必然的なステップアップではあったのだが、それとは裏腹に市場における若
干の戸惑いを招いてしまった事も事実である。第二世代から第三世代へと進化を続ける
に従って、いかにもアメリカらしい熱っぽく力感あふれた音となっていった。もちろん
、その当時としては大変魅力的ではあったのだが、逆に初期のクレルが持っていた緻密
で洒落た味わいが希薄になってきたのではという批評もあった。一方ではクレルの本流
からすれば反動的だとされながらも、AB級のパワーアンプKST-100とプリのK
SLの登場によって逆に新しいクレルの音をもたらしたとして皮肉な評価をされる時期
でもあったと言える。この様にクレル登場からクーリングファンの排除、オートキャリ
ブレーティングによる可変バイアス技術の開発、完全フルバランス化、という進化の過
程における日本側の輸入代理店がRFエンタープライゼスであったのである。
第五部『インターバル後の第四世代』
1992年、日本ではラックスがクレルをハンドリングする時代となる。KRC、K
RC-2など高精度アッテネーターを搭載してリモートコントロールを可能としたプリ
アンプの登場と共に、新技術によるクレルのパワーアンプは一気に覚醒の時代へと突入
する。可変バイアス技術を更に昇華させて、出力の大きさに応じて5段階にバイアスを
切り替えるスライディング・バイアス回路を動作原理に置いたSPB(サスティーンド
・プラトー・バイアス)を開発するのである。そして、そのバイアス切り替えのコント
ロール機能として、アンティシペーターという予測回路を搭載する。これは1800V
/usという超高速反応の回路によって、出力段の動作よりも18倍という驚異的なハ
イスピードで入力信号のレベル検出を行うという制御方式で、音楽信号を全く損なうこ
と無くSPBをコントロールするという予測センサー的な機能を同時に開発した。これ
ら新技術の集大成として登場したフラッグシップモデルが、KAS(クレル・オーディ
オ・スタンダード)である。パワートランジスターは何と60個、完全なレギュレータ
ーとして発想された電源部にも同数の60個のトランジスターを搭載し、1Ω負荷での
最大出力は何と3040Wという驚異的なスペックを打ち出したのである。しかも、と
てもこんな大型機とは思えないような、しなやかさと滑らかさを第一印象として訴えか
けるという表情を持っている。当然の事ながら、この巨大なパワーに裏付けられた低域
の再生音は深く沈み込む重量感と高速で立ち上がる反応の良さを両立させ、まさにクレ
ルサウンド熟成の薫りを聴き手に実感させるものであった。このコンセプトは速やかに
バリエーションモデルへと発展し、300W+300WのステレオバージョンであるK
SA-300Sや、KASのハーフサイズとして1Ω負荷での最大出力1400Wとい
うKAS-2などを発表していくのである。これらの最新デザインを可能とした背景と
して、使用パーツへの厳格な要求も忘れてはならない要素であった。クレルの電源トラ
ンスは、チェロやマドリガルなどハイエンドメーカーがこぞって採用している英国ホー
ルデンフィッシャーのトロイダルトランスを徹底した選別の上で使用している。
第三章『クレルの新世代』
単なる外見だけのモデルチェンジではなく、エレクトロニクスの明確な革新を伴って
登場するのがクレルである。四年前に発表されたグレーのボディーにスクゥエアなブラ
ックのエッジを持つKASとSシリーズの登場は、正直に言ってリスニングルームの雰
囲気に融合するというより、その存在感を自己主張するというデザインとして私を驚か
せたものだ。海外メーカーの多くは、デザインに自社のアイデンティティーとフィロソ
フィーを反映させるという考え方が顕著に見受けられる。この傾向を肯定的に考えても
、当時のクレルが世界中のマスコミをCEショーとは別会場のホテルに集めてKASと
Sシリーズを発表するという意気込みであったのだから、技術革新においても並々なら
ぬ自信と決意があったのであろう。そして、1996年の春クレルは日本におけるビジ
ネスパートナーをワディア、ティールでお馴染みのアクシス株式会社として、当時のそ
れを超えるほどの新技術と新しいクレルトーンを今回は静かに、しかし、以前にも増し
て力強く日本へ上陸させようとしている。96年1月にラスベガスで行われたウィンタ
ーCESで発表された〈フル・パワー・バランス〉は、まさにその期待に違わない魅力
を撒き散らしていたようだ。結果的に、アクシス株式会社が発売を予定している新シリ
ーズは以下の通りである。ステレオパワーアンプ・FPB600(予価180万円)F
PB300(予価135万円)FPB150(価格未定)の3モデルである。このネー
ミングに象徴される〈フル・パワー・バランス〉(以後FPBと表記)とは、一体どの
ような新技術なのであろうか。クレルの技術力に対して、日本側の分析力が果たして対
応できるレベルであったのかどうか、反省を促されるような事実が私の耳に入ってきた
のである。専門用語の羅列では理解に苦しむ事も多いと考え、私の頭でも理屈がわかる
程度の簡単な表現でクレルの新技術を解きほぐしていく事にする。最新技術FPBをひ
もとく上で肝心なことは、このアンプは頭脳を持っており、手足として実質的な機能を
行う部分と二つに分けて考えられるということだ。まずは、FPBがいかに強力な手足
に鍛え上げられているかという点から述べて見る事にする。
(1)「全段完全バランス構成」
その名の通り、FPBは入力から出力に至る全段を完全バランス差動回路で構成して
いる。クレルにおいては五年前のMDA-500とMDA-300に続く二世代目とな
るコモンモードリジェクション(簡単に言えばアース・グランド側から侵入するノイズ
をキャンセルする事)の能力向上は言うに及ばず、スピーカーからのリアクティブな負
荷(日本ではスピーカーの逆起電流と言われる)を引き込むことによってアンプのグラ
ンドライが乱される事からの完璧なプロテクトを可能としている。アンプ内部の各ステ
ージはグランドからの干渉から開放され、本来のリニアリティーを全く損なわずにスピ
ーカーのドライブに専念できるのである。
(2)「カレントモード・ゲイン・ステージ」
ゲインステージには、カレント・モード・デザインが導入されている。簡単に言えば
、アンプの入力から出力に至る経路のそれぞれで電圧を基準にして増幅の在り方を設計
するのではなく、回路の前後に負荷が存在していることを前提に電流領域で動作する増
幅段の事である。つまり、負荷(抵抗成分とも考えて)の大小によって流れる電流が変
化してしまうのはオームの法則からも推測できるとおり、実質の動作として音楽という
変動する信号に対して高速でリニアな増幅を行うには電流本意に設計されるべきだとい
うことである。
(3)「フル・レギュレーテッド・パワーステージ」
いかなるアンプでも最優先の目標として掲げられることは、オーディオ信号の内容や
スピーカーの負荷条件に関わらず常に求められる電流と電圧を安定してスピーカーに供
給することである。これは、スピーカーのトランスデューサーをリニアに、そしてアキ
ュレートにドライブする上で極めて重要なことであるのは言うまでもないことだ。この
実現のために最も重要な役目をになっているのが電源部である。これまでの一般的な手
法では、レギュレートせずに巨大なキャパシター・バンクで電源を構成させることが主
流となっていた。しかし、瞬間的な電力の供給に対して電流の安定性は得られるが電圧
基準を補正することは難問であった。FPBはKAS同様に出力段の電源を完全にレギ
ュレートしている。このレギュレーターは出力段のドライブ電流と電圧を監視しながら
、もし出力レールにサグ(変化)が検知されると、レギュレーターは瞬時に必要な電圧
電源素子を用いていたのだが、FPBでは出力素子2個に対して1個のレギュレーター
素子で同様な効果を引き出している。しかし、250V耐圧で16Aの容量を持つモト
ローラー性のパワー デバイスは十分にその役目をこなしており、後に述べるコントロ
ール機能の見事さがFPBの真価とも言えるものだ。
(4)「クラスAオペレーション」
FPBはフルパワーに至るまでのあらゆる出力状態で完璧なA級動作を保証する。A
級動作のメリットはデバイスの質が向上した今日でも依然変わることは無いが、一方に
おいては発熱と消費電力の問題、高温を維持することでの部品の劣化の問題も無視出来
ない要因であった。クレルはこれらの問題の解決策としてKAS、Sシリーズにおいて
SPB(サスティーンド・プラトー・バイアス)を開発したのである。FPBでは更に
このSPBを改良したSPBを搭載している。主な改良点は、バイアス・プラトーの選
択を決定するための監視領域を広げてバイアス適合動作の精度を高めたこと。また、S
PBはアンプに電源が投入される度に、その動作パラメーターをフル・キャリブレート
する。つまり、AC電源の変動によってA級動作のバイアス条件が変動する ことの無
い正確なバイアス供給が可能となったのである。
(5)「パラメーターのフルオート・キャリブレーション」
FPBは出力バイアスやレギュレーターバイアス、DCオフセットなど、アンプ内部
の電気的な調整状態を自己判定し自動化する初めてのアンプである。クレルの工場では
電源投入後10分をかけて一通りのパラメーターチェックを行い内部の動作状態を確認
するが、この極めて先進的なフィーチャーはユニット間のばらつきをなくし長期に渡る
安定性を維持し、いつまでも工場出荷時と同じ状態を再現することが出来る。こうして
、FPBは実際の動作中にも自己判定しながら、AC電圧のレベル変動など外的な要因
に対して瞬間的な治癒能力を備えている。
(6)「ダイレクト・カップリングとフル・コンプリメンタリー回路」
キャパシターはオーディオ信号経路の中にあっては信号の質を損なう可能性のある厄
介な素子と言える。FPBのシグナルパスには一切のキャパシターを存在させていない
。コンプリメンタリーデザインはクレルのキーテクノロジーの一つで、音楽信号のプラ
スとマイナスにそれぞれ全く同一のディスクリートなコンプリメンタリー回路を搭載し
て、オーディオ信号のリニアで高精度な伝送を可能としている。
(7)「クレル/モトローラー・バイポーラ出力デバイス」
KASリファレンス・モノアンプの開発で、クレル特注品として製造されているモト
ローラーの出力素子は無二の高速性とリニアリティーを誇っている。このデバイスがF
PBにも採用され、ハイスピードで強力な電流供給能力を約束しているのである。ちな
みにクレルは、このパワーデバイスの開発と製造に関して、モトローラー社に対して7
0万個という供給契約を交わして発注しているというから大したものだ。それだけ将来
の責任感を、自社のビジネスにおいて明言している証拠とも言える。
(8)「リモートコントロール」
クレルの全製品と同様に、現行のクレル多機能リモートコントローラーからの操作が
可能となっている。また、マルチアンプ駆動の際にはハードワイヤー接続によって全機
を同期することもできる。
この様な腕力と脚力を十分に鍛え上げたクレルは、従来のアンプメーカーが思いも付
かなかった新技術でFPBの完成度を一段と高めている。これらの手足をコントロール
する手段として、FPBはモトローラー製マイクロプロセッサーにアンプの頭脳として
活躍する場を与えたのだ。しかも、このマイクロプロセッサーの使用方法が大変巧妙で
ある。まず、アナログステージとは完全にアイソレートした電源供給を受けており、パ
ワーアンプの内部に小規模ながらコンピューターというデジタルデバイスを持ち込んだ
危険性を根底から解消させている。このマイクロプロセッサーは8系統の入力を備え、
各入力における処理を同時に行える能力を持っている。このマイクロプロセッサーの起
動クロックは8メガと小さめに設定されており、しかも出力波形を矩形波のままではな
く正弦波に変更し丸めて使用することにより、デジタル回路からのスパイク状ノイズの
混入を未然に防止している。しかも、各入力にはスリープモードが設定されており、プ
ログラムされている処理が必要のない場合には回路の活動を休眠状態とする配慮がなさ
れている。このマイクロプロセッサーの採用がクレルでも初めての試みであり、アンプ
の概念を変えるような仕事をしているのである。まず、最初に上げられるのがアンプの
負荷インピーダンスの測定である。つまり時々刻々とオーディオ信号の周波数変化によ
って変動するスピーカーのインピーダンスを測定しているのである。この測定の目的は
、前述の(4)で述べているSPB/2によって決定されるアイドリングを含めて6段
階のバイアス・ステージを決定するパラメーターとしてメモリーするためのものである
。そして、第二の仕事はバイアスレベルの管理である。マイクロプロセッサーは8系統
の入力を処理しつつ、同数のコントロール出力として稼働しているのだ。この両者のコ
ンビネーションによって、瞬間的にバイアスレベルをコントロールしている。言葉で表
現すれば「瞬間的」となるが、瞬きするのと同じような早さで展開される音楽の変化に
本当に対応しているのだろうか。KASで開発されたクレルアンプは、パワーステージ
のスルーレイトは100V/μsecという高速応答性を誇っている。このパワーステ
ージの応答性よりも18倍の高速性を持つSPB ステージのスルーレートは何と、1
800V/μsecの超高速応答性をもって入力信号のレベルを検出し、バイアスをス
ライディングしていくのである。そして、今度のFPBでは、マイクロプロセッサーが
更にスピーカーのインピーダンス変動を測定検出してSPB/2の仕事をサポートする
事になる。このマイクロプロセッサーが信号を受けて反応するのに要する時間は何と1
μsecである。つまり、100万分の1秒以上の時間軸で負荷インピーダンスの挙動
を察知して、バイアスレベルをコントロールするのである。「そんなに頻繁にバイアス
を変動させて、まともな音になるのか。」と懸念の声もあるだろうが、1μsecの時
間でバイアスを変更するのは上方修正だけなのである。つまり、SPB/2の仕事によ
って「入力に大きなレベルが来るぞ!」という場合と、「スピーカーのインピーダンス
が急に低下したぞ!」という状況で、より大きな出力電流が要求される場合に、より高
いバイアスレベルへ移行させるのである。そして、30秒間の時間経過でより大きな信
号レベル、または負荷インピーダンスの低下がなければ徐々にバイアスレベルを落して
いくのである。CDのサンプリング周波数でさえも44キロHz、つまり4万4千分の
一秒の精度で時間軸を取り仕切っている。ましてや、世の中に100万分の1秒しか音
を発しない楽器はありえないのだから、これだけの高速応答性があれば心配は皆無であ
る。ティールなどのインピーダンスカーブが激しく変動するスピーカーにとっては、ま
さに願ってもないアンプの登場となったわけだ。ビジネス面でも、アクシス株式会社に
とっては絶好のコンビネーションとなるアンプとスピーカーの両雄を手中に納めた形と
なった。三番目の仕事はヒートシンクの温度管理である。サーモセンサーによってヒー
トシンクの温度を検出して、状況に合わせたバイアスを設定するパラメーターを発信す
るのである。工場での出荷段階では初期のキャリブレーションを行うが、その際にはヒ
ートシンクを急速に40℃までヒートアップする。この状態でイニシアライズされたプ
ログラムをもとに、実際の動作状態では55℃から75℃を維持するようにプログラム
されており、ラックの中へ収納したり室温の変化があったときなども逐次対応してバイ
アスレベルを設定し直している。四番目の仕事はパワーステージ・レギュレーターの電
圧電流の管理であり、前述の(3)で述べたレギュレーターの機能において心臓部的な
役目を果たしている。五番目の仕事は、完全バランス構成におけるホット・コールド両
アンプのオートキャリブレーションである。この両アンプ間のインピーダンスは0・0
2Ωと極小ではあるのだが、コンプリメンタリー回路の宿命上完璧な相似形のバランス
を求められる。(5)でも述べているように、各種パラメーターを発信しながら動作中
においても監視コントロールしていくという機能はFPBの大きな特徴である。六番目
の仕事として、入力波形と出力波形の比較検出がある。これはNFBのようなループを
設けて歪率の低減を狙ったものではなく、極端な歪が出力に発生した場合にレギュレー
ター電源を瞬時にシャットダウンしてプロテクションすることが目的である。従来のよ
うにリレーを使用しての保護回路では音質にも悪影響をもたらすことが言われており、
FPBならではの先進のプロテクト・テクノロジーと言える。そして、最後はショート
サーキットの検出であり、結果としては前述と同様な手段でプロテクションを起動する
ことになる。最終ページにクレルの製品年表を添付したが、17年間のクレルの軌跡が
ご理解頂けることと思う。そして、これまで述べてきた通り新世代のクレルはハイテク
を駆使して、明らかに従来のアンプ作りから鮮明なる一線で区別出来るほどの進化を遂
げたのである。後日談として、FPB600に加えてFPB300も持ち込んで両者を
比較した。テストのために私が求める音量において若干のテンションの相違、各楽器の
実在感とも言える色合いの濃淡を聴くことが出来たが、極めて相似形の個性を聴かせて
くれた。購入の際には川又にご相談を。
第四章『クレルとアンドラ』
第一部『エグレストンワークス』
時系列は前後するが九六年一月下旬のこと、ウィンターCESの視察を終えて各輸入
商社から色々な情報が入ってきた。そんな時期に株式会社ノアの営業部長である笹本誠
氏が、内々でということで一枚のパンフレットを差し出したのである。いかにもアイビ
ーリーグ出身と思わせるトラディショナル・スーツを着こなした青年が、誇らしげにス
ピーカーに両手を添えてカメラのレンズを見詰めている。その写真の上に大きくタイト
ルされているのは、エグレストンワークス(EGGLESTON WORKS)という
ブランド名である。私は思わず食い入るように写真を見詰め、英文のコピーを可能な限
り読み取って見た。デザインの造形から数多くのスピーカーの音を推測して、そして実
物で外観から得た推測を確認するといった職業的な分析を繰り返してきた私にとって、
何と期待を持たせるデザインであることか。1996年4月19日、その予感は私に取
って大きな驚きと感動に変わるのである。この全く無名のスピーカー・マニュファクチ
ャラーは、一体どんな歴史を持っているのだろうか。1976年、ニューヨークの現代
美術館で写真家ウィリアム・エグレストンの個展が開催された。この美術館でカラー写
真の個展が開催されたのは開館以来初めての事で、広告、報道、商業写真などのレベル
から彼の写真はこの分野を一気に芸術の域にまで引き上げたのである。その息子である
ウィリアム・エグレストン三世は、過去15年間携わってきたスピーカー設計の経験に
よって、父と同様の貢献をオーディオの世界において成し遂げた人物として評価されて
いる。その大胆なスピーカーデザインは、「オーディオ/ビデオ・インテリア」誌にお
いて、エグレストンワークスのスピーカーほどスタイルとテクノロジーを調和融合させ
た事例はないと評している。エグレストン三世は父親に教わりながら、実に8歳のころ
からスピーカー設計を始めている。父親が三世にいつも言い聞かせていたのは、「ピア
ノを聴け。そして、スピーカーを聴け。」という言葉であった。ある時、彼がリビング
ルームに入っていくと、父親のスピーカーから流れ出ていたピアノの音は、実際そこに
ピアノがあると思わせるほどリアルであったという。以来、彼はスピーカーの音楽的精
度を左右するのは中域ユニットに他ならないと実感し、今日まで中域の再現性を中心に
オーディオ再生の真実を求めてきた。その過程でデザインに対する鋭い感性を生かしな
がら、自らの理論を具現化するキャビネットのアート&クラフトにも習熟していったの
である。こうして、満足すべき成果が上がった1992年テネシー州メンフィスにおい
て、彼は10名のスタッフと共にエグレストン・ワークス・スピーカー・カンパニーを
設立したのである。研究開発を繰り返し「レコーディングされた通りのサウンドを再生
する」という課題を、法外な大きさにすることなく美しく造形されたキャビネットにお
いて実現したのが、彼の姉の名を冠したアンドラ(ANDRA)なのである。ウィリア
ム・エグレストン三世の音楽的志向とインスピレーションが具現化したアンドラとは一
体どんなスピーカーなのか。現時点では掲載すべき適当な写真が手に入らず、もうすぐ
ステレオサウンド誌に登場する予定でもあり、そのデザインに関しては簡単に触れてお
く事にする。正面から見た場合には、横幅387mmと高さが約400mmの正方形に
30cmウーファーが納まったものをイメージして頂きたい。その上に横幅270mm
で高さが540mmの上部構造のミッド/ハイ・レンジが乗せられた形で、トゥイータ
ー付近の最上部がテーパーをかけられ台形の頭頂部を形作っている。このミッド/ハイ
・レンジの上部の横幅のうちMDFのキャビネット部分は213mmで、厚みが28・
5mmのイタリア産大理石が両サイドに貼り付けられている。奥行きはウーファー部分
が550mm、ミッド/ハイの上部では460mm、システムの全高が952mmと大
変コンパクトなボディーである。しかし、重厚な構造で剛性を追求した結果、重量は9
4kgとヘビー級である。ちょうどウィルソンのWATT&PUPPYのミニチュアを
サブ・ウーファーの上に乗せたような形で、例えは良くないが日本人が描く大方のイメ
ージはまさに「墓石」というのがピッタリな表現かもれない。日本のオーディオ雑誌で
は使い古された言葉なのだが、その根幹となっている思想は「ダイヤフラム以外の振動
要素を徹底排除する」という入念なキャビネット設計によるところが大きい。エンクロ
ージャーの中心素材はMDFであるが、その使用方法が半端ではない。16mm厚MD
F2枚にラミネート処理を施すことによって32mm厚としており、この上から更にア
ウター・ラミネート処理を施し総板厚は35mmとなっている。このアウター・ラミネ
ートは弾粘性ダンピング接着剤にて接着されており、エンクロージャーの各外面を伝わ
る振動要素を大幅にダンピングしている。さらに、上部は大理石で両側から挟まれてお
り、この両サイド部分の板厚は63・5mmとなる。アウター・ラミネートの表面は、
漆黒のブラックで大変美しい光沢感の鏡面仕上げであるが、思わず日本製ではないかと
疑ってしまうほどサーフェスラインの見事な仕上がりである。エンクロージャー内部は
数インチ間隔でブレーシングが施され、特異な形状の繊維を結合させたナイロン・ポリ
アミド系ファイバー「アクースタ・スタッフ」を適宜充填することにより内部の吸音処
理を行っている。極力バッフル面を小さくして豊かな音場感を発生させ、奥行きを長く
取ることによって低域のエクステンションを図るという、最近の主流となったスピーカ
ーデザインの典型例であると言える。さて、これら強力なエンクロージャーにマウント
されているドライバーが大変興味深い。エンクロージャーに贅を尽くした多くのアメリ
カ製スピーカーは、ウィルソンのようにトゥイーターにはフォーカル社製を始めとする
メタル・ドーム型を搭載する例が多いのだがアンドラは違った。アンドラが搭載したの
はダイナオーディオ製のシルク・ソフト・ドーム型ユニット、エソタールT330Dで
ある。口径28mmの大型シルク・ドームを、充分に通気性を確保した大口径のポール
ピースによってダイヤフラムに一層の稼働性を与え、無限大バッフルをシミュレーショ
ンしたという非振動リア・ダンピング・チェンバーを装備させている。既に知られてい
るスピーカーでは、ソナース・ファベールのエクストリーマーが同等なトゥイーターを
搭載しているので想像に難しくない。そして、数多くの小型ハイエンドと言われるスピ
ーカーを聴いてきた私から見ても、アンドラほど強力なミッドレンジを搭載した例は記
憶にないほどである。モレル社製(このメーカーの詳細は調査中)のMW166という
、ポリプロピレン・ダイヤフラムとダブルマグネットを採用した口径150mmのドラ
イバーをアンドラは2本使用している。このミッドレンジは何と120Hzから3・6
キHzという大変な広帯域を受け持っており、前述のトゥイーターと後で述べるウーフ
ァーとはオクターブ/6デシというなだらかなスロープ特性でつながっている。このM
W166は、通常であれば30cm級ウーファーの駆動に用いられる76mm口径のボ
イスコイルを搭載しており、正確なピストンモーションを行うことはもとより、大変高
速なトランジェント特性が実現されているのである。そして、大変ナチュラルに帯域を
広げたロールオフ特性を持っており、フルレンジとしても使用出来るほどの広帯域がア
ンドラへの採用の二番目の理由である。このMW166の後方には、ユニット前面と同
じ音圧が放射出来るようにチューニングされたトランスミッション・ラインが設けられ
ている。簡単に日本語で言えば後面開放型と言うことになるのだが、実際にはもっと理
論的な背景がある。ユニット後方の低域周波数の音波の伝播をダンピング材が減速する
ことを考慮にいれ、ダンピング材の充填密度を調整することにより最短のラインを維持
する、ラリー・D・シャープのトランスミッション・ライン理論に基づき、コンパクト
なキャビネットでドライバーの魅力を最大限に引き出すことに成功している。最後にウ
ーファーであるが、まずクロスが120Hzというサブ・ウーファー的な帯域設定に驚
く。アンドラに採用されたのはダイナオーディオ社の30cmウーファー、30W10
0である。100mmという大口径のボイスコイル、35・2gというローマス・ダイ
ヤフラム、28mmというダイナミックなストローク、柔軟なサスペンション構造とリ
ジッドなフレーム構成、強力なスペックを有する30W100をアンドラは何と2本搭
載しているのだ。エッ?・・・。先程の外観の説明では1本分のスペースしか前面にな
いではないか!
そうです、アンドラは正面のウーファーと平行に、内部にもう1本配置しているので
ある。内部のウーファーはリア後方の内部にダンピング材を充填した口径8cmの円形
ダクト2本によってエアを抜いており、プレッシャー・ドライブ・パラレル・チェンバ
ー構造となっている。つまり、後方のダクトはバスレフ・ポートとして機能しているの
ではなく、あくまでも内部ウーファーのトランジェントと高速なストロークを維持する
のが目的である。従って、前面のウーファーは事実上背面放射を行わず、内部ウーファ
ーが背面放射を受け持ってくれるため、一切の背圧が発生せず無限大バッフル同様に自
由空間における何の抵抗も受けない動作が可能となる。このウーファーの挙動を部分的
に分析すれば、B&Wのノーチラスのウーファーと類似する点があることにお気付きで
あろうか。つまり、目に見える正面のウーファーの後方には音響的に無限大の空間があ
るという事になるのだ。私が最初に驚かされたのは、まさにこのウーファーによる低域
のインパクトであった。本当に、この低域は凄い。そして、振動板が高速で反応すると
いうことはミッド/バス領域に対しても自然なロールオフ特性を有することとなり、オ
クターブ/6デシというナチュラルなクロスオーバーにも見事なマッチングを見せてい
るのである。最後に、これらを有機的に取りまとめるクロスオーバー・ネットワークで
あるが、これも見逃すことの出来ないポイントである。ネットワークの回路は専用のキ
ャビネットに納められ、ウーファーやミッドレンジの激しい背圧に悩まされることのな
いトゥイーター後方に納められている。使用素子もMITキャパシター、ヴィシェイ・
レジスター等の最高級パーツ・線材を使用し、ヴォイシングを重ねながら追い込んでい
くというチューニング仕上げらる。フロントグリルは音質的に透明なポリエステル布を
メタル・フレームに張ったもので、自由な空気の流れを妨げることはない。このフレー
ムは、バッフル面に埋め込まれた8個の小さなマグネットに吸着される形で装着され、
他社のようなグリルのフレームをくわえ込むための穴は一切ない。もちろん、このマグ
ネットの浮遊磁界がドライバーに影響する事はない。これらの総合的な結果として、出
力音圧レベルは87デシベルと高能率を維持し、ノーマル・インピーダンスは8Ω、再
生周波数帯域は24Hzから24キロHzと、現代のスピーカーに求められるスペック
の総てを 充分に満足させる能力を備えているのである。
第二部『ランデブー』
4月26日午後三時頃、アクシス株式会社の担当者が必死の形相でクレルFPB60
0を搬入してきた。この日はソニーのフル・コンデンサースピーカーであるSS-R1
0の試聴会が予定されており、運良くクレルのFPB600を日本の販売店では初めて
一般公開するという幸運に恵まれたのである。このスケジュールに合わせて頂くために
、アクシス株式会社に相当なご無理をお願いしてしまうことになった。しかも、29日
までの4日間、私にFPBを貸し与えて下さるというご理解とご協力を頂き、相当多く
の来店者にFPBをご紹介することが出来た。そして、ここには先週から待ち受けてい
たアンドラがいて、たくましいパートナーと巡り合ってしまうというロマンスが実を結
ぶことになったのである。翌日から日本の熱心なオーディオファイルの来訪を受けなが
ら、クレルとアンドラのデートが始まった。前述の通りFPB600は明晰な頭脳を持
ってはいるのだが寝起きは悪く、電源投入直後は体温が低く透明感に乏しい語り口は美
しく芯のあるアンドラを口説くほどの説得力はない。しかし、「これではいけない。」
とFPBの内臓マイクロプロセッサーが考えたのか、30分程度のヒートアップでFP
Bは見違えるほど居住まいを正してしまった。私が頻繁にテストに用いるチェスキーサ
ンプラーで、ジャズドラマーのリチャード・クルックスを起用したドラムソロの演奏が
ある。3フィート、6フィート、9フィートと、マイクから次第に遠ざかりながらドラ
ムの演奏を録音しているものだ。その中で、マイクの3フィートという直前で、2台の
スピーカーの間いっぱいに広がって強力なエネルギー感で演奏されるドラムセットのト
ラックを大音量で聴いて見た。切れ込みが鋭いスネアーと、張り詰めたテンションのエ
コーを心地良く残すタムの緊張感は迫力と同時に色々なオーディオ的分析をするのに都
合が良い。この音量とスピード感に追随出来るスピーカーは大変少なく、私は数多くの
経験からウィルソンオーディオのX1グランドスラムとWATTⅢ&PUPPYⅡ、そ
してシステム5が最高の反応とテンションを示したことを確認している。しかし、この
ドラムの再生に関しては、バスレフ方式であるPUPPY側の低音表現に若干のふくら
みとテンションのゆるみが感じられた。非常に部分的な比較であるが、その兆候はアン
ドラの低域に限っては聴き取ることは出来ない。ウーファーの背面放射がバスレフ・ポ
ートの風切り音と共鳴を伴ってダイヤフラムの振動以外の音を発することなく、アンド
ラが弾きだす低域の輪郭は鮮明そのものである。「アメリカのスピーカーにしては軽い
質感の低域だなぁ。」と初めは思っていたのだが、色々な曲を聴き込んでいくに従って
アンドラの低域の説得力が私とクレルを虜にしていった。そして、次は私のテストで定
番となっているイーグルスの再結成ライブアルバムからホテル・カルフォルニアのイン
トロを聴いた。ギターの音色は大変美しく、音場感はウィルソンのシステム5やティー
ルのCS7に勝るとも劣らない見事な展開を見せる。そして、ズシリと重たい低音のパ
ーカッションが登場する。重量感を重視する見方ではティールのCS7、低域の輪郭を
重視し余分な響きを排除しようとする見方ではジェネシス5、その両者を大きなスケー
ルで出してくれたのがテクニクスのSB-M10000ということが言えるかもしれな
い。しかし、それらの低域表現をコンパクトなボディーにもかかわらず、アンドラはテ
ンションとスピード感を更に上乗せして聴かせてくれるという離れ業を演じてくれた。
この低音楽器が、響きの中で別の音階にスライドしながら余韻を含ませていることも、
美貌のアンドラは忠実に再現してくれるのである。そして、いよいよ大貫妙子のヴォー
カルを聴きはじめる。イントロのクラリネットの音色は、トゥイーターの質感を良く反
映してくれる。リードの微細なバイブレーションが、タンギングの度ごとに浮つかない
のはシルク・ソフト・ドーム型の魅力であろうか。伴奏のバイオリンとチェロが比較的
音量感の低いピチカートで演奏されても、強力でスムースなトゥイーターによる余韻が
たっぷりと空間を満たしてくれる。さあ、ヴォーカルが入って来るぞ。アレッ、と思う
ほど口元の位置が浮かんで聴こえる。つまり、小さな口が空間に浮いているようで、そ
の360度あらゆる方向の周辺部からエコーが湧き上がって来るのだ。強力なミッドレ
ンジ・ユニットの恩恵が思わぬところで聴き取ることが出来た。オクターブ/6デシベ
ルというなだらかなつながりを持たせたトゥイーターとの関係で、ミッドレンジのトラ
ンジェントが優秀であるがゆえにバッフルの前面に固定されるヴォーカルの表現ではな
く、トゥイーター上方の空間に響きが立ち上っていくのである。更に日本語のサ行が大
変聴きやすく、かといって高域がロールオフした曇った感じもない。トランジェント特
性の良くないユニットではザラついたサ行となり、再生帯域が延びきらないと鼻がつま
った歌声になってしまう。まさに、アンドラというネーミングが象徴するがごとく、ミ
ッドレンジとトゥイーターが絶妙な一体感をもって聴かせてくれる女性ヴォーカルの極
め付けである。このトランジェントのすばらしさをエスコートしてくれたクレルは、時
間が経過するほどに熱が上がってきたのか、いよいよ若くて魅力的なアンドラを落城さ
せようと情熱あふれる語り口に熱を帯びてくるのがわかる。ダゴスティーノ氏が送りこ
んできた新世代クレルFPB600は、どうやら相当のプレイボーイらしい。次にはビ
シュコフとパリ管弦楽団によるビゼー「アルルの女/カルメン・組曲」を聴いた。文句
なし。オーケストラのステージ感は、見事にスピーカーのユニットから遊離して描かれ
、片側のチャンネルから放射された弦楽器群の余韻をもう片側が見事に引き継いでホー
ルエコーを完成させている。ここでも、ミッドレンジが大切な役目を果たしており、バ
イオリンの高音階を決してトゥイーターに一人まかせにしないという追随性がしなやか
さと分解能を高めている。さて、この辺で父親であるウィリアム・エグレストン一世が
与えた課題を、息子エグレストン三世が果たして芸術のレベルまで昇華させる事が出来
たのか。最後にピアノを聴くことにした。私が選んだ1枚は、デンオンレーベルのワン
ポイント・エディションから、レオナルド・ゲルバーによるベートーヴェンのピアノ・
ソナタ第8番ハ単調作品13「悲愴」である。スタインウェイから2mの距離で、高さ
が175cmの空間にセットされたマイクロホンB&K4006が、ノートルダム・デ
ュ・リバン教会の長い残響のなかで捕らえた鮮明な直接音と余韻を見事に捕らえている
。ピアノ・コンチェルトも良いのだが、オーケストラとのバランスで遠目に浮かぶピア
ノではなく、目の前で弦がヒットされる瞬間と、遠のいていくホールエコーとの両方を
聴いてみたかったのだ。演奏が始まった瞬間に「アレッ!」と思った。「このピアノは
、こんなにも柔軟であっただろうか。そして、質の良い鋼を叩いたときのように安定し
た響きと余韻を出していただろうか。」過去に聴いてきた記憶から、この録音ではもう
少しキャンというようなピアノであったのではないかと思えてならない。「わかった!
トゥイーターだ。そして、やはりここでもミッドレンジだ」ゲルバーの奏でるピアノの
エネルギッシュなヒットの瞬間は、とてもトゥイーター一個で再現出来るはずもない。
しかし、反応の遅いミッドレンジではジャリッとした付帯音を乗せてしまう。三世が父
親からの助言に従ってミッドレンジを重視したスピーカー作りに成功した背景には、中
域重視だからといって低域と高域の再生能力を軽く見るというような事は決してなかっ
た。むしろ、精度の高い中域の再現性に対して、マッチングするトゥイーターの選択と
、強力なウーファーの採用と低域再生のテクニックが必要条件を満たした結果なのであ
ろう。そのアンドラの魅力に対して、これまで述べてきたクレルの新技術の数々が微妙
なトランジェントの追求に絶妙の効果を発揮している。多くの輸入商社のご理解とご協
力によって、いち早く世界のハイエンド・モデルの新製品が当フロアーに入って来るこ
とは本当に喜ばしいことであると感謝している。運命的なクレルとアンドラのランデブ
ーが、思いも寄らぬラブロマンスに発展しようとは誰が想像したであろうか。本国アメ
リカでも出会うことのなかった両者が、はるばる海を越えた日本で結ばれたのである。
世の中にはめぐり合わせというものがあるようで、私はオーディオ界の仲人の大任を果
たしたような気分になってしまった。 【完】
|